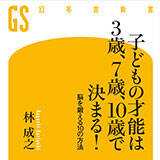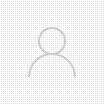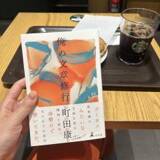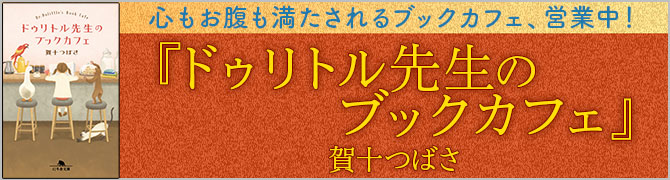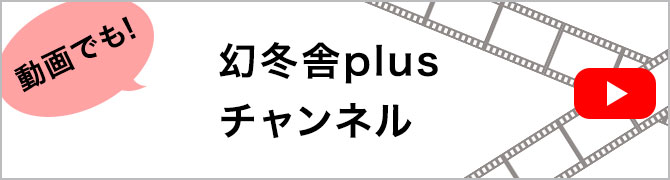早期教育は年々激化し、ついに「0歳児教育」まで出現する現代。ですが、子どもの才能を伸ばすのに一番重要なのは脳の発達に合わせた教育をすること。年齢ごとに子どもの脳の発達段階は変わるが、それに合わせて子どもをしつけ、教育すると、子どもの才能は驚異的に伸びる!『子どもの才能は3歳、7歳、10歳で決まる!』では年齢ごとにどのようにしつけ、教育すればいいのかを、著者の林成之さんが脳医学の知見からわかりやすく解説。そんな本書の中から、一部を抜粋してお届けします。
* * *
子どものわがままは、心と本能のギャップから起きる

3~7歳の脳は、まだまだ発達途上。子どもを育てるうえで知っておきたいことの一つに、「3~7歳は、心と本能のギャップが生じやすい」ということがあげられます。
子育てしていると、「子どもはどうしてこんなふうに行動するのだろう」と不思議に思うことがあるはずです。
たとえば、お友達と楽しく遊んでいたのに、お友達が帰る時間になったら、部屋の隅に行ってしまう。「ちゃんとお見送りしてバイバイを言おうね」と言っても、聞く耳を持たない。お友達が帰ってしまうと、しくしくと泣き出す。
このようなシーンで、「お友達が帰って遊べなくなるから機嫌が悪くなったのね」などと“大人の感覚”で子どもの行動をとらえるのは誤りです。大人の目には「嫌なことが我慢できない」「わがまま」などと映る子どもの行動の多くは、実は心と脳の本能の間にギャップが生じ、それにうまく対応できないために起こしてしまうもの。
先の例でいえば、友達を大好きになる友愛の心と、寂しさから自分を守りたいという本能がギャップを生み、「本当は大好きな友達にちゃんとバイバイを言いたいのに、言えない」という行動をまねいています。
脳が発達の途上にある子どもには、このようなギャップをうまく処理することができません。ましてや、自分がどうして泣きたい気持ちなのか、口で説明することなどできるはずがありません。
それなのに、大人が「悪い子ね」「そういうことをしてはいけません!」「どうしてちゃんとできないの?」などと責めるような教育をすると、子どもは大人に心を開かなくなってしまいます。
このような時期を「反抗期だから」といって“わかった気”になる人は少なくありません。しかし、子どもは反抗しているわけではなく、本能と心のギャップをさばけないだけなのです。
大人はそのことをよく理解し、子どもが取る行動の原因を正しく判断しなくてはなりません。
いたずらに叱ることなく、「○○ちゃんが大好きだから、帰っちゃうのが寂しくて、バイバイが言えなかったんだよね」などと子どもの気持ちを整理し、ギャップをうまくさばけるようになるまで見守ってあげてください。

3~7歳の子どもに父親が果たすべき役割とは
子どもにとって、お母さんの存在は非常に大きいといえます。赤ちゃんはお腹の中でお母さんの心臓の音を聞きながら脳を発達させてきているわけですから、残念ながら、お母さんとお父さんの間には越えられない壁があるのです。
お母さんは、子どもが生まれた後、できるだけ子どもと一緒に過ごし、愛情をかけなくてはなりませんし、時には厳しく叱るのも、子どもと長い時間を過ごすのも大切な役目。お父さんが愛情を込めて子どもをかわいがることも、もちろん大切ですが、お母さんにはかないません。
もしかすると、「じゃあ俺の役目は何なんだ?」と思っているお父さんもいるかもしれませんね。もちろん、お父さんにも、子どもの育脳で果たすべき大切な役割があります。特に、3~7歳ごろからは意識的にお母さんとの役割分担をしてほしいところです。
お父さんに担ってほしい役割の一つは、子どもの“逃げ道”になること。
子どもを育てる過程では、厳しく叱らなければならない場面が出てくるものです。しかし、両親がそろって厳しく叱ると、子どもは逃げ場がないと感じ、叱られることを極度に恐れるようになってしまいます。
その結果、嘘をついたり、挑戦するのを嫌がったりするようになることもありますから、子どもを叱る際は必ず“逃げ道”を用意しておくべきといえます。
そこで、お父さんの出番です。お父さんが本気で叱ったら、お母さんより怖いのは当たり前ですよね。必要以上におびえさせるよりは、叱るのはお母さんに任せ、お父さんは子どものフォローにあたる役割を担うのがよいと思います。
もう一つは、子どもと一緒にハメを外すこと。子どもは、ふざけてハメを外し、一緒に遊んでくれる大人が大好きです。「うれしい、楽しい」と感じる気持ちや「お父さんが大好き」という気持ちをしっかり育てるためにも、泥んこになって暴れたりして思いっきり遊んであげてください。
子どもの身体が大きくなってきても、お父さんのパワーがあれば、子どもと本気で取っ組み合うこともできるはずです。