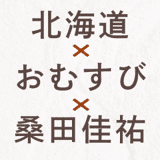引きこもり、霊能者への心酔など、どこの家庭にも起こり得る問題を絡めて家族の再生を描いた、森沢明夫さんの小説『雨上がりの川』(幻冬舎)が文庫化! 解説文を寄せたのは、自身も引きこもり経験のある、お笑い芸人「髭男爵」の山田ルイ53世さん。芸人の傍ら文筆家としても活躍し、近頃は文庫版『一発屋芸人列伝』(新潮社)を上梓しました。そこで、お二人の著書の発売を記念して、初対談をお届けします。書く苦しみや醍醐味、引きこもりの一因でもある世の中にはびこる圧についてなど、話題は尽きなくて――。

――まずは、12月に文庫化された『雨上がりの川』について伺います。山田さんが初挑戦された解説を、森沢さんはどう受け止められましたか?
森沢明夫(以下、森沢) 山田さんの解説が届いて読んだとき、僕の第一声が、わっ、おもしろい、うまい! と。失礼ながら、これ、ほんとに山田さんが書いたの? と疑ったほどです。
山田ルイ53世(以下、山田) いや、有難うございます! 人様の小説の解説なんて初めてですから、プレッシャーがすごくて。作品を読んで感銘を受けたので、そのリスペクトを背負ったから余計にです。他の小説の解説を読んで、なるほど、このくらいの感じまでなら許されるのね、と参考にして。書いては、これで大丈夫かなと悩むから、なかなか進まなくて苦労しました。僕、筆が遅いので。
森沢 山田さんは、すごくまじめな方なんですね。僕も多分、遅筆なほうです。一文字も書けない日もありますよ。
山田 本当ですか? ちなみに、どうやって物語を構築されているんですか?
森沢 僕の場合は、人間関係図から始まるんです。『雨上がりの川』でいうと、中学校でいじめに遭って引きこもりになる春香、娘を助けたいとエセ霊能者に傾倒する母・杏子、それをなんとか助け出そうとする父・淳……といった人間関係図ができてくると、よし、書けるな、と。ある大御所の作家さんが、小説は、納豆の粒と粒の間の糸を書くことだとおっしゃっていた。つまり人間関係図ができると、人(粒)と人(粒)との間の糸(物語)が書ける気がするんです。
山田 納豆! その大御所の方は、きっと実家が水戸ですね(笑)。
森沢 次に僕は、それぞれのキャラクターを細かく作り込むんです。春香は身長何センチで、血液型は何で、髪型はこんな感じで、爪を深く切るタイプで、とか、そんなことまで書き出していく。めんどくさい作業ですけど、そうすることで頭の中に春香の映像が作られていくんです。
山田 登場人物が勝手に動き出す、みたいなことですか?
森沢 そうですね。春香が一人称で語るパーツでは、春香という人間のボディスーツに僕がスーッと入り込んで、春香の視点で見えるもの、肌感覚、心の痛みとか、春香の感覚器官を使って、それを味わいながら書いているんです。
山田 だからですかね? 読んでいて、引きこもりの心理をわかって書いてらっしゃるなと思いました。僕は中学2年生から、6年間引きこもっていて。人それぞれですが、僕の場合、親に迷惑をかけたなーという後悔が強い。親には親の人生があり、楽しく暮らしたかっただろうなと。子どものためにすべてを犠牲にする必要はない。でも僕が引きこもったせいで、母は趣味のひとつをやめてしまった。親の人生を狂わせたという申し訳なさがあって。多分、春香もそんな思いを持ちながら生活しているのではと感じました。
森沢 家族みんなが、それぞれ思いやっているのにうまくいかないことって現実にありますからね。僕は引きこもりをテーマにしたというより、引きこもる人には引きこまざるをえない理由があり、洗脳される人には洗脳される理由がある、人にはそれぞれの事情があるんだよ、というのを描いたんです。人間って事情によって生き方が変わっていくでしょ。
山田 そうですね。小説の前半はいじめがあり、お母さんが洗脳され、おどろおどろしい雰囲気で。元・引きこもりの自分としては、イヤな展開だなと胸を締め付けられながらも引き込まれていって。読み進めるうちに、話の方向が変わっていきますよね。僕、あまりこういう展開の小説を読んだことがなくて、すごく新鮮でした。
森沢 基本的に僕はハッピーエンドが好きなんですが、よくよく読むと、実は大したハッピーエンドじゃないんですよ。ただ、それぞれが何かを経験することによって一歩前に進んでいる。で、ハッピーエンドになりそうな感じがするんです。
山田 だからリアリティがあるんですね。最後の春香の選択も含めて、みんながただのきれいごとではない判断をしていく。安易な美談に走らない。人間ってそうだよな、という納得感がありました。

――山田さんが書かれた、一発屋と呼ばれる人たちを取材した『一発屋芸人列伝』も、彼らのその後のリアルな人生が書かれてますよね。
森沢 これは山田さんじゃなきゃ書けない本ですよね。僕は特に、ムーディ勝山さんと天津・木村さんの“バスジャック事件”が好きでした。“ロケバス運転手”という職とネタを巡る二人の攻防に、人間性が露呈しまくるのがおもしろくて、ニヤニヤして読んでいました。
山田 一発屋の僕が一発屋の芸人さんたちに話を聞く。仲間ですから取材は楽しいし、盛り上がるんですが、芸人さんのしゃべくりのおもしろさを文章に落とし込むのが難しかったですね。空気感とか会話のテンポとか表現できてないと、その芸人さんがすべっているみたいになってしまう。そこは神経を使いました。
森沢 一発屋という言葉は世の中ではあまりいいイメージじゃないですが、実は一発当てるってすごいことなんですよね。世の中のほとんどの人は一発も当てずに終わっていくわけですから。
山田 一発屋という立ち位置だから観察できることがあるんですよ。人間の本性が露わになるというか。悪気はなく、ナチュラルに見下してくる人がいますからね。たとえば、僕の自宅をロケさせてくださいと頼まれたことがあって。スタッフさんが来たので、「どうぞ」とドアを開けたら、第一声が「へー、結構いい家に住んでるんですね」と(笑)。それ、売れてる芸人に言いますかと。対等な関係性、同じ目線の高さなら絶対出てこない言葉や表情を見せてくれる。人間観察の観測地点として、一発屋というのは面白い。
森沢 なるほど、相手の心理が露呈されるわけですね。でも、この本を読んだ人は一発屋の見方が変わると思いますよ。
山田 読んでくれた方が、「一発屋だ!」などと軽々しく揶揄できないな、と思って頂けるように書いたつもりです。
森沢 でも決して、揶揄するなよ、とは言っていない。登場する芸人さんたちを上げすぎず、下げすぎず、そこのサジ加減が、うまい! と思いました。
山田 いや、恥ずかしいわ! これは、見抜かれてますね(笑)。
――ところで、そもそもお二人は、書くことは楽しいですか?
山田 僕はしんどいほうが多いです。先生はどうですか?
森沢 はい。楽しくないですよ(笑)。僕は取材が好きなんです。本を書くにあたって誰かに話を聞くとか、題材となる現場を見に行くとか。そこで好奇心を満たし、いろんな経験をして、自分の中にそれが入った、ってところで終わりにしたいくらい。
山田 僕も出版社の方から、小説を書いてみませんか? というお話をいただくことがあるんです。でも、さっき先生がおっしゃった納豆みたいになって物語が降りてくるっていう感覚はまだピンとこなくて。そもそも書き出しがよくわからない。『雨上がりの川』で、淳が自宅のベランダから川を眺める冒頭の描写は、この後の家族の行方を暗示する感じで、生意気ですが「さすがプロ!」と思いました。先生は書き出しをどうやって決めるんですか?
森沢 書き出すまでの時間はめちゃくちゃ長いです。気分的には、書き出せたら半分終わったような感じ。僕は、小説が持っている温度感、匂い、色などが定まらないと書き出せないんです。そこがモヤモヤしたまま書き出すと、何度も書き直すことになる。それは虚しいので、最初からピタッと決めておきたいんです。
山田 そうなんですね。何か具体的にコツとかワザみたいなものは?
森沢 僕の場合は音楽ですね。その小説の雰囲気に合う音楽を数曲セレクトしてプレイリストに入れておくんです。歌詞があると気持ちがそっちに引っ張られるので、たいていインストゥルメンタルなんですが、それらを聴いてコーヒーを飲みながら、これから書く小説のテンションに合わせていく。そして書き出す……という感じです。
山田 いや、カッコええな!(笑)。物語のBGMとして音楽が流れると。

――森沢さんの小説執筆話に興味津々の山田さん。森沢さんからこんな提案が。
森沢 山田さんは ご自身の題材をたくさん持っているから、小説を書くなら私小説がいいかもしれませんね。
山田 何年か前に出した『ヒキコモリ漂流記』は、自分の体験に重ね合わせて私小説のつもりで書いた部分もありましたね。
森沢 自分の視点で書くという方法もありますが、たとえば、家族のことを描くなら、父の視点、母の視点、弟の視点で描くのも一つの手法です。
山田 なるほど。ただ、我が家は家族の関係が希薄すぎて。兄や弟は30年近い間、一度も会っていないですし、両親とは決して仲が悪いというわけではないんですが、会ったり電話で話したりすることはほとんどない。2011年の震災のとき、久しぶりにおふくろから電話がかかってきて、「揺れたね」と。「関西の方まで揺れたのか……大きな地震だったんだな!」と思ってたら、僕に一言も無しに兵庫から関東に実家が引っ越してた(笑)。
森沢 離れすぎていて、家族の視点がわからないですね。
山田 はい。だから、お正月に実家に家族が集まるとか、そういう“普通”は、うちにはないんです。
森沢 『雨上がりの川』の解説文にも書いてくださいましたよね。子どもは高校に行って勉強して、親は親らしく、みたいな、“普通”の物差しに人は翻弄されると。
山田 そうです。僕が引きこもっていたとき、僕自身や両親が苛まれていたのも“普通”の物差しだったんじゃないかなと。
森沢 ただ最近、みんながみんな同じ方向じゃなくても、違っていいんだよ、という価値観の多様化がじわじわと浸透してきたように感じます。その意味で世の中が少しよくなってきたのかなと。
山田 それは確かに。みんな違っていい、というのは素晴らしいメッセージだと僕も思います。でも今度は逆に、〝みんなが〟多様性を認めないとダメだ、みたいな“圧”が強まり過ぎている気もする。それって結局、「みんなと一緒じゃないと居心地が悪い」ってことなのではと。
森沢 なるほど、鋭いですね。結局、一択に走ってしまう、と。
山田 このコロナ禍でも、やたら「こんなときこそ~しよう」みたいなことを言いがちです。この〝こそ〟は暴力的(笑)。いつ落ち込んだらええねんと思う。そんな前向きに何かしなくても、良いと思うんですね。オンライン飲み会も流行りましたが僕は苦手で、そもそも芸能界の友だちは? と訊かれたら、「相方」と答えるしかないほど、実生活の社交がなくオフラインですから(笑)。
森沢 他に何か、気になる圧はありますか?
山田 ここ何年か感じているのは、“ロカハラ”。ローカルフードハラスメントです。
森沢 なんですか、それ?
山田 コロナ前は、地方営業によく行ってたんですが、その土地の名産品を必ず勧められる。別に良いんですけど、何回も食べたことあるんですね(笑)。カツオのたたきとか。しかも地元の方に囲まれて食べることになるので、ただ「おいしいですね」ではよろしくない。「!?……うまい!!」みたいな、最高のリアクションを求められているようで、しんどくなってしまう。大体、45年生きていたら、大抵のものは食べてますからね。目を引ん剝くほどうまいもんってもうなかなかないでしょう(笑)。
森沢 山田さんは正直だな。僕は勧められたらとりあえず食べるタイプなんですよ。コンビニでも、ヘンな味のジュースとか変わった商品が出るたびに試したくなる。で、たいてい「マズイ」って。9割5分、外すんですけどね(笑)。
山田 いるいる、そういう人。チャレンジャーですね。
森沢 しかし、山田さんって、“圧・評論家”ですねぇ。日本にはびこる小さな圧をすごい感じとっている。
山田 「貴族」「一発屋」「ひきこもり」に続くキーワードが! 一発屋の人生、この先も長いですから、ありがたくその肩書き頂戴しておきます(笑)。

文・構成/村瀬素子
撮影/菅井淳子