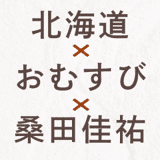ニューヨークで暮らすようになって、20年近くになる。
学生時代に旅行で訪れて以来、ニューヨークは、私にとって自由を象徴する街だった。社会の中に居場所を見つけられないフリークやアウトサイダーを受け入れてくれる街。どんな人間だって自分自身でいられる街。新卒の採用システムの中で、自分が評価されるとは思えず、かといって、オルタナティブな進路があることも知らなかったから日本を飛び出すことにして、アメリカでの大学院留学を志願した。
憧れのニューヨークにある名門学校への入学はかなわなかったけれど、記念受験のつもりだった隣の州の大学院には入学を許され、留学時代には時間を見つけてはニューヨークに遊びに行った。
大学院には、ニューヨーク出身だけど、西海岸を散々放浪し、大学院に進学するために、いやいや東海岸に戻ってきた同級生がいた。
一度、実家を訪ねるという彼の車に乗せてもらったことがある。
「ニューヨークを嫌になる」という気持ちが理解できなかった私が、
「何が嫌になったの?」
と言うタイミングで、車はニューヨーク市に入ろうとする料金所前の渋滞に巻き込まれた。
一向に動く気配がない、と思ったら、渋滞の先っぽで、女性二人が大声をあげて怒鳴り合っていた。おそらく争いのきっかけは、割り込もうとしたのを入れなかった、という程度のことだろう。
彼はうんざりした様子でこう答えた。
「あれだよ、あれ。ニューヨークは人の気を狂わせてしまうんだ」
タフそうな女性たちが声をあげて罵り合う光景すら、私のニューヨークへのあこがれに油を注いだ。
「一度はニューヨークに暮らしてみたい」と、なんとか就職先を見つけて移住した。ニューヨークは物価は高いし、競争も激しい。家賃を払うのが精一杯だった安月給の時代には、決して優しい場所ではなかったけれど、誰もが夢を追いかけて頑張っている、そう思えたから苦にはならなかった。ずっとニューヨークに暮らす、という覚悟を決めたことはなかったけれど、より良い職場、もっと面白い仕事をと、目先のことを一つずつ片付けているうちに、気が付いたらこんなに時間が経っていた。
最初の6年間は会社員として働いた。一番目は日本企業のニューヨーク支局、次はアメリカの中小企業、最後はマルチナショナルの報道機関と、「この会社、肌に合わない」と転職を繰り返したあげく、向いてなかったのは会社という組織体系だったのだと気がついて、不景気のさなかに自分が所属していた部署がごっそりなくなるのを機に独立した。どこの会社にもある社内政治と足の引っ張りあいにうんざりしたのもあるし、会社の利益のために頑張れない自分に気がついたこともあった。母がフリーランスだったから、ぼんやりと「通勤定期を持たない、満員電車に乗らない人生っていいな」といつも漠然と思っていたこともある。
その間、若くして勢いで結婚もしたし、30になる頃には離婚も経験した。留学時代に付き合い始めた彼は、私が在籍した大学があった街の住民、つまり「タウニー」だった。ニューイングランドの名門大学の学生はだいたい、特権階級にありがちなスノッブか、見ているだけで疲れてしまうほどの競争主義者で、いつしか遊びを学校の外に求めるようになった頃に、彼と出会った。
彼は、フロアがガラガラになる明け方までは絶対家に帰らないタイプで、私も楽しいことに貪欲だったから磁石のように惹かれ合ったのだと思う。ニューヨークに引っ越して何年か経った頃プロポーズされて、「人生でいちばん貧乏だった時代を、笑って過ごせたのだから、この人と一緒にいればきっとどんなに悪いことが起きても楽しく生きていけるだろう」と思ったものだ。お金はなかったから、セントラルパークに25ドル払って集会届けを出し、かなりデタラメな結婚式と、「出席者全員が帰宅する頃にはへべれけ」を目標にパーティを開いて目標を達成したはいいけれど、何年か経って、自分たちが人生に求めているものが乖離していたことが明白になった。イタリア系アメリカ人の彼にとって、労働は生活の糧であり、それ以上でもそれ以下でもなかったから、ワーカホリックの妻を理解できなかった。夫婦仲が破綻し始めた時、彼はアルコールに、私は仕事に、それぞれのめり込み、離婚という帰結はあまりにも自然だった。
誰のせいでもない離婚だったから、原因は?と聞かれると言葉に窮した。自分よりも若くして結婚と離婚を経験していた元同僚のアメリカ人女性の友達がこう言ったのを聞いて納得した。
「アメリカ人の離婚の原因のほぼ半分は『Grow Apart』(訳すとすれば、違う方向に大人になる、成長の過程で絆を失う、というところだろうか)。よくあることよ」
そのあとも何度か同棲と別れを経験した。誰もに「いいボーイフレンドだ」と言われる日本人の彼に結婚を示唆されたこともあったけれど、ちょうど離婚したばかりで、これからは誰からも文句を言われずに仕事に没頭できると張り切っていた頃だったから、家庭を作る自分がイメージできなかった。そのあと付き合った何人かのアメリカ人男性は、同世代なだけに痛みや傷を抱えすぎていて、きちんと向き合うことができなかった。今は、誰もいないといえば嘘になるけれど、約束のない自由な関係が心地よくて、よっぽど地面が揺れるような衝撃的な恋でもしない限り、しばらく誰かと暮らしたりする気にはならないだろうと感じている。

フリーライターとして独立したのは10数年前だ。学生時代から雑誌にちょこちょこ寄稿したりしていたし、雑誌の仕事についた人間が周りに何人もいたから、最初の数年はそれなりにしんどかったものの食うには困らなかった。独立当初は仕事と呼べるものはなんでも引き受けたけれど、「本当に好きな仕事」の割合が増えるにつれて、自分なりの専門分野もできた。30代は、仕事人として、そして一人の人間としてのアイデンティティを探しながら、がむしゃらに働いていたら、あっという間に終わってしまった。今は、毎日仕事と遊びに夢中になって、帰宅する頃にはクタクタで、ベッドに入ると同時に寝てしまう。だから一人でいることを寂しいと思うこともない。
この数年は仕事の関係で、年に延べ2か月くらいの時間を日本で過ごすようになった。日本にいて、自分と同世代の男女と話をしているうちに、ときどき、
「自分はこの人生で大丈夫か?」
「結婚したいと思わない自分はおかしいのではないか」
と思ってしまうことがある。
「そのうちYumiも幸せになれるよ」
などと言われると、「そうだよね!」と返事をしながら、ニューヨークに戻ってハッと我に帰る。「シングル=不幸」と思わせるプレッシャーがない。周りには、恋愛や別れを繰り返しながら、社会の中で生き生きと頑張っている女性が山ほどいる。自分が自由に、毎日たのしく飛び回って生きていけるのは、ニューヨークの自由な価値観と、街のエネルギーを吸収しながら、またそのエネルギーを作る原動力になりながら、一生懸命生きている女性たちのおかげなのだと思う。
本連載は、『ピンヒールははかない』(佐久間裕美子 著)として2017年6月に書籍化されました。続きはぜひ書籍でお楽しみ下さい。