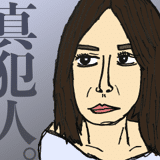クリスマスイブの日の事実をつなげていくと、葵にはどうしても解けない謎があった。
悲しみと悩みに暮れていた、その時――目の前に真っ白なアルパカが現れた!
そして、「ランスロット」と名乗るのだった――。
(第一話「アルパカ探偵、聖夜の幽霊を弔う」つづき)
6
「――あ、ここで大丈夫です。もう、すぐそこなので」
「そう? じゃ、停めるよ」
「今日はどうも、ありがとうございました」
車を降り、運転席側に回ってから、葵は俊作に礼を言った。
「イベント、楽しんでもらえたかな?」
はい、と葵は頷いた。ファルコンズのファン感謝祭に参加してよかったと、心の底から思っていた。健也を慕っていた人たちに会えたこと、そして、ファルコンズというチームが、どれほどファンを大切にしているかを知れたこと。選手としての健也の偉大さを実感できたことは、自分にとって大きなプラスになると、葵は信じていた。
「喜んでもらえたようでなによりだよ。でも、こんな特別な日に、呼び出しちゃってごめんね」
雛子からパーティに誘われていたことを思い出し、少し切なさを覚えたが、葵は「いいんです」と笑顔で言った。「両親も、行ってきなさいと送り出してくれましたから」
「そっか。じゃあ、気を付けて帰ってね。また、母に会いに来てよ。あの、元気なお友達と一緒にさ」
俊作はそう言い、クラクションをぱんっ、と鳴らして走り去った。
一人になると、急に夜の寒さが身に沁みた。もう午後九時過ぎだ。予定を伝えてあるとはいえ、あまり遅くなると両親が心配する。葵はマフラーをしっかり首に巻き、自宅へと続く路地に足を向けた。
辺りはしんと静まり返っている。空気は澄み、夜空はどこまでも晴れ、星々がまばゆいほどに瞬いていた。聖夜だからだろうか、何か神々しいものが自分を見守ってくれているような気がした。
その時、葵は足音を聞いて立ち止まった。
前方から、誰かがこちらに向かってきている。
魅入られたかのようにその場から動けずにいると、数メートル先の街灯の光の下に、ふっと二つの影が現れた。
葵は我が目を疑った。
光の中に、一頭の真っ白なアルパカが佇んでいた。
アルパカは黒い大きな瞳で葵をじっと見つめている。もこもことした白い毛で全身が覆われており、その長い首の中ほどには、翼を広げた鳥をかたどったような、勲章に似た金色の飾りがついている。
そこから伸びた細い黒のベルトを目でたどり、葵は思わず声を上げそうになった。アルパカの隣に、奇妙な格好をした人影が寄り添っていた。全身をすっぽり包む黒のローブに、顔を覆い隠すフード。その姿はまるで魔法使いだ。
「――実に素晴らしい聖夜だと思わないかね」
出し抜けに、威厳のある低い声で、アルパカがそう言った。
いや、そんなはずはない。確かに言葉に合わせてアルパカが口をもごもごさせていたが、喋ったのは隣にいる黒ずくめの男に決まっている。
そう頭で理解していたのに、なぜか葵は、アルパカに向かって、「あなたはどなたですか」と尋ねていた。
「私はランスロット」
堂々とした名乗りだった。「ああ、立派な名前だな」とすんなり葵は受け入れた。その声には、それだけの力強さがあった。
そこでアルパカは、隣に佇む男に目を向けた。
「ちなみに、この男には名前はない。私に仕えている従者だ」
男は何の反応も見せずに、黙って革のベルトを掴んでいる。
「無口な男だが、とびきりの善人でもある。まかり間違っても、君に危害を加えるようなことはない。安心したまえ」
「はあ、そうなんですか……」
「時に君、寒くはないかね」
「は、はい、大丈夫です。コートの下に何枚も着ていますから」
「寒ければ、遠慮なく申し出てくれ。私の温もりを分けてあげよう」
確かに、ランスロットはいかにも暖かそうな、長い毛のコートに身を包んでいる。そのふわふわした首筋に抱きついたら、さぞかし気持ちいいだろう……。
いや、そんなはしたない真似はダメだ。心に浮かんだ想像を振り払い、葵は尋ねた。
「どうして、ランスロットさんはこんな街中に?」
「ふむ。真っ当な質問だ。私は動物園で飼われているわけでも、アルパカ牧場で同胞たちと仲良く暮らしているわけでもない。探偵を生業としているのだ。芳しき謎の気配を感じたので、こうしてやってきたというわけだ」
「探偵……」
その説明で、葵は数日前に雛子から聞いた噂話を思い出した。――悩みを抱えて街を歩いていると、どこからともなくアルパカが現れて、さらっと謎を解いてくれるんだって――。
「では、あなたがアルパカ探偵さん……?」
「いかにも」とランスロットが重々しく頷く。「君を悩ませている問題を、遠慮なく私に打ち明けたまえ。見返りは何もいらない。貴族が下々の者に手を差し伸べるのは当然のことだからな」
「えっ、貴族なんですか?」
「中世から連綿と続く血筋のな」ランスロットは両耳をぴこぴこと動かしてみせた。「さあ、話してみてくれないか」
自分は夢を見ているのだろうか。葵は現実感を欠いたまま、健也の幽霊を目撃した話をランスロットに語った。
「――記憶が混ざってしまったのだろうと、家政婦の文江さんは言いました。たぶん、そうなんだろうと思います。……すみません、こんなくだらない話をしてしまって」
葵が話し終えると、ランスロットは「ふぇ~」と、ため息とも鳴き声ともつかない声を漏らした。
「人間というのは、実に不思議な生き物だ。嘘をついたり隠し事をしたりと、様々な手段で成り行きに抗おうとする。正直にすべてを打ち明けた方が、ずっと簡単だというのに、だ。……まったくもって、愛すべき存在だな」
むしろアルパカの方がずっと不思議で愛すべき生き物だと思ったが、葵は「はあ」と気の抜けた相槌を打った。
「最初に言っておこう」ランスロットが右前脚を軽く持ち上げ、器用に葵を指した。「君の記憶は、おそらく正しい」
――はたして、アルパカ探偵・ランスロットは、いかにして謎を解くのか? 続きはぜひ、発売中の『アルパカ探偵、街をゆく』(幻冬舎文庫)にてお読みください。
そして、次回、再び、4コマ漫画のオマケが!!

『アルパカ探偵、街をゆく』試し読み&オマケ企画の記事をもっと読む
『アルパカ探偵、街をゆく』試し読み&オマケ企画

『化学探偵Mr.キュリー』がベストセラーとなっている、人気の喜多喜久さんの新作は、なんと、あのもふもふのアルパカが謎を解くという、ほっこりしたミステリー。
愛する人を失い、心に傷を負った人たちが、悲しみの淵をさまよっていると、アルパカが現れ、希望への扉を開いてくれるのです。癒し系ミステリーの一部を、試し読み、いかがですか?