
「令和」と決まった新元号の5月1日に約200年ぶりとなる天皇の「譲位」が行なわれます。
明仁天皇は退位にあたって何を言い残し、徳仁新天皇は即位にあたって何を告げ知らせるのでしょう?
天皇の言葉はわかりやすいようで、実は、奥が深いもの。
過去の発言や歴史を踏まえなくては、その真意を読み解くことができません。
辻田真佐憲さんの新刊『天皇のお言葉~明治・大正・昭和・天皇~』は、この稀有な歴史的機会を冷静に立ち会うための必読書です。
「病身の天皇」として知られる大正天皇。どのように病は深刻になっていったのでしょうか。
「己れは別に身体は悪くないだろー」
(大正一〇・一九二一年)
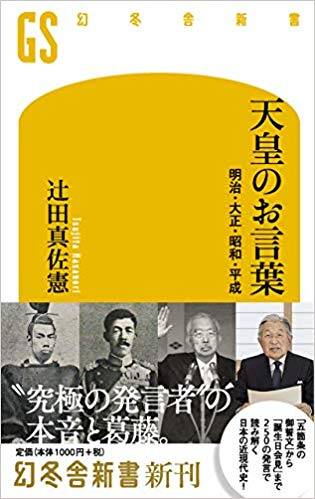 一九一八年一一月、ドイツが休戦協定に調印し、第一次世界大戦が終了した。翌年一月パリ講和会議が開かれると、日本は五大国のひとつとしてこれに参加し、六月ヴェルサイユ講和条約に調印した。これにより、赤道以北のドイツ領南洋諸島は、日本の委任統治領となった。
一九一八年一一月、ドイツが休戦協定に調印し、第一次世界大戦が終了した。翌年一月パリ講和会議が開かれると、日本は五大国のひとつとしてこれに参加し、六月ヴェルサイユ講和条約に調印した。これにより、赤道以北のドイツ領南洋諸島は、日本の委任統治領となった。
日本の国威が大いに上がるかたわらで、天皇の病は深刻になった。大戦中すでに言語障害や歩行困難の症状があらわれていたが、一九一九年には帝国議会の開院式に臨席できないほどまでに状態が悪化していた。
そして一九二〇年、静養先の葉山御用邸からなかなか帰京できなくなり、さまざまな憶測が巻き起こる事態になった。もはや隠すこともできず、三月三〇日、ついに天皇の病状が宮内省より発表された。
「陛下践祚以来、常に内外多事に渉らせられ、殊に大礼前後は、各種の典式等日夜相連り、尋(つい)で大戦の参加となり、終始宸襟を労させ給ふこと尠からず。御心神に幾分か御疲労の御模様あらせられ、且一両年前より、御尿中に時々糖分を見ること之れあり、昨秋以来、時々挫骨神経痛を発せられる」
これを皮切りに、天皇の病状が定期的に発表された。部分的に引用するとつぎのようになる。
「爾後是等の御症状[第一回発表の症状]は漸次御軽快あらせられたるも、御疲労は依然事に臨みて生じ易く、御倦怠の折柄には御態度に弛緩を来し、御発語に障害起り、明晰を欠くこと偶々(たまたま)之れあり」(同年七月二四日、第二回発表)
「唯御発語の障碍は依然として、特に御心身幾分の御緊張を要せらるゝ場合には、御難儀に伺はる」(一九二一年四月一六日、第三回発表)
「且御態度の弛緩及御発語の故障も近頃其度を増させられ、又動もすれば御倦怠起り易く、御注意力御記憶力も減退し、要するに一般の御容態は時々消長を免れざるも、概して快方に向はせられざる様拝察し奉る」(同年一〇月四日、第四回発表)
このように、天皇の症状は概して悪化していった。そしてついに快方に向かっていないとまで発表されるにいたったのである。
国政の停滞は、このままでは必然だった。そのため慎重な審議が行なわれ、一九二一年一一月二五日、弱冠二〇歳の皇太子・裕仁親王が摂政に立てられることになった。そのときの詔書はつぎのとおりだった。
朕、久きに亙るの疾患に由り、大政を親らすることを能はざるを以て、皇族会議及枢密顧問の議を経て、皇太子裕仁親王、摂政に任ず。茲に之を宣布す。
これで全文である。ずいぶんとあっさりした内容で、あらためて大意を示すまでもない。天皇はこの決定に関わっておらず、正親町実正侍従長が、天皇用の印籠(「可」「聞」「覧」と記された印を入れた箱)を摂政に渡すため持ち出そうとすると、抵抗したといわれる。
先程侍従長は此処に在りし印を持ち去れり。
これは、その後間もなく謁見した内山小二郎侍従武官長が、天皇より聞いた言葉だった。「持ち去れり」という表現から、不本意な気持ちが読み取れる(四竈孝輔『侍従武官日記』)。
なお、摂政任命の詔書とともに、第五回の病状発表が行なわれた。その内容はこれまでになく赤裸々だった。天皇は生来病弱で、「脳膜炎様の御疾患」「重症の百日咳」「腸チフス」「胸膜炎」などに罹っていたが、践祚以後は政務の多忙も加わり、近年ついに「御脳力御衰退の徴候」を呈するにいたった。そして、体重などには問題ないとしつつも、こう続けた。
「御記銘、御判断、御思考等の諸脳力漸次御衰へさせられ、御考慮の環境も、従つて狭隘とならせらる。殊に御記憶力に至りては、御衰退の兆最も著しく、加之(しかのみならず)御発語の御障碍あらせらるゝ為め、御意思の御表現甚だ御困難に拝し奉るは、洵に恐懼に堪へざる所なり」
敬語を多用しつつも、かなり厳しい表現といわざるをえない。それにもかかわらず、天皇は同年一二月八日、四竈孝輔侍従武官に、
己れは別に身体は悪くないだろー。
といっていた(『侍従武官日記』)。天皇は病状の自覚がなかった。それはかえって事態の深刻さを如実に物語っていた。
* * *
続きは、『天皇のお言葉~明治・大正・昭和・平成~』をご覧ください。
天皇のお言葉

明治・大正・昭和・平成の天皇たちは何を語ってきたのか? 250の発言から読み解く知れれざる日本の近現代史。
















