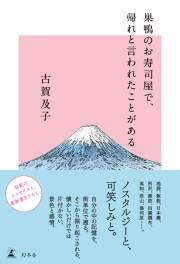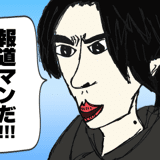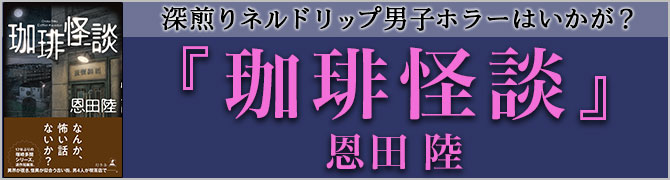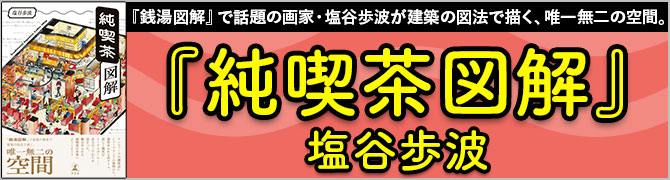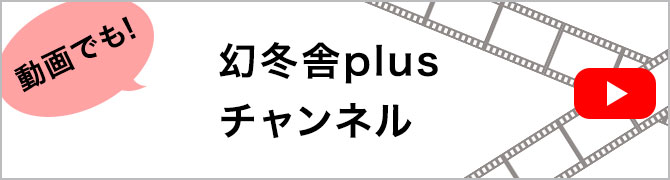気鋭のエッセイスト・古賀及子さんの書き下ろしエッセイ『巣鴨のお寿司屋で、帰れと言われたことがある』より、18歳の頃、祖父母と1泊で諏訪旅行したときの思い出です。

諏訪、祖父と間欠泉
父方の祖父は、取りまとめと段取りの鬼だった。
何事も事前の調査と準備を怠らず、立案内容はぬかりない。報告連絡相談に気を配り、身の回りのすべてにおいて整理整頓を徹底させて目を配る。不測の事態にさらされ、予定のA案の雲行きが怪しくなれば、即座にB案に切り替えるし、なんならC案、D案まで用意する、強靭な運営力を誇る。未来はもちろん過去もきれいに整えるのが祖父流で、取り仕切ったプロジェクトが完了したあとは、たとえそれが仕事じゃない、プライベートでも趣味でもボランティアでも、写真入りの細かなレポートを作って関係者に行き届くよう手配した。
大正七年生まれ。もとは陸軍の軍人で、戦後は商社でサラリーマンをしながら長く将校会の世話役をつとめた。同期のみなさんとの会合や旅行は折に触れ祖父が取り仕切っていたらしい。段取り力が買われてのことか、それとも携わりながら身につけたのか。
私は十八歳の頃、この祖父が祖母と暮らす東京の品川区の家に居候として転がり込んだ。自宅が埼玉県の山奥にあって東京の短大に通うのに難儀して、都心暮らしの祖父母に泣きついたのだ。
ありがたいことに歓迎してもらい、私は祖父母宅の空き部屋で寝起きするようになった。祖父母は家の一階のみを使って暮らし、二階は洗濯物を干すのに祖母がベランダに出るくらいだったから空いていた。
私は五人きょうだいの長子として育った。実家を出て祖父母のところにやってきた時点でまだ一番下の弟が六歳だ。父は仕事で忙しく、母は小さな子どもの世話に追われてあまり上の子らに構うことができず、ざっくりいうと私は「せねばならない」ことに、ほとんどさらされないまま実家の世界でやってきた。
毎日体を洗わねばならないとか、髪を洗わねばならないとか、爪は切らねばならないといった清潔観念にまったく薄く、勉強をせねばならない、知識をつけねばならないといった向上心もない。もちろん両親はご飯を食べさせてくれたし、体を壊せば心配して看病してくれたけれど、外で体を動かして体力をつけねばならないといった、健康にまつわる圧力もかかった覚えはない。
結果的に、私は極めて野生的な存在として、それなりの年齢まで育ってしまった。
髪の毛はからまって鳥の巣のようだ。顔も洗わず歯も磨かず、パンツとブラジャーの存在は知っていたけれど、その上に着る下着のことは長く知らなかった。靴下もほとんど履かない。家から出るように促されることがないため、野生の荒々しいさまでずっと家にいた。
自分をまるっきり整えないまま、ただ存在すれば許される時間をやりすごしてきた私だから、居候として受け入れた祖父母はずいぶん驚いたようだった。
使ったものを片さねばならないことも私は知らず、入居時に祖父の手で片付けられ掃除され、すっきりときれいだった部屋はすぐに散らかって、足の踏み場もなくなった。様子を見にきた祖父は驚き困惑していた。
「使ったものは、元あった場所に戻すと散らからないんだよ」と、祖父にとっては当たり前だろうことを丁寧に何度も教えてくれるのだけど、当時の私はそれがどういう意味なのか本当にわからない。ぽかんとしてあいまいにうなずいて結局そのままだった。
ちょうど携帯電話が普及した頃で私も契約していたから、よく学校の友人と長電話をするのだけど、電話をする私の声が大きいこともまた祖父を驚かせた。
「電話をするときは意識して小声で喋らないと、人の声というのは電話口では自然と大きくなるよ」と祖父は教えてくれた。知らなかった。
箸の持ち方も祖父に習った。私は漢字が全然書けなくて、祖父は字引きをくれた。出かけるときはハンカチかハンドタオルを持つと、手を洗ったときや汗が出たときにふけて便利だとも教えてくれた。私はそれまで、手を洗ったあとは髪でふいて、汗は下敷きを顔に垂直にあてて切っていた。歯を毎日朝と夜に磨いたほうがいいというのも、祖父に説得されて身につけた。 あるとき、祖父が将校会の旅行に出かけてお土産を買ってきてくれた。
たわしで作ったリスの置物で、お土産屋で見つけたものだという。祖父の連隊は笠宮崇仁三(みかさのみやたかひと)親王のお付きの武官が集まっていて、戦後もずっと親王のお供をしていた。リスの置物を「殿下もいかがですか」と伺ったのだけど、「ちくちくするものは好かない」とおっしゃったとのことで、へえ、などと聞いていたら祖父が急に、「旅行を計画してみなさい」と言う。
「計画について、ちょっと勉強したほうがいいから」と。
皇室の話題がなんで私に計画の立て方を教える話になるのか。祖父は自分がこんなにしっかりとした段取りをもって計画して大きな旅行を取りまとめて充実を得ているのに、この孫はなんでここまであれこれの脇が甘いのだと、あらためてはっとしたのではないか。
それで数ヶ月後の秋、祖父母と私で長野県の諏(す)訪(わ)に一泊で紅葉を観に行くことになった。諏訪に、というのは祖父がその近くに山荘を持っており、水回りの修理の様子を見るついでがあったからだった。 旅の費用は祖父が出してくれるというから贅沢な話で、にもかかわらず驚くことにというか案の定というか、私はのらりくらり電車の予約も宿の予約も先送りにしてあいまいに過ごし、結局は気を揉んだ祖父が全部手配してくれたのだから情けない。私は祖父に対してちょっと、そんなこと家族の旅行で練習しなくてもちゃんとできるのにと思ったのではなかったか。外の世界を知ろうとせず、自信だけは妙にあった。
一泊二日の諏訪旅行は両日よく晴れた。初日に電車で諏訪まで着くとまずはホテルに荷物を置いて、祖父がその段取り力をもってして事前に手配した観光タクシーに乗る。友人のつてでベテランの運転手さんにお願いできたと祖父が言うとおり、おっとりして優しい運転手さんが、素人目にも穴場とわかる紅葉スポットを連れて回ってくれた。こんな道をタクシーで登るのかと、砂利道をごとごと揺れながらタクシーは走る。もみじといちょうの紅葉が美しい狭い道路へ入って登ると崖に出た。向こうの山の一面が真っ赤に紅葉している。「すばらしい」と祖父がうめいて、祖母はお土産にと落ち葉を少し拾って文庫本にはさんだ。私は絶景を持て余してとりあえず深呼吸する。
それからよどみなくタクシーは本来の目的である祖父の山荘へ、様子の確認のために向かった。山荘の前には管理所のスタッフの方が待ってくれていて、修理は万事抜かりなく進行しているとのこと。山荘は当時すでに築年数を重ねてがたがたで、祖父は折をみては焦らず少しずつ修理しているようだった。祖父が亡くなったあとも祖母は毎夏この山荘へ避暑にやってきた。祖母が九十八歳まで生きたのは、夏を山荘で過ごしたおかげで猛暑を何年もまともにくらわなかったからじゃないかと、葬式の日にはみんなで噂した。
山荘を後にし、タクシーは諏訪湖の間欠泉の前に私たちを降ろして去った。それなりにあちこちにあるらしいけれど、間欠泉というのを私はこの諏訪湖でしか見たことがない。一定の時間間隔で、熱湯と水蒸気をどーんと噴き出す温泉だ。間もなく噴出しますと知らせるアナウンスがあって見物エリアで待つと、ドドドドと湯気とお湯が噴き出した。お湯の柱はどんどん高くぶち上がり、うおおと見物客から歓声があがる。えっ、すごい、すごい。
祖父も祖母も見上げて笑っていた。祖父は満足すると喜んで笑う。声を上げるのではなく、ぎゅっと頬が上がって笑顔になる。
祖父の笑顔を確認した私も、もう一度噴き上がるてっぺんを見上げて、笑った。
「すっごいね!」
親とどこかへ出かけるということがもうほとんどなかった頃だ。祖父母に囲まれて一日連れられるようにあちこちへ行って、会う人の誰もかれもに穏やかに優しくしてもらって、私は終始、呆然としていた。これは、どういう一日だ。ホテルの、ぱりぱりに糊のきいたシーツとふとんカバーの間にはさまって、天井を見る。祖父母はもう眠っていた。この旅の意味をつかみかねて迷うような気持ちをじりじりと手放すようにじっくり寝入る。
翌日、ホテルを出ると峠の釜めしで釜めしを三つ買って帰った。このあたりの名物だ。陶器の釜入りで重いけれど、食べたいかと聞かれて、食べよう、私が持って帰ると言ったのだった。道中、私が祖父母にできることは何もなかったから、最後に三個の釜めしを運ぶことができて、それくらいでもせめて気持ちは救われた。
長野からの特急を降り新宿まで戻り、山手線に乗って自宅につながる私鉄への乗り換え駅まで行く途中、近くに立った若い男性が連れの男性に、自分がいかに勉強ができて難しい資格試験を簡単にクリアできそうかと話すのが聞こえた。もうそれなりの年齢なのに、祖父母に守られて呑気な旅行をなんの負担もなく不安もなくしてきたばかりの私とは、その男性は真逆のように思えて、ちょっと顔を見た。よく日焼けして、坊主頭をしていた。
帰って釜めしを食べた。祖父母の家のあたりは戸建てがぎゅっと詰まって建つ。台所とダイニングテーブルがある一階は、日が当たらずいつも暗い。そんな部屋で蛍光灯に照らされて、釜めしの杏と栗があざやかだ。おいしいねえ、及子が頑張って持って帰ってきてくれたおかげだねえと祖父母は口々に言った。
この旅で私が何か変わったかといえばそういうこともなく、だらしなく祖父母の世話になり続けた。その後、一人暮らしの機会を得て祖父母の元を離れてからも、決まらない生活を続けて、でもやっと徐々に生きることの地ならしをはじめる。
祖父が八十五歳で亡くなった五年後、私は子どもを持った。生まれた子を抱いて、例の山荘を目当てに諏訪を再訪した際に、間欠泉のあのとんでもない迫力と祖父の顔を思い出した。
諏訪湖の間欠泉は、もともと昭和五十八年に行われた温泉の掘削中に噴出し、その当初は五十メートルも噴き上がったらしい。時代が進むとともに徐々に噴出の間隔が広がり、高くも噴き上がらなくなって、再訪の頃はコンプレッサーを使い人力で噴出させているのだと案内があった。
二度目の間欠泉の噴出は、祖父母と一緒に見たのに比べて半分以下の高さだったけれど、子どもは喜んで頬を上げて笑った。
巣鴨のお寿司屋で、帰れと言われたことがある
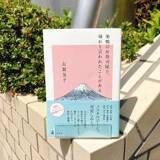
ノスタルジーと、可笑しみと。
池袋、飯能、日本橋、所沢、諏訪、田園調布、高知、恐山、湯河原……。
自分の中の記憶を、街単位で遡る。そこから掘り起こされる、懐かしいだけでは片付かない、景色と感情。
気鋭のエッセイスト、最新書き下ろし。
『好きな食べ物がみつからない』が話題の、最注目のエッセイスト・古賀及子最新書き下ろしエッセイ。
幼い頃からの「土地と思い出」を辿ってみたら、土地土地、時代時代で、切ない! でもなんだか可笑しいエピソードが横溢!