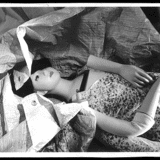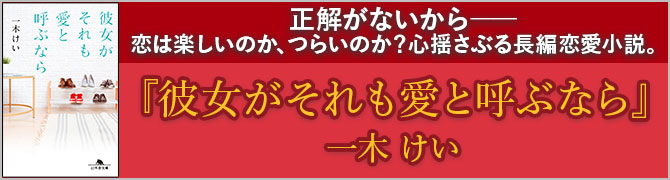今年2019年6月にリリースした僕のアルバム「ざわざわ」(ソニーレコーズ)が先日、第57回レコード・アカデミー賞(音楽之友社・主催)現代曲部門の受賞盤に選ばれました。
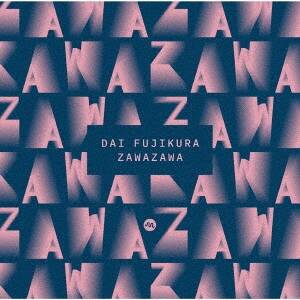
作曲家藤倉大の最新作品集。「世界にあてた私の手紙」(2016)、「チャンス・モンスーン」(2017)、『ダイヤモンド・ダスト』(2018)に続いて4作目。タイトルにもなっている「ざわざわ」は、山田和樹指揮する東京混声合唱団によるもの。藤倉さんが東京混声合唱団のレジデントアーティストに就任して初めての委嘱作品として有名。
僕は一応クラシック音楽の世界の作曲家で、曲だけ作っていればいいようなものなのに、自分の作品を集めたアルバム作りに精を出し、自分で録音までするトラックもあります。
「でさ、なんでそこまで録音にこだわるの?」
僕の録音に費やす労力、録音にまつわるほとんどの作業を自分でやりたい、というマニアっぷりを側で見ている演奏家の友たちがよく言います。
クラシック音楽には、もともと「生演奏をしてなんぼ、それを聴いてなんぼ」という価値観が強い。録音はそこから派生した、まさにおまけのようなもの。
ところが僕の友人のポップミュージシャン、デヴィッド・シルヴィアンがかねがねこう言っています。
「ポップスとは正反対だね」
つまりポップスは「録音してなんぼ」ということ。だから彼らはレコーディング・アーティストと呼ばれるわけです。
ポップスはライヴで演奏を聴く見るより、録音で聴く機会のほうが圧倒的に多いのです。
もちろん僕の音楽がポップスほど多くの人に聴かれることはないと思いますが、クラシック現代音楽という小さな世界でも、生演奏より録音で聴くほうが多そうです。
特に今はネット環境さえ整っていれば録音ならいつでも聴けます。
だからこそ僕は録音に熱意をかけてアルバムを作りたい。
僕が、個々のプレイヤーに演奏してもらった録音を自分でミックスダウンして好み通りの音響に仕立て上げる——それは作曲した時間よりも、おそらく演奏家が作品を演奏するために費やした練習時間よりも遥かに時間がかかる作業です。
永遠に終わりのない世界でもあります。
それでもその労力を費やした彼岸には、僕の耳が納得する音が流れる世界が待っている。他の人にはどう聴こえるかはわかりませんが、そう信じてひたすら作業しています。
録音した音を自分好みに音響処理すると一気に立体的、ある時は鼻先を引っ掻き、ある時は首のあたりをジュワーっと温かい液体が包んでくる(単に温泉に行きたいだけかも)、そしてある時は足の裏を冷やっとなにかが触ったと思ったら、そのあとドーンと背を押して宙に浮く。そんな音作りができるんです。いや少なくても僕は目指しています。
ここまで読んでいただいてわかるかもしれませんが〈僕が聴きたい録音〉とはクラシック音楽の普通のレコーディングエンジニアが作る音とは全然、違うようです。
なので最近は僕のアルバムではなく、演奏家が自分のアルバムに僕の曲を収録してくれる時も「藤倉さんならどうしますか?」とミックスダウンについて訊かれます。
僕がミックスした音源を「参考」として送ると、そのレコード会社のチームとどうやら正反対なものであるようです。
時には「うちの会社としては、こういうミックスだと藤倉さんの曲のトラックだけちょっと浮くので、今回のアルバムには収録できないけど、これはこれで、なんとか別の形で出したいですね」と言ってくださるレーベルの人もいます。
今から思うと19歳だったか大学生の頃、まだ僕が自分のパソコンを持つ前からこういう作業は、当時レコード・プロデューサーとしても活躍していた僕の作曲の先生の家のスタジオで、作曲のレッスンもしてもらわずにひたすら先生から録音技術について教わりながら指図(?)もして自分の曲の録音を自分好みの響きに作り上げる作業に没頭していました。
今もその延長。
こうやって自分の、CDという「録音物」が、今年の1枚として選んでもらえたのは作品そのものを褒められるより嬉しいことです。
藤倉大の無限大∞

ロンドン在住、42歳、作曲家。これまで数々の著名な作曲賞を受賞してきた藤倉大の、アグレッシブな創作生活の風景。音の世界にどっぷり浸かる作曲家は、日々、何を見、何を感じるのか。