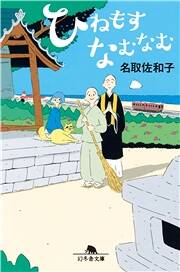自分に自信のない若手僧侶・仁心(にしん)は、岩手の寺の住職・田貫(たぬき)の後継としてはるばる高知からやってきた。田貫は供養の為ならゲームもやるし、ぬいぐるみ探しもする少々変わった坊さんだった。面倒に巻き込まれつつも師として尊敬しはじめる仁心だが、田貫には重大な秘密があり……。切なさに胸がギュッ、泣けて元気の出る小説『ひねもすなむなむ』(名取佐和子著、幻冬舎文庫)から試し読みをお届けします。
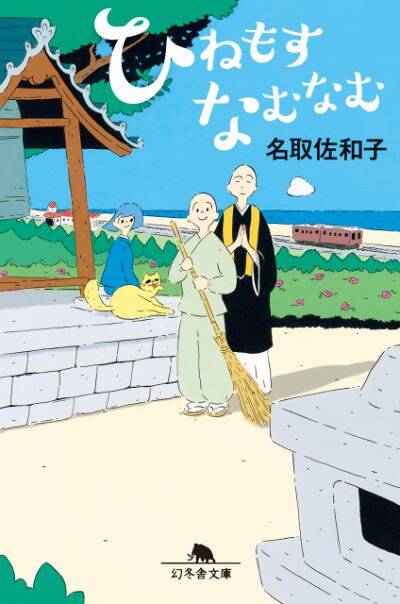
登場人物

木戸仁心(きど・にしん)
高知からはるばる岩手までやってきた若手のお坊さん。自分に自信がない。料理好き。

田貫恵快(たぬき・けいかい)
鐘丈寺の住職。スラっと飄々としている。供養のためならなんでもやる。

名無しくん
タヌキにそっくりな近所の野良猫。どこにでも現れる。
* * *
#2
「あはは。僕は田貫だけど、タヌキじゃない。正真正銘の人間です。紛らわしくてごめんね」
恵快は笑いながら上体を起こす。糸のように細くなったたれ目が印象的な笑顔だ。白くてつるりとした肌は、剃髪の似合うきれいな頭の形とあいまってゆで卵に似ている。三十八歳と聞かされている実年齢よりだいぶ若々しい、青年のような僧侶だった。
仁心達とは少し距離を取って、茂みの近くに座っているタヌキを指さし、恵快はつづける。
「ちなみにあっちは正真正銘の猫です。体つきや毛色は、タヌキそっくりだけどね。このあたりを縄張りにしてる野良猫で、名前はまだない。僕は“名無し君”って呼んでます」
次々と流れる情報を追いかけて、うなずくのが精一杯の仁心の肩を叩き、恵快は糸のようなたれ目のまま言った。
「長旅で疲れたでしょう。晩ごはんを用意したから、どうぞ」
恵快は本堂よりややさがって右隣に建つ、木造二階建ての古めかしい建物に仁心を案内した。昔ながらの和風家屋に見えるそこが、僧侶が寝起きし、寺務所も兼ねる庫裏だという。
滑りのいい引き戸をあけると、広々とした土間が見えた。恵快は跳ねるようにあがっていってしまう。なんだか飄々として、現実味の薄い住職だ。タヌキに化かされている可能性を捨てきれないまま、仁心はキャリーケースを土間に置いてあとを追った。
長い廊下は明かりがついておらず、暗い。よく磨かれて黒光りしている床は冷たく、分厚めのスポーツソックスを履いていても、足の裏から体温を奪われた。仁心は、裸足で悠々と廊下を踏みしめていく恵快が信じられない。並んだドアには“寺務所”や“客殿”といったプレートがそれぞれついていた。
「住職一人の寺だと、プライベートはあってないようなもんですか」
仁心の質問に、恵快は「まあそうねえ」とうなずいたあと、あわてて振り返る。
「でも、真夜中とか早朝とか、非常識な時間に訪ねてくる人はいないから。安心してね」
「だいじょうぶです。ここに来るって決めた時点で、覚悟はできてます」
仁心の言葉に、恵快は苦笑いを浮かべたが、それ以上何も言わなかった。
廊下の突き当たりにある引き戸が細くあいていた。なかから温風と光が漏れてくる。

「食堂の戸はちょっと建て付けが悪くなってきていて、あけしめに力がいるんです」
恵快はよいしょと細い腰を落として、引き戸を一気にあけはなった。一瞬にしてあたたかい空気といいにおいに包まれ、仁心のお腹が鳴ってしまう。
「──すみません」
「謝らなくていいよ。もうこんな時間だもの。お腹も空いたでしょう。晩ごはんにしようね。仁心君は座っててください」
恵快はにこにこ笑って仁心にダイニングチェアをすすめ、自分はカセットコンロが置かれた食卓に土鍋をセットし、また厨房に戻っていく。
「今日は仁心君の歓迎会ってことで、お鍋で、にぎやかに──」
「あ、俺、手伝います」
包丁を左手で持った恵快の手つきが危なっかしくて、仁心は座ったばかりの椅子から立ちあがる。恵快は特に断りも恐縮もせず、場所と包丁を仁心にすんなり譲り渡した。
仁心はシンクに置かれた厚揚げと大根と白菜と里芋を見まわし、尋ねる。
「これらを鍋の具材にするんですね」
「うん。スープはこの白味噌と豆乳で。桜葉さんがね、鍋料理なら住職にも作れるだろうって教えてくれたんだ」
「ああ、桜葉さん。面談では大変お世話になりました」
ここまで来る途中さんざん疑心の対象にしたことは伏せて、仁心はしれっと感謝を口にした。この気持ちも嘘ではない。そして住職を名乗る恵快の口から桜葉の名前が出たことで、仁心はようやく鐘丈寺が現実に存在していることを信じられた。タヌキによる大がかりな採用ドッキリじゃなくてよかったと心底ホッとする。
恵快はどこまで仁心の気持ちを汲めているのか、ふふふと笑いながら肩をすくめた。
「その桜葉さんがせっかく書いてくれたレシピの紙を、どこかにやっちゃって──」
ごそごそ作務衣のポケットを探っている恵快を尻目に、仁心は包丁を持ち、里芋の皮をむきはじめる。その慣れた手つきと速さに、恵快は目を丸くした。
「仁心君、お料理上手だねえ」
「上手かどうかはわからんけど、料理は好きです。前の寺では炊事係をしてました」
仁心の言葉に、恵快が目をかがやかせる。彼が今何を考えているか、仁心はたやすく読み取れた。だから、自分から申し出る。
「もしよかったら、こっちでも炊事を担当させてください」
「お、助かる。炊事も担当してもらおう」
「も?」
聞き咎めた仁心の肩を、恵快が気安く叩いた。
「未来の住職は、鐘丈寺でのお仕事すべてを知ってなきゃあ」
その言葉の意味するところを考えると、仁心はうまく応じられない。恵快は気にした様子もなく、仁心の知らないメロディを口笛で吹きながら、食卓に箸を並べた。
仁心は恵快に断ってから冷蔵庫をのぞかせてもらい、残り物らしい人参としめじを取りだす。
「これも鍋に入れてしもうてええですか。歯ごたえにバリエーションが出て楽しいき」
「どうぞ、どうぞ。今日からここは、仁心君の台所だよ」
恵快の大げさな表現に、仁心は苦笑してみせたが、内心嬉しかったし、新しい寺と初対面の住職に馴染めるかと不安だった気持ちがだいぶ落ち着いた。

野菜を次々と切っていく仁心のそばに、恵快が寄ってくる。
「僕は料理の何が苦手って、切るのがダメだね。絶望的に下手なんだ」
仁心は恵快の包丁さばきを思い出し、「ですね」と言いそうになるのをどうにかこらえた。
「この包丁は右利き用ですから。住職は左利き用を使えばええんやないですか」
「え。包丁にも左利き用とかあるんだ? ギターみたいだね」
恵快は驚いた様子だったが、買いたいとは言わなかった。
仁心はそんな恵快に頼んで、出汁用の昆布にハサミで切り目を入れてもらう。子どものお手伝いみたいだが、恵快は嬉々としてやってくれた。
鍋底に昆布を敷き、切った野菜をすべて入れると、それらがひたる程度まで水を注ぐ。
さらに仁心は粗塩を目分量で振り入れ、カセットコンロの火をつけた。

この調子や、と自分に言い聞かせる。料理をすれば、台所を知れる。台所を知れば、人と親しめる。人と親しめば、その寺に馴染める。仁心は高知で身につけた寺で生きるコツを、ここ岩手の鐘丈寺でも使おうとしていた。
野菜に火が通るのを待っているあいだに、仁心は箸が三膳出ていることに気づく。
「もう一人おるんですか?」
「うん。そこに座ってる。仁心君は見えないの?」
「ええっ」
仁心が飛びあがるのを見て、恵快は嬉しそうに笑った。
「仁心君、さては怖がりだね? ふふ、冗談だよ。もうじき桜葉さんがやって来るんだ」
図星を指され、仁心は能面のような顔で鍋蓋を取る。野菜がよく煮えたのをたしかめてから、もくもくと白味噌を豆乳で溶き、まわし入れた。煮汁を小皿にすくって味見すると、黒胡椒をざりざりと振りかける。
「できあがりです」
仁心の言葉に、恵快は子どものように両手を突きあげ、やったーと喜んだ。仁心が「熱いですよ」とわざわざ注意して取り分けた厚揚げを一気に頬ばり、仰け反る。
「口のなか火傷したみたい」
「いわんこっちゃない」
「でもいいんだ。おいしいから。おいしくごはんを食べられるのが、僕は嬉しいから」
恵快が本当に嬉しそうに言ったその言葉に、仁心の心はしんとする。思わず箸が止まったのを湯気の向こうから気取られないよう、仁心は鍋から新しい厚揚げをすくって、恵快の取り皿に入れてやった。
仁心が二度目のおかわりをしたところで、玄関の引き戸がひらく音がした。同時に大きな声が響きわたる。
「おばんでござんす」
* * *
先を読みたい方はぜひ『ひねもすなむなむ』で!
試し読みは、まだまだつづきます。次回をお楽しみに。
ひねもすなむなむ

自分に自信のない若手僧侶・仁心は、岩手の寺の住職・田貫の後継としてはるばる高知からやってきた。田貫は供養の為ならゲームもやるし、ぬいぐるみ探しもする少々変わった坊さんだった。面倒に巻き込まれつつも師として尊敬しはじめる仁心だが、田貫には重大な秘密があり......。後悔のない人生なんてない。「今」を生きるための力をくれる物語。