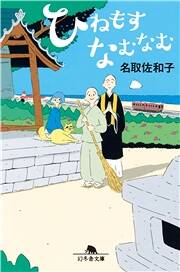自分に自信のない若手僧侶・仁心(にしん)は、岩手の寺の住職・田貫(たぬき)の後継としてはるばる高知からやってきた。田貫は供養の為ならゲームもやるし、ぬいぐるみ探しもする少々変わった坊さんだった。面倒に巻き込まれつつも師として尊敬しはじめる仁心だが、田貫には重大な秘密があり……。切なさに胸がギュッ、泣けて元気の出る小説『ひねもすなむなむ』(名取佐和子著、幻冬舎文庫)から試し読みをお届けします。
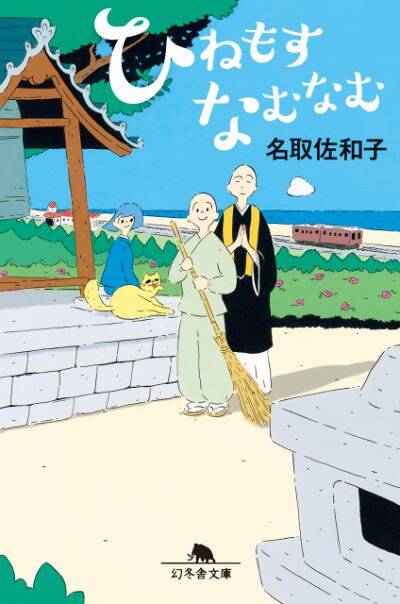
登場人物

木戸仁心(きど・にしん)
高知からはるばる岩手までやってきた若手のお坊さん。自分に自信がない。料理好き。

田貫恵快(たぬき・けいかい)
鐘丈寺の住職。スラっと飄々としている。供養のためならなんでもやる。

名無しくん
タヌキにそっくりな近所の野良猫。どこにでも現れる。
桜葉虎太郎(さくらば・こたろう)
スキンヘッドで色黒、恰幅までいい檀家総代。五香社という葬儀会社を営む。
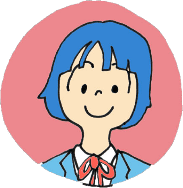
桜葉千蓮(さくらば・ちれん)
檀家総代の孫。女子高生。ゲームが得意。祖父には秘密にしていることがある。
* * *
#5
千蓮はぱたぱたと足音を立ててまず運転席にまわりこみ、恵快に頭をさげる。
「じっちゃん、お酒のんじゃったんですね。すみません」
「お酒は、僕がすすめたんだ。今日は、ウチの新しいお坊さんの歓迎会だったから」
「あ、ついに来たの、新人さん」
千蓮はきょろきょろと見まわし、自分の祖父に肩を貸す仁心にやっと気づいたようだ。
あわてて厚みのない体を折って挨拶した。近い距離で向き合うと、ずいぶん背の高い少女だと気づく。百七十三センチの仁心が目線を下げずに話せるくらいの位置に顔があった。
顔がとても小さく、骨格も華奢なので、威圧感はないが、百七十センチは超えているかもしれない。
夜の黒にくっきり浮かびあがる白い肌は、祖父の虎太郎の肌とは対照的だ。少し赤みをおびた丸い頬とこけしみたいなボブヘアとあいまって、いかにも雪国の少女といった印象を受ける。天賦のモデル体型を全然活かしきれていない幼さは、傍目にはもったいないが、身内は安心だろう。たしかに箱入り孫娘だな、と仁心は納得しつつ、簡単に名乗った。
肩を貸す人が仁心から千蓮に代わると、虎太郎は「ただいまあ」と声を張りあげる。千蓮はしっかりとアーチを描く眉をひそめ、はいはいと聞き流した。
仁心は祖父と孫娘の眉の形がよく似ていることに気づく。眉だけでなく、ひょっとしたら気質も似ているのかもしれない。少し警戒を強めた仁心の視線を受けて、千蓮は「仁心、さん?」とまだ耳慣れないであろう名前を口にした。ぎこちない口調で精一杯の感謝を述べてくれる。
「鐘丈寺に来てくれて、ありがとうございます。わたし、住職とじっちゃんが求人で苦労してたの知ってるから──嬉しいです。歓迎します」
「いや、俺は、礼を言われるようなことなんて何ひとつ──」
仁心は口ごもった。同僚とうまくいかず龍命寺に居づらくなると共に、僧侶という職業にも限界を感じてはじめた転職活動で、他業種の面接もたくさん受けたなか、「ウチに来てください」と言ってくれたのが鐘丈寺だけだったなんて、とても正直には告白できない。
千蓮は恵快に向かって笑顔を作る。
「住職、お弟子さんが来たら、少しは時間が取れるでしょう? 今度、相談のってください」
「もちろんのるよ。時間がなくてものるさ。あ、でも千蓮ちゃん、仁心君はべつに僕の弟子じゃないよ」
じゃあ何? と首をかしげる千蓮に、恵快は朗らかに言いきった。
「鐘丈寺の仲間です」

こっそり耳をそばだてていた仁心はむせてしまう。仲間という空々しい言葉を、ここまであたたかく響かせられる恵快に驚いた。
千蓮は自分に身を委ねて船を漕ぎはじめた虎太郎の体を懸命に支えつつ、そっかそっかとうなずく。虎太郎の身幅の半分にも満たない華奢な千蓮を気遣い、仁心は声をかけた。
「一人でだいじょうぶ? お家の人を誰か呼んだら?」
えっ、と千蓮が困ったように目を泳がせた。寝ていたはずの虎太郎がぴくりと腕を震わせ、顔をあげる。阿修羅も逃げだすレベルのおそろしい形相だ。仁心はわけがわからない。
「一人でだいじょうぶだよ。それに、この家にはじっちゃんとわたししかいねえから」
ワンクッション置いたあと、千蓮はさばさばと答えてくれたが、仁心と目を合わせようとはしなかった。無理にあげたらしい口角が、ひくひくと震えている。虎太郎の血走ったどんぐり眼は圧を強くして、今にも焼き殺されそうな視線が仁心に突き刺さってきた。
仁心がおおいにうろたえ、目を泳がせていると、恵快からのんびりした声がかかる。
「そろそろ帰ろうか、仁心君」
誰もがその言葉にすがるように顔をあげ、「おやすみなさい」と言い合った。
帰りは車がないので、歩きだ。桜葉家から鐘丈寺までは、徒歩三十分ほどだという。
電車と飛行機を駆使した長旅の当日に、駅から鐘丈寺そして桜葉邸から鐘丈寺と、合計一時間以上のウォーキングを課せられた仁心は、膝が笑いっぱなしになっているのを感じつつ、恵快と並んで歩いた。
街灯は少なく、圧倒的に暗い道がどこまでもつづく。一歩踏みだすごとに、両脇の森林から、木々の黒いシルエットが生き物のように迫ってきた。人なのか獣なのかわからない鳴き声が響き渡り、仁心は闇の奥で自分達を見つめる視線まで感じはじめる。

ふだんなら怖くて大騒ぎするところだが、今夜の仁心は恐怖を上回る自己嫌悪に打ちひしがれていた。
「俺、桜葉さんトコで失言してもうたんですよね」
「失言ではないよ」
「そやけど──」
「あの日に亡くなったんだ」
恵快は少し息を切らしながら、千蓮の母親であり、虎太郎の娘だった女性が東日本大震災の犠牲になったことを教えてくれた。
「このあたりの被害はマシなほうだったらしいけど、それでもね、無傷じゃいられない」
鐘丈寺の山門も潰れたと聞き、仁心は二本の石柱がぽつんと立っているだけの鐘丈寺の入口を思い出す。うつむいて、暗い道を歩く自分の足元を見つめた。景色とともに生活や人生が一変した過去が、この地にはあるのだと思い知る。いつもと変わらぬ朝に「いってきます」「いってらっしゃい」と手を振り合ったのが最後の会話になった親子が、何組いたのだろう。仁心は東日本大震災という字面と津波の映像を一般常識として知っているだけの自分が、ことさらよそ者に感じられた。
仁心君と呼びかけられ、仁心はやっと顔をあげる。隣で恵快が腰をかがめるようにのぞきこんでいた。
「死は特別なことじゃないよ」
僧侶であり余命を知る者でもある恵快が言うと、重みが違う。仁心は背筋を伸ばして、次の言葉を待った。
「だからこそ、誰もが誰かの死を抱いて生きている。死はどれも違っていて、どれも尊く、せつない。僕ら僧侶はそのことさえ胸に刻んでおけばいいと思うんだ。いろんな人の死に、頻繁に接する仕事だからこそね」
「はい」
仁心は恵快の言葉を心の深い位置で受け止め、うなずいた。
歩きはじめて二十分ほど経つと、恵快の息づかいがますます乱れてきたのがわかった。
胸をおさえて呼吸するたび喉が鳴り、明らかに苦しそうだ。着物の袖口からのぞいた手首の痣が、刻印のように黒々とかがやき、仁心はどきりとさせられる。
「だいじょうぶですか。苦しいなら休憩しましょうか。あ、タクシーを呼べば──」
「ゆっくり歩いていけば問題ないよ。だいじょうぶ」
恵快は笑顔で言う。その顔色が白いのか青いのか、闇のなかではわからなかった。
「緩和ケアを選択して対症療法でやってるから、体はまだそこまでつらくないんだ。体力も残ってる。おかげで法要も日常業務も滞りなく執り行える。ぽっくりとは逝かないと思うから、安心してね」
「はあ」
頼りない返事をする仁心に、恵快は合掌して静かに告げた。
「世の中には、予期できない突然の死が溢れてる。そんななか僕は、臨終までの時間を明確にしてもらったんだ。ありがたいと思う。せっかくだから、いろいろ準備してから逝くよ」
そのあと、恵快は自分の言葉どおり、鐘丈寺までゆっくり歩ききった。一時間近くかかったが、笑顔のまま山門に辿り着く。そして仁心がそのままなかに入ろうとするのを、手で制した。
「ちょっと待って、仁心君。僕から先に入らせてもらっていい?」
「あっ、すみません。もちろんです」
礼儀の問題かとあわてて後ろにまわった仁心に代わって、恵快は大股で山門をくぐり、しだれた萩の低木に覆われた敷石に足をかける。そのまま後ろを振り返り、かぼそい明かりの下でにっこり笑った。
「おかえり、仁心君」

なんや、これが言いたかっただけかと肩すかしを食らいつつも、仁心の心はふわりと軽くなる。一足早い北国の春を胸いっぱいに吸いこんで恥ずかしさと照れくささをおさえこみ、小さな声で返した。
「ただいま、です」
* * *
先を読みたい方はぜひ『ひねもすなむなむ』で!
ひねもすなむなむ

自分に自信のない若手僧侶・仁心は、岩手の寺の住職・田貫の後継としてはるばる高知からやってきた。田貫は供養の為ならゲームもやるし、ぬいぐるみ探しもする少々変わった坊さんだった。面倒に巻き込まれつつも師として尊敬しはじめる仁心だが、田貫には重大な秘密があり......。後悔のない人生なんてない。「今」を生きるための力をくれる物語。