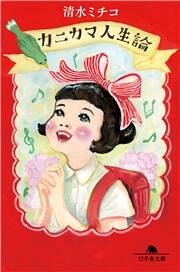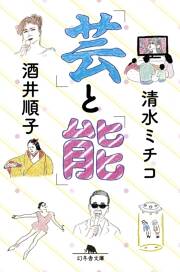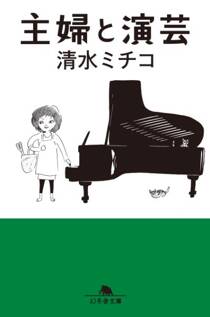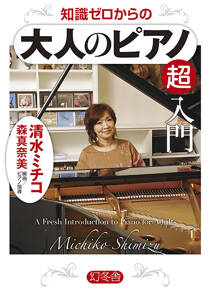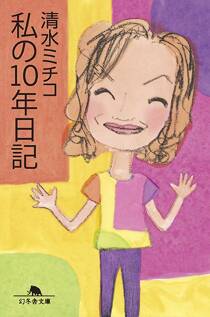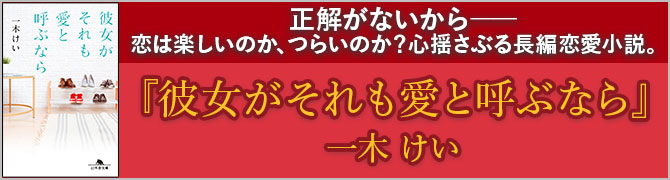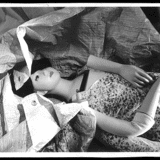
清水ミチコさんのエッセイ『カニカマ人生論』が文庫化されました!
“人生論”だけに、清水ミチコさんが背中を押してもらった「名言・迷言」の数々がちりばめられています。「背中を押すどころか、むしろヒクような話もたくさん」と清水さんは冒頭で書かれていますが……文庫化を記念して「よりぬき カニカマ人生論」を再びお届けします。
* * *
いよいよ、ジァン・ジァンでの私の初ライブが迫ってきました。「ぴあ」で自分の名前を確認すると、そこで初めて(本当に出るんだな)と、強く実感しました。出るのはわかっているのですが、改めて文字で確認すると、もうもどれないんだ、という決定的な気持ちになるんですよね。私の友人が、(夫と絶対に離婚する!)と強く決めてたのに、いざ離婚届の文字を改めて見ると、本当に別れるんだ、という現実が身に染みた、とぶっちゃけてたことがありましたが、よくわかる気がします。
「字」の持つ魔力って不思議ですよね。子供の頃に必ず学校で「将来の夢」を書かされたのも、「漠然とでいいから人生に目標を」という、さりげない親心だったのかもしれません。字にすることによって、初めて自分で自分の心をのぞき見ることができるという。
また話がそれてしまいました。本番当日の話です。客席はガラガラで、声をかけた知り合い20人ほどと、冷やかしで入ったらしきお客さんが2、3人。それでも私は楽屋でガチガチに緊張し、紙コップのコーヒーで温めても、指先がどんどん冷たくなりました。そして、いざ開演。何をしゃべったかはまったく覚えてませんが、10分ほどたった頃に、客席に大柄な男性が、静かにそうーっと入ってきました。ダウンコートがすごく目立ってて、私はライブを続けながらも、ふとその人の顔を見たら、永六輔さんだ! とわかりました。一瞬ひるむ私。
ところがです。またしばらくしてからふと見ると、ほかの人よりも(たまらん!)という風に、ものすごく体をねじって笑ってくださってるではありませんか。その大きな体を揺らしながら、たまに涙を拭いてます。私は自分でもみるみる自信がつくのがわかりました。そんなつもりはなくても、あれ以上の応援があるでしょうか。おまえは神か?(おまえとは何だ!)私は強気で行けました。
笑い上手という言葉があるなら、まさに永さんはそれでした。おなかから爆発するような笑い方は台風のようで、同時に人を幸せにし、場を浄化するかのような無邪気さがあります。客席はいつのまにか、永さんの笑い声につられて笑ってしまうという効果もあり、私もさっきまでの緊張はとうに消え、指先も気持ちもじんわり温かくなり、軽快にステージを降りました(ライブって最高だ!)。
翌日、連絡をいただき、永さんとお会いしました。あの姿を思い出しながら、(どんなに褒めてくれるだろうか)と期待したのですが、アテは外れ、注意の嵐で驚きました。「とにかく態度が悪いね。終わったあとに、おじぎもせず『ありがとうございました~』と言いながら、もう足の向きがステージを降りようとしてる。あれはよくない。芸人はね、どんなにふざけても始まりと終わりには、ちゃんと客席に向かっておじぎ、挨拶するもんなの」。そう言われて(芸人て! 私、芸人なのか? いやでも、こんな芸能のベテランがそうおっしゃるんだからきっとそうなのかも)という気になりました。今でもジャンルやカテゴリーなんて、人が勝手に決めるのでいいと思ってます。いくら「モデルです」と言い張ったって、「今日も落語やってね!」と、ずうっと言われ続けるんだったら、そっちではないか。需要と供給では、完全に需要がモノを言いそうです。
「あとキミ、名前を名乗ってなかったからね。最後まで」など、うっかりさもご指摘いただき、また「普通のモノマネだと、黒柳徹子クンなんか、高い声でキンキンまくしたてる人が多いんだけど、キミの耳には低く聞こえるのかと思って、そこはとっても驚いた」ともおっしゃってました。私は(あの黒柳さんのことをクンづけしておられる!)と、二人の信頼関係に軽く意識が飛びました。そして、「あなたね、まずモノマネの歴史って知ってるの? 江戸時代に門付と言ってね、」と、その流れるような話しぶりとうんちくは、話芸とはこのことかと思わされるような濃密さでしたが、「少しは自分で調べなさい」と、最後はチクリ。
「門付から始まって、そのあと声色って呼ぶ時代もあったけど、キミみたいにレパートリーに対して辛辣なモノマネってのは、歴代いなかった。普通は持ち上げるよ。だから新しいジャンルとして、職種名を作っちゃえば?」と、そこから一緒に考えてくださいました。厳しくて優しい。ホロリとしてるうちに、永さんは(そうだ)という顔で言いました。「ボイス・コピーはどう? 声のコピー」「はあ。そうですねえ」今考えたら笑っちゃいますけど。「職業は?」「ボイス・コピーです」「は?」ですよね。そして、結局最後に永さんが「そうだ、イミテーション・シンガーはどう?」と出してくれた言葉に、「それにします!」と返事をして、私のジャンルは決まりました。
しばらくはインタビューなんかで「職種は何になるんですか?」と聞かれれば、真顔で「イミテーション・シンガーです」と、恥ずかしげもなく名乗ってました。そして必ずそのあと「それはどういうことですか?」と、こちらよりももっと真顔で聞かれ、私もそれを「つまりですね」などと説明するうちに、だんだん面倒になってきました。1年後には、一番融通が利く「タレント」に変更(テキトー)。
永さんの言葉をメモしながら聞いてた私でしたが、永さんもまた、初日の感想をメモなさってたらしき手帳を開いては、「あ、そうだ。これも言わなくちゃ」と、たくさんダメ出しをしてくださり、最後にこう結びました。「とにかく、ひとことで言うとね。キミは芸はプロだけど、生き方がアマチュア」