
今年9月1日で発生から100年を迎える関東大震災は、民俗学や民藝運動の誕生、民謡や盆踊りの復興の契機になると同時に、愛国心を醸成し、戦争への流れを作った歴史の分岐点でした。7月26日に発売された『関東大震災 その100年の呪縛』では民俗学者・畑中章宏さんが、大震災が日本人の情動に与えた影響をその後の100年の歴史とともに検証。その一部を本書より抜粋してお届けします。
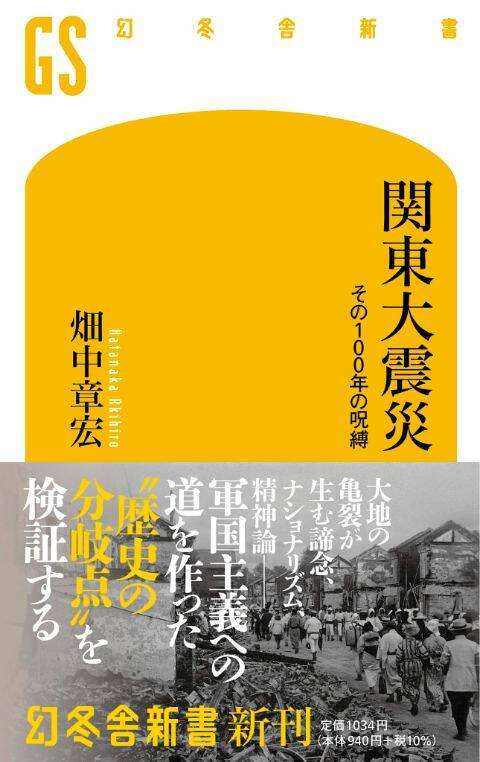
山の手の〈非当事者性〉
「大震災に遭遇した」「大震災を経験した」といっても、被害の度合いにより、その反応は大きく異なる。そしてその度合いは〈当事者〉と〈非当事者〉の断絶を生みだした。破壊的な状況を呈した「下町」にたいして、「震災記」を著した知識人、文化人の多くは「山の手」に住んでいたり、その時そこにいたりしたため、それほど震えなかったようなのである。
震災の当日、上野公園の竹の台陳列館(現在の東京国立博物館の南側、噴水と奏楽堂の中間付近)でおこなわれた二科展の会場とその周辺には、画家の津田青楓、小出楢重、安井曽太郎、有島生馬らがいた。彼らも激しい揺れに遭遇し、会場は混乱したものの生命の危機にさらされてはいない。
物理学者で随筆家の寺田寅彦(1878~1935)も同じ会場にいて、科学的感覚で震動を意識しつつ、自宅に戻った。
……宅に帰ったら瓦が二三枚落ちて壁土が少しこぼれていたが、庭の葉鶏頭はおよそ天下に何事もなかったように真紅の葉を紺碧の空の下にかがやかしていたことであった。しかしその時刻にはもうあの恐ろしい前代未聞の火事の渦巻が下町一帯に広がりつつあった。そして生きながら焼かれる人々の叫喚の声が念仏や題目の声に和してこの世の地獄を現しつつある間に、山の手ではからすうりの花が薄暮れの垣根に咲きそろっていつもの蛾の群れはいつものようにせわしく蜜をせせっているのであった。
(「からすうりの花と蛾」)
竹の台陳列館も寺田の自宅も、地盤の固い本郷台地にあり、台地の震動は少なかったとみられる。
火災や地震に関心を抱いていた寺田はその後、震災の実態を調査することとなり、火炎旋風の発生した時間と場所、発見者・遭遇者の談話、当日の気象状況、火災によって生じた積雲の写真と解説、周辺への飛来落下物などを、震災予防調査会の報告書に詳細に記録している。しかし、震災以降、地震科学を推進していくことになる寺田の潜在意識のどこかに、こうした震えなかった体験があったのではないか。

なお1891年(明治24)10月28日に発生した濃尾地震を契機に、その翌年に組織された震災予防調査会は、関東大震災に際して有効な対策を打ちだせなかったという批判を受ける。その後、東京帝国大学に専門の研究機関として地震研究所が設置され、1925年の震災予防評議会の設置とともに廃止された。
文学者たちのリアリティ
震災に遭遇した当時の文学者たちは、それぞれの文学思想、あるいは方法論により、地震の直後から、大災害のリアリティを追究し、記録を試みた。その代表的なものが1924年(大正13)4月に刊行された田山花袋(1872~1930)の『東京震災記』である。『蒲団』『田舎教師』などの作品で知られる自然主義作家は、大震災の状況を克明に記録し、作品化したのだ。
この本によると、花袋は地震が発生したとき代々木の家で、子どもたちと会話をかわしていた。
……そこにゴオという音が南のほうから響いて来たのである。
と、いつも地震などそんなにこわがらない長男が、ぐらぐらと来ると同時に、『オッ!地震』と叫んで、立上るより早く、一目散に戸外に飛び出した。弟も妹も母親もすぐそれにつづいた。私は少時しばらくじっとして様子を見ていたが、いつもと違って、非常に大きいらしいのに、慌てて皆なの後を追って飛び出していた。
それは何とも言われない光景であった。あたりはしんとした。世界の終りでもなければ容易に見られまいと思われるような寂寞が、沈黙が一時あたりを領した。誰も何も言うものはなかった。声を出すものもなかった。唯ただ、内から遁にげ出す気け勢はいばかりがあたりに満ちた。
女達は裏の竹藪の方へと遁げて行ったが、私と長男と次男とは、柿の樹と梅の樹とに身を凭よせたまま、怒濤の中に漂った舟でもあるかのように、自分の家屋のぐらぐらと動揺するのをじっと見詰めた。この時、前の二階屋の瓦は凄まじい響を立てて落ちた。
(『東京震災記』)
「さすが花袋」というべき描写力、表現力で、実際に同様の経験を関東の人びとは、記憶と体感をよみがえらせたにちがいない。また大地震を体験しなかった地域の人びとも、大震動をリアルに感じたことだろう。
花袋と家族はその後、家の外でお茶を飲んだり、葡萄を食べたりして、余震が静まってから、倒れた家具、瓦などを皆で片づけた。そうしているとだれかが、「このくらいですめば、そう大した大地震というほどのこともない……」と口にしたという。
……その間に、東京の市街の方では、あの大きな火災が起り、あの凄まじい火の旋風が捲まき上がり、何処に行っても全く火で、どうしても遁のがれることができずに、敢えなく焼け死んだものが数万の上にのぼるというような悲惨事が起っていたのであった。
(同前)
花袋の家も揺れはしたが、人的被害を受けるほどではなく、下町の被害との空間的、心理的な距離感を抱かせる。
1914年の転居から自殺に至るまで、東京府北豊島郡滝野川町字田端(現・東京都北区田端)に住んでいた芥川龍之介(1892~1927)の「大震日録」によると、芥川も大きな揺れを感じたものの、深刻な被害を受けていない。
芥川は昼ごろ茶の間でパンと牛乳をとり、お茶を飲もうとしたところで大きな揺れを感じて、母親とともに屋外に出た。妻の文ふみは2階で眠っていた次男の多加志を助けに行き、伯母のフキは梯子段の下に立って、妻と多加志を呼び続けた。芥川が妻と伯母と多加志とともに家の外に出ると、父の道章と長男の比呂志がいない。お手伝いのしづが再び家に入り、比呂志を抱いて出てきて、道章は庭を回って出てきた。
この間家大いに動き、歩行はなはだ自由ならず。屋瓦の乱墜するもの十余。大震ようやく静まれば、風あり、面を吹いて過ぐ。土臭ほとんど噎むせばんと欲す。父と屋の内外を見れば、被害は屋瓦の墜ちたると石燈籠の倒れたるのみ。
(「大震日録」)
妻・文の証言によると、芥川は妻と子を家内におき、真っ先に逃げ出したというが、それはともかく人も家も被害はほとんどなかったこともあり、芥川は自警団として活動することになる。
自警団について、言語学者の安田敏朗は「流言というメディア──関東大震災時朝鮮人虐殺と『15円50銭』をめぐって」で、各種の資料から、もともとは1918年の米騒動や社会主義思想の浸透といった事態に危機感を抱いた警察組織が「民衆の警察化」をはかるため、青年団や在郷軍人会などを軸に組織させた「警察の協力組織・補助機関」だったと指摘している。そして、少なくとも神奈川県下の自警団は関東大震災以前にすでに設立されており、もちろん震災後にも結成された。自警団の数は、東京1593、神奈川603、千葉366、埼玉300、群馬469、栃木19などあわせて3689所に達したという内務省調査があるという。
ところで、日本の近代文学史上で見たとき、関東大震災で亡くなった文学者は、鎌倉の別荘で津波に襲われた厨川白村(1880~1923)くらいだったといわれている。ただ白村も現代ではなじみが薄くなっている。そうすると関東大震災で亡くなった最も著名な人物は、震災そのものではなく、憲兵隊員によって虐殺された大杉栄と伊藤野枝にちがいない。
山の手に住んで、心の底から震えなかった人びとは、〈当事者〉であるにもかかわらず目を曇らせていき、〈当事者性〉をなおざりにしてしまう。彼らがなぜそうなったかといえば、災害のもつ〈事件性〉にたいして無自覚だったせいだろう。〈事件性〉の追究に意識を向けることがなかったために、さらに大きな問題に向きあうことができなかったのだ。
* * *
つづきは、『関東大震災 その100年の呪縛」をご覧ください。
















