
今年9月1日で発生から100年を迎える関東大震災は、民俗学や民藝運動の誕生、民謡や盆踊りの復興の契機になると同時に、愛国心を醸成し、戦争への流れを作った歴史の分岐点でした。7月26日に発売された『関東大震災 その100年の呪縛』では民俗学者・畑中章宏さんが、大震災が日本人の情動に与えた影響をその後の100年の歴史とともに検証。その一部を本書より抜粋してお届けします。
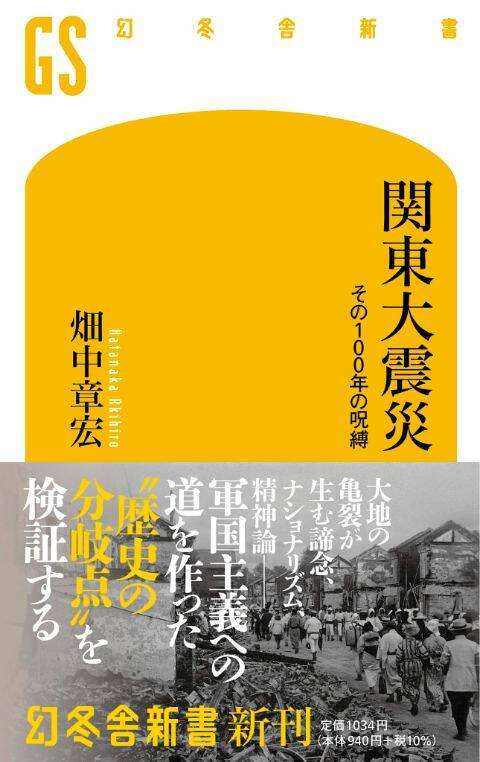
〈観察〉と〈傍観〉
日露戦争の際に従軍記者を務め、『第二軍従征日記』(1905年)を執筆していた田山花袋は、戦場で数多くの死体を見知っていた。そんな花袋でも、「醜悪な状態と腐りかけた臭気とには辟易し」、鼻をおおった。本所の被服廠跡にたどり着いた花袋を待ち受けていたのは、黒焦げになった夥しい数の死体の集積だった。
『まア、あんなものをわざわざ見て行かなくっても好いだろうに……』ふとこういう女の声が私のすぐ向こうでしたので、ひょいと私は顔を上げて見た。私はびっくりした。そこには黒焦げになった人間の頭顱(とうろ)が、まるで炭た団どんでも積み重ねたかのように際限なく重なり合っているではないか。『あっ、これだな! これが被服廠だな!』突差(とっさ)の間にも私はこう思った。
(『東京震災記』)
思わず声をあげた花袋の横では、その悲惨な光景を「レンズの中に蔵(おさ)めるために、大きな写真機などを抱えて、その方へと入っていくものも」少なくなかった。報道に携わる人びとが、われ先にと大挙して被災地に入ったのではないか。じつは彼らと同じように従軍記者として戦場を取材したことのある花袋だったが、どうしてもそれをまともに見ることはできなかった。
従って被服廠跡の悲惨な光景を私にたずねるものがあったにしても、私は『よく見なかった』とか『よく見るに忍びなかった』とかいうより他に為し方がなかった。私はその炭団の山をちらと見ただけで、そのまま急いでその傍を通ってしまった。
(同前)
『よく見なかった』『よく見るに忍びなかった』という表現を使っているものの、花袋は旺盛な好奇心で被災地に目を向けようとしていたことがわかる。しかし、作家は焼け野原になった東京を歩きまわることで、感情が揺さぶられ、異様な昂奮に包まれていくことも冷静に叙述するのだ。

花袋はいっぽうで、本所・回向院の真っ黒になった地蔵像の前で、「唯、地球の何処かが、時の調子でちょっと皺が寄ったかどうしたかのに過ぎない」という諦めの境地とともに、仏像に引きよせられている。安政江戸地震でも隅田川にさえぎられ、数えきれない人びとが苦しみながら焼け死んだのではなかったか。そしてまた、同じ過あやまちを繰りかえしてしまったことに、「どうしてこう人間は忘れっぽいのだろう?」と嘆いてもいる。
日本の近代文学史上、田山花袋は自然主義文学者の旗手として、リアリズムをモットーにする作家だとされる。そんな花袋がありのまま、思いのままを記した『東京震災記』は評判となり、当時からよく読まれた。
花袋の震災記録文学の魅力は、災害の悲惨を花袋の文学性がよく捉えているからであり、また小説作品にはない、ノンフィクションとしての物語性がじゅうぶんにいきわたっているからだろう。ただ、記録としてみたときには〈社会性〉には乏しく、客観的観察を口実にした傍観者の叙述にとどまっているともいえるのだ。
折口信夫の帰宅困難
まだ鮮明に記憶している人も少なからずいるはずだが、東日本大震災の際、東京とその近郊に住む多くの人びとが帰宅困難に陥った。しかし、関東大震災における帰宅困難は、強烈な時代相をおびたものだった。
民俗学者の折口信夫(1887~1953)は地震が起こったとき、沖縄から台湾に及ぶ民俗・民族採訪の旅から東京への帰途で、北九州の門司港にいた。折口が震災を知ったのは神戸港に停泊した9月2日で、その夜は大阪の実家に寄らず、横浜行きの船に乗りこんだ。そして、震災から3日経った4日正午に横浜港に上陸し、そこから谷中清水町の自宅まで歩いて戻ることになった。
大正十二年の地震のとき、九月四日の夕方ここを通って、私は下谷・根津の方へ向かった。自警団と称する団体の人々が、刀を抜きそばめて私をとり囲んだ。その表情を忘れない。戦争の時にも思い出した。平らかな生を楽しむ国びとだと思っていたが、一旦事があると、あんなにすさみ切ってしまう。あの時代にあって以来というものは、この国の、わが心ひく優れた顔の女子達を見ても、心をゆるして思うようなことができなくなった。
(「自歌自註 春のことぶれ」)
折口が自警団に取りかこまれたのは、芝の増上寺あたりだったようである。震災の混乱のなかで、朝鮮人が暴動を起こすという流言蜚語が広まり、自警を称して乱暴なふるまいに出るものが現われていたのだ。
折口は震災の翌年、横浜から谷中の自宅までの道すがらに見た光景と、そのときに沸きおこった感情を釈しやく迢ちよう空くうの号で「砂けぶり」という詩にうたった。「砂けぶり」は2篇からなり、とくにその「二」には折口が遭遇した状況が描かれている。
両国橋まで来た折口が、せめてもの安らいに橋の上から水の色を見ようとしたところ、「汚れ腐っていた」女性の水死体を見つける。
横浜からあるいて 来ました。
疲れきつたからだです─。
そんなに おどろかさないでください。
朝鮮人になつちまひたい 気がします
深川だ。
あゝ まつさをな空だ─。
野菜でも作らう。
この青天井のするどさ。
夜になつた─。
また 蠟燭と流言の夜だ。
まつくらな町で 金棒ひいて
夜警に出掛けようか
井戸のなかへ
毒を入れてまはると言ふ人々─。
われわれを叱つて下さる
神々のつかはしめ だらう
(「砂けぶり 二」)
「朝鮮人になつちまひたい」「われわれを叱つて下さる/神々のつかはしめ/だらう」という詩句からは、事態を認識することができず、〈災害〉を神話的に理解しようとする折口の苦渋をみることができる。
おん身らは 誰をころしたと思ふ。
かの尊い 御ミ名ナにおいて─。
おそろしい呪文だ。
万歳 ばんざあい
我らの死は、
涅槃を無視する─。
擾乱ジヨウランの 歓喜と
飽満する 痛苦と
(同前)
帰宅を急ぐ折口自身も、検問に呼びとめられ、身の上を問われることになる。そして、自分が日本人であり、自宅が東京にあり、横浜から歩いてきたことを説明して、ようやく解放されたのだった。
帰宅困難に陥った折口は、身の危険にさらされた事態を、それまで用いてこなかった四行詩(基本が四行からなる詩)によって表現した。この詩が難解に見えるのは、精神的、身体的なアイデンティティの崩壊にさらされた苦渋の記憶だからである。
* * *
つづきは、『関東大震災 その100年の呪縛」をご覧ください。
















