
今年9月1日で発生から100年を迎える関東大震災は、民俗学や民藝運動の誕生、民謡や盆踊りの復興の契機になると同時に、愛国心を醸成し、戦争への流れを作った歴史の分岐点でした。7月26日に発売された『関東大震災 その100年の呪縛』では民俗学者・畑中章宏さんが、大震災が日本人の情動に与えた影響をその後の100年の歴史とともに検証。その一部を本書より抜粋してお届けします。
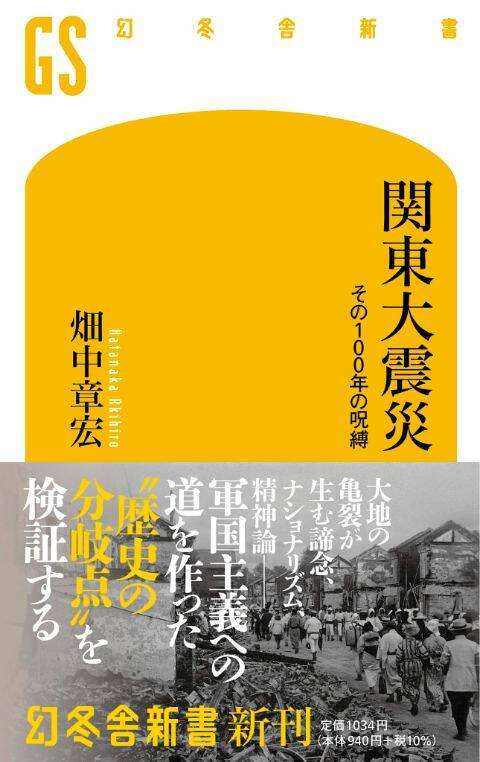
〈天譴論〉の発生
「関東大震災がなぜ起こったか」という疑問を科学を離れて無理につくり、大震災を堕落した社会への制裁とみなす〈天譴論〉を主張した人びとがいた。そのなかには実業家の渋沢栄一(1840~1931)やキリスト者の内村鑑三(1861~1930)などもいた。

日本資本主義化の推進者であり、当時のオピニオンリーダーともいうべき渋沢栄一は、震災直後に新聞紙上で次のように記した。
大東京の再造についてはこれは極めて慎重にすべきで、思うに今回の大しん害は天譴だとも思われる。明治維新以来帝国の文化はしんしんとして進んだが、その源泉地は東京横浜であつた。それが全潰したのである。しかしこの文化は果して道理にかない、天道にかなった文化であったろうか。近来の政治は如何、また経済界は私利私欲を目的とする傾向はなかったか。余はある意味において天譴として畏縮するものである。
(『報知新聞』1923年9月10日付夕刊)
こうした渋沢の〈天譴論〉にたいし、芥川龍之介が批判している。
この大震を天譴と思えとは渋沢子爵のいうところなり。だれか自ら省れば脚に疵なきものあらんや。脚に疵あるは天譴を蒙るゆえん、あるいは天譴を蒙れりと思い得るゆえんなるべし、されど我は妻子を殺し、彼は家すら焼かれざるを見れば、だれかまたいわゆる天譴の不公平なるに驚かざらんや。不公平なる天譴を信ずるは天譴を信ぜざるにしかざるべし。否、天の蒼生に、──当世に行わるる言葉を使えば、自然の我々人間に冷淡なることを知らざるべからず。
(「大震に際せる感想」)
大震災はブルジョアとプロレタリアを分かつことはなく、猛火は仁人と潑皮を分けへだてはしない。東京市民をあたかも「獣心」である、一切の人間を禽獣と選ぶことなしなどというのは、意気地なきセンテイメンタリズムにすぎないと芥川は言うのだ。
だれか自ら省れば脚に疵なきものあらんや。僕のごときは両脚の疵、ほとんど両脚を中断せんとす。されど幸いにこの大震を天譴なりと思うあたわず。いわんや天譴の不公平なるにも呪詛の声を挙ぐるあたわず。ただ姉弟の家を焼かれ、数人の知友を死せしめしが故に、已み難き遺憾を感ずるのみ。我等は皆歎くべし、歎きたりといえども絶望すべからず。絶望は死と暗黒とへの門なり。
(同前)
芥川は、「天譴なり」などという言葉を信じるべきではない、冷淡な自然の前に、「アダム以来の人間」を樹立し、「否定的精神の奴隷」となることがないようにと戒める。「アダム以来の人間」「否定的精神の奴隷」というきわめて文学的表現で、芥川は天譴論をなじる。
素朴であるがゆえに手に負えず、しかも、渋沢をはじめとする社会的有力者たちが「天罰」を口にしたことにたいし、感覚が鋭敏で理知的な文人は、難解なメタファーでしか応じることができなかったことになる。非常時においては、短絡的で類型的な言説が幅を利かせ、理性は疎んじられもするのだ。
なお渋沢栄一は、地震が起こったとき日本橋兜町の事務所にいた。事務所は倒壊をまぬかれたが大きなダメージを受け、渋沢もあわやのところを助けられる。そして隣の第一銀行で昼食をとった後、王子にある家に帰り避難している。
震災後には、「大震災善後会」を発足させて義損金を募り、海外にも呼びかけて、大企業関係者、経済界、商工会議所、教会関係の重要人物に電報を打ち、アメリカからは13万ドルを超える義捐金を集めた。また、臨時の病院を設けたり、炊き出しを実施したり、避難所などの対策にも取り組み復興に尽力していることを付けくわえておこう。
没落にたいするカタルシス
内村鑑三も婦人雑誌のなかで、この渋沢栄一の言を引用しながら、「実に然しかりであります。有島事件は風教堕落の絶下でありました。東京市民の霊魂は、その財産と肉体が滅びる前に既に滅びて居たのであります。斯かる市民に斯かる天災が臨んで、それが天譴または天罰として感ぜられるるは当然であります」と断言している。この引用に出てくる「有島事件」とは、作家の有島武郎が『婦人公論』記者の波多野秋子と心中した事件を指し、この事件は当時の世相をにぎわして、震災直前の話題を独占したスキャンダルだった。
震災を成金や資本家にたいする天譴と考え、彼らが一夜にして無一物になったことを「因果応報」だと捉え、彼らの没落にカタルシスを感じる人びともいた。
また東京朝日新聞の記者だった杉村楚人冠(1872~1945)は、こんなふうに記す。
地震で東京が焼けて一面の野原になってしまったのを見たとき、あわれなという感じよりも、何だかそうれ見ろといって見たいような気が腹のどこかやらでした。それが私ばかりかと思ったら、大分同じ思いをした人があるらしい。怪しからぬことかも知れぬが、実際そんな気がしたのだから仕方がない。
(「余震」)
そんな楚人冠もじつは震災で二人の息子を亡くしていたのだ。
* * *
つづきは、『関東大震災 その100年の呪縛」をご覧ください。
















