
100年前の9月1日に発生した関東大震災は、民俗学や民藝運動の誕生、民謡や盆踊りの復興の契機になると同時に、愛国心を醸成し、戦争への流れを作った歴史の分岐点でした。7月26日に発売された『関東大震災 その100年の呪縛』では民俗学者・畑中章宏さんが、大震災が日本人の情動に与えた影響をその後の100年の歴史とともに検証。その一部を本書より抜粋してお届けします。
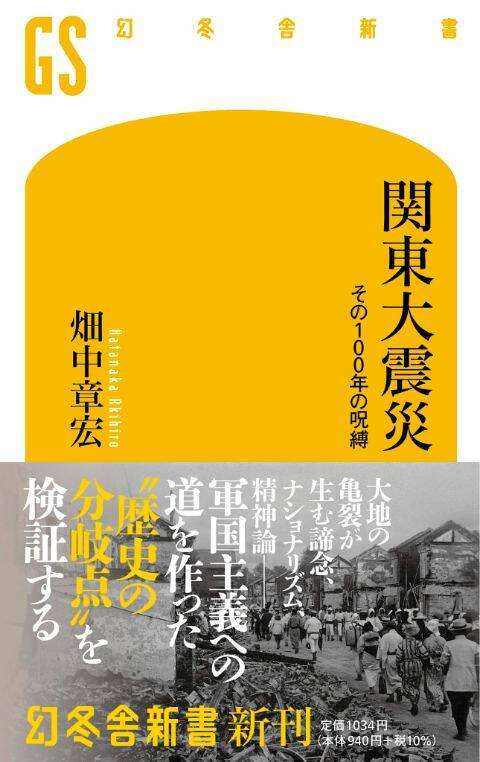
「いびつな近代」のはじまり
関東大震災は大規模な自然災害という側面とともに、さまざまな矛盾を露呈させた〈社会的事件〉だった。そして、ここでまた芥川龍之介に登場してもらい、震災後の日本の方向性を決めていった感情について述べておきたいと思う。
芥川龍之介の震災後の著作のひとつ「東京人」(雑誌『カメラ』初出時の題は「感想一つ」)には、こんなエピソードが記されている。
東京に生まれ、東京に育ち、東京に住んでいる僕はいまだかつて愛郷心なるものに同情を感じた覚えはない。また同情を感じないことを得意としていたのも確かである。
元来愛郷心なるものは、県人会の世話にもならず、旧藩主の厄介にもならないかぎり、いわば無用の長物である。東京を愛するのもこの例に洩れない。とかく東京東京とありがたそうに騒ぎまわるのはまだ東京の珍しい田舎者にかぎったことである。──そう僕は確信していた。
(「東京人」)
芥川は大地震の翌日、「野口君」といろいろな話をしたという。この「野口君」は、東京・日本橋の呉服商・染色家の野口彦兵衛の次男・野口真造である。呉服屋である野口も、この日はふだんのような元禄袖の紗の羽織は着ないで、火事頭巾のようなものに雲竜の刺し子こという装いだった。
芥川が「罹災民は続々東京を去っている」と言うと、
「そりゃあなた、お国者はみんな帰ってしまうでしょう。──」
野口君は言下にこういった。
「その代りに江戸っ児こだけは残りますよ。」
(同前)
という会話がなされた。
芥川は野口の言葉を聞いたとき、ある心強さを感じた。それは野口の服装のためか、空を濁らせた煙のためか、大地震におびえていたためかはっきりしなかった。その瞬間、芥川も〈愛郷心〉に似た勇ましい気持ちがし、心の底に、それまでは軽蔑していた「江戸っ児」の感情が、自分にもいくぶんか残っているらしいと思ったのだった。

こうした芥川の感情は、震災以前にはなかった〈郷愁〉が、未来への批判的展望を覆いかくしていったことを示しているのではないか。そして「江戸っ児(子)意識」とでもいうべき〈愛郷心〉はやがて〈大衆ナショナリズム〉につながっていくことになる。ここでいう〈大衆ナショナリズム〉とは下からの国家主義というべきものであり、震災によって震えた郷土にたいして生じた、それまでになかった郷愁が、やがて政治にからめとられていくのである。
文明史的転換の機会を失う
最後に取りあげた〈愛郷心〉の生成という事態を含めて、関東大震災には、次のような問題や感情が見える。
大災害に当事者性をもって向きあったかどうか。あるいは客観的観察、リアリズムを口実にした傍観者的態度も透けて見える。大災害を天災、あるいは天譴として合理化することは、未来の災害にたいする教訓になりえたのだろうか。混乱や流言蜚語に便乗して発揮される暴力性はスキャンダルにとどまったように思われる。
情報の取捨選択は、結果的に無関心に流れ、災害の〈中心〉と〈周縁〉をつくりだしていく。そして、眼前の破滅的状況は、諦念とともに観念的な郷愁(ノスタルジア)を生みだしていったのである。
関東大震災は〈近代化〉の途上にある日本の首都を襲うことで、文明史的転換に結びつく契機となる可能性をはらんでいた。また近代的意識にもとづく〈当事者性〉や、災害を〈事件〉として、あるいは〈社会現象〉として検証していく理性をもちえたかもしれない。しかし当時の人びとは批判的転換の機会を逃し、震災の呪縛にとらわれていくことになるのである。
* * *
つづきは、『関東大震災 その100年の呪縛」をご覧ください。

















