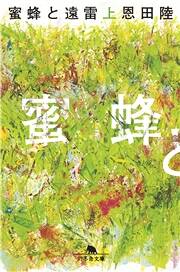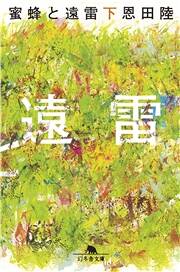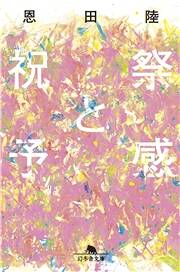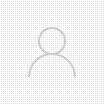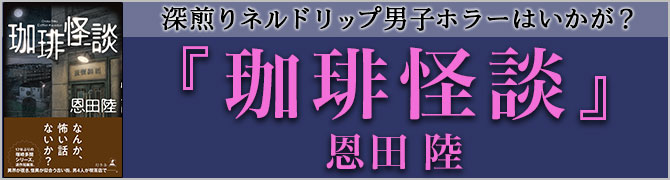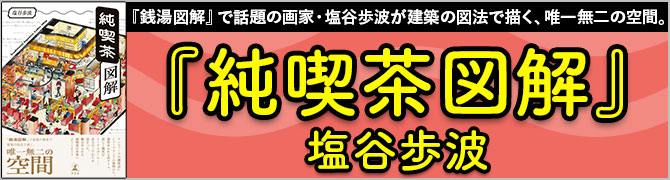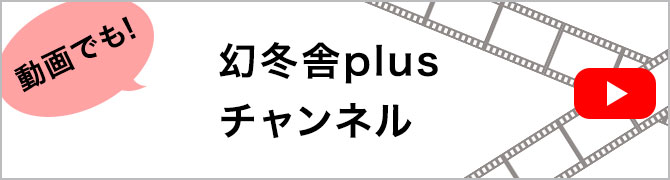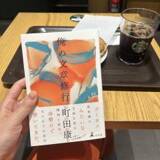
「『蜜蜂と遠雷』がなければ『spring』は書けなかった」
──ところで、『spring』にかんして「『蜜蜂と遠雷』を書いていなければこの作品は書けなかった」とおっしゃっています。それはどのような点で、意味で、でしょうか? 共通点ももちろんありますが、ベクトルが真逆だと感じた作品でもありました。
恩田 『蜜蜂と遠雷』を書かなければ、あそこまで意識的に音楽を聴くことはなかったと思います。耳を育てるには時間がかかるのだ、ということがよく分かりました。浜松国際ピアノコンクールを1、2回聴いただけでは、あの小説は書けなかった。
ものごとを消化し理解するには寝かせることも、繰り返すことも必要なんだと納得できたので、それは『spring』にも活かされました。

──3年おきの浜松のコンクールに5回、行きましたもんね。なるほど「耳を育てるには時間がかかるのだ」です。このフレーズも、まさに「恩田節」だ。
恩田 能動的に「聴く」という行為がいかに難しいか痛感しました。
──「耳を育てる」を、今度は「目を育てる」に変換したというわけですね。そうして出来上がった全四章立ての小説の、それぞれの話者、書き手(ナレーター)が異なる構成にびっくりしました。これは最初から決めていたことなのでしょうか。
恩田 はい。ただ、語り手を誰にするかは2人目の稔(みのる)さんまでしか決めていませんでした。
第二章で七瀬(ななせ)が登場して、「あ、次はこの子でいいじゃん」と第三章に決まったんですが、4人目がギリギリまで決まらず、ジャン・ジャメにしようか、それともここだけ三人称にしようか、と迷ったんですが、第三章まで書いても春という人物がよく分からなかったので、最後に「じゃあ本人に語ってもらおう」というので語り手が春になりました。
──師ジャン・ジャメが、話者として春について語るパートも読みたかったけど、実際、採用された春本人の語り(なのか意識なのかわかりませんが)のほうが、衝撃度がはるかに高いですね。『蜜蜂と遠雷』の連載中、わたしが「風間塵(かざまじん)の内面は書かないんですか?」と聞いたことがあって、そのとき恩田さんが「彼みたいなタイプの天才の内面は、天然すぎて書けない」とおっしゃったので、なるほどそうかもしれない、と納得したのですが。
恩田 その点、萬春は意外と普通の感覚を持っているところもあり、受け身のところもあるので、書けたというのはあります。
春のモデルは誰?
──わたしは、この人が主人公・萬春のモデルなんじゃないかな、と羽生結弦(はにゅうゆづる)さんを思い浮かべました。その思いはわたしの中で最終章でさらにくっきりしました。もちろん主人公にはいろいろなキャラクターやパーソナリティが溶け込んでいると思いますが、羽生さんが比重としてけっこう入ってたりしますか?
恩田 えっ、そうなんですか? びっくりです。一度も考えたことなかったなあ。私は全く違うイメージだったので。春にモデルはいないし、私の妄想イメージでしかなかったです。
──そうなんですね。違ったかぁ。モデルといえば、これもわたしの思い込みかもしれませんが、作曲家・七瀬パートだけでなく主人公にも、藤倉大(ふじくら・だい)さん(映画『蜜蜂と遠雷』でピアノ曲「春と修羅」を作曲)の要素をわたしは感じたのですが、これも気のせいでしょうか(笑)。
恩田 藤倉大さんの天才っぷりには圧倒されたので(そもそも私が作曲家という仕事に憧れているというのもありますが)、かなり影響は受けていると思います。参考にした部分もあります。特に七瀬はそうですね。でも主人公はそうでもないです。
──『spring』は、かなりの分量、音楽について言及した音楽小説でもありますね。まったく音楽のないバレエもありうるのか、バレエってやはり音楽がいっしょであることが大前提なんでしょうか。
恩田 20世紀最高の振付家のひとり、モーリス・ベジャールは、「踊りは見える音楽だ」とはっきり言っています。ですので、音楽は前提ですね。まあ、コンテンポラリーで無音のものはあるかもしれませんが。あくまでそれは演出のひとつ、ということでしょう。
──なるほど。ジョン・ケージ「4分33秒」で踊るとか、いいかもしれませんね(笑)。「無音ではない。沈黙を踊るのだ」みたいな。
恩田 それ、すでに誰かがやってそうな気がします(笑)。
取材相手に「言語化できない」と言われたが…
──ピアノ・コンクールの全体を描くという『蜜蜂と遠雷』の強固な構成(それゆえ書き手は窮屈だったはず)と比較して、『spring』の表現はシンプルかつ自由で、作者の、書きながら楽しんでいる様子が目に浮かびました。
恩田 コンクール期間、と限定されていた『蜜蜂と遠雷』に比べると、時系列も自由なぶん、制限はありませんでしたが、逆にくくりがないのは、それはそれでたいへんでした。一人のダンサーの成長というよりは、バレエそのものについて描きたかったので、どこまで広げていいのか悩んだ部分はあります。
──「バレエそのもの」について書きたかった場合に、『蜜蜂と遠雷』方式でなく、この書き方を採用したところが驚きです。ランダムに書いているように見せて、きっちり「なぜ」「何を」「どんなふうに」踊るのか、が見事に表現されていて、しかも面白い。
恩田 バレエ、あるいは芸術について多面的に語るにはこの手法かな、と思ったんですが、書いている時はやはり試行錯誤で、けっこう悩みました。
──一人の天才についてではなく、芸術を多面的に語るって、ものすごく高いハードルじゃないですか。とにかく言葉にしなきゃならないわけですからね。本文中に「言語化」という言葉・単語が何度か出てきますが、おっしゃるように、この小説は非・言語的なものを言語化する大挑戦だったと思います。こういうところが、いったん『蜜蜂と遠雷』を経験したおかげでいくらか易しくなった、というところでしょうか。
恩田 『spring』で最初に取材したコンテンポラリーのダンサーで振付家、金森穣(かなもり・じょう)さんにお会いした時、ものすごく明晰でなんでもきちんと言葉で説明なさる方なのに、「踊っている時のことだけは言語化できない」と言われ、私はガーンとショックを受けたんです。
でも、「いや、言語化できないものを言語化するのが自分の商売だ」と決意を新たにした、というのがありまして。
不安な中でも、『蜜蜂と遠雷』ができたんだから、これもなんとかなるだろう、と楽観的になれたのは、あの経験があったからだと思います。
──すごい心意気です。まさに作家の面目躍如と言ってしまえばそれまでですが、それにしても、これほど作中作として、バレエの、しかもオリジナル作品が多数出てくる小説は、空前絶後。すべて書き分ける恩田さんの膂力(りょりょく)にひれ伏したくなります。しかもそれが楽しかった、と。踊りのプロじゃないのに、頭の中で踊りのイメージが湧いてくるところが凄すぎます。
恩田 なるべくバレエ用語や専門用語は使わずに、読者に踊る場面を想像してもらいたい、という方針は『蜜蜂と遠雷』と同じでした。
次のページ:「人間の矛盾」についての作品
恩田陸氏インタビューの記事をもっと読む
恩田陸氏インタビュー
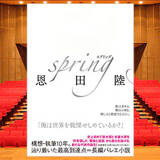
ひとことで言って、出てくる登場人物が全員、本当に全員、魅力的な最新刊『spring』(筑摩書房)。この小説の主人公が、天才男性ダンサーにして振付家でもある萬春(よろず・はる)だ。彼を少年時代から描いたバレエ小説が大好評の恩田陸さん。「『蜜蜂と遠雷』を書かなければ『spring』は生まれなかった」とも語る著者に、執筆の経緯や両作品の関係性、作品そのものについて、そして創作論まで、『蜜蜂と遠雷』の担当編集者が訊(き)いた。
撮影/砂金有美
- バックナンバー