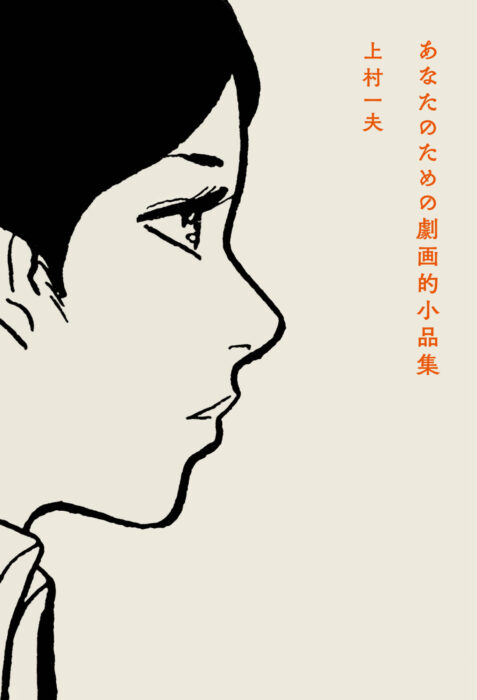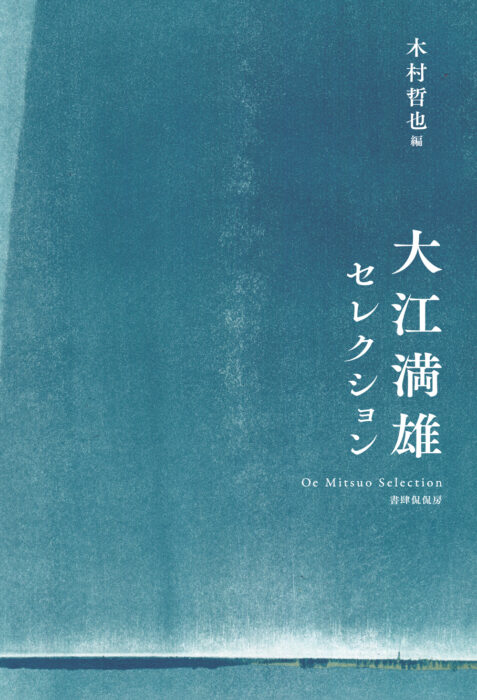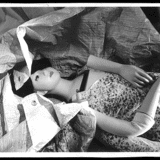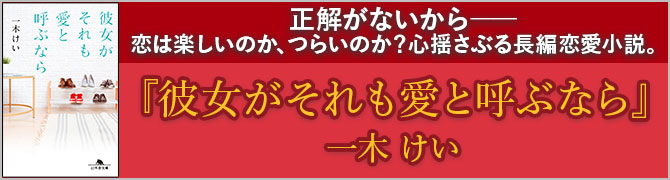忙しいとは、万事、気持ちに余裕がなくなることである。
早朝、時間通り羽田空港に到着し、神戸行きのチケットを発券しようと自動チェックイン機にQRコードをかざすと、何度やってもエラーが出て、そこから先に進むことができない。近くにいた係の人に「この機械、少しおかしいみたいですが」と尋ねると、彼はわたしのスマートフォンを覗き込み、表情を変えずにこう言った。
「これは神戸から羽田行きの便ですね」
いつもと微妙に時間が違っていたから、気になってはいたのだった。チケットの予約をしたのはその三週間ほど前。その時期は仕事が立て込んでいたから、よく確認もせず、実行ボタンを押してしまったのだろう。物事のひずみは、必ずどこかに出てくるものである。
三宮駅からバスに乗り、山の麓にある「杏杏」まで行く(飛行機のチケットは、何とか買いなおすことができた)。神戸は外食の文化が根づいている街で、中心街にはモーニングを出している喫茶店がたくさんある。しかし住宅地の中にまで、朝粥を出す小さな店があることには、その文化の歴史と奥深さが感じられた。中華粥と豚まんの朝ごはんを食べ終わるころには、気持ちは晴れやかなものに変わっていて、「これは外で食べる効能だ」と思った。
わたしの実家は、その店から十五分ほど歩いた平野という街にあり、いま家は空き家となり、売りに出されている。昨年の夏、家にあった荷物を仕分け、残ったものはすべて処分したので、家の中には何もない。そのがらんとした空間にいると、まだ自分の家のような、もう誰かほかの人の手に渡ってしまったような所在なさがあり、落ち着かなかった。
畳に座ると、昨年の夏、ここまで来たときのことが思い出され、その時からは一年という時間が流れている。わたしはその時間を東京で慌ただしく過ごしたが、そのあいだこの部屋にも、同じだけの時間が流れていたのだろう。
誰にも見られることのない時間とは、はたして重いのか、それとも軽いものなのだろうか。
なぜ人は、同時に違う場所にはいられないのだろう。

そのようなことを考えていても寂しくなるだけなので、外に出かけることにした。
人の姿をほとんど見かけることのない商店街を歩いていると、カラカラ音をたて、気持ちよく回っている床屋のサインポールを見かけた。普段であれば何も考えずそのまま通りすぎるところだが、その時は何か思うところがあったのだろう。表に値段は出ていなかったが、そんなに高くないはずとあたりをつけ中に入ると、手持ちぶさたの様子でいた店の夫婦のほうが驚いて、「さあさあ、どうぞこちらへ」「カバンはそちらの椅子に」などと、どっしりとした革の椅子にまたたく間に座らされた。
「お客さん、髪の量が多いので、少しさばいときますね」
最初、ご主人のさばくという言葉がわからなかったが、ああ、すくということかとすぐ納得した。子どものころは母がバリカンで髪を切ってくれたので、神戸で床屋に入った回数は考えてみれば数えるほど。そのころから、床屋には大人が行く場所というイメージがあり、髪を切りながらたわいもない話をするなんて自分にはとてもムリと思っていたのだが、いつの間にかわたしも、そうした初々しさのない年齢になってしまった。
「お客さん、このあたりのかたですか?」
東京から来ましたと言うと、なんでまたという顔をされたので、近所の〇〇町に実家があること、そこはいま空き家になっていて、定期的に様子を見に帰ってくることなどを話した。家を売りに出していることは、なぜか話せなかった。
壁に、見覚えのある構図の、雪を被った山の写真があった。
「あの山はエベレストですか」
実家にも、わたしが同じ角度から撮った写真が飾られていたから、すぐにわかった。紺碧の空を背景に、神々しく光る三角錐の山頂。
「ああ、よくわかりましたね。昔、ここに来ていた人がくれた写真でね。ゴーキョ・ピークでしたっけ? その場所から撮ったと、その人が見せてくれました。わたしがいいねって言ったら、大きく引き伸ばして、持ってきてくれたんです」
わたしが撮った写真も母が額装し、キッチンの壁に掛けられていたが、長い年月のあいだに油と埃がこびりつき、ついこのあいだ、ほかの荷物と一緒に処分した。
「その人は十年ほどまえにあっちに行ってしまったから、もうここには来られないんやけど」
この床屋は父親の代からやっていて、彼もここで生まれ育ったという。最近近くに小さな水族館ができて、孫がきたときには連れて行けとせがまれるらしい。
「またこちらに帰ってきたときには、お立ち寄りください」
わたしは少しためらいながら「はい」と答え、床屋をあとにした。散髪と髭剃りで、料金は三千三百円だった。
今回のおすすめ本
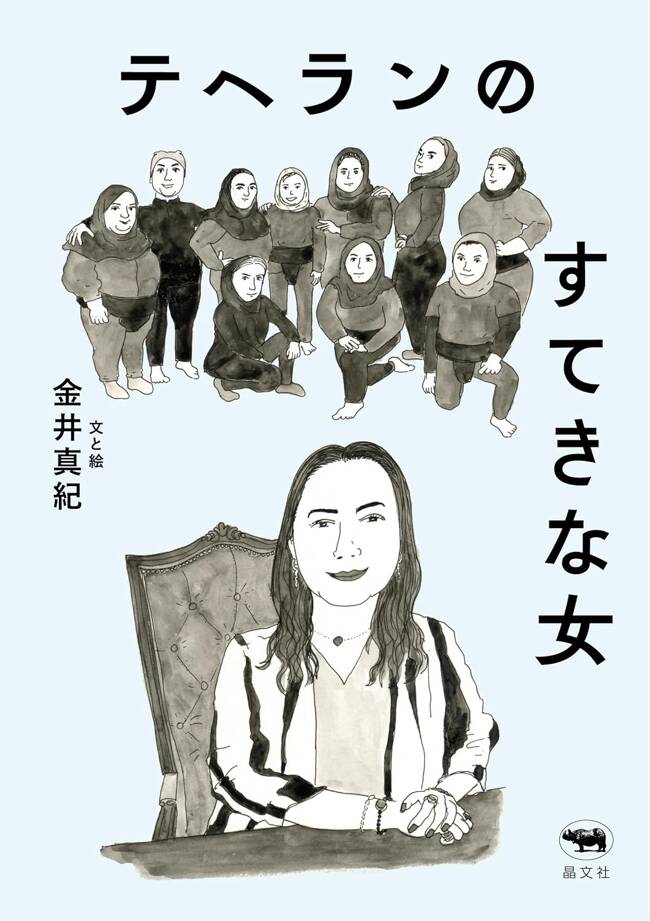
『テヘランのすてきな女』金井真紀 晶文社
人は外見だけではわからない。ヒジャブという覆いに隠された、彼女たちの素顔とは。その中に入ると、案外わたしたちと変わらない、「世界で一番かっこいい」女性たちがいた。
◯連載「本屋の時間」は単行本でもお楽しみいただけます

連載「本屋の時間」に大きく手を加え、再構成したエッセイ集『小さな声、光る棚 新刊書店Titleの日常』は、引き続き絶賛発売中。店が開店して5年のあいだ、その場に立ち会い考えた定点観測的エッセイ。お求めは全国の書店にて。Title WEBS
◯2025年3月14日(金)~ 2025年3月31日(月)Title2階ギャラリー
漫画家・上村一夫が1974年に発表した短編集『あなたのための劇画的小品集』の復刊にあたり、当時の上村作品を振り返る原画展を開催します。昭和の絵師と呼ばれた上村一夫は、女性の美しさと情念の世界を描かせたら当代一と言われた漫画家でした。なかでも1972年に漫画アクションに連載された「同棲時代」は、当時の若者を中心に人気を集め、社会現象にもなりました。本展では、『あなたのための劇画的小品集』と同時代に描かれた挿絵や生原稿を約二十点展示。その他、近年海外で出版された海外版の書籍の展示・販売や、グッズの販売も行います。
◯2025年4月5日(土)~ 2025年4月22日(火)Title2階ギャラリー
大江満雄(1906-91)は、異なる思想を持つさまざまな人たちと共にありたいという「他者志向」をもち、かれらといかに理解し合えるか、生涯をかけて模索した詩人です。その対話の詩学は、いまも私たちに多くの示唆を与えてくれます。
Titleでは、書肆侃侃房『大江満雄セレクション』刊行に伴い、著作をはじめ、初公開となる遺品や自筆資料、写真などを紹介する大江満雄展を開催します。
貴重な遺品や私信に加え、大江が晩年「風の森」と名付けて、終の棲家とした家の写真パネルなども展示。本書収録の詩や散文もご紹介します。
【店主・辻山による連載<日本の「地の塩」を巡る旅>が単行本になりました】
スタジオジブリの小冊子『熱風』(毎月10日頃発売)にて連載していた「日本の「地の塩」をめぐる旅」が待望の書籍化。 辻山良雄が日本各地の少し偏屈、でも愛すべき本屋を訪ね、生き方や仕事に対する考え方を訊いた、発見いっぱいの旅の記録。生きかたに仕事に迷える人、必読です。
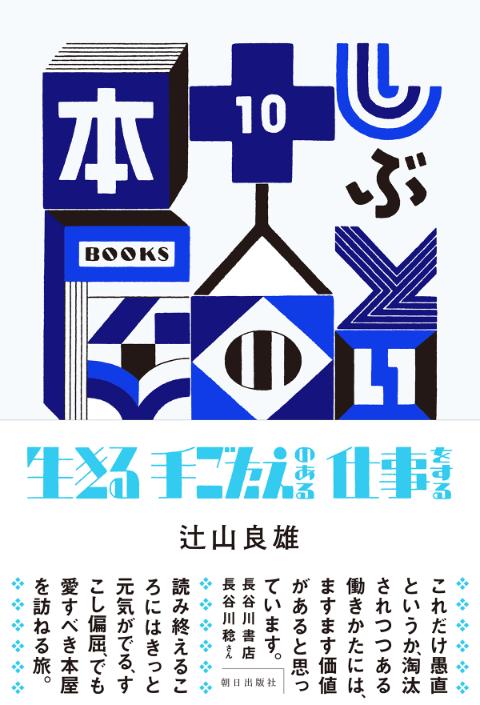 『しぶとい十人の本屋 生きる手ごたえのある仕事をする』
『しぶとい十人の本屋 生きる手ごたえのある仕事をする』
著:辻山良雄 装丁:寄藤文平+垣内晴 出版社:朝日出版社
発売日:2024年6月4日 四六判ソフトカバー/360ページ
版元サイト /Titleサイト
◯【書評】
『生きるための読書』津野海太郎(新潮社)ーーー現役編集者としての嗅覚[評]辻山良雄
(新潮社Web)
◯【お知らせ】
メメント・モリ(死を想え) /〈わたし〉になるための読書(4)
「MySCUE(マイスキュー)」
シニアケアの情報サイト「MySCUE(マイスキュー)」でスタートした店主・辻山の新連載・第4回。老いや死生観が根底のテーマにある書籍を3冊紹介しています。
NHKラジオ第1で放送中の「ラジオ深夜便」にて毎月本を紹介します。
毎月第三日曜日、23時8分頃から約1時間、店主・辻山が毎月3冊、紹介します。コーナータイトルは「本の国から」。1週間の聴き逃し配信もございますので、ぜひお聞きくださいませ。
本屋の時間の記事をもっと読む
本屋の時間

東京・荻窪にある新刊書店「Title(タイトル)」店主の日々。好きな本のこと、本屋について、お店で起こった様々な出来事などを綴ります。「本屋」という、国境も時空も自由に超えられるものたちが集まる空間から見えるものとは。