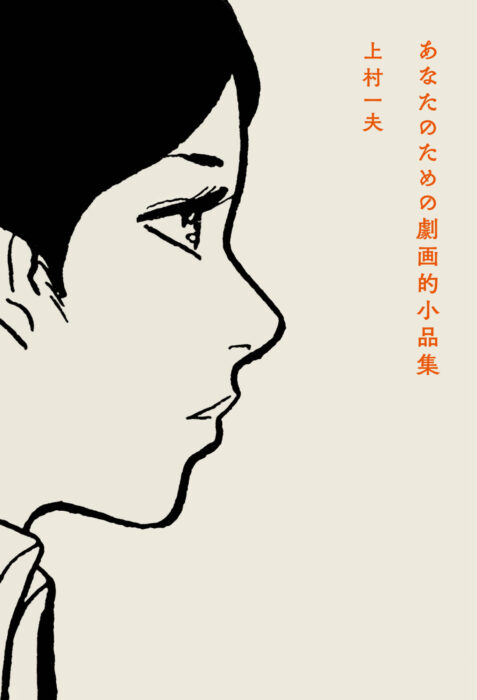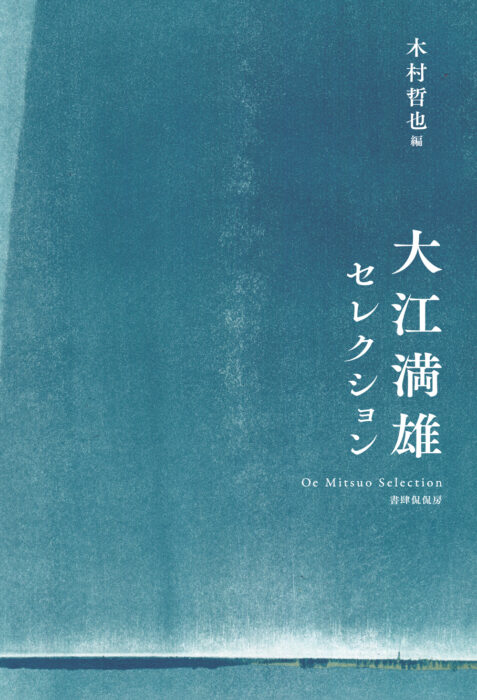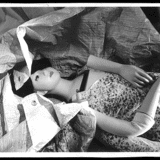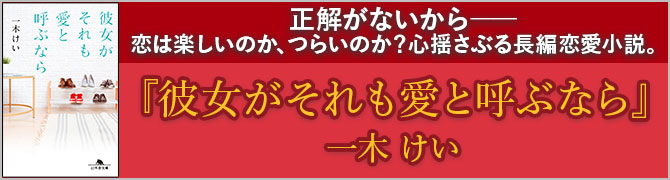今年は紫式部を主人公にした大河ドラマ『光る君へ』を毎週楽しみに見ているが、第三十四回の放送の中で、中宮・彰子がまひろ(紫式部)に対し、次のように言うシーンがあった。「そなたの物語だが、何が面白いのかわからぬ。男たちが何を言っているかもわからないし、光る君が何をしたいのかもわからぬ」。
彰子は何も、意地悪からそのように言ったのではない。それは彼女にとって素朴な疑問で、時の最高権力者・藤原道長の娘として大切に育てられた彰子は、まだよのなかというものがわかっておらず、したがって『源氏物語』に描かれた男女の機微もピンとこなかった。しかしその「光る君が何をしたいのかもわからぬ」という言葉には、わたしが長年『源氏物語』に抱いていた、かすかな違和感の在り処を示されたようで、目のまえが少し明るくなった。
大体が「源氏」に出てくる男君はみな、何をしたいのかよくわからない。彼らのほとんどは皇族か、貴族の中でも最も上流階級に属するエリートで、この国の政の中心にいるはずなのだが、色恋にうつつを抜かすか、さもなければよをはかなんで、ざめざめと嘆き悲しんでいるかのいずれかで、そこに強い信念や人生の目的を見つけることはできない。
でもいまのわたしたちだって、別の時代や違う文化圏にいる人たちからすれば、「ずっと小さな画面を見ているばかりの、何をしたいのかわからない人たち」だろう。そればかりか、この世界にいる多くの人は、自分でもほんとうのところ何をしたいのか、よくわかっていないのではないか。かといってそれを認めてしまえば、話はそこから先に進まないから、いかにも自分で決めましたという顔つきで、それらしくふるまっているだけなのだ。
彰子の何気ない言葉は、案外、人間の普遍というものを突いていたのかもしれない。

数年前、新宿西口の喫茶店で古い友人と会った。用件をひと通り済ませ、少し間が開いたあと、彼は少し躊躇いながらこう言った。「まあ俺は、早くこの世からいなくなろうと思ってるから……」。
わたしは突然のことに驚いて、何も言葉を返すことができなかったが、彼は「だって生きていても、この先何もええことなんかないやろ」と続けた。
彼は大企業の重要な役職についており、世間的には成功した人と見られているが、パートナーとの関係や子どもの進路など、ままならないこともあるようだ。だが彼の憂いは、そうした個人的なことに留まらず、多くの人に共通するもっと根深い場所から発せられたもののように思えた。
誰しも生きていればいつかは病気になる。
人間が地球を酷使した結果、気温の上昇は年々酷くなるばかりである。
世界のどこかでは今日も戦争が行われている。
そのような世界で、人は自分のしたいこともわからないままウロウロと生き、時間がくれば死んでいく。つらいばかりに思えるよのなかで、どうしてこの先も生きながらえていこうと思えるのか。『源氏物語』では巻がすすむにつれ、そうした憂いが深いものとなって現れるが、古今東西の文学は、多かれ少なかれこの無常観を主題にしていると思う。
だが、人になぐさめを与えることができるのもまた文学なのだ。
ドラマの中で、まひろは道長に、わが身に起きたことはすべて「物語の種」であると、作家としての決意を語りつつ、次のように続けている。「ひとたび物語になってしまえば、わが身に起きたことなど霧のかなた。まことのことかどうかもわからなくなってしまうのでございます」。
それは読む人にとっても同じで、たとえそれが「まことのこと」でなくとも、そこに明らかにされている憂きこころが、読むものの辛さやさびしさをなぐさめるのだ。文学は「何をしたいのかもわからぬ」登場人物たちを、何も言わずに包み込むが、それはそうした彼らの苦しみこそが、人間の持つ普遍的な宿業だからだ。
この物語が、作者の生きた時間をはるかに越え、いまも生きながらえている秘密は、案外そのようなところにあるのではないか。
今回のおすすめ本
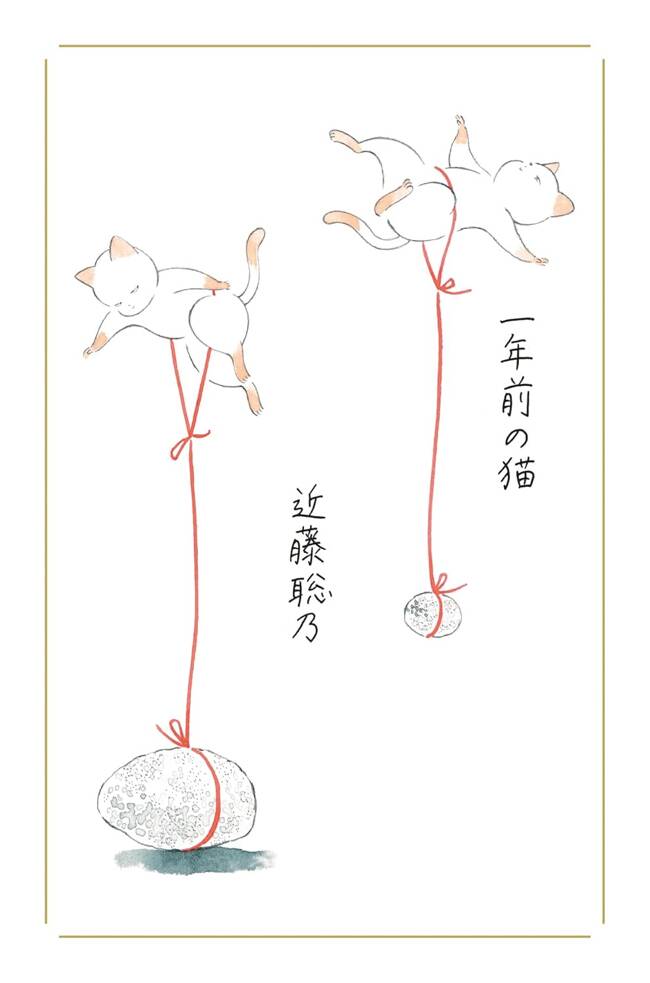
『一年前の猫』近藤聡乃 ナナロク社
猫は、人間とともに暮らしてきた生きものだ。我々のすぐ隣にいながら、我関せずと、その場所で独自の営みを過ごしている。そんなつかず離れずの距離感が、小さな一冊となった愛らしい本。
◯連載「本屋の時間」は単行本でもお楽しみいただけます

連載「本屋の時間」に大きく手を加え、再構成したエッセイ集『小さな声、光る棚 新刊書店Titleの日常』は、引き続き絶賛発売中。店が開店して5年のあいだ、その場に立ち会い考えた定点観測的エッセイ。お求めは全国の書店にて。Title WEBS
◯2025年3月14日(金)~ 2025年3月31日(月)Title2階ギャラリー
漫画家・上村一夫が1974年に発表した短編集『あなたのための劇画的小品集』の復刊にあたり、当時の上村作品を振り返る原画展を開催します。昭和の絵師と呼ばれた上村一夫は、女性の美しさと情念の世界を描かせたら当代一と言われた漫画家でした。なかでも1972年に漫画アクションに連載された「同棲時代」は、当時の若者を中心に人気を集め、社会現象にもなりました。本展では、『あなたのための劇画的小品集』と同時代に描かれた挿絵や生原稿を約二十点展示。その他、近年海外で出版された海外版の書籍の展示・販売や、グッズの販売も行います。
◯2025年4月5日(土)~ 2025年4月22日(火)Title2階ギャラリー
大江満雄(1906-91)は、異なる思想を持つさまざまな人たちと共にありたいという「他者志向」をもち、かれらといかに理解し合えるか、生涯をかけて模索した詩人です。その対話の詩学は、いまも私たちに多くの示唆を与えてくれます。
Titleでは、書肆侃侃房『大江満雄セレクション』刊行に伴い、著作をはじめ、初公開となる遺品や自筆資料、写真などを紹介する大江満雄展を開催します。
貴重な遺品や私信に加え、大江が晩年「風の森」と名付けて、終の棲家とした家の写真パネルなども展示。本書収録の詩や散文もご紹介します。
【店主・辻山による連載<日本の「地の塩」を巡る旅>が単行本になりました】
スタジオジブリの小冊子『熱風』(毎月10日頃発売)にて連載していた「日本の「地の塩」をめぐる旅」が待望の書籍化。 辻山良雄が日本各地の少し偏屈、でも愛すべき本屋を訪ね、生き方や仕事に対する考え方を訊いた、発見いっぱいの旅の記録。生きかたに仕事に迷える人、必読です。
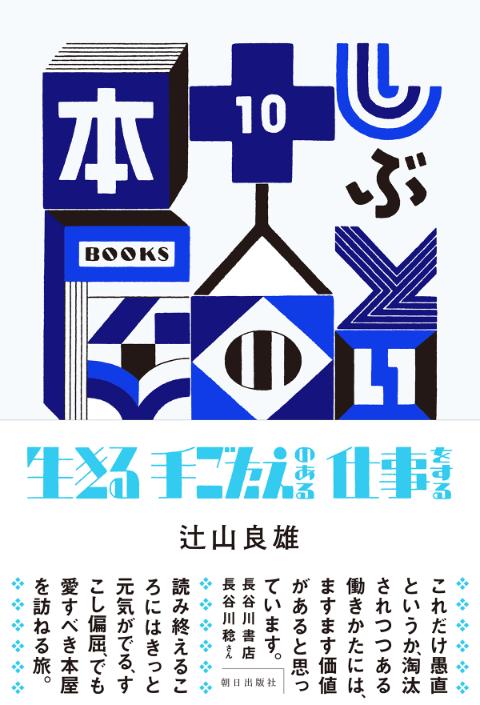 『しぶとい十人の本屋 生きる手ごたえのある仕事をする』
『しぶとい十人の本屋 生きる手ごたえのある仕事をする』
著:辻山良雄 装丁:寄藤文平+垣内晴 出版社:朝日出版社
発売日:2024年6月4日 四六判ソフトカバー/360ページ
版元サイト /Titleサイト
◯【書評】
『生きるための読書』津野海太郎(新潮社)ーーー現役編集者としての嗅覚[評]辻山良雄
(新潮社Web)
◯【お知らせ】
メメント・モリ(死を想え) /〈わたし〉になるための読書(4)
「MySCUE(マイスキュー)」
シニアケアの情報サイト「MySCUE(マイスキュー)」でスタートした店主・辻山の新連載・第4回。老いや死生観が根底のテーマにある書籍を3冊紹介しています。
NHKラジオ第1で放送中の「ラジオ深夜便」にて毎月本を紹介します。
毎月第三日曜日、23時8分頃から約1時間、店主・辻山が毎月3冊、紹介します。コーナータイトルは「本の国から」。1週間の聴き逃し配信もございますので、ぜひお聞きくださいませ。
本屋の時間の記事をもっと読む
本屋の時間

東京・荻窪にある新刊書店「Title(タイトル)」店主の日々。好きな本のこと、本屋について、お店で起こった様々な出来事などを綴ります。「本屋」という、国境も時空も自由に超えられるものたちが集まる空間から見えるものとは。