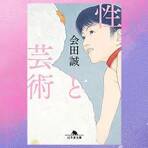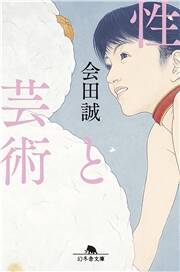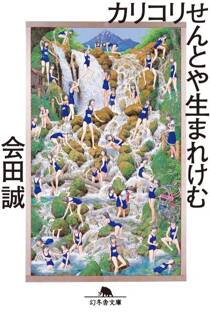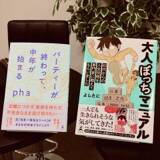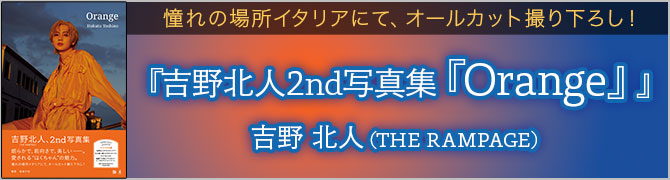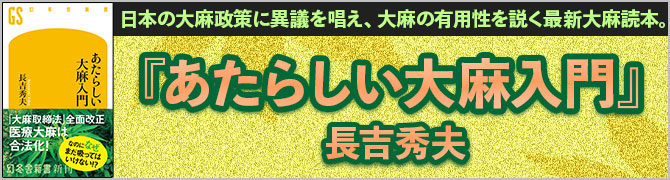日本を代表する現代美術家・会田誠による「犬」は、2012年森美術館展覧会での撤去抗議をはじめ、数々の批判に晒されてきた。裸の少女の“残虐”ともいえる絵をなぜ描いたのか――? その理由を作者自らが解説した『性と芸術』が文庫になりました。文庫版書き下ろし「僕の母親(と少し父親」」に加え、大野左紀子さん、二村ヒトシさんの解説を収録。単行本からさらに充実した内容です。
冒頭「はじめに」をお届けします。

『犬』全解説
本書のための書き下ろし。2021年12月24日脱稿。当日のツイートは以下のようなものだった。
「2年以上苦戦していた文章がさっきようやく書き終わった。ほぼ遺書だ。俺にメリークリスマス。」
はじめに
今から30年以上前の1989年、私が23歳の時に描いた『犬』という絵画作品について書いてみたい。『犬』はその後シリーズ化して、今までに計6作描いたが、それを1作ずつ丁寧に解説するという趣旨ではない。主に最初の1作目が発想された背景についてのみ、詳しく書くつもりだ。
なぜ書くのか。理由は主にネットである。
私はツイッターを2011年に始めてから、本格的にネット内の言葉に触れるようになった(遅かろう)。そこでは『犬』について語られることが(自作の中で相対的に)異様に多いことに気づいた。その大半が悪口である。
2012年に東京の森美術館における個展「天才でごめんなさい」で、『犬』シリーズを含む、私の性を扱った作品群を展示し、抗議活動が起こったことが大きな要因である。さらには、2018年に京都造形芸術大学(現・京都芸術大学)における社会人のための講座「人はなぜヌードを描くのか、見たいのか。」で、私が行ったレクチャーに対し受講者の一人が提訴したことも要因だろう。
ネットにはポジティヴであれネガティヴであれ、盛り上がる話題(政治、民族、差別など)と、盛り上がらない話題(真面目な美術論など)があり、「性」や「表現規制」の話題が前者であることはよくよく観察済みだった。表現規制に触れそうな性的作品を作ったのは自分であり、自分が蒔いた種であることは百も承知しているので、嘆きはしなかった。しかしそれにしても、なぜいつも『犬』ばかりなんだ、とは思った。『犬』以外にも性的な作品はいろいろあるし、性以外の問題を扱った危険な作品もいろいろあるのに……。
逆に「会田さんの絵の中では『犬』が好き♡」などと言われると、今度は困惑してしまう。最初に断言しておくが、『犬』は「ちょうど自分と性的な趣味の合う人々を探して、彼らに愛してもらいたいがために描いたイラスト♡」ではないからだ。
なにせデビュー前の学生時代の作品である。人生の助走期間に作ったプロトタイプと言ってもいい。だからそのコンセプトというか、作品を成立させている〈意味的な構造〉はすごく単純だ。
「低俗な変態的画題を、風雅な日本画調で描こうとしました」
おそらくこの一言で済む、ささやかなワン・アイデアである。自分の真情を吐露した素直な絵ではなく、作為的な〈仕掛け〉があるとしても、それはとてもシンプルなものだ。
しかしだからと言って、ネットに溢れる悪評に対して作者としてきちんと応えようとしたら、それ相応の文字量を必要とするだろうということも予想できた。
例えばこの文章を書き始めようとしていた頃、私は一つのツイートを投稿した。それは、見知らぬ人が私の『犬(雪月花のうち〝雪〟)』の画像をアップした上で〈この絵に世間は抗議しなくて良いのか?〉といったことをツイートしているのを(わざわざ)エゴサーチで見つけ、それに私が返答したものだった。
「僕が大昔に描いたこの絵自体が、マルチな方向に向けられた『抗議』です。ややこしいでしょ? 美術家なので普段言葉は使いませんが、強いて使うとそうなっちゃいます。イラストレーターではない美術家とは、そういうお仕事です。最初から愛されることを目的にしていません。」
この「マルチな方向に向けられた『抗議』」とは何か。なぜ「愛されることを目的にして」いないのか。140文字では到底書ききれないそれを、これからゆっくり説明してゆこうと思う。23歳の私はあの時いかなるマルチな──複数の方向に対峙していたのか。そのややこしく絡まった方向性の糸を、できるだけ分かりやすく解きほぐしてみたい。
もちろん分かっている──美術作品の解説なんて作者本人はしない方がいいことは。だからこんな悪趣味は一生にこれ一度きりとする。本来無言の佇まいが良しとされる美術作品に言葉を喋らせたら──いったんそれを許可してしまったら──たった一作でもこれくらい饒舌になるという、最悪のサンプルをお見せしよう。ついてこれる人だけついてきてくれればいい。
* * *
続きは、『性と芸術』をご覧ください。