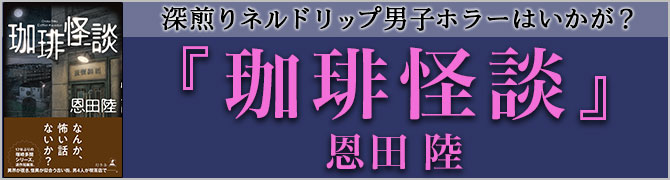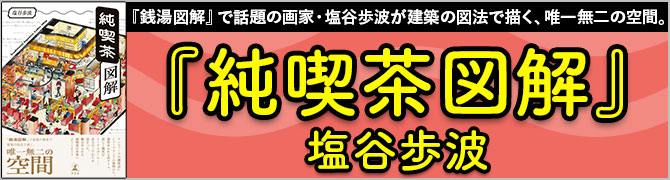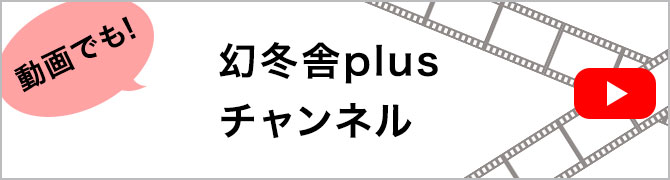諏訪や横浜を旅したご近所友達のぽんさんと、金曜日に「湯島に行こう」ということになった。地下鉄を使ったドアツードアで1時間。大目的は木村硝子本店のアウトレットセールである。
文京区湯島は、世田谷に住む我々にはあまり縁のない場所だ。
「じゃあ、買い物のあとは散策して、おいしいものを食べよう」「湯島天神もあるしね。だったら一日有休とるわ」と話がサクサク進む。
知らない街は、買い物だけで終わったらもったいない。歩き回って食べて見物して。いつものこたびスタートである。
最寄りの駅に集合して千代田線に乗る。東京の西から東へ、ひたすら電車に揺られながらおしゃべりが止まらない。
話題は「最近の自分は、いかにぽんこつか」だった。互いの仕事現場の物忘れによる失敗、勘違い、早合点、集中力の低下、一度に複数の作業ができなくなった……などなど。
「本当に気をつけないとね、私たち」と、ぽんこつのワンテーマを1時間話し続け、気づいたら、湯島を乗り越して根津だった。
慌てて飛び降り、ひと駅戻るぽんこつふたり。
旅の愉しみは、往路のおしゃべりからすでに始まっていると私は思う。平日の昼間、乗り物に揺られながら交わす会話に、愚痴や悪口は似合わない。今日一日のんびりするぞというおおらかな決意と、この先に待っているわくわくを想像するだけで、会話は、どんな失敗も自ずと愉快なものになる。
湯島の街は、坂の街だ。
妻恋坂、清水坂、三組坂。坂名の由来を記した教育委員会の看板を読むのも好きで、あちこちで立ち止まる。これは、心に余裕がないと絶対に止まれない。
坂の両脇には石垣のホテルや味わい深い古ビル、新しいマンションが不思議と心地よいバランスで隣り合う。坂道はどれも静かで、街路樹が点在し、昔、屋敷が建ち並んでいた街にしかない品格のようなものを感じる。地元下北沢から電車で一本だが、坂の街にはるばる遠くに来た感が強まる。
目当ての木村硝子店は1910年創業の老舗だ。やはり、ゆるやかな坂の途中にある。
年に一度、春市という待ちに待ったアウトレットセールがあり、私は興奮気味に吟味。ハンドメイドの極薄のグラスや、バンビと呼ばれる脚(ステム)の短い、繊細なワイングラスを買い込んだ。
ぽんさんも目を輝かせて、店内を回遊魚のように動き回っていた。
買い物は30分ほどで堪能。
さあ、これからどこへ行こう。
なんとなく、大通りに出る。一応、春市の案内メールにあった湯島の観光情報もチェックするが、「よくわからないから、とりあえず歩こう」と上を向く。そう、スマホとにらめっこしていると、街の風景を見逃す。それでは目的が「誰かの良いと言った店の確認作業」になってしまう。とはいえこれ、口で言うほど簡単ではない。“意識して見ない”と選択することが大事な時代になった。
まずは自分たちの足で“街の相場”を知る。
ここでいうところの相場とは、金額だけではない。どんな雰囲気や格式の店が多く、自分たちを受けいれてくれそうかどうか。街の懐にとびこんで探る感覚に近い。
あてずっぽうに知らない小径を歩き、たまたま目に留まった雰囲気の良さそうな小さなビストロで立ち止まると、「先月オープンしました!」と、ソムリエエプロンの若い男性が、外に飛び出してきた。
満面の笑みで手渡されたチラシから、即座に頭の中で計算をする。ランチとワインで4、5千円くらい。きょうび、1、2杯飲んだらどこでもそれくらいになるだろうが、ガラス越しに見える店内は、奥に細く、狭い。きっと私達のおしゃべりの声は響き渡る。ほかのお客さんに迷惑をかけるだろう。
隣り合うテーブルがあまり近くなく、できれば正方形の間取りで、天井が高い方が反響がしづらいので安心する。
どのテーブルで食事をどうとるかは、おしゃべりふたりにとっては、価格や味と同じくらい重要な問題なのである。
5千円支払って気を使いながらワインを飲むのはちょっと……ね、というげんきんな直感が一瞬のアイコンタクトでぽんさんとわかりあえたので、「また来ます」と頭を下げた。
この年齢になると、5千円支払うのはやぶさかではないにしても、気を張って食事をしたくないと、つい思ってしまうのだ。
しばらくいろんな路地や坂を歩く。
だんだん海外の観光客が増え、通りに出ると、あきらかに街の雰囲気がガラリと変わった。秋葉原だった。
「え、湯島って秋葉原まで歩けるの?」
土地勘のない私たちは、初めてスマホの地図を取り出す。上野、御徒町にも行ける。頑張れば神保町や神田にも。湯島の雰囲気がそれらの街とまったく違うので、私達はしばらくぽかんとした。
ぽんさんが、新発見の面持ちで言う。
「湯島って文京区のイメージだけど、千代田区と台東区に接してたんだね」
賑やかな秋葉原から引き返し、あっちに行ったりこっちに来たり。同じ道を通ると、短いなりに土地勘がついてくる。
私達は、おしゃべりが気にならないホテルの1階の大きなイタリアンに入り、ピザをあてに、生ビールとジンリッキーを。オープンキッチンには石窯があり、国産食材や山椒、ハーブの使い方も独創的で、本格派の店だった。
デザートを相談したスタッフが、アルバイトの男子大学生で、イタリアンには珍しいフランスの本格菓子があるのはなぜかという話から「じつはシェフがフレンチ出身で。そうだ、沖縄に姉妹店があるんですよ。すごく素敵なんです。写真おみせしましょうか」と、しゃがみ込んで自分のスマホを開く。
話はどんどん盛り上がり、最後はインスタIDを交換するしまつで、「(こんなに話し込んで)お仕事大丈夫?」と聞いたら、「さっきから僕、もう休憩なんです。だから平気です。こんなにデザート喜んでくださったら嬉しいんで」。
シェフを尊敬し、この店を愛しているのがじんじん伝わってくる、心ある接客だった。
会計を済ませると、Tシャツ姿の普段着になった彼が、店の外まで挨拶に来た。
一期一会の言葉が清々しく体に染み込む。
ランチに2時間を費やし、ぷらぷらと歩きながら「湯島天神行こうか」と、ポンさんが言う。オッケー、その前に、あそこ探してみようと私。来るときに見かけて、気になっていた路地裏のパン屋だ。小さな店だけれど、ずいぶん客で賑わっていた。
しかし、店名がわからず、記憶もおぼろげなので、行ったり来たり。やっとたどり着くと、「ごめんなさい。最後の食パン1斤が今売れてしまったところです」、と頭を下げられた。思いつきで行動しているので、それもしかたあるまいと、あらためて湯島天神へ。
街の表示を頼りに参道を探す。
と、驚くほどひっそりとした住宅地の間に、「学問のみち」と書かれた紫色の小さな幟を見つけた。
「こんな地味なところに、本当にあの有名な湯島天神があるのだろうか」と不安げに進んだ先に、突然石階段が現れた。脇の看板に「天神石坂(天神男坂)」とある。三八の急な石階段の向こうに、鳥居が見える。
ゼイゼイ言いながらなんとか登りきると、眼前に空と緑と境内が広がり、くもり空にも関わらず大きく感激した。
「着いたー」
たいした歩数ではないのに、頂上にたどり着いた登山客のように嬉しい。
境内にある「劇団新派」「講談座発祥の地」の石碑を読む。──坂だろうが文豪の屋敷跡だろうが、何かの発祥の地だろうが、由来を綴った街角にある文字板を読むのが無条件に好きだ。ずっと昔からそこにあるのに、みなに忘れられているような寂しさに惹かれるんだろうか。
本殿のすぐ後ろにマンションがそびえる。さっきの石階段の参道も、両脇に低層の高級そうなマンションが佇んでいた。近代の建物と、江戸時代の天神信仰の中心地がこれほど近くに隣り合う光景を、不思議な思いで見つめた。
都会の真ん中で、そこだけぽっかりと切り取られた空は、今にも泣き出しそうな曇天だ。にも関わらず、履き清められた境内に立ち、じっと見上げていると、なにかに包まれるように、すぅっと心が鎮まってゆく。
歴史も悲しみも喜びも包み込んで、優しく沈黙しているような空間。「神聖」とはどういうものかわからなくても、ここに立てばきっとわかる。
記念写真を撮ったら、あの時私が感じた、不思議に研ぎ澄まされた空気が映し出されていて、どきりとした。
参拝をしておみくじを引き、天神信仰の象徴・牛の像を撫で、何度も深呼吸をし、別の鳥居から出たら、こちらが正面だったとわかった。
大きな料理屋や茶房が並ぶ、観光客が喜びそうな参道らしい参道に出た。
だが私は、住宅地の間を縫うようにひっそりした小路の男坂のほうが好きだ。昔の人もゼイゼイ言いながら、あの階段を登ったのかなと想像する足がかりが、あちらのほうがたくさんある。
日も陰ってきたので湯島駅に戻り、地下鉄に乗った。
下北沢に着くと小雨が降り始め、帰宅と同時に大雨に。鍋を火にかけ、夕食の支度のためエプロンを締める。
さっきまであの神々しい境内にいたことが嘘のように、日常が流れ出す。
台所に立つのも風呂に入るのも寝る時刻も、だいたい昨日と同じ。だが、昼間のこたびは違った。ぽっかりと都会の隙間に空いたあの空のように、私の慌ただしい日々のなかで、深呼吸できる非日常のご褒美のような時間だった。

ある日、逗子へアジフライを食べに ~おとなのこたび~の記事をもっと読む
ある日、逗子へアジフライを食べに ~おとなのこたび~

早朝の喫茶店や、思い立って日帰りで出かけた海のまち、器を求めて少し遠くまで足を延ばした日曜日。「いつも」のちょっと外に出かけることは、人生を豊かにしてくれる。そんな記憶を綴った珠玉の旅エッセイ。