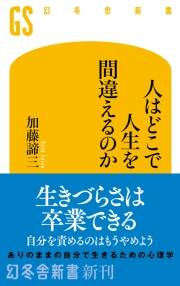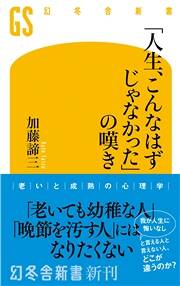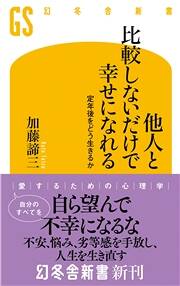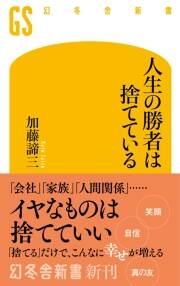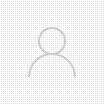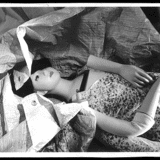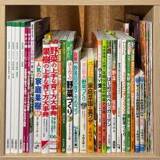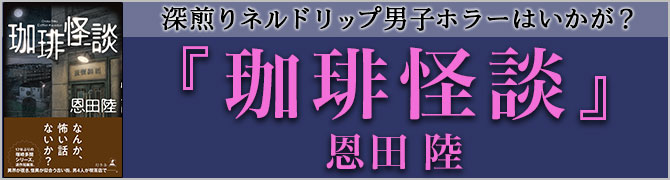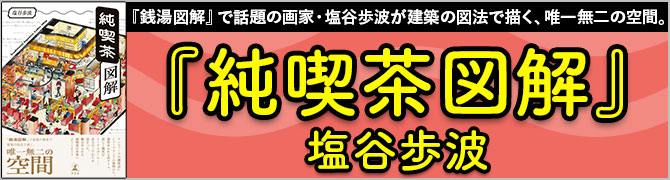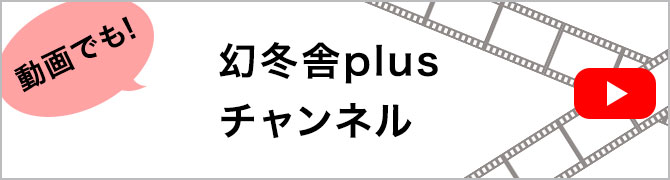「テレフォン人生相談」の回答者として活躍され、人生相談のレジェンドでもある加藤諦三さんの新刊『人はどこで人生を間違えるのか』が好評発売中です。本書から一部を再編集してご紹介します。
* * *
健康な人は、他人をあるがままに見られる
自分の中にあるものを外へと表していくと、それが、他人について歪んだ認識を持つ結果になる。
カレン・ホルナイは、この心理過程を「外化」と述べている。
欲求不満な人、憎しみの塊のような人、そういう人は憎しみを外化して、他人を歪めて解釈する。優しい人を鬼のように思うこともある。
他人をあるがままに見られる人は、心理的に健康な人なのである。
他方、外化ばかりしている人はあなたを憎んでいるのではない。実際には、人生そのものを憎んでいるのである。あなたが嫌いなのではなく、生きることが嫌いなのだ。
例えば、「あのブドウは酸っぱい」と言う人が自己憎悪の人である。本当はそのブドウが欲しくて、心の底ではそのブドウが甘いことを知っている。しかし、それを認めることができない。これは合理化であり、現実否認の結果だ。そのため、「あのブドウは酸っぱい」と主張することになる。
自分がブドウを取れないことを憎む。本当は社会的に成功したいと願っているが、成功できない。だから「社会的に成功することなんてくだらない」と言い出す。社会的に成功できない自分を憎むのである。ブドウを取れる自分が「理想の自分」になる。
外化は、自我価値の剥奪からの防衛以外でも起きる。さびしさから外化が起きる。人とつながっていたいという願望がある。愛情飢餓感から起きる。裏切られた時の憎しみはすごい。外化とは現実否認である。
自分の恋人は理想の女性、あるいは男性であって欲しいと願う。そうすると、現実の恋人を見ないで、相手を理想の女性あるいは男性としてしまう。
外化をして生きている人は、現実の厳しさに耐えられない。現実否認をしながら、現実から目を背けて生きていこうとする。現実を突きつけられたら苦しくて卒倒するかもしれない。
しかし、現実は現実である。相手は女神でもなければ、白馬の騎士でもない。だからどうしても現実を受け入れられない。
だから一目惚れをする人は、たいてい次から次へと恋人を替えていくのである。そして、相手が自分の要求に叶うように変わらないので不満になる。多くの人が自分自身への不満から投射された、幻想たる非現実的な(過大評価されているがゆえに)パートナーを創造するのを強いられる(*1)。
ありのままを受け入れることから始めよ
自分が理想の自我像に達していないから、人と自分を比較する。優れた人に劣等感を抱く。実は深刻な劣等感のある人は、他人と自分を比較しているのではなく、心の中で理想の自我像と「現実の自分」を比較して劣等感に苦しんでいる。それを、他人に外化して、他人を通して感じているだけである。
外化は相手の現実を認めない。自分の現実も認めない。それは自分にとって重要な他者が、自分の現実を認めてくれなかったからである。
親は子どもの現実を見ない。非現実的なほど高い期待を子どもにかける。その親の期待を子どもは内面化する。現実よりも心の葛藤が優位を占めるようになる。優先順位第一位が心の葛藤の解決になる。そうして子どもも現実を見ないようになる。その結果、心が遭難する。準備なしの登山である。
現実の遭難でなく、心が遭難することもある。
「こうあって欲しい」という願望を現実と見なしてしまう。「何でこんなことができないのか?」と子どもを非難する親ほど、子どもにしがみついている。「何で誰々さんのようになれないのよ症候群」の親には敵意がある。子どもを愛する能力がない。
親に愛する能力がなく、その上に親から敵意を持たれてもなお、今日まで生き抜いてきた人は心理的にすごい人である。その自分を信じてほしい。
「愛の不能」と「無視」の弊害
愛の不能は、相手の適性や、限界を無視することである。無視は不安の結果である。そして、不安ゆえに相手にしがみつく。親は、子どもにしがみつく。
そしてこの親の無視の中に敵意が表現されている。相手の限界を考えないで、「何でこんなこと、できないのだ」と言う親の子どもへの怒り。自分に対する怒りを外の対象に置き換えるのが外化である。
母親への愛情欲求が強ければ、自分を虐待した母親でも「母親はいい人」と言い張る。それが外化である。事実が人に影響を与えるのではなく、事実に対するその人の解釈が人に影響を与える。そのことについて決定的な影響を与えるのが、外化である。
幼児期の母親との関係は、生涯にわたって極めて重要であることは、我々の常識では、残念ながら見落とされている。
パーソナリティーは、幼児期の環境内の重要な人物との関係から発展してきたものである。まったく生物学的に生命が始まったばかりのときでさえ──子宮内の受精卵──その細胞と環境とは一つのものであり、解きがたく結び合わされている(*2)。
ある人があなたに対して「ある言葉」を発した。客観的事実として認められるのは、たったこれだけのことである。だが、その言葉をどう受け取るかは人によって違う。
自分が自分自身をバカにしている人は、ある人の何気ない言葉を「私をバカにした」と解釈する。そしてその何気ない一言が、その人にとってものすごい影響力を持ってしまう。
自分が自分自身に失望していると、妻が自分に失望していると思ってしまう(*3)。そして妻に煩く小言を言う。理由を見つけては妻を責め続ける。自分自身に失望している親は子どもを責め続ける。「自分がもっと多くを欲している」ことを認めることは、自分が人生において意気地なしであり、臆病と認めることだ。それよりも妻を非難している方が心理的に楽なのである。
夫婦関係でも親子関係でも、自分が意気地なしであり、臆病と認めるよりも、相手を責めている方が心理的に楽である。そうなると、相手が嫌いでも相手がいなければ生きていかれなくなる。
註)
*1 Abraham H. Maslow, Motivation and Personality, Haper & Row, 1954, p.197. 小口忠彦訳、『人間性の心理学』、産業能率大学出版部、1971、286頁
*2 Rollo May, The Meaning of Anxiety, W. W. Norton & Company, 1977. 小野泰博訳、『不安の人間学』、誠信書房、1963、117頁
*3 George Weinberg, The Pliant Animal, St. Martin's Press, 1981. 加藤諦三訳、『プライアント・アニマル』、三笠書房、1981、127頁
人はどこで人生を間違えるのか
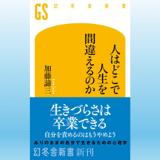
手に入らない成功、不本意な評価、漠然とした生きづらさ――「自分は生き方をどう間違えたのか?」と悩む人は多いだろう。その原因は、実は、不安や怒りにまかせて他人を責めてしまう「外化」という心理メカニズムにある。それによって、あなたは自分をごまかし、人間関係を歪め、自分で不幸を引き寄せているのだ。「外化」の罠から抜け出せれば、ほんとうの自分を取り戻し、もっと楽に生きるための道筋が見えてくる。人生相談のカリスマが贈る、満足のいく人生を送るための心理学。