

開店から1年5か月の史上最速で、ミシュラン三つ星を獲得したシェフがいる。大卒で企業に務めた後、料理学校に通い、26才で仏料理店の門を叩いた遅まきのスタート。しかし塩1粒、熱0.1度にこだわる圧倒的情熱で、修業時代から現在に至るまで不可能の壁を打ち破ってきた。心を揺さぶる世界最高峰の料理に挑み続けるシェフ・米田肇のドキュメント。
フランスに生まれフランスに育ったフランス人シェフでも生涯の憧れである
ミシュラン三ツ星を、なぜこの日本人は手にすることができたのか?
アンコール御礼!
トワイライトエクスプレス 瑞風で供される食事を担当する料理人の一人でもある、天才シェフ・米田肇を追ったノンフィクション『天才シェフの絶対温度 「HAJIME」米田肇の物語』の試し読みを全4回でお届けします!
* * *
(フランスでの修業を終え、帰国してから勤めた『ミシェル・ブラス トーヤ ジャポン』を)辞める時期を半年後にしたのは、突然辞めて店に迷惑をかけるわけにはいかなかったからでもあるが、もう一つ別の理由もあった。毎年、秋には、ミシェル・ブラスが洞爺湖にやって来る。独立する前に、もう一度彼の仕事を目に刻んでおきたかった。
ミシェルにはそれまでに2度会っていた。物静かで、洞爺湖に来ても、コックコートを着て厨房にいるよりは、肩にセーターを羽織って散歩道で雲を見上げていることの方が多いような人だ。挨拶以上の話をするのは難しいし、まして、何か具体的なことを学べるなどとは思ってもいなかった。それでも、彼が料理をする姿を垣間見るだけでも、きっとその後の自分の糧になるはずだと思った。
けれど、人生という舞台には、しばしば登場人物の想像もしない脚本が用意されている。
3度目に遭遇したミシェルに、肇は想像もしなかった難題をつきつけられ脂汗を流すことになる。
「このときは、いろんなことがありました。まずルセット(メニュー)がなかなか送られてこないんです。ミシェルは来日する前にルセットをあらかじめ送ってくることになっていたのに、送ってこない。料理の内容が決まらなければ、準備ができないので、こっちは焦るんだけど結局送られてこなくて、ルセットが決まったのはミシェルが洞爺湖に着いてから。しかも、いったん決まった後も内容がコロコロ変わる。営業中に変わるんです。最初のお客さんに料理を出してるのに、次のお客さんの料理は『いや、もうちょっとあれを加えよう』なんて言って、料理を変えてしまう。最後の盛りつけまで終わってるのに、『やっぱりこの皿じゃ駄目だ。あの皿を持ってきて』って、皿を替えて、また違う盛りつけをしたり。スタッフは大変です。『もう勘弁してよ』って、ミシェルのいないところでですけど、愚痴をこぼすスタッフもいました。彼らの気持ちもわからないではないけれど、私は天才の秘密を見たような気がしました。あんなにビシッと決まったお皿を作る人が、こんなにあがいてるんだって。そういう姿を見るのは初めてでした。ほんとに最後の最後、皿をお客さんのテーブルに運ぶ直前のギリギリまで彼は考え続けてるんです。すごいなって、素直に思いました。私は単純なのかもしれないけれど、ただただ感動してました。自分の取り組んでいる料理人という仕事の秘密を見つけたと思った。彼はいつまでもあがき続けるだろう。だからこそ、ミシェル・ブラスは偉大なシェフなんだって」
一皿の料理に向かって悪戦苦闘するミシェル・ブラスの姿が、肇には独立を目指している自分に対する餞(はなむけ)のように思えてならなかった。それはつまり自分が彼ほどの成功を収めたとしても、苦しみながら料理を作らなければならないということでもある。けれど、それは救いでもあった。それは、あがき続ければ、努力さえ怠らなければ、いつかは彼の立っている場所に達することができるということでもある。
偉大な料理人の苦悩を知り、密かに感動しながら、焼き上げた鳩の胸肉を3つに切り分けていたときのことだ。
手元に視線を感じて目を上げると、ミシェル・ブラスがそばまでやって来て、包丁を使う肇の手元を見つめていた。かっと身体が熱くなった。ミシェルが自分の仕事に注目している。包丁の扱いには自信があった。フランスでも自分より上手く包丁を使う料理人はいなかったし、それは北海道に来てからも同じだった。魚をおろすのも誰よりも速かったから、厨房のみんなに包丁の使い方を教えていたくらいだ。
洞爺湖の『ミシェル・ブラス』の厨房のスタッフの3分の2は、ライヨールの本店で修業を積んでいる。にもかかわらず、新入りの自分がいきなりヴィヨンドのシェフを任されたのだって、この包丁の技があるからだ。
心臓は高鳴ったけれど、緊張はしなかった。いつものように素早く、美しく肉を切り終えて、顔を上げた。心臓の高鳴りが消えた。理解の眼差しがそこにあるものとばかり思っていたからだ。
肇が覗き込んだのは、無表情の冷たい目つきだった。しかも、かすかに首を傾げはしなかったか。
気のせいと思いたかったけれど、次のオーダーが入って、肇がふたたび鳩を切っていると、ミシェルがまた近づいて来た。そして、今度ははっきりと感想を口にした。
「ノン、ノン。セ・パ・ビヤン」
駄目、駄目。お前下手だな。正直、むっとした。
「えっ、何が? どこが悪いのって。それなら、あなたが切ってみろって思いました。もちろん口には出しませんでしたけど……。出さなくてよかった」
いや、ミシェルはこのとき、この日本人のヴィヨンド・シェフの心の声を正確に聞き取っていたに違いない。その証拠に、肇がその次の鳩を焼き上げて切ろうとしていると、今度は肇の隣に立ってこう言ったのだ。
そのいつもの肇の定位置に立つと、ミシェルは険しい顔を少しだけ緩めた。肇が焼いた鳩の胸肉を手に取り、肉の弾力を確かめて言った。
「キュイソン パルフェ」
キュイソンは火入れ、パルフェは完璧。つまり「火入れは完璧だ」と言った。
次に肇の包丁の刃にそっと親指の腹を押し当てて、満足そうに頷いた。
「クペ ビヤン」
よく切れる、ということだ。包丁を研ぐのは、フランス料理でも料理人の仕事であり、それはつまり肇の包丁の手入れを認めたということだろう。
ミシェルは軽く胸肉に左手をそえると、手入れの行き届いた肇の包丁で胸肉を切った。
そのときの肇の印象を正確に描写するなら、包丁で切ったというより包丁で触れたと書いた方がいいかもしれない。肉にそえた左手にも、包丁を握った右手にも、ミシェルはほとんど力を入れていないように見えた。二筋の線を描くように、すっすっと軽く包丁を動かした次の瞬間には、胸肉の塊が3つに分かれていた。
(「第六章 これで完璧だと思ったら、それはもう完璧ではない。」より)
※この連載は、『天才シェフの絶対温度 「HAJIME」米田肇の物語』の試し読みです。
つづきは、7月17日に公開予定です。お楽しみに!
天才シェフの絶対温度
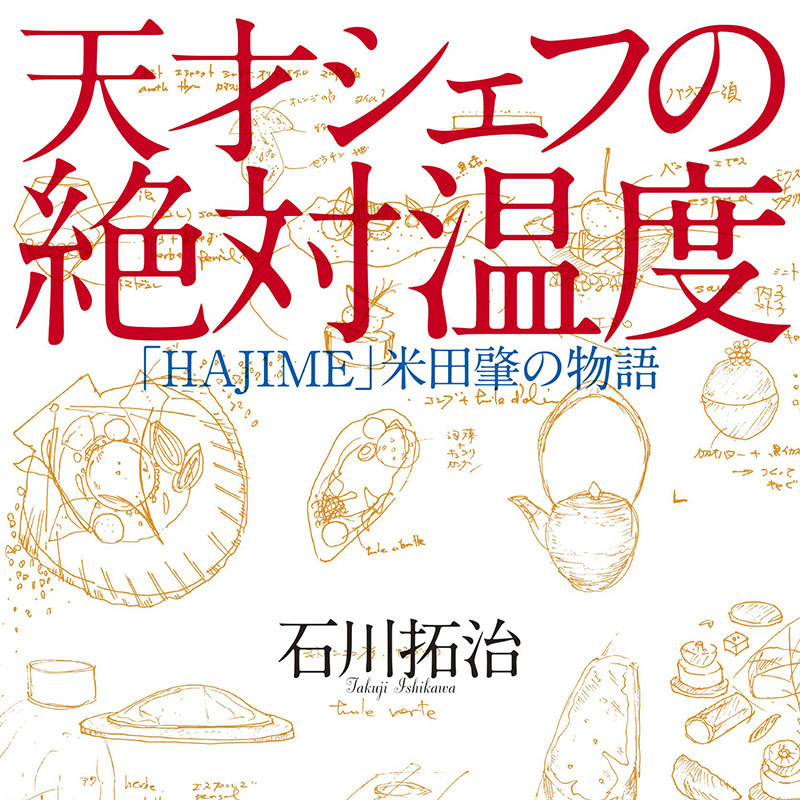
開店から1年5ヶ月の史上最速で、ミシュラン三つ星を獲得!
心揺さぶる世界最高峰の料理に挑み続けるシェフ・米田肇のドキュメント。
















