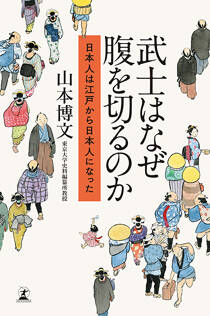「日本人はもともととてもすばらしい民族だった」「日本人は、もっと日本人であることに自信をもってよい」……そう語るのは、歴史学者の山本博文東京大学教授。江戸時代にくわしい教授は、著書『武士はなぜ腹を切るのか』で、義理固さ、我慢強さ、勤勉さといった、日本人ならではの美徳をとり上げながら、当時の武士や庶民の姿を活き活きと描いています。昔の人はカッコよかったんだな、と素直に思えるこの本。一部を抜粋してご紹介します。

実は「仇討ち」の成功率は低かった
江戸時代は、仇討ち、つまり復讐が認められていました。武士たる者、親や兄弟を殺されたら、自分の力で復讐するのが当然だと考えられていたのでしょう。そのため、届け出さえすれば、必ず認められました。
仇討ちが社会的に黙認されていたのは、むしろ武士たちの「汚名を雪がずにはおれない」という自尊心のためでした。
「親を殺されて平気な顔をしているヤツは武士ではない」ということでしょう。武士は、面子をつぶされたり、汚名を着せられたりすることを極端に嫌がります。
たとえば江戸時代、親や兄を殺されるなどして「敵」をもった場合、まずはそれを討つために、幕府に届け出ます。そのうえで一度、脱藩し、浪人の身となって敵を追いかけます。
浪人なので当然禄はありませんが、どこかに雇われるというわけにもいきません。たまに日傭取りや用心棒などで糊口をしのぐことは可能だったかもしれませんが、基本的には仇討ちを狙っているあいだの生活は、親類などに頼るほかありませんでした。親類も、仇討ちが成し遂げられないと一門に悪い評判が立ってしまうため、何としても成功させようとがんばったのでしょう。
このように苦しい生活を強いられる仇討ちですが、成功率は江戸時代を通してたった数パーセントだったのではないかといわれています。
というのも、交通機関も通信機関も、現代と違って発達していませんでしたから、敵がどこに潜んでいるか、簡単にはわからないわけです。
場合によっては、敵の顔さえ、わからない場合もあります。そのうえ、敵を討つまでは藩に帰ることはなりません。しかし、なかなか会えないからといって途中で諦めたりしたら、それこそ武士の名折れといわれてしまいます。
そんな思いをしてやっとのことで敵を見つけ出したとしても、返り討ちに遭ってしまうこともあります。それでも、めぐり合えるだけましかもしれません。相手がどこにいるかもわからないまま一生を終えることも珍しくはなかったのです。本音をいうなら、武士たちだって「義理」のためとはいえ、仇討ちはしんどいなぁと思っていたことでしょう。
『忠臣蔵』に見る武士の「義」
さて、みなさんご存じの有名な仇討ちといえば、やはり『忠臣蔵』でしょうか。
実は『忠臣蔵』というのは歌舞伎や文楽のタイトルであって、歴史上、そういう名前の事件は起こっていません。本当に起こったのは赤穂事件、つまり赤穂藩主・浅野内匠頭の起こした江戸城松之廊下での刃傷沙汰に始まり、その責任を問われた切腹処分に起因する赤穂浪士たちの討ち入りまでの、一連の出来事です。
この赤穂事件を物語にしたのが『仮名手本忠臣蔵』で、“忠臣”つまり、忠実な臣下たちの手本という意味と、蔵=(大石)内蔵助をはじめとする忠実な部下たちという意味になっています。
この赤穂事件、詳細に調べていくと、実にさまざまなことがわかってきます。とくに一級史料である浪士たちの手紙などはたいへん興味深く、そこには彼らの本音が吐露されています。
たとえば浪士のひとりである神崎与五郎は、妻おかつに宛てた手紙のなかで「私もあなたが恋しいけれど、これは人たるものの務めなのだ」と書いています。一方、茅野和助も、討ち入り直前に兄弟に宛てた手紙のなかで「この場を逃れることは、私だけでなく一家の面目にかかわり、ことに武士として生きている以上、甥の武次郎や倅の猪之吉などにもよくないし、とにかく武士の道を外れることになります」といっているのです。
彼らのいう「人たるものの務め」「武士の道」とは、何か。それは言い換えると、「義」にほかなりません。つまり、討ち入りは、彼らにとっては武士として、どうしても行わなければならない「義」だったのです。
当時の武士は「かぶき者」だった
そもそも浅野家の家臣たちは、内匠頭は吉良上野介との“喧嘩”のすえに刃傷におよんだのだ、と考えていました。武家社会では「喧嘩両成敗」という天下の大法があり、両者が行ったのが本当に“喧嘩”であれば、当然、内匠頭だけでなく上野介も切腹になったはずなのです。
ところが、上野介はただ逃げただけで、“喧嘩”ではないということで、内匠頭にだけ一方的に、即日切腹の沙汰が下ったのでした。浅野の家臣、つまり赤穂藩士たちから見たら、幕府の処分は片落ちだった。簡単にいうと、えこひいきに思えたのです。ですから平等に上野介の切腹を願ったのですが、幕府は聞いてくれない。そのうえ、赤穂城は明け渡しになり、自分たちは浪人する。だから赤穂の浪士たちは、自分たちの手で上野介を討とうと決心したわけです。
売られた喧嘩は買わなきゃならない、というのは、現代の常識から見れば、どう考えてもまともな人間のすることではなく、「やくざ」の論理です。けれど、武士はそういう社会に生きてきた。誰かが斬りかかってきたら応戦する。自分に降りかかった汚名は血をもって雪ぐ。家や藩主が受けた汚名は、仇討ちで晴らす。
とくに赤穂事件が起こったのは、江戸時代でもまだまだ、武断政治の殺伐とした気風が残っていた頃。この頃の武士のメンタリティは、「かぶき者」的心性であると、私は思っています。
「かぶき者」とは、十七世紀に多かった無頼者たちのことで、武士や武士に奉公する者に特有の、やくざでイナセな気風をもつ者のことです。
彼らはどんな苦しいことでも我慢して強がりをいい、自分を頼る者や仲間のためには命を棄てても後悔しない、という倫理に基づいて行動していました。
赤穂事件の浪士たちは、この心性によって主君の汚名を晴らし、仇を討ち取り、後世に「義士」として名を残しました。
それは彼らの行った仇討ちが、「義理を果たす」「汚名を雪ぐ」といった武士の倫理に適ったものであり、人々が忘れかけていた武士の生き様を象徴するものだったからなのです。