
世間を震撼させた凶悪殺人犯と対話し、衝動や思考を聞き出してきたノンフィクション作家の小野一光氏。残虐で自己中心的、凶暴で狡猾、だが人の懐に入り込むのが異常に上手い。そんな殺人犯の放つ独特な臭気を探り続けた衝撃の取材録が、幻冬舎新書『人殺しの論理 凶悪殺人犯へのインタビュー』である。
発売6日で即重版となった大反響の本書から今回は「プロローグ」を全文公開。小野氏はなぜ神経をすり減らしながらも殺人犯への取材を続けるのだろうか?

プロローグ
アクリル板で仕切られた殺風景な拘置所の面会室が、幾度も顔を合わせた相手との今生の別れの場となる。そういう経験が何度かあった。
この面会時間を限りに、目の前にいる相手の生きている姿は、二度と見ることができなくなる。なぜならば、彼らが次に拘置所を出ることができるのは、命の灯が消えたときだけだからだ。しかもそれまでの間、親族や弁護士でもない私とは、手紙をやりとりすることも、面会することも許されていない。
それが死刑の確定した被告人と、取材者である私に突きつけられる現実である。
相手は、その判決で明らかなように、凶悪犯罪に関わっている。さらに具体的にいえば、何人もの命を奪っている。ときには命乞いする相手を殺め、またあるときには複数でひとりを殺めるなど、その犯行内容は酸鼻(さんび)を極めるものばかりだ。
とはいえ、同じ相手と長期間にわたって面会を繰り返し、手紙のやりとりを重ねていくうちに、その人物の人間的な部分が見えてくることがある。たとえ凶悪犯であっても、そうして心を通わせるようになった相手との、未来永劫の別れには、やはり一抹の寂しさがつきまとう。
死刑執行のニュースに胸を締めつけられるようになった
私がこれまでに直接会ってきた殺人犯のなかで、本書執筆時に死刑判決が確定しているのは5人。そのうち2人に関しては、そうした気持ちをとくに強く抱いた。
だからいまだに臨時ニュースなどで、「本日×名の死刑が執行された」といった見出しが現れると、胸を締めつけられるような感覚に襲われる。
ああ、××でなければよいが、と。
そしてしばらくしてから、ニュースで刑が執行された死刑囚の名前が出て、当該の人物ではないことを確認すると、胸を撫で下ろすというのが常だ。
自分自身の想像力の乏しさ故かもしれないが、死刑判決を受ける被告人に何度も会うということが、そのような感情を呼び起こすものだとは、予想もしていなかった。
死刑執行の一報に過敏な反応を見せる私は、それと同時に、被害者遺族に対する罪悪感にも襲われる。ごく一部の例外を除いて、遺族からすれば加害者という存在は、紛れもなく憎しみの対象である。その加害者の無事に胸を撫で下ろす私がいるのだ。悲しみに暮れる遺族に対して申し訳ないという気持ちが湧き上がってくる。
実際に、かつて取材をした、息子を殺された母親から電話がかかってきたことがある。
「小野さんは××について悪く書かないんですね」
咎める口調で彼女は言った。××とは彼女の息子を殺害した男である。私は××とは拘置所で面会を続け、その一方で被害者の母である彼女からも話を聞き、雑誌の記事を作成した。そこでは××との面会を続けるなかで、彼に人間的な魅力があることに気づいたことが書かれていた。
私はありのままを書いたつもりでいたが、それを不快に感じる母親の心情に配慮が足りなかったことを身に染みて感じた。
殺人事件の取材は絶望を目の当たりにする仕事
人の命というものが、一度失われると取り返しのつかないものである以上、事件取材、とりわけ殺人事件の取材は、多くの絶望を目の当たりにすることになる。
肉親を失った遺族の多くが、犯行からいくら年月を経てもなお、“そのとき”から時間が動いていないことを知っている。私が彼らから感じた絶望は、筆舌に尽くし難いほどに、深い。
先の電話をかけてきた母親は、取材で家を訪れた私に、静かな口調で言っていた。
「歳は取ります。時間は過ぎます。でも、私の心のなかの時計は、止まったままなんですよ……」
彼女は、失った息子がいまだに家に戻ってくるのではないかと信じ、事件から10年が経過しても、当時の住まいから引っ越せずにいた。前言に続いて口にした言葉が耳にこびりついて離れない。
「やっぱり自分がお腹を痛めて産んだ子供ですから。いまも、××(息子)はあの世で私のことを待っててくれてるって思うんです。……わかるでしょ? だから、矛盾してるんです。あの世で待っててねって言う自分と、家に帰ってくるのを待っている自分がいるんです。おかしいんですね。本当に、おかしいんですよ。でも、おかしくならなきゃ、生きていられないんです」
殺人事件は、被害者遺族だけでなく、加害者親族も不幸にする。東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件で1989年に逮捕され、のちに死刑が執行された宮崎勤の父は94年に自殺した。また、2008年に発生した秋葉原通り魔事件で死刑が確定した加藤智大(ともひろ)の弟も、14年に自殺している。その他、同様のケースは数多い。
殺人事件の取材は、多くの絶望を目の当たりにすると書いたが、それだけではない。不幸のただなかにいる被害者遺族や加害者親族、双方の関係者に対して、記者を名乗る第三者が「話を聞かせてもらえないか」と土足で踏み込む作業なのだ。それこそ数限りない拒絶を経験することになる。
新聞社やテレビ局などに入社し、報道部に配属された新人記者のほとんどは警察担当、いわゆる「サツ担」という仕事を経験させられる。それは、「事件取材にはあらゆる取材に求められる要素が詰まっている」という考えによるものだ。実際、悲しみや怒り、不安や不信と直接対峙し、事件の真相に近づこうとする取材には、忍耐力や判断力、さらには相手の感情の機微に敏感になる能力などが求められる。
人はなぜ愚かな事件を繰り返すのか
事件取材を20年以上にわたって続けてきた私だが、いまだに殺人犯に面会を申し込む際には緊張し、被害者遺族や加害者親族などに取材しようとする前には気が重くなる。正直言って、なぜ自分がこの仕事を続けているのか不思議でならない。少なくとも、カネを稼ぐための仕事という認識であれば、とっくに放棄しているはずだ。事件取材とは、それほどに神経を磨り減らす仕事であるということは断言できる。
ではなぜ会社員の職務でもないのに、フリーランスである私がこの仕事に携わるのか。根底にあるのは、人間に対する興味なのだと思う。若い頃からカンボジアやアフガニスタン、イラクなどの紛争地帯を取材し、人の死が身近にある現場を訪ね歩いてきた。そこで悲惨な状況を目にするたびに、人間はなぜこのような愚行を繰り返すのだろうかとの疑問を抱き続けた。殺人事件についても同じだ。被害者側も加害者側も不幸になるというのに、なぜ事件は繰り返されるのか。それを知る手がかりになればとの一縷(いちる)の望みが、事件取材を続ける原動力となっている気がしてならない。
懲りずに事件取材に関わり続ける私だが、馬齢と場数を重ねることによって、変化してきたことがある。若い時分はとにかく相手から話を「聞き出す」ことだけを求めてきた。それは空いている器の中身をとにかく埋めなければ、との強迫観念に近いものから生じた行動だったと思う。しかしいまは少し違う。相手が自分一人の胸のうちに留めておけないものを「受けとめる」ということを理想とするようになった。
つまりそれは、こちらから強引に話を引き出そうとはせずに、相手から溢れ出た話の受け皿になるということを意味する。
取材というのは、そもそもが相手の心を少なからずかき乱す行為だ。だからこそ、可能な限り相手の負担は小さくしなければならない。そしてできることならば、自分に話すことで、相手がこれまで抱えてきた負担を軽減させる助けになるよう努力する必要がある。
もちろん、すべてがそのように上手くいくわけではない。これまでに数多くの失敗と過ちを重ね、取材という大義名分で人の心を傷つけてしまったとの自覚がある。だからこそ、それらの反省と後悔の末に導き出した結論が、かかる取材方法を選択させた。
これから取り上げるのは、そんな私がどのように殺人事件の取材を重ねてきたかということの記録である。もちろん、未熟だった時代も含め、包み隠さず明かしていくつもりだ。
またこれらの記録は同時に、平穏に生きる人々にはまったく関係ないと思われる殺人犯という存在が、じつは決して遠い存在ではないということを伝えるものでもある。
衝撃の取材録『人殺しの論理 凶悪殺人犯へのインタビュー』好評発売中!
人殺しの論理の記事をもっと読む
人殺しの論理
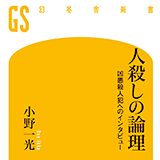
幻冬舎新書『人殺しの論理 凶悪殺人犯へのインタビュー』の最新情報をお知らせいたします。
















