
北極、南極、深海、砂漠……私たちには想像もつかない「辺境」に暮らす生物がいる。そんな彼らに光を当てた一冊が、生物学者で「科学界のインディ・ジョーンズ」の異名をもつ長沼毅先生の、『辺境生物はすごい! 人生で大切なことは、すべて彼らから教わった』だ。知れば知るほど、私たちの常識はくつがえされ、人間社会や生命について考えることがどんどん面白くなっていく。そんな知的好奇心をくすぐる本書から、一部を抜粋してお届けします。
人類は「愛情遺伝子」を持っている
あらゆる生物種の未来には、「絶滅する」か「進化する」かの2つの道しかありません。ですからわれわれホモ・サピエンスも、絶滅さえしなければ、放っておいても何らかの形で進化を遂げるでしょう。

しかし、その前に絶滅してしまうおそれもあります。もしそれを避けることのできる進化が可能なのであれば、自らの手で行わなければいけません。
そこで目を向けるべき問題のひとつは、やはりホモ・サピエンスの持つ凶暴性だと思います。「戦争中心社会」を平和なものに転換させるのは、人類をより長く存続させるための重要な選択肢のひとつでしょう。
そもそも、ホモ・サピエンスは遺伝的にひたすら凶暴な性質だけを持ち合わせているわけではありません。単に好戦的で凶暴なだけだったとしたら、とっくの昔に殺し合って滅びていたはずです。
しかし、そうはなりませんでした。いたずらに競争し、他人を裏切ったりいじめたり騙したりするばかりではなく、むしろ他人と協力し、お互いに助け合いながら生きてきたからこそ、ホモ・サピエンスは今日の繁栄を手にしたのでしょう。
そういう人間の性質には、遺伝子的な背景もあります。他者との「協調」を促すホルモンを分泌させる遺伝子が存在するのです。広い意味では、「協調性遺伝子」もしくは「愛情遺伝子」と呼んでもかまわないでしょう。
たとえば、オキシトシンというホルモンがあります。生殖や出産に関連するもので、女性ホルモンのひとつです。でも、これは、ヒトの女性に特有のホルモンではありません。もともと、魚類が海水環境と体液のあいだで塩分のバランスを取るために必要だったのがオキシトシンというホルモンです。
もともと「水」や「塩分」に関わるホルモンだったので、生物が陸上に進出すると、このオキシトシンは排尿に関わるようになりました。さらに、排尿器官と生殖器が近い存在であることから、オキシトシンは生殖関連ホルモンになっていきます。
哺乳類が登場すると、やはり「水」まわりのホルモンということで、オキシトシンは授乳にも関わるようになりました。幼子に乳を与える慈母のホルモンといってもよいでしょう。
この慈母ホルモンともいえるオキシトシンは、脳内ホルモンとしても機能しています。脳を「やさしいお母さん脳」にするホルモンなのです。このことはマウスを用いた実験でたしかめられています。オキシトシンが働かないように遺伝子操作された実験用のマウスは、ふつうのマウスと比べて、協調性行動や愛着性行動が乏しくなってしまうのです。
授乳という行為はスキンシップを伴いますから、それを司るホルモンが協調や愛着の必要な行動にも関与することは、十分にあり得るでしょう。ですから、そのオキシトシンそのものやオキシトシンのレセプター(受容体)を作る遺伝子のことを「協調性遺伝子」あるいは「愛情遺伝子」だと考えていいだろうと思うのです。
「戦争中心社会」を乗り越える
魚類にもマウスにもオキシトシンはありますから、「無益な同胞殺し」をするチンパンジーやイルカも、当然この協調性遺伝子やオキシトシン受容体の遺伝子を持っています。

しかし、そのスイッチがどのようなタイミングでONになるかは、種によって違うでしょう。「効き目」はそれによって変わります。もしかすると、チンパンジーは協調性遺伝子やオキシトシン受容体の遺伝子がONになっている時間が短く、平和的なボノボは長いのかもしれません。
また、スイッチの入り方は、同じ種の中でも個体差があるはずです。同じ人間でも、協調性遺伝子が活性化している個人もいれば、不活性な個人もいるでしょう。だとすれば、協調性遺伝子が活発に機能する人が増えたほうが、社会は平和なものになりそうです。
もちろん、放っておいても人類がそちらの方向に進化する可能性はあります。ダーウィニズムの観点からは、協調性遺伝子の働きが活発な人ほど子孫を残しやすい環境圧があれば、協調性に欠ける人は自然に淘汰されるでしょう。単純な話、思いやりのない粗暴な人が異性にモテなくなれば、性淘汰によって協調性遺伝子の活発な人間が増えるわけです。
しかし現状でも、結婚して子供を持てるような人は、それなりに協調性行動や愛着性行動が取れる人でしょう。だからこそ人間社会は、お互いの協力によって発展してきたのだと思います。
とはいえ、それでも「戦争中心社会」であることに変わりはありません。その結果、生物は本来「卵子中心社会」になるはずなのに、人間の社会は男性中心文化のほうが成功しやすくなっている。これを根本的に変えようと思ったら、協調性遺伝子がもっと大幅に活性化するような進化が必要ではないでしょうか。
そんな進化をもたらすために、何をすればいいのかはまだわかりません。協調性遺伝子のスイッチングに関わるウイルスがあるかどうかもわかりませんし、環境の影響でエピジェネティックにそのON/OFFを切り換えられるかどうかも不明です。
でも、遺伝子のスイッチを後天的に切り換えることが可能で、その「獲得形質」が遺伝することがわかっている以上、協調性遺伝子の活性化を研究する価値は大いにあるでしょう。21世紀の生物学は、そういう領域に足を踏み入れたのです。
* * *
この続きは幻冬舎新書『辺境生物はすごい!』をご覧ください。
辺境生物はすごい!
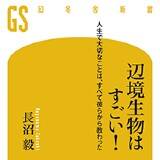
北極、南極、深海、砂漠……私たちには想像もつかない「辺境」に暮らす生物がいる。そんな彼らに光を当てた一冊が、生物学者で「科学界のインディ・ジョーンズ」の異名をもつ長沼毅先生の、『辺境生物はすごい!――人生で大切なことは、すべて彼らから教わった』だ。知れば知るほど、私たちの常識はくつがえされ、人間社会や生命について考えることがどんどん面白くなっていく。そんな知的好奇心をくすぐる本書から、一部を抜粋してお届けします。


















