
家族のかたちやあり方はどんどん変わっているのに、家族は仲良く支え合うもの、といった“理想”の価値観が根深く残る日本社会。そんな窮屈な「家族はこうあらねばならない」に対し、NO!を唱える声が、ここ数年、あちこちで聞かれるようになりました。今回の「家族が苦しい」特集では、そんな声をあらためて拾い集めてみることに。
第1回目は『家族という病』(下重暁子、幻冬舎新書、2015年刊)の冒頭をご紹介します。“一家団欒という呪縛”を一刀両断する先陣を切ったこの本は、発売当初から大きな反響を呼びました。
* * *

友人・知人に会うと、
「あなた、家族のこと知ってる?」
と聞く癖がついた。
「もちろん、よく知ってるに決まってるじゃない」
と怪訝(けげん)な顔で答えが返ってくる。
「ほんとに?」
重ねて聞くと、不思議そうに問い返される。
「どうしてそんなこと聞くの、あなたは知らないの?」
その通り、私は最近、自分の家族について何も知らなかったと愕然(がくぜん)としているのだ。
一人、二人と失っていくに従って、大切なことを聞いていなかったなと気づかされる。
父はほんとうは、何を拠(よ)り所(どころ)に生きていたのか。母はなぜ私に異常とも思える愛情を注いだのか。兄は妹である私にどんな感情を抱いていたのか。何一つ知らなかった……。
もっと早くに聞いておけばよかったと思うが、後の祭りである。彼等は話の出来ない世界に行ってしまっている。あれこれ想像をたくましくするだけである。
むしろ親しい友人・知人とは、わかり合おうと努力するせいか、よく話をし、お互いのことについても知っている場合が多い。情に溺(おぼ)れることなく理性で判断しようとするから、的確に把握することも出来る。
それに対して同じ家で長年一緒に暮らしたからといって、いったい家族の何がわかるのだろうか。日々の暮らしで精一杯であり、相手の心の中まで踏み込んでいなかった。いや踏み込んではいけないとどこかで思い、「ああか、こうか」と思いながら見守っていることが多いのだ。
いじめや家庭内暴力などが報道されると、もっと親子が日頃から話し合っていればとか、相談出来る雰囲気があればとかいうが、土台無理である。
子供は親に心の中を見られまいとするし、心配をかけたくないという思いがある。親は子供がどこか変だと気づいても、問いただすことをはばかる。幼い頃は別として、小学校から中学校へと進み、体も心も大人になりつつある段階にあっては、子供は親に心の内を素直に見せなくなる。反抗期は親という身近な権威を乗り越えようとする時期だけに、自分の思いとは正反対のことすらしてみせる。
親から虐待を受けているのになぜ外部に助けを求めないのかと思うのだが、そんな子供はかえって、外に向けて親のことは一言も言わなかったり、自分が悪いのだと言ってみせたりする。けなげにも、外に向かって家族を守ってみせようとするのだ。
そんな過酷さを子供に強いる家族とは何なのか。
私は長い間、もっとも近い存在である家族とは、人間にとって、私にとって何なのかという疑問を持ち続けてきた。
正直に、私にとって家族とは何だったのかを告白することから始めよう。
「家族」と十把一絡(じっぱひとからげ)にすると、私には答えることが出来ない。しかし、一人ひとり切り離して父・母・兄と個人として見ることで、彼らとの関連を語ることは出来る。
私は家族という単位が苦手なのだ。個としてとらえて考えを進めたい。
なぜ私は家族を避けてきたのか
父のことを考えようとすると胸の奥がちくりとする。私は父と極力目を合わさぬよう、近づかないようにして生きてきた。それはいつ頃からで、なぜだろうか。
幼い頃、父は一種の憧れだった。陸軍の将校だったせいで、毎朝馬が迎えに来た。父は軍服で長靴(ちょうか)をはき、ひらりとマントをひるがえして馬に乗って出かけていった。私は毎朝母に抱かれ、馬ににんじんをやりながら父を見送った。
敗戦になり、父は落ちた偶像となった。もともと画家志望だったのだが、軍人の家の長男で、陸軍幼年学校、陸軍士官学校とエリートコースを歩むことを強要される。何度もぬけ出しては、絵の学校に通い、そのたびに水を張った洗面器を持って廊下に立たされ、ついに諦める。なぜ諦めたのか。そんなに好きなら家出をしてでもその道を歩むべきなのに……。
自分の書斎をアトリエに、ひまさえあれば油絵を描き、中国の旅順(りょじゅん)やハルピンに赴任中は、風景のデッサンを送ってきた。敗戦後は二度と戦争や軍隊はごめんだと言いながら、その後日本が力をつけ、右傾化するにつれ、かつて教育された考え方に戻っていくことが、私には許せなかった。父と顔を合わせることを避け、不自由な足をひきずりながら歩いてくる姿を見つけると、横道へ逸れた。食事も同じ時間を避けて話をしないようにした。
なぜ私は父と話をしなかったのか。感情の激しい人だけに、怒り出すのを見たくなかったからだと自分では思っていたが、父への反抗を心の支えにしていただけだったのではないか。
その時点で私は父を理解することを拒否したのだ。父と意思の疎通をはかろうとすることをやめ、以後老人性結核で亡くなるまで、仕事の忙しさを理由に入院している父の見舞いにも行かなかった。
亡くなってから結核病棟の枕元に私の新聞記事が貼ってあるのを見て、目をそむけたくなった。廊下に出ると、父の俳句が貼られていた。
春蘭の芽にひた祈る子の受験
紅絹(もみ)掛けし衣桁(いこう)の陰や嫁が君
芸術家肌で傷つきやすく優しい神経の持ち主だった。胸の奥が痛くなった。私は慌ててそこから目をそらした。
生前、私は父と話をせず、背を向け続けた。
主治医から「なぜ見舞いに来ないのか」と手紙が来た時も、「あなたに私と父の確執(かくしつ)がわかるか」と腹を立てた。父の本心がどこにあったのか聞こうともせず、わかり合えなかったことに今は内心忸怩(じくじ)たる思いがある。
一方で、安手のホームドラマのように、最後にわかり合えたような場面で終わらなかったことに多少の満足もある。父も私も突っ張っていた。それだけに情感の面ではよく似ていた。実は一番よくわかっていたのかもしれないと思う。
母が亡くなって二十年以上経った三年前、軽井沢の山荘で私が知らなかった母の一面を知ることになった。
母は私のためなら何でもした。娘のために生きているような人で、あらん限りの愛情を注いでくれることがうとましく、私はある時期から自分について母には語らなくなった。私の出ているテレビや活字についても知人から教えてもらうまで知らないことを彼女は悲しんでいた。もっと自分自身のために生きてくれたら、私はどんなに楽だったろう。
軽井沢の山荘で母の遺品を整理している時、父との結婚前、旅順にいた父との間でやり取りした百通近い手紙が見つかった。そこには私の知らぬ女としての母がいた。その手紙は上越という雪深い地に育ち、毎日限りなく降ってくる灰色の雪と戦い、忍耐し、そのために積もり積もった情熱を一気に噴出させようとする強い意志があふれていた。
二人共再婚だったが、父には三歳の男の子があり、母はその子供を理解するために自分の子(なぜか女の子)が欲しいと手紙の中でも訴えていた。私はその母の強い意志の下に生まれたのだ。
兄は、大学生になるまでその事実を知らずに育った。戦後父との折り合いが悪く、東京の祖父母の下で育ったので、私は正面から兄と話をした記憶がない。いずれと思っているうちに一年間の闘病後、ガンで亡くなった。
結局私は、父、母、兄の三人の家族と、わかり合う前に別れてしまった。
私だけではない。
多くの人達が、家族を知らないうちに、両親やきょうだいが何を考え感じていたのか確かめぬうちに、別れてしまうのではないかという気がするのだ。
私達は家族を選んで生まれてくることは出来ない。産声をあげた時には、枠は決まっている。その枠の中で家族を演じてみせる。父・母・子供という役割を。家族団欒(だんらん)の名の下に、お互いが、よく知ったふりをし、愛し合っていると思い込む。何でも許せる美しい空間……。そこでは個は埋没し、家族という巨大な生き物と化す。
家族団欒という幻想ではなく、一人ひとりの個人をとり戻すことが、ほんとうの家族を知る近道ではないのか。
家族という病の記事をもっと読む
家族という病
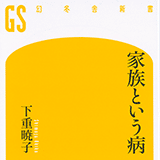
日本人の多くが「一家団欒(だんらん)」という言葉にあこがれ、そうあらねばならないという呪縛にとらわれている。しかし、そもそも「家族」とは、それほどすばらしいものなのか。実際には、家族がらみの事件やトラブルを挙げればキリがない。それなのになぜ、日本で「家族」は美化されるのか。一方で、「家族」という幻想に取り憑かれ、口を開けば家族の話しかしない人もいる。そんな人たちを著者は「家族のことしか話題がない人はつまらない」「家族写真入りの年賀状は幸せの押し売り」と一刀両断。家族の実態をえぐりつつ、「家族とは何か」を提起する一冊。
- バックナンバー
















