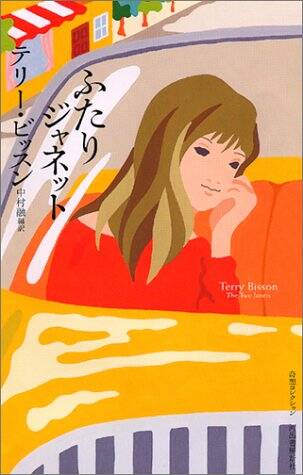「夫婦がお互いを理解するために本を勧めあった格闘の軌跡である。」そんな一文で始まる『読書で離婚を考えた。』(円城塔×田辺青蛙)。単行本刊行時から話題となった本書が、2月6日に文庫で発売されました(解説は作家の花房観音さん)。冒頭を抜粋してお届けします。実際には、本文の下に注釈がたくさん入っていますが、ウェブでは掲載が難しいので、ぜひ本でご覧ください。

第2回 クマと生きる 円城 塔
課題図書……『羆嵐』吉村 昭
課題図書は『羆嵐』ということなので、入手は簡単。ある程度の大きさの書店へ行って新潮文庫の棚を探せばまあ、あるでしょう。
ただちょっと困るのは、表紙が怖いわけですよ。新潮文庫の『羆嵐』は。この表紙のせいで今まで読んでいなかったと言っても過言ではない。かも知れない。
でも今ならもしかして、『ユリ熊嵐』コラボカバーとかになっているかも知れないと──まあ、そんなことはないですね。人食い熊がしっかりこちらを睨んでいます。これはあの、「もともとはスイス土産だったはずなのに、いつのまにか北海道名産ということになっている木彫りの熊なのだ、木彫りの熊」と自分に言い聞かせてレジへ持って行きます。| スイス土産だったんですか!? うちの実家にもありました。そういえば家には無いですね。よし! 次、北海道に行った時に買います!
「カバーおかけしますか」
「(いつもより強い調子で)はい」
ということで『羆嵐』です。ちなみに「羆」の字はヒグマ。『熊嵐』ではありません。クマによる被害を熊害と呼ぶことがありますが、その場合の読みは熊ユウ害ガイ。熊の音読みがユウだからで、羆の音読みは「ヒ」です。ヒガイとはあまり言わないですね。「熊」や「羆」の字をじっと見ていると、「」の部分が足みたいに見えてきてかわいい。
あらすじ。
大正4年冬、苫前(とままえ)郡の三毛別(さんけべつ)六線沢の山深い開拓地に、一頭の羆が現れた──。
といったところで、ほとんど内容としては全てです。この小説はいわゆる三毛別羆事件に取材しており、お話もほぼ世に知られる事件のとおりに進んでいきます。札幌丘珠事件、福岡大学ワンゲル部・羆襲撃事件などと並んで有名すぎる獣害事件です。誰でも知っています。知らない者がいようか、いやいない。
羆が人を襲います。嵐のように襲うので羆嵐──というわけではありません。もっと哀しい謂れがあります。
三毛別羆事件から今年(2015年)でちょうど百年経ちますが、北海道では今でも市街地に羆が出没することがあります。むしろこの頃、増えてきました。そのたびごとに他の地方の方からは、「羆と共生できないものか」「羆を撃ち殺すのは人間のエゴ」といった意見が上がるようですが、
「一度、人間の食べ物(もしくは人間)を食べてしまった羆との共存は無理」
というのが正直なところです。人間の居住地を拡大したせいで羆の住処(すみか)が縮小している、羆の縄張りに先に入り込んだのは人間の方である、羆嵐は特殊な例、というのはその通りなのですが、無理なものは無理、と北海道で育った僕などは思うわけです。
小学校あたりで習いますからね。「死んだふりは無駄」「木に登っても駄目」「羆に取られたものを取り返そうとしてはいけない」「背中を見せたら死ぬ」「出会わないのが一番」など。
もし出会ってしまったらどうすればいいかというと、「目を睨んだままじりじりと後退しろ」と無茶なことを言われた記憶があります。あと、「羆は前足が短いから下り坂が苦手である。どうにもならなくなったら下り坂を逃げろ」とも言われました。ほんとかどうかは知りません。自分の場合、ごくごく素朴に、「羆と出会ったら死ぬ」という感覚があります。月輪熊とはワケが違います。
というわけで、釧路湿原あたりに旅行にでかけ、遠くに羆が見えたからといって餌をあげようとしたりするのは本気でやめてください。死ぬから。周辺住人を巻き込んで死ぬから。
と、誰もがみんな概要は知っている三毛別羆事件、こうして改めて読んでみて驚いたのは、小説の力と呼ぶべきもので、淡々とした筆致がもたらす緊張感や、厳冬の北海道の身を切る寒さなどがそれはもうひしひしと伝わってきます。ちょっと映像を見ているのか字を読んでいるのかわからないくらいの臨場感です。事件の時系列も、誰が死ぬのかもだいたい知っている。それでも新たな体験として目の前に現れてくるわけです。
知っていることと実感することは違います。そういう意味で、ほとんどノンフィクションのような吉村文体は、自然現象としての出来事を血をかよわせている人間の話にしているということができそうです。年表の上のただの名前が息づく人間に生まれ変わるとでも言うべきでしょうか。
今ここで、吉村文体と呼びましたが、一見、最小限の事実を淡々と連ねていくだけに見える、とても不思議な文体です。この文体にしてノンフィクションではないというのが面白いところで、よくよく考えていくと語り手が誰なのか謎であり、誰の客観性なのか不思議な気持ちになってきます。かといってノンフィクションを偽装した小説と言うのも違う気がする。僕の中では、堀田善衞と並んで二大謎文体ということになっています。
羆となるとつい過剰に話し出すのが北海道の人ですが、そのくらい日常的で自然な相手なのです。| 夫の実家に初めて行った時も、クマの話題が普通にたくさん出てきて驚きました。札幌の住宅地の中にクマが出る!? と驚きましたが、話している当人は割と日ハムの試合結果でも話すように淡々としていたのが印象的でした。
だから、居間の中央に(妻の)ジーンズが抜け殻のように脱ぎ捨てられているのを見ると、ああ、熊害(ゆうがい)……と思いますし、廊下に(妻の)靴下の片一方だけが落ちていたら、ああ、熊害……と心の中でつぶやくことになるわけです。冷蔵庫の中の常備菜が何か(スプーン)で抉えぐりとられたようになっているのを見ては、ああ、熊害……と、半開きのままのドアにカーテン、つけっぱなしの明かりにでくわすたびに、ああ、熊害……と浮かびます。夜中にガサガサと物音がすると、ああ、冷蔵庫を漁っているのだなと、そして翌朝、流しの中でひからびている皿とスプーンを観察しながら、ふむ、昨夜はなになにを食べたのだな、と推理してみることになります。妻の姿が見えないと、布団の温度を確かめてみたりしますね。
うむ。まだ遠くへは行っていない。近くにいる。
というわけで、これまで妻との仕事を断り続けていたのは、何か理不尽な目に遭いそうだからとか、生活との切り分けができないと喧嘩になるからとか、相手の分まで仕事をさせられそうだからとか色々理由はあるわけですが、一番はやっぱり、
「羆と仕事はしないだろう」
ということですね。こう言うと、「お前はどうして羆と結婚したのだ」と妻に詰め寄られたりするわけですが、単純な質問にいつも単純な答えがあるとは限りません。まあ、このくらいお互いの作業が分離している仕事だと平気なのではないでしょうか。
さて、次回の課題図書ですが、そうですね。リアルすぎる熊に震え上がったところで、テリー・ビッスンの「熊が火を発見する」でどうでしょう。手近なところでは、「奇想コレクション」の『ふたりジャネット』に入っていたはず。
と書いてふと思いましたが、こういうところが僕があまり売れない理由なんじゃないでしょうか。連載的には、『きまぐれオレンジ☆ロード』第1巻とかにするべきなのでは。
いやあ、でも、『羆嵐』なら「熊が火を発見する」でしょう。うん。
わしはこういう風にしか生きられん駄目な男や、許してくれ、かあちゃん。と謎方言になりつつ、では次は、「熊が火を発見する」で。
夫から妻への一冊 「熊が火を発見する」テリー・ビッスン(『ふたりジャネット』所収)