
「唯一生き残ることができるのは、変化できる者である」
ダーウィンが言ったとされるこの言葉は、自己啓発系のセミナーや記事などでよく使われ、ついには政治の場面でも引用されました。
しかしこれは彼自身の進化論に照らし合わせてみると、そんなことを言っていないというのは明らかです。
生物の観察を通じて人間の生き方を考える長沼毅さんの新書『辺境生物はすごい!』から、キリンを例にとって進化論の概要を説明した箇所を抜粋しました。(幻冬舎plus・柳生)
「キリンの首は、高所の葉を食べるために進化して長くなった」というのは間違い

言うまでもなく、現代の生物学における進化論は、チャールズ・ダーウィンの主著『種の起源』から始まりました。その基本的な考えに、ダーウィンの時代にはなかった遺伝子に関する知見を加えた現代の進化論のことを「ネオ・ダーウィニズム」といいます。
ダーウィン以前にもさまざまな進化論が唱えられていましたが、それは根本的なところでダーウィンの考え方とは違いました。それは、生物の進化に「目的」があると考えるか、進化は単なる「結果」にすぎないと考えるかという点です。ダーウィンの進化論は、後者でした。つまりそれ以前は、進化には目的があると考えるのが主流だったのです。
その中でもとくに有名なのは、18世紀から19世紀にかけて活躍したフランスのジャン=バティスト・ラマルクの進化論でしょう。
彼の考え方は、「用不用説」と呼ばれています。簡単にいうと、よく使う器官は次第に発達し、使わない器官は次第に衰えるということ。それ自体は私たちにもよくあることですが(たとえば寝たきりの生活が続けば足腰が弱ります)、それだけでは個体の変化にすぎません。ラマルクの進化論の特徴は、その変化が子孫に受け継がれる(つまり「獲得形質」が遺伝する)と考えたところです。
その説にしたがえば、たとえばキリンの首が長くなったのは、「祖先が高いところにある葉を食べるために首を伸ばしたから」ということになるでしょう。努力の甲斐あって少しだけ首が長くなり、その形質が子孫に遺伝する。さらに子孫が「もっと高いところの葉を食べよう」と努力して、また少し首が長くなる……ということを何百世代にもわたって続けた結果、現在のキリンになったというわけです。
「それが正解じゃないの?」と思う人もいるかもしれません。実際、多くの人が「キリンは高い木の葉を食べるために首が伸びた」と、進化を目的論的に考えています。
でも、そうやって進化を起こすには、親の獲得形質が子に遺伝しなければなりません。果たして、そんなことが起こるでしょうか。もし獲得形質が遺伝するなら、整形手術をした人の子は「整形後」の親の顔に似ることになります。
でも、ふつうはそう考えません。手術で二重まぶたにした親から、二重まぶたの子が生まれたら、ちょっと気持ち悪いと思いませんか? 実際、現在は遺伝子の研究が進んだことで、親の獲得形質は子に遺伝しないことがわかっています。ですから、ラマルクの「用不用説」は成り立ちません。
生物の進化には、目的も方向性もない
そのラマルク説と違い、ダーウィンは生物の進化に「目的」はなく、それは偶然の「結果」にすぎないと考えました。たまたま突然変異によって親と違う形質の子が生まれ、その個体が淘汰されずに生き残ることによって、進化が起こると考えたのです。
現在では、その突然変異が遺伝子のミスコピーによって起こることがわかっています。「ミス」ですから、そこに目的などありません。いつ起こるかわからない偶然によって、親とは少し違う形質の子が生まれるのです。親の形質は周囲の環境にうまく適応している(だからこそ親は子孫を残すまで生き残れた)のですから、突然変異を起こして親と違う形質を持った子は、当然ながら生き残りにくいでしょう。

しかし中には、たまたまその形質が環境に合っていたために、生き残って子孫を残す個体もいます。突然変異によって生じた特徴が、次の世代に受け継がれるのです。それを何世代も重ねていくと、やがて祖先とは(サルとヒトぐらい)違う形質になるでしょう。その違いが大きくなり、もともとの祖先種とは交配できなくなった時点で、「新種」の生物として独立したと見なすわけです。
したがって、生物がまるで自ら目的や方向性を持って進化してきたように見えるのは、結果論にすぎません。環境に合うように進化してきたのではなく、たまたま持って生まれた形質が環境に合っていたから、生き残った。そこに方向性を与えたのは、環境のほうなのです。
たとえば前章では、生きるために必要な資源の少ない辺境にいる「スローライフ」な生物の話をしました。彼らは、その環境で生き延びるために遅いライフサイクルを自ら選んだわけではありません。遺伝子の突然変異の結果、たまたまゆっくり成長する、あるいはゆっくり増殖するようになった個体が生まれた。ふつうなら生存競争に敗れるところ、資源の乏しい環境においてはむしろ「超省資源ライフ」いわゆる「断捨離ライフ」で生き残ることができた。資源の少ない環境が、そういう個体を選んだのです。
その意味では、偶然そういう性質を持って生まれ、かつ、その性質が選ばれるような環境に生まれてきた彼らは「運がよかった」ということになるでしょう。生物の進化には、そういう側面があるのです。
辺境生物はすごい!
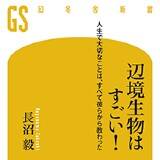
北極、南極、深海、砂漠……私たちには想像もつかない「辺境」に暮らす生物がいる。そんな彼らに光を当てた一冊が、生物学者で「科学界のインディ・ジョーンズ」の異名をもつ長沼毅先生の、『辺境生物はすごい!――人生で大切なことは、すべて彼らから教わった』だ。知れば知るほど、私たちの常識はくつがえされ、人間社会や生命について考えることがどんどん面白くなっていく。そんな知的好奇心をくすぐる本書から、一部を抜粋してお届けします。


















