
ミステリー作家の中山七里さんが『毒島刑事最後の事件』を上梓した。毒があり、クセもある主人公・毒島真理が出版界の闇に挑んだ『作家刑事毒島』。今作はその続編かつ前日譚にあたる。執筆自体は三年前だったものの、現在社会で問題視されるSNSの恐ろしさに深く切り込んだ内容。本インタビューではその、魅力に迫った――。(後編)

百本の物語、
デビュー時に構想
—「刑事犬養隼人」シリーズにつながっているんですね。中山作品は、作品世界が少しずつリンクしています。
デビューした時に、物書きを続けていくための計画を立てて、大まかなストーリーラインを百本作ったんです。それをバラ売りするのではなくて、ひとつの大きな世界を少しずつ切り取った形で出していこうと決めた。年代順に、彼はこういうことをして、そのとき彼女はこうしていて、というのが頭の中に入ってるんです。
版元さんからオファーをいただくと、このテーマでこの枚数ならこのストーリーラインが合うかなというのを当てはめて、プロットを練ります。主要な人物についてはもう十本のシリーズになっていますが、話はすべてリンクしていて、最終的にはこういう形になるというイメージがあるんです。
そのストーリーラインでは犬養刑事のトレーナー役はもともと想定していて、彼が作家兼業で登場したのは編集者さんのオファーに対応したから。性格がこんなに極端だとか、そこまでは考えていませんでしたけれど。
—今年がデビュー十周年ですが、その大構想はどれぐらいまで進んでいるんですか?
先日、祥伝社さんから刊行した『ヒポクラテスの試練』が五十作目でした。各版元さんに既に預けている原稿がまだたくさんあって、基本的に二ヶ月に一本ずつのペースで二〇二四年の十月まで刊行が決まっています。なので、書かずに残っているネタはあと二十数本。そろそろ百一本目を考えているんですけど、思いつかないんですよ。
—三日でプロットを書くというのは本当ですか?
三日間、ほかのことを何もせずに集中できたら、最初から最後まで書くことができます。文章も全部頭のなかにできあがります。あとは少しずつ 〝ダウンロード〟するだけ。だから私は書いている途中で迷ったりとか止まったりとか一切しないんです。
—まったく迷わないんですか!?
迷うということに関しては、執筆に限らず、生まれてこの方迷ったことがない(笑)。家内と結婚するときも、会ったその場でデートを申し込んで、三週間目に戸籍謄本と印鑑持ってきてくれってお願いした(笑)。区役所に行って婚姻届出して、隣に東京厚生年金会館があったから結婚式あげますって予約入れて、道路の向かい側の不動産屋さんを覗いたらいい物件があったのでここに住みますって、その間三十分。悩むこと一切なし。だって悩んだって時間の無駄だもの。
失敗して学び、
地獄を楽しむ
—選択を後悔することはないんですか?
ないです。モットーが「地獄を楽しむ」。生きていたら、どうせいろんなことがあるんだから、楽しまなければ損だっていう性格なんですよ(笑)。
承認欲求がないことと通じているかもしれませんが、失敗しないと学べないことは多い。褒められるだけならそれで終わり。叱られたり、反抗されたり、障害に直面したりすることで、成功したときよりはるかにたくさんのことを得られる。だから失敗するのも楽しい。いまの社会システムって成功しか認めない傾向がありますが、失敗してこそ蓄積がある。
—リアルな描写にいつも引き寄せられますが、実はあまり取材をされないとも伺っています。
正しくは、取材する時間がないんです(笑)。人によると思いますけれど、僕の場合は想像力で何とかしようとしています。単なる空想ではなくて、理路整然と想像を重ねていくことで現実に近づいていく。取材に行っても関係者全員に話を聞けるわけではないし、行ける場所にも限界がある。ドキュメンタリーを書いてるわけでもないし、小説世界のクオリティーやリアリティーを得るためなら、取材するよりは想像力を研ぎすましたほうがいいと思っています。
—映画鑑賞をよくされるそうですね。
〝スイッチ〟です。映画を見ていると記憶の引き出しが開く。「インディ・ジョーンズ」を見て殺人のトリックが浮かぶなどです。あまり関連のないものが出てくる。プロットを立てる三日間はよく映画を見ます。仕事が頭にあるから、あまり楽しめないんですけどね(笑)。ちなみに本作のプロットを考えながら見ていた映画は、ジョン・フォード監督の『わが谷は緑なりき』。この映画を知っている人が読めば、何の関係もないと思うはずですが、プロットは出てきたんです。
—「書きたいものはない」と公言されていますが、作家のスタイルとしては異質ではないですか?
自分を作家だと思っていません。物書きという仕事をしているだけ。せいぜい言って小説家ですね。作家性というのも、少なくとも自分であれこれ言うものではなくて、版元さんとか読者さんが決めることだと思っています。
版元さんがこういう作品が欲しいと期待して注文してくれるわけです。自分が頼むなら、と考えたら、要求されていることはわかるでしょう。こういう仕様でお願いしたいと言われてるのに、まったく違うものを作ったりしたら、普通に考えて二度と仕事は来ませんよ。百を要求されたら百二十を返す努力をする。
—なんだか毒島刑事の言葉を聞いているようです。
似ていますね(笑)。論理性を突き詰めていくと、どんどん自分の評価が低くなっていく。逆に、自己評価が高い人ほど理屈がなくなっていく。論理的な毒島刑事は、自己評価が低くて当然です。
危機に覚えた幸福、
読者は必ず存在する
—毒島シリーズは、本作の次にあたる第三弾『毒島刑事の嘲笑』も連載は終わっています(小誌2019年7月号から2020年4月号に掲載)。
敵は「思想」で、右も左も真ん中も全部敵に回しています(笑)。第三弾のあとは、オファーがあれば書かせてもらいます。
もともとシリーズにするつもりはなかったんですよ。他のどのシリーズもそうですが、結果的にそうなったものばかりです。最近になって、一作目からシリーズものとして考えてほしいというオファーがありましたが、はじめてでしたね。
でも、シリーズものは難しいですよ。出し惜しみすると読者には絶対わかっちゃいますから。全力投球しているから、主人公の行く末を確かめたい、という気持ちになる。たとえば、大沢在昌さんの『新宿鮫』や京極夏彦さんの『姑獲鳥の夏』、往年の人気シリーズの第一作にはすべてが凝縮されていると思います。
毒島シリーズも、すべてを注ぎ込むという気持ちで毎回書いています。出さなかったら宝の持ち腐れ。ストーリーにしてもキャラクターにしてもその時にやらなきゃいけないことが必ずある。その代わりに、毎回乾いた雑巾を絞るようなことになるんですけど(笑)。
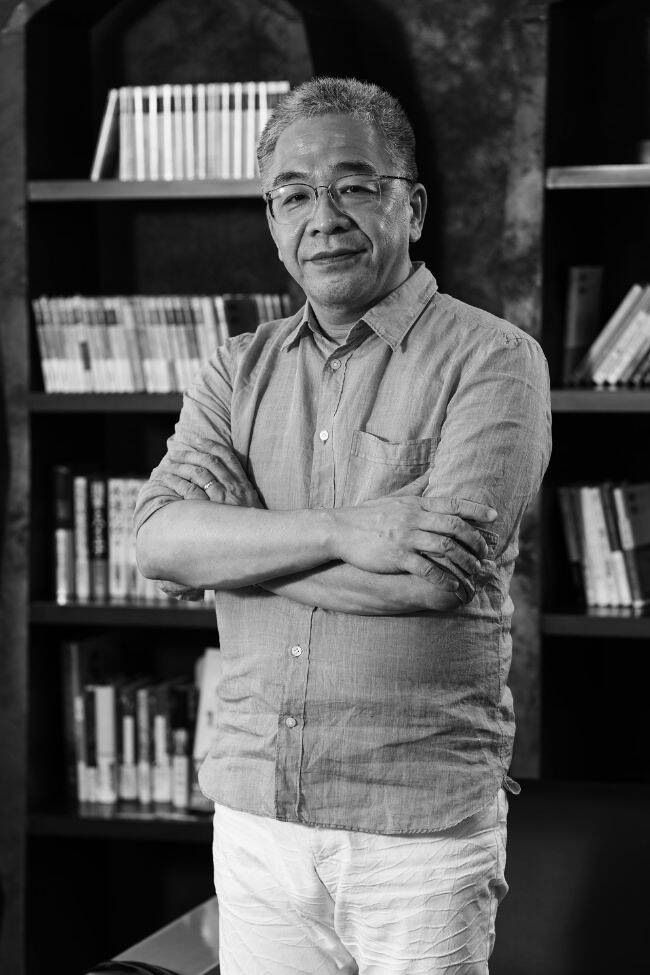
—本作は非常事態と言っていい状況が続くなかでの刊行です。ここコロナ禍で、どんな影響がありましたか?
今後、二〇二〇年という時代設定で書くと、コロナの話は避けて通れない。みんながマスクをしている生活をどう描写するか。握手もハグもできない。恋愛ものや官能小説といったジャンルは変わらざるを得ない。パラダイムシフトですね。
ミステリーではコロナをトリックに使う人が出るでしょうね。マスクを使った一人二役とか、私ももう三つほど考えました。
生活としては、コロナ禍前もずっと引きこもって原稿を書いてたのでまったく変わっていません。でも、どれだけ版元さんや書店さんが大変な目に遭ったかと考えると、何としても利益を生み出せるものを書かなければいけない。そういう危機感があります。利潤を生むものを書けなかったら明日から仕事はないとも思っています。
そんなシビアな状況ですが、うれしかったこともありますよ。しばらく閉まっていた本屋さんが開いた時、気になってた本をたくさん買ったとネットで報告している人がいて、あぁ、本を好きな人がいるんだなって、ほんとに慰めになりました。私はこういう人たちのおかげで生活できているんだって、正直にそう感じました。だからこそ、裏切っちゃいけないなって思います。みなさんが楽しめるものを書きたいです。
毒島刑事最後の事件

刑事・毒島は警視庁随一の検挙率を誇るが、出世には興味がない。犯人を追うことに何よりも生きがいを覚え、仲間内では一を話せば十を返す能弁で煙たがられている。そんな異色の名刑事が、今日も巧みな心理戦で犯人を追い詰める――。7月22日発売、ミステリー作家・中山七里さんの新刊『毒島刑事最後の事件』を紹介します!
















