
華やかな学歴・職歴、野心をもった女として生きるときの、世の中の面倒くささとぶつかる疑問を楽しく描いた『高学歴エリート女はダメですか』(山口真由著)は、女性だけでなく、男性読者からも共感を得ながら、絶賛発売中。本書から試し読みをお届けします。
あのときの悔しさを忘れない
小出恵介が17歳の少女と性行為に及んで、結果として無期限で活動中止となったというのが、目下の私と妹の家での話題だ。
17歳の少女に落ち度があったのか知らないが、小出恵介に傲慢で短慮な側面があったのも、否定しがたい事実であるというのが、我々が到達した結論である。
小出恵介が17歳の少女に対して、「20代半ばの女がすごいアプローチをかけてきたけど、そんなババア、俺が相手にするわけがない」という趣旨を語ったと、「フライデー」に書かれていた。
っていうかさ、小出恵介って33歳(当時)なわけじゃん? どういう神経があれば、33歳の男が自分より10歳近く若い女性を「ババア」呼ばわりできるわけ?
この発言が、私たち30代女性にとって決定打になることは間違いない。そして、小出ファンの多くは30代の女性なのだろう。ということで、彼が完全復活に至るまでの前途は多難である。
私は29歳のときに、友達の家で会った男の人に「いくつ?」と聞かれた。年齢を答えると「なんだ……ババアじゃん」といわれて、一瞬、言葉を失った。
念のため付言するけど、相手は30代後半で、身長が低くて、顔色が悪くて、趣味の悪いニット帽を室内でも被った自称クリエイターという(=いかがわしい)……。その上から目線は、いったいどこに根拠があるのよ? だけど私はこのとき、何も言い返すことができなかったのだ。今思い出しても悔しい。
(1)上野千鶴子にフェミニズムを学んだタレントの遙はるか洋子は、「『年齢は?』と男に聞かれたら、『年収は?』と聞き返す」らしい。なかなか戦闘的だ。
(2)夏木マリのクラスになると、「年齢は単なる記号にすぎない」という有名な名言で切り返すこともできる。まぁ、夏木マリさんに年齢を聞いたりしないだろうが。
このとき私が言い返せなかったのは、「若さ」は女の価値のひとつと思っているからだ。
「モテる自慢」の一言で片づけられた送り狼未遂事件
転職を考えていた20代のころ、同業の大先輩に紹介された。私より30歳近くも上で、仕事での評価が確立した人だ。はじめはオフィスで会い、その後、紹介してくれた人を交えて飲みに行った。後日、「食事でもしよう」と、またお声がけをいただいた。仕事上のアドバイスから国際社会の中の日本の位置づけまで、彼はなんでも一家言あり、ひとかどの人物という感じだったし、そういう人が私を面白い話し相手と評価してくれていることに、一人前の社会人になったような誇らしさを覚えた。
送ってくれるという紳士的な大先輩のお言葉に甘えて、私は一緒にタクシーに乗った。だから、私の家の前でタクシーが止まり、私と一緒に彼も降りてこようとしたとき、一瞬、その意図を理解できなかった。
「いいじゃない?」
という彼のささやきが、やけに生々しく耳に響き、私は瞬時に彼の意図を悟る。
だからこそ、あくまで気づかないふりをして、「またまたぁ」と笑い飛ばし、後部座席のドアをバタンと閉めて、タクシーの運転手さんに
「ご自宅までお願いします!」
とできるだけ、からっとした口調で告げたのだ。

一人で家に帰ってシャワーを浴びていたら、急に自分が惨めに思えて泣けてきた。そこで、私は、その当時付き合っていた人に電話をかけた。
付き合っていた彼と話すうちに、私は二つの事実に衝撃を受けた。ひとつめは、親子ほど年の離れた大先輩であろうとも男性と二人でごはんを食べたことを彼が面白くないと思っていること。二つめは、「はい、モテる自慢ね」と片づけられたこと。
そこで、私は学んだのだ。
私たち働く女子と働いて社会を支えてきた男性たちとの間には、埋めがたい溝があると(で、とにかくその日は一人でやけ酒を決め込む……)。
「男たちは女子をメスと見ている」
後年、私はやっぱりこのタクシーでの出来事に納得できずに、他の男友達に愚痴をいった。
「ねぇ、これってセクハラだよね!?」と。
すると、男友達は私にこう告げた。
「何いってるんだ。君にはNOという権利があったんだろ。じゃあ、それはセクハラでもなんでもないだろう。だいたいねぇ、男たちは常にお膳立てして奢って誘って、女たちは最後にNOというだけなんだ。これがダメなら、もはや口説くことすらできないだろう」
そうなのか。そういうことなのか。
大学1年生になったばかりの東大のクラスで、私は「男子」についてある発見をした。全60名中女子が6名という圧倒的な偏りのあるクラスは、大半が男子校出身者だった(←偏差値が高い学校には男子校が多いから)。
男子校出身者の多くは、女子と目も合わせず、会話もぎこちない。だが、それは無関心ではなく、逆に異性に対する関心の裏返しだ。実際、男たちだけの空間では、クラスの女子を話題にして評価するらしい。その評価の内容は、成績でも能力でもなく、主に私たちがどれだけ性的にアピーリングであるかというところにあるらしい。
ハーバード大学の男子サッカー部員だって、女子部の1年生を性的に評価してレポートにまとめて部内で回し読みしているのだから、これは知性や教養が低いゆえ云々という問題ではない。
「彼らは女子をメスと見ている」。それが私の発見だった。
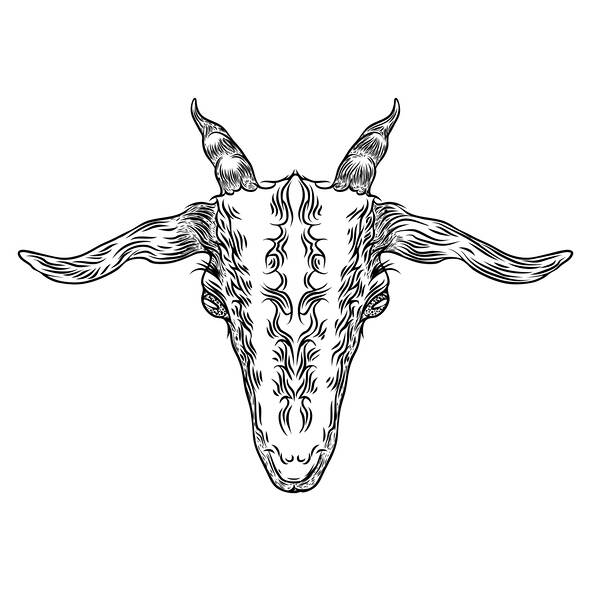
もっとも、性的対象と見られることに憤慨するほどでもなかった。だいたい、ニキビを頬に残す10代の男の子たちは、見た目からわかりやすくオスの匂いをぎらつかせていて、滑稽こつけいだとは思ったが、脅威に思うほどでもなかったから。
ところが、大学生活中から、彼らは明らかに垢抜けはじめ、社会に出て働きはじめてからは、着るものも食べに連れて行くところもスマートになった。家族を持って社会的地位を得てからは、昔のとがったオス臭さなんてまったく感じられないほどに、「余裕のある紳士」になった人が大多数だろう。
「女として見られること」への優越感と嫌悪感
だが、一人でタクシーを降りて家に帰った私は、上辺がどれほど洗練されようが、(全員ではないだろうが、少なくとも一部の)根本にはあのオス臭さが残っているのだと知って厭わしさを覚えた。駒場キャンパスの能天気な青空のもとでは滑稽に感じた欲望を、このときの私は笑えなかった。オス臭さがわかりやすくプンプンする男の子たちとは異なり、上辺を取り繕って、常識ある大人として登場しながら、同じ欲望を隠し持つのは卑劣だと感じたからだ。
最近になってそれが、相手への憎悪ではなく、自分への嫌悪ではないかと思うに至った。
性的な関心を向けられたとき、おそらく、私は、反射的に優越感と嫌悪感の両方を抱く。
優越感は、同期の男の子たちにはアクセスできない、自分にだけ開かれたドアがあるということに対して。いや、もっと直截的に、どれほど円熟した男であろうと、この瞬間の愚かな衝動をコントロールできないことに対して。その原因の一端が私にあるとしたら、私は彼を支配しているような、そんな全能感がわく。
嫌悪感は、自分に媚びがあったことに対して。若いときでさえ、いや、若いときだからこそ、私は、それがある種の男たちに代えがたい価値を与えることを十分に理解していた。そして、その構造に乗っかったのだろう。いや、そういう理性的な計算だけならまだよかった。どこかで私は女として見られることに、愉悦があったのかもしれない。そのとき、私は、彼らが私をメスと見たのではなく、私自身の中にメスを見出して、心底、「気持ち悪っ」と思った。
優越と嫌悪──女性であることへの強い執着を、私は自分の中に見出す。私の感じた優越の一端は、お釣りがくるような年齢差にあった。駒場キャンパスの大学生のように若者同士ではない。「若さ」の価値を共有する者の間では、年齢差は若いほうに優越感をもたらす。
年を経ても私は、女であることから逃れられないだろう。ならば、これから年を取るにしたがって、優越感は薄れ、嫌悪感ばかりが強くなっていくのだろうか。
そして、私はあのときタクシーから一緒に降りてこようとした男を憎んだ。あの男のオス臭さに反応して、私は自分の内側にメスの匂いを見つけ、嫌悪感にうんざりする。でも、それでも相手の目の中に確認せざるをえない。私がまだ性的対象として見られうるかを。
こんなグダグダした複雑な惨めさを生み出したのが、あっけらかんとした単純な欲望なんて、とてつもなく恨めしい。
待って。深刻な話を書いててふと我に返ったけど、最近、複雑な葛藤とかないかも。「いくつ?」とか聞いてくる男たちがいるチャラチャラした場所に行かなくなったし(っていうか、呼ばれなくなったし)。大先輩とごはん行くより、家のお風呂でチューハイ飲むほうが楽しいし。うむ……女であることから解脱したのだろうか。やばい。瀬戸内寂聴ばりの悟りとかまだ開きたくないわ──。欲望、カモン。
高学歴エリート女はダメですかの記事をもっと読む
高学歴エリート女はダメですか

華麗なる学歴はもとより、恋も仕事も全力投球、成功への道を着々と歩んできた山口真由氏。ある日ふと、未婚で37歳、普通の生活もまともにできていないかもしれない自己肯定感の低い自分に気づく――。このままでいいのか? どこまで走り続ければ私は幸せになれるのか? の疑問を抱え、自身と周囲のハイスペック女子の“あるある”や、注目の芸能ニュースもとりあげつつ、女の幸せを考えるエッセイ集。
















