
登場人物全員、同姓同名! 著者最高傑作、2020年最高の社会派ミステリの呼び声高い話題のノンストップミステリ『同姓同名』のプロローグを抜粋してお届けします。お楽しみくださいませ。
『同姓同名』
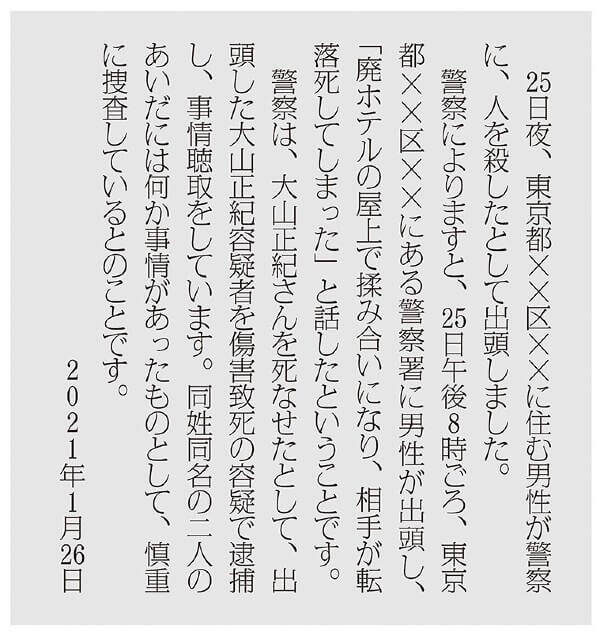
プロローグ
九月のIOC総会で東京での開催が決まったオリンピックの話題に世間が沸く中、大山正紀(おおやままさのり)は他人に知られるわけにはいかないどす黒い感情を押し隠し、血の色の夕日に照らされた公園の草むらに潜んでいた。
大山正紀は影と化して公園内の様子を覗き続けた。呼吸するたび、白い吐息が湿った葉を揺らす。
木製ベンチの上で女児が飛び跳ねていた。弟らしき男児が紙飛行機を掲げ、その周りを走り回っている。
「ほら、危ないから下りて」
母親が女児を抱き上げ、砂地に下ろした。膨れっ面で抗議する女児。駄目、と言い聞かせる母親──。
男児が母親のスカートの裾を握り締め、呼びかけた。
「僕、ブランコで遊びたい!」
母親はブランコを見た。一つだけのブランコは、小学校低学年の女の子が揺らしている。
「お姉ちゃんが遊んでるでしょ」
「やだやだやだ! 僕もブランコ!」
男児はブランコを見つめながら、全身でスカートの裾を引っ張った。
「我がまま言わないの!」
夕暮れ時の公園に響き渡る母親の怒声。何人かの少年少女が振り返ったものの、すぐ自分たちの世界に戻った。
大山正紀は公園にいる人間の一挙手一投足を観察していた。
ブランコの女の子が漕ぐのをやめ、降り立った。可愛らしい顔立ちだ。男児に近づき、ブランコを指差す。
「使っていいよ」
男児の顔がぱっと明るくなった。
「ありがとうね」母親が女の子にほほ笑みかけた。「いいの?」
「……うん。飽きたから」
男児はブランコに駆けていき、立ち漕ぎしはじめた。
母親が男児のもとに駆けつける。
「ほら、危ないから座って乗りなさい!」
男児はぶーぶーと文句を言いながらも従った。母親がそばで見守る中、おとなしくブランコで遊びはじめる。
大山正紀は草むらの中でじっとしたまま、女の子を目で追った。乾いた唇を舌で舐める。
女の子は公園の片隅でしゃがみ込み、散らばった枯れ葉の中で咲く一輪の白い花を突っついている。
大山正紀は女の子を眺め続けた。目の前の草を蜘蛛が這はっている。身じろぎせずにいると、蜘蛛は葉から大山正紀の顔に移った。皮膚を這う脚の感触──。
蜘蛛は頰を這い回ったあげく、ぽとっと土の上に落下した。大山正紀は視線を落とすと、指で蜘蛛を押し潰つぶした。体液が弾け、指先にこびりついた。親指と人差し指をこすり合わせながら、また女の子に目を戻す。
そのうち公園から少しずつ人が消えていく。
母親が女児と男児を連れて帰ると、女の子はまた一人でブランコに座った。錆さびた鎖を軋きしませながら漕ぎはじめる。
午後四時半になると、公園に残っているのは子供たちだけになった。
大山正紀は、ブランコで遊ぶ女の子を見つめた。奥の砂場では、幼稚園児と思おぼしき女児と男児が仲良く小山を作っている。
大山正紀は、ふー、ふー、と息を吐いた。腐葉土のような臭気が鼻をつく。
纏わりつく草が冷気を遮っているからか、体そのものが熱を持っているからか、寒さは全く感じなかった。むしろ、ジャンパーが暑く、高熱を出しているようだった。
閑静な住宅街の片隅にある公園だ。十メートル走をするまでもなく反対側に出られる木立があり、その入り口の横にコンクリート造りの公衆トイレがある。
近所の人たちはみんな顔見知りで、事件などもなく、暗くなるまで子供たちだけで遊ばせておいても心配がない。
だからこそ、狙い目だった。
大山正紀は意を決し、草むらから姿を現した。ジャンパーやジーンズに付着した葉っぱを払い落とす。
ブランコに近づき、女の子に声をかけた。
「ねえ。ちょっといい?」
女の子は揺らしていたブランコの速度を落としていき、停止した。ワンピースから伸びる両脚をぶらぶらさせながら、不思議そうな顔で大山正紀を見上げる。
「一人で遊んでるの?」
尋ねると、女の子は小さくうなずいた。
「お母さんは?」
「夜までお仕事だよ」
「友達はいないの?」
「……学校にはいるよ」
夕暮れの公園同様、寂しげな表情を覗かせた。そこに付け入る隙があると思った。
「面白い物を見せてあげよっか?」
具体的に何かの名前を出したら、『別にいい』と言われたときに困る。抽象的な台詞せりふで興味を引けば、食いつくはずだ。
案の定、女の子は身を乗り出した。
「面白い物って何?」
「それは秘密だよ。こっちには持ってこられないんだ」
「大きいの?」
大山正紀は両腕を目いっぱい使って大きさを表現してみせた。何なのか分からないほど想像が膨らむものだ。
「魔法みたいに不思議な物だよ」
「魔法!」
女の子は目を輝かせていた。
「そうだよ。本当は誰にも見せちゃ駄目なんだけど、君だけは特別だよ」
「どこにあるの?」
「あっちだよ」
大山正紀は公衆トイレの方向を指差してみせた。四本の常緑樹の陰に建っているので、公園の中からは死角になっている。
女の子は迷いを見せた。
「……見たくないなら他の子に見せるよ」
大山正紀は他の子を探すそぶりを見せた。女の子にはもう興味をなくしつつあるように装う。
立ち去る気配を匂わせると、女の子がブランコから立ち上がった。小さな手で大山正紀のズボンの腰部分を握る。
「何?」
素っ気なく訊きいてやる。
「……あたし、見たい」
──食いついた。
大山正紀は唇の端が緩むのを感じながら、女の子に手を差し伸べた。
昼間の通り雨による水溜まりは、泥水の中に夕日を飲み込み、血溜まりに見えた。
* * *
(次回に続く)


















