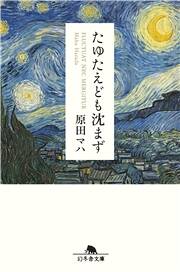19世紀後半、栄華をきわめるパリの美術界。画商・林忠正は、助手の重吉とともに浮世絵を売り込んでいた。野心あふれる彼らの前に現れたのは、日本に憧れる無名画家・ゴッホと、兄を献身的に支える画商のテオ。その奇跡の出会いが「世界を変える一枚」を生む……。原田マハさんが贈るアート小説、『たゆたえども沈まず』。読むほどに引き込まれる物語の冒頭をご紹介します。
* * *
「どうぞ、中へ」
ドアが大きく開けられ、重吉は、竜宮城に招き入れられた浦島太郎よろしく、おっかなびっくり、室内に足を踏み入れた。

室内は、ありとあらゆる日本美術の書画工芸品で埋め尽くされていた。
勇ましい鷹と松林が描かれた屏風、竜虎のふすま絵、山と積まれた巻物、螺鈿が施された漆器の文箱、朱漆の鏡台、手鏡、銅器、銀器、日本刀の鍔、金泥の仏画――。中国製の黒漆の椅子や紫檀の卓、衝立、文人画のたぐいもある。そのすべてが整然と展示され、窓からの光を反射して鈍い輝きを放っていた。
「これは……」と重吉は日本語でつぶやきかけて、すぐさまフランス語で言った。
「すごい。まるで、美術館に迷い込んだようだ」
と、そのとき。
松林鷹図屏風の裏で、くすっとかすかな笑い声がした。続いて、いかにも愉快そうな声色の日本語が聞こえてきた。
「なかなかやるじゃないか、シゲ。独り言もフランス語で言えるとはな」
はっとして、重吉は、屏風のほうを振り向いた。
屏風の陰から、黒い三つ揃いのスーツとシルクのタイを身に着け、黒髪をきっちりと撫でつけた、すらりとした男が現れた。
男は、頬を紅潮させてぽかんとしている重吉に向かって、にやりと笑いかけた。
「よく来たな、シゲ。待っていたぞ」
男の名は、林忠正。
日本美術を扱う美術商「若井・林商会」の主であり、目下、パリの美術市場に「ジャポニスム」という名の嵐をもたらしている風雲児であった。
加納重吉が林忠正と出会ったのは、かれこれ十年以上まえのことになる。
しかしながら、その日の記憶は、重吉の中にしっかりと刻印されて、鮮やかに残っている。
一八七四年(明治七年)、重吉は、旧加賀藩・石川県から、官費生として東京の開成学校に入学した。
代々高名な蘭学者の家に生まれた重吉は、幼い頃より抜きん出た秀才であり、早くからその将来を嘱望されていた。十九歳になったとき、県の支援を得て、外国語と西洋の学問を修め、故郷に帰って官吏として活躍するべく、東京へと送り込まれたのである。
開成学校は、明治維新後、政府によって開校された西洋の各学科を教える「大学南校」が、幾度かの改変ののちに外国語と西洋の学問の専門学校となったものである。最終的には一八七七年に東京医学校と合併して東京大学と総称されることになる。
重吉は、その秀才ゆえだろうか、自分はほかの誰とも違う、ほかの誰かと同じであってはいけないと心密かに思っているところがあり、少々ひねくれた性質も併せ持っていた。そんなこともあって、開成学校に入学する際、迷わずにフランス語を専攻できる諸芸科を選んだ。
諸芸科というのは、法学、理学、工学の三つの専門学科に対して、総合的に一般教養と語学を学ぶ学科で、いってしまえば雑多な学科であった。
重吉の学力をもってすれば、ほかの三つの学科のどれを専攻してもじゅうぶんに才能を発揮できたはずなのに、彼はそうしなかった。三つの学科は英語を基本として学習するので、それまでドイツ語やフランス語を学んできた学生、あるいはこれから学びたい学生にとっては、在籍するのは本意ではない。重吉は、すでに郷里で英語を独学し、習得してしまったという気持ちだったので、せっかくならば違う言語を身に付けたいと思っていた。
「明治」に元号が改まり、七年が過ぎていた。日本はそろそろ本気で諸外国に追いつかなければならない頃だった。東京府にはガス灯が点り、大通りには街路樹が植栽された。世界地図の中で、日本だけが空白のまま取り残されるわけにはもはやいかないのだ。
開成学校では、優秀な生徒を十人ほど選抜し、先進諸国へ留学させる制度を持っていた。フランス留学は、わずかにひとり、できるかできないかであったが、重吉は最初からこれを狙っていた。
――日本から一歩も出ないで外国の学問を教わったところで、しょせん、井の中の蛙じゃないか。
本気で学ぶなら、留学するしかない。アメリカやドイツではなく、フランスへ。
おれは、外国をこの目で見て、ほんものの世界を知って、金沢はもちろん、日本の役に立つようになるんだ。
そのためには、なんといってもパリだ。パリこそは、産業も文化も世界一だと聞く。ということは、世界の中心ではないか。
胸のうちに、そんな闘志を燃え上がらせていた。気分だけは「天下取り」のつもりだった。
だから、「フランス馬鹿」の偏屈な男だとか、とっつきにくいやつだとか、同級生たちから陰口を叩かれようとも、べつだん気に留めず、ただひたすらフランス語の学習に没頭した。

当初はあまのじゃくな気持ちも多分にあって始めたフランス語だったが、勉強するうちに、その奥深さにどんどん引き込まれていった。
フランス語とは、まるで言語の芸術のごとしだ。なめらかな発音。綴り。構成。――すべてが一幅の山水画のようにも感じる。
フランス人の教師が教科書として与えてくれた数々の本――ジャン=ジャック・ルソーなどの書に加え、ジョルジュ・サンドやデュマなどの小説を読むにつれ、どうしようもなく心が震えた。
いつか、必ずフランスへ――パリへ行きたい。
手が届かない貴婦人に憧れるように、重吉は、パリへの思いを募らせた。
そしてついに、日本人の担当教官、庵野修成から、君を留学生に推薦しよう、とのひと言を得た。全生徒の中でも抜きん出て語学が堪能な君こそ留学生にふさわしい、と言われて、まんざらでもない気がした。
ところが、留学先はイギリスだという。重吉は、即座に推薦を辞退した。
――本気で世界の真ん中で活躍したいなら、パリでなければ意味がないんだ。
頑なにフランス留学にこだわる重吉を、同級生たちは陰でせせら笑った。
――そうまでしてフランスに忠義を立てるなんて、ほんもののフランス馬鹿だな。
――いまや英語かドイツ語が主流なんだ。フランス語にうつつを抜かしてたら、出世できんぞ。
――あいつは出世する気なんざ、さらさらないのさ。華族の令嬢の家庭教師あたりが、いってせいぜいのところだろう。
重吉の耳に届くように、わざと近くでひそひそ話をする輩もいた。
――好きなように言えばいい。蛙どもが……。
そう強がってはみたが、留学を果たせなければ、自分だとて蛙の中の一匹なのだ。
――どうしたらいいんだ。
悶々とするうちに、次第に勉強に身が入らなくなってしまった。どんなにがんばっても、空回りしているだけのような気がしてきた。
――どうすれば、フランスへ行けるんだ。……井戸の外へ出られるんだ。
そんなある日のこと。
開成学校の校門から通りへ出たとき、ふいに背後から声をかけられた。
「Souhaitez-vous aller Paris?(パリに行きたいんだって?)」
はっとして、立ち止まった。
――フランス人?
振り向くと、見知らぬ日本人の青年が校門の傍らに立っていた。青年は、重吉の驚いた顔をみつめて、ふっと笑った。
「君は、なかなか賢明だな」
言いながら、重吉の隣へと歩み寄り、「行こう」と小声で言った。
「おれたちがつるんでいると、英国一派がまたなんだかんだよからぬ噂を立てるだろう。……ちょっと付き合ってくれないか」
重吉の返事も聞かずに、そのまま、日本橋の茶屋まで連れ出した。
その青年こそが、林忠正であった。
忠正は二十三歳で、開成学校が南校だった時代に廃藩置県まえの富山藩から派遣されて入学し、重吉の三年先輩だった。諸芸科に林という名の大変な秀才がいる、と噂に聞いてはいたが、重吉が直接会うのはそれが初めてのことだった。
忠正のほうでも、三年下にとんでもない語学の秀才が入った、と聞いて、こちらは当初から注目していたという。
「どれほどの秀才か、一度話をしたいものだと思っていたんだ」
茶屋に落ち着いたあと、忠正は、手酌で熱燗を飲みながら、ごくすなおな口調で言った。
重吉は、自分が先輩であろうと高飛車に構えず、まっすぐに好奇心を向けてくる忠正の様子に、たちまち好感を持った。
「聞けば、君は、庵野先生から頂いた英国留学への推薦を辞退したそうじゃないか。大変な噂になっていたぞ。……英国留学といえば、出世の道が拓けたも同然じゃないか。誰だって飛びつきたいはずなのに、どうしてなんだ?」
「それは……」
重吉は、一瞬うつむいたが、すぐに顔を上げて答えた。
「……イギリスには、パリがないからです」
忠正は、きょとんとして、目を瞬かせた。それから、ぷっと噴き出して、笑い出した。あんまり笑うので、周りの客が皆、ふたりを見ている。重吉は、たまらなくなって、
「林さん。……そんなに笑わないでくださいよ。笑いすぎですよ」
小声で言ったが、なんだか自分もおかしくなってきて、つい、一緒に笑い出してしまった。
気持ちよく笑い合ったあと、忠正は、「いやあ、いいな。実にいい」と、涙目になって言った。
「そうなんだ。その通り。イギリスには、パリがない。パリじゃなけりゃあ、意味がないんだ。おれもまったく同感だ」
愉快そうな声でそう言って、徳利を差し出した。
「さあ、飲んでくれ、我が同志よ。パリの話をしようじゃないか」