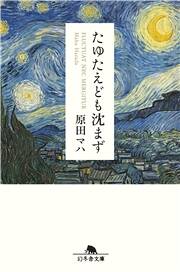19世紀後半、栄華をきわめるパリの美術界。画商・林忠正は、助手の重吉とともに浮世絵を売り込んでいた。野心あふれる彼らの前に現れたのは、日本に憧れる無名画家・ゴッホと、兄を献身的に支える画商のテオ。その奇跡の出会いが「世界を変える一枚」を生む……。原田マハさんが贈るアート小説、『たゆたえども沈まず』。読むほどに引き込まれる物語の冒頭をご紹介します。
* * *
忠正は、富山藩の医学の名門、長崎家に生まれ、その後、親族の林家の養子となり、家督を継いですぐに東京へ出て新しい学問を志した。特に、外国語を学ぼうと心に決めていた。

忠正が選んだのは英語ではなく、フランス語であった。重吉同様、彼もまた、多少斜に構えているところもあったのだが、ナポレオン公の物語に触れる機会があり、革命の嵐が吹き荒れ、ついにナポレオンが手中にした天下の都、パリに憧れて、フランス語を習得しようと決心したのだった。
学び始めた頃は、フランス語を学んでいるといえば、人の見る目も変わったものだが、最近すっかり世の中の風潮は英語一辺倒で、フランス語を学んでいるといえば、変わった人を見る目になる――と忠正はぼやいた。
「ときに、知っているか。おれたちが在籍しているフランス語の諸芸科……今期で廃止されるそうだ」
えっ、と重吉は思わず身を乗り出した。
「まさか……まったく聞いていませんよ、そんなこと。それじゃあ、僕らはどうなるんですか」
忠正は、「さあね」と人ごとのように言って、勢いよく猪口をあおった。
「フランスに行くほかはないな」
世界の列強国にくらべて、長いあいだ国を閉ざしていた日本は、もっと貪欲に自己主張をしてしかるべきだと、忠正は考えていた。
そのためには、世界中から富と人と文化が集まってくるパリで、日本人が闘っているところを見せてやろうじゃないかという思いがあった。
重吉同様、忠正もまた、フランス留学の道を探っていた。しかし、圧倒的に英語ができる生徒が増えたいまとなっては、高い公費を使ってフランスに留学生を送り込むくらいなら、イギリスかアメリカに送ったほうが人材を活かせるだろう、ということで、政府も学校も、フランス公費留学を廃止しようとしているらしかった。
「やはり、狭き門、というわけですね……」重吉がつぶやくと、
「狭くったって、入り込む隙間があればいいさ。門は閉ざされたも同然なんだ。フランスのほうが、アメリカよりもずっと長い歴史と伝統があるし、イギリスに負けず劣らず文化も芸術もあるってのに……こんちくしょう」
吐き捨てるように忠正が言った。重吉は、返す言葉を失って黙りこくった。
ふたりは、しばらく黙ったままで、開いた障子の向こう側に流れている隅田川の支流を眺めるともなく眺めていた。
ややあって、忠正は、ついと膝を立てると、
「気持ちのいい宵だ。少し、歩いてみるか」
と誘った。
川面を渡る五月の宵風が、少し酔った頬に心地よかった。ふたりは、並んでそぞろ歩きしながら、日本橋のたもとへやって来ると、どちらからともなく立ち止まった。
川岸の杭に小舟が何艘も綱でつなぎ留められ、ぎいい、ぎいいときしんでいる。ちゃぷちゃぷと川水がその腹を叩く音が響き、磯の香りが漂っている。
重吉は、橋桁が川面に落とす闇の中で、生き物のように舟々がぶつかり合ってうごめくのを眺めながら、もはや自分が活かされる道はないのだろうか――と、暗澹とした気持ちが胸の中に広がるのを感じていた。
傍らで長いこと沈黙していた忠正だったが、ふと顔を上げると、「なあ」と重吉に語りかけた。
「たゆたえども沈まず――って、知ってるか」
突然のことで、今度は重吉が目を瞬かせた。忠正は、ふっと笑みを口もとに浮かべた。
「パリのことだよ」
「……パリ?」
「そう。……たゆたえども、パリは沈まず」
花の都、パリ。
しかし、昔から、その中心部を流れるセーヌ川が、幾度も氾濫し、街とそこに住む人々を苦しめてきた。
パリの水害は珍しいことではなく、その都度、人々は力を合わせて街を再建した。数十年まえには大きな都市計画が行われ、街の様子はいっそう華やかに、麗しくなったという。
ヨーロッパの、世界の経済と文化の中心地として、絢爛と輝く宝石のごとき都、パリは、しかしながら、いまなお洪水の危険と隣り合わせである。
セーヌが流れている限り、どうしたって水害という魔物から逃れることはできないのだ。
それでも、人々はパリを愛した。愛し続けた。
セーヌで生活をする船乗りたちは、ことさらにパリと運命を共にしてきた。セーヌを往来して貨物を運び、漁をし、生きてきた。だからこそ、パリが水害で苦しめられれば、なんとしても救おうと闘った。どんなときであれ、何度でも。
いつしか船乗りたちは、自分たちの船に、いつもつぶやいているまじないの言葉をプレートに書いて掲げるようになった。
――たゆたえども沈まず。
パリは、いかなる苦境に追い込まれようと、たゆたいこそすれ、決して沈まない。まるで、セーヌの中心に浮かんでいるシテ島のように。
洪水が起こるたびに、水底に沈んでしまうかのように見えるシテ島は、荒れ狂う波の中にあっても、船のようにたゆたい、決して沈まず、ふたたび船乗りたちの目の前に姿を現す。水害のあと、ことさらに、シテ島は神々しく船乗りたちの目に映った。
そうなのだ。それは、パリそのものの姿。
どんなときであれ、何度でも。流れに逆らわず、激流に身を委ね、決して沈まず、やがて立ち上がる。
そんな街。
それこそが、パリなのだ。
「なあ、シゲ。……おれは、いつかきっと行く。行ってみせる。たゆたえども、決して沈まない街……パリに」
シゲ、と親しみを込めて呼ばれて、重吉は、水面にたゆたう小舟に放っていた視線を、傍らの忠正に向けた。
忠正の横顔は、凜として風を受けていた。その瞳は、未来を見据えて輝いていた。

一八八六年 一月上旬 パリ 二区 モンマルトル大通り
狭くない店舗の壁を埋め尽くして、数え切れないほどの油彩画がみっちりと隙間なく掛けられている。
それらの多くは、裸体の女神像、もしくは裸体の神々の群像である。やや暗く、深い奥ゆきのある背景の中に燦然と浮かび上がる、まぶしいほど白い裸体。かたちよくふくらんだ乳房、きゅっとくびれた腰、なめらかな肌。女神たちの体は、すみずみまで明るく光がゆき届き、ただひとつの傷も一点のしみも描かれていない。当然、性器など存在しないかのように、その部分から消し去られている。
薔薇色の頬は夕暮れの空のように照り映え、みずみずしい瞳は星を宿したようにきらめいている。いたずらなキューピッドが舞い降りて、女神のつややかな唇にそっと接吻する。女神は驚いて、しかし陶然と、可憐なくちづけを受けている。
ほかの絵では、魔物と闘う勇敢なアポロンが描かれている。盛り上がった筋肉に、鈍く輝く甲冑を着け、剣を勇ましく振りかざす。
またほかの絵では、うっすらと蒸気にけむるヴェネチアの港をいままさに出る帆船、その舳先にはポセイドンが猛々しく立ち、はるか彼方の理想郷を指差して、出航の時を告げている。
それらの絵の前に、ひとり、佇んでいる男の姿があった。
濃灰のウールの三つ揃い、固く糊を利かせたスタンドカラーのシャツ、首元にきつく結ばれた黒い織り模様のタイ。すらりと細身の体型に、仕立てのいいスーツがよく映えている。すっきりと撫でつけた赤毛の髪、鳶色の瞳。両腕を組んで、壁いちめんにぎっしりと並んだ絵を、端から端まで、ぐるりと見回して、大きなため息をついた。
――ふん。……絵空事の絵。
ここにあるのは、絵空事を描いた、どうしようもなく陳腐で、退屈で、くそくらえな絵ばっかりだ。
こんなつまらない絵を展示して、毎日毎日売りさばかなくちゃならないなんて……。
男は、仰々しい金色のフレームに収められたヴィーナスを、力ないまなざしで見上げた。それから、いかにも落ち着かない様子で、きれいに刈り込んだ口ひげに手を当てながら、よく磨いた革靴の先を板張りの床にせわしなく打ちつけた。
ここは、「グーピル商会」モンマルトル大通り支店の店内。
パリを中心に、オランダのハーグ、ベルギーのブリュッセル、ロンドン、ニューヨークにまでも支店を出し、世界的な大成功を収めている、当代きっての人気画廊である。
男は、モンマルトル大通り支店の支配人であった。名前を、テオドルス・ファン・ゴッホと言う。
五年まえ、二十四歳の若さでこの店の支配人の座を得てから、真面目に、ときに大胆に、絵を売りさばいてきた。
第三共和政下のパリは空前の好景気に沸いていた。ヨーロッパ全土に鉄道網が広がり始め、人とカネとモノとがパリを目指して集まってきていた。ヨーロッパばかりではない。やはり好景気に沸くアメリカからも、花の都・パリへと、裕福な人々が、芸術家を目指す若者たちが、次々に押し寄せてきていた。
パリに集まった資本はさまざまな投機に使われ、富める者はさらに豊かになっていった。人々は都市文化を謳歌し、浮かれ、消費して市場を肥やした。
パリほど華やかな街は、おそらく世界じゅう見渡したところでほかにはないだろう。
――まるで、大金持ちのパトロンにドレスや宝石を買い与えられる高級娼婦のようだ。
オランダ人のテオは、狂ったように人々が消費に走るこの街に、自分もまたひとかたならぬ執着を感じつつも、一方で、どこか冷めたまなざしで傍観しているようなところがあった。
かつてはパリに憧れ、恋い焦がれて、どうしてもこの街で仕事がしたくて、何もかもうっちゃってやって来たのに。
すっかり慣れ親しんだいまとなっては、どんな人間でも――異邦人であれ異教徒であれ――いともあっさり受け入れてしまうこの街の寛容さが、かえってつまらなく思えたりもする。