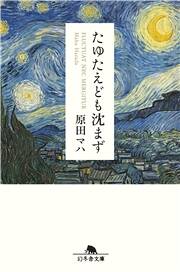19世紀後半、栄華をきわめるパリの美術界。画商・林忠正は、助手の重吉とともに浮世絵を売り込んでいた。野心あふれる彼らの前に現れたのは、日本に憧れる無名画家・ゴッホと、兄を献身的に支える画商のテオ。その奇跡の出会いが「世界を変える一枚」を生む……。原田マハさんが贈るアート小説、『たゆたえども沈まず』。読むほどに引き込まれる物語の冒頭をご紹介します。
* * *
自分だけは特別だと――だからこそ、この街に受け入れられたんだと、優越感に浸っていられたのは、悲しいほど短期間だった。
別に、自分は特別だったわけじゃない。商才があったわけでもないし、秀でた能力があったわけでもない。ただ、偶然に――十九世紀もあと十何年かで終わろうとしているこの時期に、運よくパリに居合わせたに過ぎないのだ。

仕事がうまくいき、会社の信用も得て、外国人の身であるにもかかわらず、大手画廊の支配人の立場で、この花の都の中心に躍り出たような気がしていた時期もあった。金持ちの相手をそつなくこなし、普遍的価値に裏打ちされたフランス芸術アカデミーの画家たちの絵を売りさばいて、いい気になっていたのだ。自分もまた、パリの社交界に出入りする名士にでもなったように。
実際は、社交界に出入りしている名士のお相手を務めるだけで、自分自身がえらくなったわけでもなんでもない。
確かに、それなりの給金は手にしている。同年代の仲間にくらべても、決して悪くない。いや、むしろいい。
けれど、一ヶ月分の給金をもってしても、この壁に掛けてあるいちばん有名な画家の絵――そう、あの権威主義者、ジャン=レオン・ジェロームの絵の一枚すら、買えやしないじゃないか。
テオは、いまいましげな目で、もう一度、壁いちめんに掛かっている絵を眺めた。その中央にある大型のカンヴァス、透き通ったなめらかな肌の女神の立像は、フランス芸術アカデミーの権威、ジェロームの筆で描かれたものだった。
――それにしても。
まいったな……今朝方、ブーグローの新作が到着したばかりだってのに。この壁ときたら、どうだい、蜘蛛一匹ですらぶら下がれない混雑ぶりじゃないか。
あまり隙間なく絵を掛けては、かえって絵のよさが引き立ちませんよ。このまえ、思い切って社長に忠告したのに。……客にしてみれば選択肢が多いほうがいいに決まっているじゃないか、とか言って、まったく取りつく島もなかったもんだ。
それでまた、新着の作品が掛けられていなければ、あれはどうした、なんで倉庫に入れたまんまなんだ、とかなんとか、文句たらたらになるんだろう。
まったく、どうすりゃあいいんだ。
ドアをノックする音がした。「入れ」と応えると、生真面目にきっちりとスーツを着込んだ社員のピエールが足早に入ってきた。
「マダム・シャッソーがご到着です」
「通してくれ」と言って、テオは、襟もとのタイをきゅっと締め直した。
ややあって、ボルドーのタフタとベルベットのドレスに身を包んだ婦人が現れた。テオは満面に笑みをたたえながら、こつこつとリズミカルに靴音を響かせて彼女に近づくと、優雅に差し出された子羊革の手袋の手を取り、甲に接吻した。
「ようこそ、マダム。お待ちしておりました」
うやうやしいあいさつに、シャッソー夫人は満足げに目を細めた。傍らのお付きの女性に何かささやいて帰らせてから、壁を埋め尽くした絵画を見渡して、
「それであなたのお薦めの絵はどれなのかしら、テオドール?」
そう尋ねた。フランス人はテオの名前をオランダふうに「テオドルス」などとは決して呼ばない。
「先月、私たちがシャンティにある古城を買ったことは、あなたもご存じよね? 応接間と客室と食堂に飾るものを、できるだけ早く買いたいのです。ほんとうは主人と一緒に選びにきたかったのだけど、まったく、あの人ったら忙しいのなんのって……グーピルに任せておけば間違いないんだから、ひとりで行ってテオドールに相談してこい、だなんて。ねえ、ひどいと思いませんこと?」
そして、上目遣いにテオを見た。テオは、口もとに微笑を寄せて、
「ご主人さまにご信用いただき、光栄です」
慇懃に述べて、胸に手を当てた。
シャッソー夫人の夫は貿易業で富を成し、パリ市内に百貨店を営んでいる実業家であった。自宅を飾る絵を買うのは、もっぱら夫人の役割である。
そう――夫の稼いだ金で好きなように絵を買い求めるご婦人方の相手をするには、すらりと長身で優雅な出で立ちの、どことなく色気も漂わせている若い支配人がふさわしいというものだ。

目下、パリには、シャッソーのような新興の富裕層があまた存在する。そして彼らの多くは、セーヌ県知事、ジョルジュ・オスマンのパリ大改造によって造られた瀟洒なアパルトマンに住み、地方に夏の家を所有して、応接間や、書斎や、寝室や、食堂や、そのほかありとあらゆる家の中の壁をフランス芸術アカデミー所属の人気画家の絵で飾りたがっている。彼らこそ、「グーピル商会」を潤してくれる顧客なのである。
「グーピル商会」の顧客は、壁に余白があるのは貧しい証拠だといわんばかりに、とにかく絵でいっぱいに埋めたがる。が、絵ならなんでもいい、というわけではない。「権威」と「名」のある画家に限る。応接間に招き入れた客が、おおすばらしい、この作品は誰それのものですね、と感嘆し、あなたの審美眼にはおそれいりました、と賛美を送るような、きわめつきの画家でなければならない。――そういう画家の作品を求めるなら、「グーピル商会」がふさわしい。なにしろ、あの画廊の創業者、アドルフ・グーピルの娘婿は、天下のジャン=レオン・ジェロームなのだから。
そうとも。グーピルで絵を買えば、間違いないんだ――。
「シャッソー家の新しい別荘にふさわしい作品が、ちょうど今朝ほど到着したところです」
倉庫で荷解きを終えたばかりで、さてどこに飾ればいいんだと思案していたブーグローの作品を思い浮かべながら、テオが言った。
――ちょうどいい。名画がなんたるか微塵もわかりはしない成金のマダムに、飾るまでもなく売りつけてしまえ。
「まあ、ほんとう? どこに飾ってあるの?」
壁いちめんの絵を見渡して、夫人が尋ねた。テオは、膨らませた腰にかけてぴたりと這わせたドレスの背中に、そっと手を添えて、
「まずはあなたにご覧に入れるために、まだ壁に掛けていないのです。さあ、こちらへ。すばらしい作品ですよ。間違いなく、あなた好みの……」
そして、奥の応接室へと夫人を誘い、ブーグローの作品を見せた。
海に浮かぶ貝の舟、その中央に立つ裸身の女神。つややかな白い肌、風に揺れる金色の髪。女神の周囲を飛び回る、桃のような尻を持った愛らしいキューピッドたち。
「まあ……なんてすばらしいの。ため息が出そうだわ」
筆触の跡がまったくない、きめ細かに塗り上げられたカンヴァスをつくづく眺めて、シャッソー夫人は、実際、ため息をついた。
テオのほうも、小さくため息をついた。こちらは、夫人に気づかれないように、こっそりと。
「お気に召しましたか、マダム?」
「ええ、もちろん。これ、いただくわ。ほかにはないの? 同じ画家のものは」
苦い笑みが込み上げてくるのをテオは感じていた。まったく、このマダムは、「お気に召した」画家の名前すら訊きはしないのだ。
結局、シャッソー夫人は、ブーグローの作品を三点、ジェロームの作品を一点、パスカル・ダニャン=ブーヴレの小品を二点、購入した。
テオが請求書を準備しているあいだ、シャッソー夫人は、応接の長椅子にゆったりと腰掛け、画廊の使用人が運んできた熱いチョコレートを味わっていた。花のかたちを模したデミタスカップをソーサーにかちゃりと戻すと、「ときに、テオドール。あなたは……」と、おもむろに語りかけた。
「……『印象派』とか呼ばれている画家たちのことを、どう思って?」
細かな彫りの入った華奢な作りの銀のペンを走らせていた手をふと止めて、テオは顔を上げた。
「これはまた……新興の画家一派が、あなたのお目に留まったとは。意外ですね」
「あら」と夫人は、ちょっと不満そうな声を出した。
「あたくし、流行には敏感なのよ。おかしな画家たちが世の中を騒がせていることくらい、承知していますわ」
「存じ上げております。あなたが人一倍芸術に関心をお持ちであることは。……しかしながら、印象派にご興味を寄せておられるとは、いま知りました」
「まあ、それは誤解よ」と、夫人はいっそう不満げな声で返した。
「あたくし、印象派を知ってはいても、別に興味を持っているわけじゃないわ。あんなぼさぼさに毛羽立ったような色の絵……どこが真ん中かわからないような構図も、見ていて居心地が悪いじゃないの」
「展覧会を見にいかれたことがあるのですか?」
テオはペンを動かしながら訊いた。
「もっとも、『印象派』展は、ここ数年、開催されていませんが……」
「行くわけないじゃないの、あんな……」
少し語気を強めて、夫人が返した。
「……あんなおぞましい絵を見るために、わざわざ展覧会に行くほど、あたくしひまじゃなくってよ」
「これは失礼いたしました。……おっしゃる通りです、マダム。おぞましいです、印象派など」
さらりと言って、テオはペンを置いた。
「そう? じゃあ、やっぱりあなたも、あたくしと同意見なのね?」
「グーピル商会」のエンブレム入りの便箋をきっちりと畳み、白い封筒に入れると、テオは立ち上がった。そして、夫人に向かって、にっこり笑いかけた。
「もちろんですよ、マダム。印象派……あんなものは、芸術の範疇には入りません」
そして、革の手袋をはめた手に、請求書入り封筒を軽く握らせた。