
「ルパンの娘」「K2 池袋署刑事課 神崎・黒木」で話題の横関大さん。最新刊は犬犬犬犬犬だらけのハートウォーミングミステリ『わんダフル・デイズ』。
盲導犬訓練施設で働く歩美は、訓練士の研修生。
たくさんのラブラドール・レトリバーに囲まれて、一人前になるため勉強中。
ある日、盲導犬と暮らす飼い主から「犬の様子がおかしい」と連絡を受け、犬と話せるという、美男子なのに謎多き先輩訓練士・阿久津と一緒に様子を見に行くことになるが……。
お利口に職務を全うする盲導犬たちの姿を通して見えてくるのは、その飼主、家族など、人間たちの悩み、嘘、そして罪。
毛だらけで身も心もあたたまるハートウォーミングミステリの一部を試し読み!
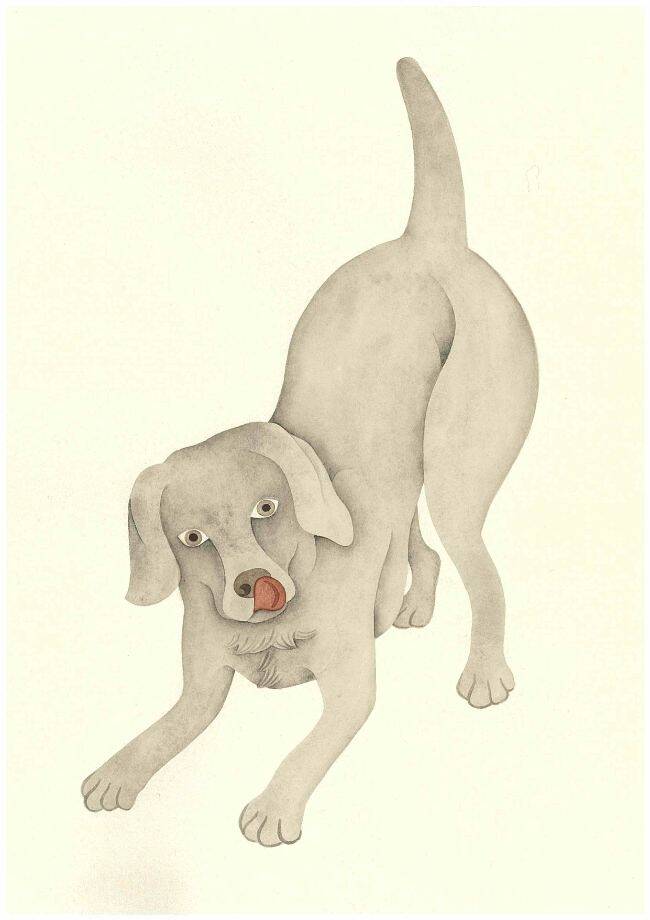
兼松家の前で車を停めた。阿久津が後部座席から降りながら言った。
「とにかく一晩、ジャックをセンターに連れていくことにする。これから兼松さんに事情を話してくるから」
「ジャック……」
ハンドルから手を離し、歩美はジャックの背中を撫でた。わずかだがジャックが震えている。しばらく待っていると、阿久津が玄関先から出てきた。そのまま車の方に向かってきた阿久津だったが、不意に立ち止まって足元から何かを拾い上げた。思案するような顔つきで、指につまんだ何かを見つめている。
「どうしたんですか?」
歩美は思わず車から降り、阿久津のもとに駆け寄っていた。阿久津が指でつまんでいるのは四角い物体だった。半透明のセロファンのようなものに包まれている。阿久津がセロファンを剝がすと、茶色い固形物が現れた。その匂いを嗅いで、阿久津が言った。
「キャラメル」
「キャラメル?」
「そう。キャラメル」
阿久津はキャラメルを手の平の上で転がしながら、何かを考えているようだった。あっ。歩美はアスファルトの上にへばりついているそれを発見する。阿久津が手にしているものと同じミルクキャラメルだった。こちらは車に踏まれてしまったようで、形状をとどめていない。
「阿久津さん、ここにもキャラメルが落ちてますよ。あっ、こっちにもある」
アスファルトにこびりついたキャラメルを剝がそうとしていると、車のドアが閉まる音が聞こえた。振り返ると阿久津が後部座席に乗り込んだところだった。窓を開けて、阿久津が言った。
「もう一軒、行きたいところがある。お願いできるかな?」
「合点承知の助」と歩美がおどけて言っても、阿久津はくすりとも笑わずに手にしたキャラメルを眺めていた。
いったんハーネス多摩に戻り、医療棟のスタッフにジャックを預け、次に向かった先は西多摩市内にある住宅街だった。路肩に車を停め、阿久津は一軒の洋風住宅のインターホンを押した。表札には『木島』と書かれていた。しばらく待っていると、中から四十代前半くらいの女性が姿を現した。
「突然すみません。ハーネス多摩の岸本です。以前、こちらでパピーウォーカーをされていましたね。その件で伺いました」
「ジャックですね」奥さんが懐かしそうな笑みを見せた。「憶えていますとも。ところでジャックが何か?」
「いえいえ。近くまで来たものですから、ジャックの近況を報告しようと思った次第です。少しお邪魔してよろしいですか?」
「そういうことですか。どうぞお上がりください」
靴を脱ぎ、阿久津とともにリビングに案内される。白い壁紙を基調とした、シンプルな内装だった。ソファに座って待っていると、奥さんがお盆を持ってやってきた。冷たい緑茶が注がれたグラスをテーブルの上に置きながら、奥さんが言った。
「それでジャックは元気にしているんですか?」
「ええ、元気ですよ」歩美はうなずいた。「ジャックは大変優秀な盲導犬になりました。今もユーザーのもとで仕事に励んでいます。ジャックが立派な盲導犬になれたのも、木島家の皆さんがパピーウォーカーとして愛情を注いでくださったお陰です。大変感謝しております」
パピーウォーカー。生後二、三ヵ月の盲導犬候補である仔犬を約一年間、自宅で預かってくれるボランティアのことだ。たっぷりの愛情を注がれる環境で成長することにより、人間とともに生活することに慣れ、人間のことが大好きな犬になる。それがパピーウォーカーという制度の目的だった。たった一年間という短い期間ではあるが、仔犬にとっても、それを預かる家庭にとっても、貴重で忘れがたい一年間になるらしい。木島家がジャックのパピーウォーカーをしていたことは、ここに来るまでの車中で阿久津から教えられていた。
「あれからもう五年、いや六年も経つんですものね。早いものですわ」
奥さんが目を細めた。木島家の方々はジャックのことを今も忘れていない。その事実に歩美は少し嬉しくなった。できればジャックをここに連れてきて、奥さんを喜ばせてあげたいところだったが、原則としてそれは禁止されている。
「ご主人と息子さんはお元気ですか? できればご挨拶をしたいと思うのですが」
木島家の家族構成についても阿久津から事前に聞かされている。奥さんは首を横に振って答えた。
「主人は仕事に行っておりますし、息子は学校です。息子は学校が終わったら塾に行くので、帰りは遅いです。主人の方も帰りは遅いと思いますよ」
話している奥さんの顔を盗み見た。初対面なので以前との比較はできないが、あまり健康そうな顔ではない。顔色も青白く、頰のあたりもやつれているような気がした。隣の阿久津を見ると、話を聞いているのか、いないのか、家の中を見回している。歩美は阿久津がここに来た真意を推理する。
ジャックの不調が木島家と関係あるとでもいうのだろうか。しかし木島家ではジャックが兼松家にいることを知らないはずだ。自分が育てた犬が誰のもとで働いているか。そうした情報がパピーウォーカーに対して明かされることはないからだ。
「ところで奥様」歩美はグラスの緑茶を一口飲んでから訊いた。「引退した盲導犬を引きとる制度があることはご存じですか?」
「ええ。そうした制度があることは存じております。ジャックを飼っていたとき、センターの方にも説明されましたから」
「ボランティアに頼らざるをえないのが、今の我々の業界の現実です。もしも木島家の方々が希望されるなら、パピーウォーカーである木島さんを最優先して、ジャックをもう一度お預けすることも可能です。ただし引退した盲導犬を引きとるということは、看とるということです。精神的にも余裕があるようでしたら、一度ご検討いただけると嬉しいです」
「有り難いお申し出です。息子もジャックのことが大好きでした。ジャックが去ってから、ラブラドールを飼おうと考えたくらいです」
当たり前のことだが、パピーウォーカーになろうと考えるくらいだから、木島家のご家族は全員が犬を好きなのだろう。
「ですが、ジャックを再び引きとることはないと思います」
奥さんが小さく頭を下げた。その表情はどこかしら悲しんでいるように見受けられた。
「わかりました。別に無理にとは言いませんので、気になさらないでください。我々はこれで失礼します」
歩美たちは奥さんに見送られて外に出た。時刻は午後二時になろうとしていた。朝早くから働いているので、お腹が空いている。
「それで何かわかったんですか?」
歩美がそう訊いても、阿久津は返事をしない。黙って俯いている。
「センターに戻りましょうか。車の中で話を聞かせてください」
歩美がそう言っても、阿久津は車に乗ろうとしなかった。そんな阿久津を見て、歩美は苛立った。「何してるんですか。帰らないなら置いていきますよ」
「僕はもうちょっと調べてみるから、先に帰ってて」
「調べるって、何するんですか?」
「聞き込み」
「聞き込み?」
いったい何を知りたいというのだろう。しかしそれ以前の問題として、この男に他人から話を聞き出せるわけがないと歩美は思った。しゃあないな、と歩美は覚悟を決める。
「私も付き合いますよ。それより腹ごしらえしましょう。聞き込みはそれからでもいいですよね」
勝手に決めつけて、歩美は運転席に乗り込んだ。ジャックの不調。兼松家の前に落ちていたキャラメル。パピーウォーカーである木島家。ジャックの周りでいったい何が起きているのか。それが気になっているのも事実だった。
アクセルを踏む前に、木島家の方に目を向けた。道路に面して柵があり、その向こうに狭い芝生の庭があった。さまざまな樹木が植えられているが、手入れが行き届いていないようで、どこか荒れた印象を受けた。
(つづきは『わんダフル・デイズ』でお楽しみくださいませ)
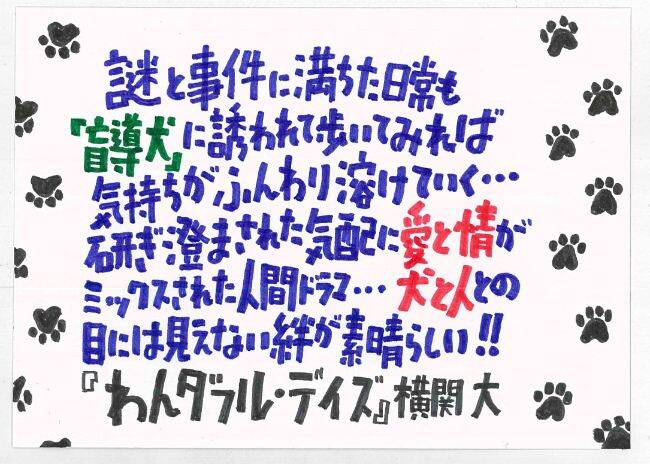
ふつうの毎日が「わんダフル」!の記事をもっと読む
ふつうの毎日が「わんダフル」!

「ルパンの娘」でお馴染みの横関大さんの最新刊『わんダフル・デイズ』の刊行記念特集です。
「犬と歩けば謎に当たる?!」
毛だらけで温かな犬たちが活躍するハートウォーミングミステリをお楽しみください。

















