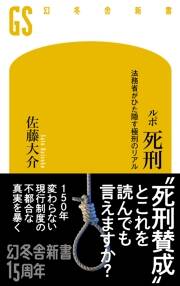死刑囚、刑務官、被害者遺族、元法相などへのインタビューで死刑制度の全貌に迫る書籍『ルポ 死刑 法務省がひた隠す極刑のリアル』(佐藤大介著、幻冬舎新書)がたちまち3刷となり、話題を呼んでいる。
ここでは本書の一部を抜粋して紹介。刑が執行された「元死刑囚」の家族の思いとは――。
* * *

「立派な最期でした」と告げられた母の涙
棺に入った息子は、花に囲まれ、穏やかに眠っているように見えた。
「(最期に)母ちゃんの顔を見ることはできんかったね」
母は声を絞り出して語りかけた。
福岡市早良(さわら)区の福岡拘置所。その一角にある刑場で、松田幸則元死刑囚(当時39)に死刑が執行されたのは2012年9月27日だった。
報せを受けた70代後半の母は、その翌日に熊本県内から駆けつけ、拘置所内で行われた葬儀で手を合わせた。
応対した拘置所幹部は「立派な最期でした」と告げた。遺書は書かれていなかったが、執行直前に母への遺言を遺していた。
「母ちゃんにいろいろ迷惑かけてすいませんでした。元気で長生きしてください。母ちゃんの子どもに生まれてよかった」
その言葉を伝えられた母は、拘置所の職員たちに頭を下げながら、ただただ泣いた。
松田元死刑囚が事件を起こしたのは2003年10月16日。熊本県松橋町(現・宇城市)で男女2人を殺害し、現金を奪った。
逮捕されたのは、それから2週間あまりが経った11月4日。松田元死刑囚は、取り調べに対して大筋で容疑を認め、動機について「借金返済に困ってやった」と供述したと報じられている。
松田元死刑囚はその月の25日、強盗殺人罪で熊本地検に起訴された。
起訴状には、松田元死刑囚が被害者宅を訪れ、柳刃包丁で2人の胸を数回刺して殺害し、現金約8万円や腕時計などを奪ったことが「犯罪事実」として記された。

松田元死刑囚は被害者や消費者金融などから計数百万円の借金があり、返済に困っていたことが動機とされ、柳刃包丁や奪った腕時計などは、松田元死刑囚の自宅近くの空き家から見つかっていた。
2004年1月から熊本地裁で公判が始まり、2006年9月21日の判決公判では、裁判長は「反省の態度がまったく見られない」などと述べ、求刑通り死刑判決を下した。
控訴審でも、福岡高裁は2007年10月3日、熊本地裁判決を支持して控訴を棄却。最高裁に上告したが、松田元死刑囚自らが上告を取り下げ、2009年4月3日付けで死刑が確定した。

臆病で口下手な「凶悪犯」
判決文に書かれた起訴内容や、事件当時の新聞報道を読むかぎりでは、借金の返済を逃れるために2人を包丁で刺し殺し、金品を奪った松田元死刑囚の犯行は「極めて残忍」という表現そのものだ。
逮捕直後の新聞紙面は「これで安心して出歩けるようになった」「余りにも簡単に人を殺しすぎる。世の中、どうにかならないのか」といった、近隣住民たちの声を掲載している。そこから浮かんでくるのは、凶悪犯としての松田元死刑囚だ。
だが、一審で弁護を担当した三角恒(みすみ・こう)弁護士は、逮捕直後に接見した松田元死刑囚の印象を「おとなしいし、どちらかというと優しい感じの青年という印象でしたね。言葉遣いも丁寧だし、粗暴な感じはまったくしなかった」と話す。
死刑が執行されたことには「2人を殺した事実は重い」としながらも、複雑な表情を見せながら、こう続けた。
「本当に死刑にならなくてはいけない事案だったのでしょうか」
三角弁護士は接見の際、松田元死刑囚に凶器となった包丁を持って行った理由を尋ねている。その答えは、意外なものだった。
「脅すためだった」「殺すためじゃなかった」
では、なぜ金品を奪ったのか。その問いにも、松田元死刑囚は「(犯行後に)一度車で(現場を)離れてから、また戻ってきて盗んだ」と説明した。
それが事実であれば、殺人罪と窃盗罪に問われ、強盗殺人罪では訴追されない可能性があった。
「事実と違うのなら、絶対に(検察の取り調べで)認めちゃダメだ」。三角弁護士は何度も念を押したが、松田元死刑囚は罪を認め、強盗殺人を「自白した」という形になった。

松田元死刑囚は、三角弁護士に「死者から物を盗ることのほうがより罪が重いと思った」と説明したという。
そうした松田元死刑囚を、三角弁護士は「臆病だったんだと思います」と言う。
「脅すつもりだったとしても、本人は怖くてたまらないんです。相手に『なんだ、お前』みたいなことを言われて、もうめった刺しにしてしまう。怖さが高じてのことだろうけれど、そうした犯行を以(もっ)て『残虐だ』という評価になってしまうんです」
公判で、弁護側は強盗殺人罪にはあたらないことを主張し、死刑回避に努めた。その一方で、松田元死刑囚は被害者への深い謝罪とともに、何度も死刑への覚悟を口にしていた。
だが、判決では反省がみられないと指弾されている。「口下手だったせいか、その思いを公判で十分に表現できなかったのかもしれません」。三角弁護士は、そう振り返った。
松田元死刑囚は逮捕直前、母を抱きしめたときのことが「忘れられない」と三角弁護士に話している。
「逮捕される前、自分の母親を抱きしめたら、母親が小さかったと言うんです。こんなに自分の母親というのは小さいものなのかと思ったって。そのとき、涙を流していたかどうかは覚えていませんが、気持ちとしては泣いていたんだと思います。母親に対して済まないという気持ちで」
三角弁護士が弁護を担ったのは、一審で死刑判決が下されたときまでだった。控訴審で別の弁護士がついた後も、松田元死刑囚からは年賀状などの手紙が何度か寄せられた。新しい弁護士もよくしてくれていること、元気に過ごしていること……。

だが、福岡高裁での控訴審は、一審の死刑判決を支持した。上告を自ら取り下げたことを聞いたとき、三角弁護士は「どきっとはしなかった」と言う。
「控訴だって取り下げたいということを言っていたくらいですから。いつまでもこういうことをしたくないと、潔く逝きたいと。だから、取り下げたんでしょう」
一方で、母親からは「息子は死刑になるんですね」と何度も質された。「わからない」と答えるのが精いっぱいだったが、結局は母親の言葉どおりとなった。
「これ以上の親不孝はないですよね」。三角弁護士は、そうつぶやいた。
小さな集落で生きる「殺人犯の母」
「もうよかです」
玄関の引き戸を開け、応対した年老いた女性は、私が訪問の意図を告げると、うつむきながらもはっきりとした口調で拒絶の意志を示した。
山間部の畑に囲まれた、小さな集落。街灯は少なく午後7時を回ると、一帯は真夜中のような暗闇に沈む。虫の音や蛙の鳴き声が響く中、さらに暗闇を濃くしたような一角に、小さな墓地があった。

真新しい花が飾られた墓石には、正面に「松田家」と名前が刻まれている。松田元死刑囚の母である女性は、その約2カ月前に刑死した息子が眠る墓に寄り添うように、集落の片隅で愛犬とともに暮らしていた。
「テレビや新聞にいろいろと書かれてな、だいぶ辛かな目にあっとるでな。またウソ書かれるでな」
顔の深い皺が、疲労の影を一層濃くしていた。「殺人犯の母」に対し、小さな集落で浴びせられた視線は刺すような痛みを伴っていただろうことは容易に想像がつく。その痛みは和らぐことなく「死刑囚の母」、そして「死刑になった男の母」と言葉を変えて、女性を苦しめている。
訪問の意図は事前に手紙で伝えておいたが、取材に関する行為の一つ一つが、その苦しみを増幅させていたのは間違いない。取り繕う言葉が見つからないまま、私は突然に訪問した非礼をただ詫びるしかなかった。
母親が引き戸を閉めようとする手を止めたのは、松田元死刑囚がアンケートで母親のことを気遣う内容を記していたことを伝え「お母さんのことを本当に心配していたようですね」と話しかけたときだった。
母親は、一呼吸した後で、小さく「はい」とうなずいた。
2012年に行った確定死刑囚へのアンケートで、松田元死刑囚は「取り返しの付かないことをしたと強く後悔するとともに、被害者やその遺族の方々に対して言葉では言い表せないほどに申し訳なく思っています」と、犯した罪への謝罪と反省の言葉を連ねていた。
自ら上告を取り下げた理由は「被害者の遺族の方々の為にも、一日でも早く裁判を終わらせなければと考えていました」と説明し、死刑が確定してしまうと連絡が取れなくなる知人や友人との面会や手紙のやり取りをした後に、上告を取り下げたと書いている。
だが、そうしたなかで「日々の生活の中で感じている楽しみや喜び、悩み」を尋ねた箇所では、一貫して母への思いがつづられていた。
「いつも自分のことは二の次にして私に精一杯のことをしてくれているので、自分の生活がちゃんとできているのだろうかと心配しており、一人残された母のことを思うと申し訳なさと自分に対する腹立たしさから気が狂いそうになってしまいます」
聞けなかった母の問い
死刑執行の前日、母親は「息子がどうかなる」との兆(きざ)しを感じたという。
翌朝、福岡拘置所から死刑を執行したとの電話があり、天を仰いだ。

アンケートで松田元死刑囚は、死刑執行の告知を「できれば1カ月くらい前、それが無理であれば2週間くらい前」に行ってほしいと記していた。執行方式についても「アメリカのような薬物注射」を望んでいたが、いずれも果たされることはなかった。
松田元死刑囚は、執行の直前に母親へ送った手紙に「(執行の)順番が近づいてきている」と書いていたという。だが、死刑執行への恐怖などには触れず、母親への感謝の気持ちをつづっていた。
「『母ちゃん、好きなもの食べて、元気でおって』っていうてな。『母ちゃんは自分にばっかりお金を送ってくれて、いつも感謝しとる』って。いつも感謝しとったです。私も精いっぱいなことをしたんでな……」
拘置所で息子と対面し、霊柩車(れいきゅうしゃ)に遺体を乗せるとき、拘置所の刑務官が母親に言った。
「模範囚でした。いつも笑顔で、頭が低かった」
別の刑務官も「私は松田に教わりました」と語りかけてきた。松田元死刑囚は、立ち会いの拘置所幹部や刑務官らにそれぞれお礼を述べ、静かに絞首台に立ったという。「お母さん、最期は立派でしたよ」。母親は、拘置所幹部にそう言われた。
「こぎゃんうれしかったことはないと、泣いたですたい。来てよかったと思ったですたい」
視線を落としたまま話す母親に、少し間を置いて「そうした言葉を聞いて、お母さんはどう思われましたか」と尋ねた。
母親は、一瞬視線を上げて私と目を合わせ、それからまたうつむいて「私は……本当はですね……」と言葉を続けた。
「ほんとは、電気を押しなった人たちに、どぎゃんした気持ちで押しなったですかと聞こうかと思ったですたいね。ばってん、もう、できんかったですたい」
目隠しに後ろ手錠をされた死刑囚は、絞首のロープをかけられた直後、立たされた踏み板が開いて地下に落下する。母親の言う「電気を押しなった人たち」とは、踏み板を外すボタンを押した刑務官のことを指していた。
「でも、仕事上、仕様がなかったですもんな。電気のスイッチ押すのはな。そんなの聞いても、返事はできんもんな。仕様がなかったもんな」
母親は、自分に言い聞かせるように「仕様がなかった」との言葉を繰り返した。
どんなに「模範囚」であったとしても、抵抗することなく「立派な最期」を迎えたにしても、一人息子が絞首刑に処された事実は変わらない。
絞首台の上に立った息子の首に縄をかけ、奈落の底に落とす「電気のスイッチ」を押したのは、目の前にいる刑務官たちだと思うと、母親は胸が張り裂ける思いだった。

松田元死刑囚が独房に残した私物は、すべて引き取った。衣類や日用品はきれいに整理され、母親が差し入れた現金は細かくノートに記録されていた。
受け取った手紙も大事に保管されていたが、その束の上には松田元死刑囚が母親に記した書きかけの手紙があった。4枚の便箋の日付は、死刑執行の2日前だった。それらを見て、母親はまた涙を流した。
荼毘に付された息子を抱えながら、母親の脳裏には事件後の日々がよぎった。
周囲からは「死刑の家族とはつき合えん」とささやかれ、先立った夫が生前手にした退職金も「奪ったカネだろう」と言われた。後ろ指を差され続けることに耐えられず、夫と自殺を話し合った日は数え切れない。首を吊ろうとロープを手に、夫婦で夜中の山中をさまよい、そのまま朝を迎えた日もあった。
生活から笑いや楽しさが失われるなか、母親は2人の被害者の名前を札に書いて壁に貼り、夫と毎日手を合わせてきた。
だが、そうした苦しみが、死刑囚となった息子に刑が執行されたことで消えるわけではない。むしろ、息子が殺(あや)めた2人の死に加え、息子当人の死にも向き合うこととなり、心には底知れない暗闇が広がるようだった。
「苦しかです。でも、生きていくしかなかとです」
母親は、絞り出すように言葉を続けた。
面会室で、松田元死刑囚は母親にこう話したことがあるという。
「もし無期懲役になっても、帰れるころには母ちゃんたちはおらんけ。母ちゃんが元気なうちに帰るよ」
息子がどんな姿で帰ってくるのか、意味することは明らかだった。あえて「死」という言葉を避けながら、落ち着き払った様子で話す姿に、母親は語りかける言葉が見つからなかった。やがて、その言葉どおりに、息子は刑に服し、母親のもとに帰ってきた。
「私が元気なうちに(息子が)帰ってきてくれた。それがうれしかです。いろいろつろう目にあったけど、自分らにとってはいつまでも一人息子ですけんの」。母親はそう話し、目頭を拭った。
独り暮らしの居間の仏壇には、夫の横に息子の写真を置き、母親は毎日の出来事を静かに語りかけている。
* * *
150年変わらぬ死刑制度の不都合な真実を暴く『ルポ 死刑 法務省がひた隠す極刑のリアル』好評発売中
ルポ 死刑の記事をもっと読む
ルポ 死刑

2021年11月25日刊行の幻冬舎新書『ルポ 死刑 法務省がひた隠す極刑のリアル』の最新情報をお知らせいたします。