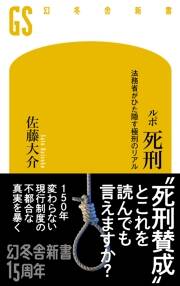死刑囚、刑務官、被害者遺族、元法相などへのインタビューで死刑制度の全貌に迫る書籍『ルポ 死刑 法務省がひた隠す極刑のリアル』(佐藤大介著、幻冬舎新書)がたちまち3刷となり、話題を呼んでいる。
ここでは本書の一部を抜粋して紹介。絞首刑は憲法が禁ずる「残虐な刑罰」にあたらないのだろうか?
* * *

「残虐性なし」の根拠は1928年の論文
日本が死刑執行の方法として採用しているのは絞首刑だ。刑法11条には「死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する」と記されている。
だが、絞首刑は憲法で禁じられた「残虐な刑罰」にあたるのではないかとし、見直しを求める声は専門家のなかにも根強い。
憲法36条には「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」と明記されており、この解釈が、絞首刑が違憲であるかどうかが争われる裁判でのカギとなっていた。
日本では、1948年と1955年に最高裁が絞首刑は残虐な刑罰にあたらないとの判決を下し、絞首刑による死刑が合憲であるとの根拠となっている。
1948年の最高裁判決では、死刑制度そのものが「直ちに同条(憲法36条)にいわゆる残虐な刑罰に該当するとは考えられない」としたうえで、「ただ死刑といえども、他の刑罰の場合におけると同様に、その執行の方法等がその時代と環境とにおいて人道上の見地から一般に残虐性を有するものと認められる場合には、勿論これを残虐な刑罰といわねばならぬ」とした。
判決はさらに具体例に言及し「将来若(も)し死刑について火あぶり、はりつけ、さらし首、釜ゆでの刑のごとき残虐な執行方法を定める法律が制定されたとするならば、その法律こそは、まさに憲法36条に違反するものというべきである」としている。
つまり、憲法が禁止した「残虐な刑罰」は「火あぶり、はりつけ、さらし首、釜ゆでの刑」などであり、これらと比較して絞首刑は不必要に精神的・肉体的な苦痛を与えるものではないと判断しているのだ。

さらに、1955年の最高裁判決では「現在各国において採用している死刑執行方法は、絞殺、斬殺、銃殺、電気殺、瓦斯(ガス)殺等であるが、これらの比較考量において一長一短の批判があるけれども、現在わが国の採用している絞首方法が他の方法に比して特に人道上残虐であるとする理由は認められない」とし、同様に絞首刑の残虐性を否定している。
では、絞首刑の残虐性を、どういった根拠で否定したのだろうか。その手がかりとなる専門家の鑑定結果がある。
この判決が出される前の1952年と1953年、強盗殺人事件の控訴審でやはり死刑が憲法36条違反であるとの主張がなされ、東京高裁は3人の鑑定人を採用した。
なかでも、その具体性から注目を集めたのが、法医学者の古畑種基(たねもと)博士による鑑定結果だった。
古畑博士は、1928年に執筆されたシュワルツアッヘル博士(ウィーン大学法医学教授)の論文を引用して、「頸(けい)部に索条をかけて、体重をもって懸垂(けんすい)すると(中略)左右頸動脈と両椎骨動脈を完全に圧塞(あつさく)することができる」と指摘している。
縊死(いし)を試みた者や絞首された者は「体重が頸部に作用した瞬間に人事不省に陥り全く意識を失う。それ故に定型的縊死は最も苦痛のない安楽な死に方であるということは、法医学上の常識となっているのである」とした。
そのうえで、死刑囚への苦痛が少ない執行方法は「青酸ガスによる方法と縊死による方法」と断じている。
この鑑定が、1955年の最高裁判決に大きく影響したことは間違いないだろう。
しかし、現在の法医学の水準から見て、当時の鑑定結果がどれだけ妥当性を持っているかは疑問の余地がある。ここで引用されている論文は、今から100年近く前に書かれたものだ。
果たして、絞首刑は本当に「苦痛が少なく」「残虐性のない執行方法」と言えるのだろうか。
絞首刑の再現実験では頭部が切断
踏み台が開き、首にロープを巻かれた人形が落下して宙づりになった直後、人形の首から上の部分が切り離された。
人形とはいえ、ショッキングな映像に、見つめていた裁判員のなかには、思わず手で口元を押さえる人もいた。

2011年10月11日、大阪地裁。2009年7月に大阪市此花(このはな)区でパチンコ店が放火されて客と従業員の計5人が死亡し、殺人などの罪に問われた高見素直被告(当時)の裁判員裁判で、人形を使った絞首刑の再現実験で頭部が切断される様子を収録した英国の番組が上映された。
この日は、死刑の違憲性が審理されており、映像は弁護側の求めによって上映された。さらに、オーストリアの法医学者、ヴァルテル・ラブル博士が弁護側証人として出廷し、「ロープの長さや体重などの要素で、身体が傷つく可能性がある」と証言した。
絞首刑に関する古畑博士の鑑定結果も「正しくない」とし、首が切断されたり、長時間苦しみながら死亡したりすることも考えられると指摘している。
また、絞首刑における死因は、頸動脈の圧迫による脳の酸欠や窒息だけでなく、まれに首の骨折や神経の損傷による心停止もあると説明し「何が起こるか予想はつかない」と証言した。
裁判では、死刑の違憲性が争点の一つとなり、裁判員裁判としては審理期間が60日間と異例の長さになっていた。死刑の違憲性審理について、大阪地裁は「憲法判断は裁判官がするが、裁判員の審理参加は任意とする」と決定し、裁判員6人中4人が審理すべてに参加していた。
死刑の違憲性をめぐる形式的な審理ではなく、裁判員が参加し、実質的な審理を伴う裁判として注目されていた。

元検察幹部の主張「残虐な刑罰にあたる」
弁護側は証人としてラブル博士のほか、もう1人の専門家を呼んでいた。元最高検検事の土本武司・筑波大名誉教授だ。
土本氏は、死刑制度そのものは存置すべきとの立場をとっている。だが、東京高検検事として死刑執行に立ち会った経験から、絞首刑は「むごたらしく、正視に堪えない残虐な刑だ」と述べ、憲法36条で禁じられた「残虐な刑罰」にあたるとの主張を展開した。
土本氏は翌12日の公判で、当時の手記を参考にしながら「踏み板が外れる音がした後、死刑囚の首にはロープが食い込み、宙づりになっていた。医務官らが死刑囚の脈などを確かめ『絶息しました』と告げていた」と、自らが立ち会った死刑執行の模様を振り返った。さらに、こう証言を続けている。
「少し前まで呼吸し体温があった人間が、後ろ手錠をされて両脚をひざで縛られ、踏み板が外れると同時に自分の体重で落下し、首を基点にしてユラユラと揺れていた。あれを見てむごたらしいと思わない人は、正常な感覚ではない」
さらに、死刑を合憲とした1955年の最高裁判決についても「当時妥当性があったとしても、今日なおも妥当性を持つとの判断は早計に過ぎる」と、否定的な見解を述べている。
閉廷後の記者会見では、検事時代に死刑囚の男性と文通したエピソードも紹介した。
「交流を続けるうちに彼の心が清らかな状態に変わった。果たして、強制的に命を剥奪していいのかと考えた」
「人間は変わりうるもので、それに対応できる法制度が検討されるべきだ」
土本氏は、こう振り返っている。

踏襲された判断
大阪地裁での公判は、2011年10月31日に和田真裁判長が高見被告への死刑判決を言い渡した。「身勝手極まりない動機で、多数の死傷者を出したという凶悪重大な犯行」「死刑をもって臨むしかない」。
高見被告の犯行が厳しく断罪されるなか、判決は絞首刑が違憲かどうかという点についても、これまでの判例と同じく合憲と判断した。
判決では、ラブル博士や土本氏の見解のほか、裁判員の意見を聴いたうえで、絞首刑は意識喪失までに最低でも5~8秒、首の絞まり方によっては2分以上かかり、その間、受刑者が苦痛を感じ続ける可能性があるとの事実関係を認めている。
だが、それでも「残虐な刑罰」にあたらない理由として、判決では「受刑者の意に反して、その生命を奪い、罪を償わせる制度であり、ある程度のむごたらしさを伴うことは避けがたい」と述べている。
死刑制度の持つ本質的な要素について、これほど凝縮して書き示した文章はないだろう。判決では、絞首刑が残虐な刑罰ではないとの結論を、こう導き出している。
「絞首刑が死刑の執行方法の中で最善のものと言えるかは議論のあるところだが、死刑に処せられる者は、それに値する罪を犯した者で、執行に伴う多少の精神的・肉体的苦痛は当然甘受すべきである。確かに絞首刑には前近代的なところがあり、死亡するまでに予測不可能な点があるが、だからといって残虐な刑罰に当たるとはいえず、憲法に違反しない」(要旨)
高見被告の弁護を務めた後藤貞人(さだと)弁護士は、死刑判決を下し、絞首刑も合憲とした一審の判断に不満を示しながらも、判決の内容については「残虐性を認めている。絞首刑で、人は速やかには死なないというのを、首がちぎれる可能性があるというところを認めたわけです。誰も反論する人はいなかったんですから」とも話している。
同時に、違憲かどうかの審理が尽くされていないことへの悔しさもにじませた。
高見被告側は判決を不服として控訴したが、大阪高裁の中谷雄二郎裁判長は2013年7月31日、控訴を棄却した。裁判はさらに上告手続きがとられ、最高裁で争われたが、2016年2月に上告が棄却され、高見被告の死刑が確定している。
* * *
150年変わらぬ死刑制度の不都合な真実を暴く『ルポ 死刑 法務省がひた隠す極刑のリアル』好評発売中
ルポ 死刑

2021年11月25日刊行の幻冬舎新書『ルポ 死刑 法務省がひた隠す極刑のリアル』の最新情報をお知らせいたします。