
直木賞候補『スモールワールズ』で話題をかっさらった一穂ミチ。
いま注目度ナンバー1の作家は、その観察眼で人間の生々しさを抉り出してきた。どこまでも見抜いていく彼女の視線が次に向かったのは、テレビ局で働く「普通の人々」。
2月9日刊行の『砂嵐に星屑』に込めた想いとは? なぜ今「テレビ」なのか?
放送作家として30年間テレビ業界の最前線に立ち続け、その経験を活かした長編小説『僕の種がない』を発表したばかりの鈴木おさむさんは、本作をどう楽しんだのか? リスペクト対談、始まります。
* * *
たとえ王者の座を退いても、テレビの力はすごい。
一穂 実は私、鈴木おさむさんが昔AERAで連載されていたエッセイを読んでおりまして、そこでテレビ業界について教えていただいた部分が大きいんです。
鈴木 おおっ、嬉しい。今はウェブ(AERA dot.)で連載しているんですが、紙の雑誌の頃となるとかれこれ十数年前になりますかね。
一穂 一番印象に残っているのが、「仕事のご褒美は、仕事である」と書かれていたことでした。ひとつの仕事をやり遂げられたら、周囲から新しい仕事を任せてもらえる。それが何よりのご褒美だというようなことを書いてらっしゃって、すごく感動した記憶があるんです。
鈴木 僕は一九歳で放送作家としてこの世界に入ったんですが、会社員ではなくフリーの立場なので、仕事に応じてギャランティーが支払われるんですね。最初の頃なんて、ノーギャラでした。その状態から始まり、お金をもらえる仕事がもらえるようになった時は、めちゃくちゃ嬉しかった。ギャラがもらえることじゃなくて、次の仕事をもらえることが嬉しかったんです。
一穂 今は放送作家の仕事のみならず、ドラマに舞台に小説にといろいろなお仕事をされていますが、そういう気持ちは消えないものですか?
鈴木 消えないですね。ただ、昔と今との違いで言えば、自分から新しい仕事を作りにいっているんです。例えば僕はここ一年ぐらい、漫画を本気でやっているんですね(※『ティラノ部長』『お化けと風鈴』の原作を担当、自身のインスタグラムで連載)。これは完全に自分発信で、やりたいから勝手に始めてしまった。なんでそんなにいろいろやるかっていうと、自分が世に出したもので、世の中が変わるとまでは思わないけれども、少しでも世の中をザワつかせることができたらいいな、と。そのためには、いろんなアプローチの仕方をしたほうがいいだろうと思っちゃうんです。
一穂 去年の秋に出された小説『僕の種がない』もすごく面白かったです。精巣の中の精子を探す場面をこんなにも臨場感たっぷりに描いた物語は、史上初めてだと思います。
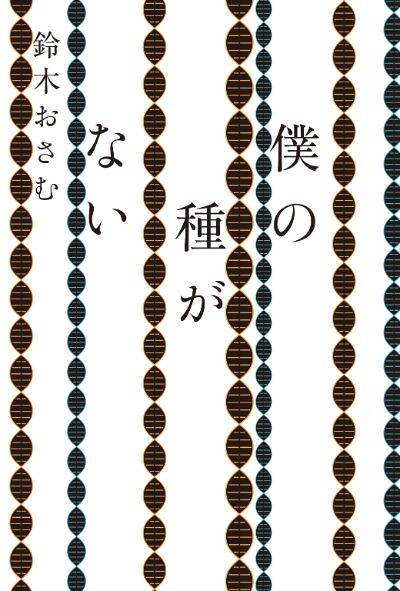
余命半年の芸人に意を決して提案する。「ここか
らなんとか子供を作りませんか?」。だが、その芸
人は無精子症だった……。
それでも諦めずに、奇跡を起こそうとする物語。
鈴木 まさにあの小説は、男性不妊であるとか精子検査についてを詳細に書くことで、男女問わず読んでくれた方がちょっとザワついてくれないかなと思ったんですよね。
一穂 このタイトルを書店で見かけた時、ドキッとする男の人はいっぱいいると思うんです。「いやいや、自分は……」みたいな気持ちで最初は目をそらしてしまうかもしれないけれども、そういう方が不安に思っているであろうことが小説の中に全部書かれている。検査で病院へ行ったらどんなことをするんだろうとか、絶望的な結果を突きつけられた時に、最後の手段ってあるのかとか。世の中に存在する価値が大きい物語だと感じました。
鈴木 ありがとうございます。『僕の種がない』は男性不妊を物語の入口にしているんですけれども、今回読ませていただいた一穂さんの『砂嵐に星屑』と同じ題材を扱っている面もあります。お互い、テレビ業界に関わる人間の話ですよね。特に最終話(「〈冬〉眠れぬ夜のあなた」)は、上司からドキュメンタリーのVTR 作りを任された新米テレビマンの晴一が、芸人さんに密着するお話で。テレビ的に面白いものを作るということと、その人の傷を開いて見せるってところが重なってしまうという点は、『僕の種がない』でも書きたかったところでした。
ドキュメンタリーが一番自由な「ふり」をできる
一穂 鈴木さんの小説は、傷だらけになりながらもカメラと被写体の間にある距離を踏み越えていく人々の物語でしたよね。お互いがむき出しでぶつかり合っていった果てに生まれる美しいもの、美しい瞬間を描き出されていたと思うんです。私の小説は四編全部、お互いの距離を保ったまま踏み込めない人たちの話なんですよ。そういう意味では、人間のあり方が対極なのかもしれないと思いました。なんていうか、私が書く小説の登場人物は弱っちくて、鈴木さんの小説に出てくる人たちはみんなハングリーで、たくましい。もちろん彼らの中にはちゃんと弱さもありつつ、なのですが。
鈴木 それはたぶん、僕が今まで出会ってきたテレビマンたちを登場人物のモデルにしているからですね。今はだいぶ変わってきましたけど、テレビ業界にいる人たちって本当に狂っているんです(笑)。例えばカメラを向けたことによって相手が傷付くようなことがあったら、本気で心配したフリして謝って、次の日には平気で忘れることができる人が向いているんですよね。異常な世界だなぁと思います。
一穂 その世界の異常性に、ご自身が飲み込まれそうだなとか、飲まれているなと思った瞬間はありますか?
鈴木 飲まれそうだなって感じたことはなくて、自分が飲み込む側にいたんだなっていうことにここ数年で気付きましたね。「面白い」って言葉はすごいんですよ。テレビ界にいると、それが正義になっちゃうんです。「面白い」という言葉で何でも乗り越えようとしていたり、乗り越えさせようとしている恐怖。自分もその催眠術にかかっていることに、長いこと気付かなかった(苦笑)。
一穂 「面白い」という実体のあるようでないようなものをテレビというメディアが発すると、巨大な暴力にもなり得る、と。ただ最近は、「コンプライアンス」が叫ばれることが多くなってきましたよね。道徳的に守らなければならない、越えてはならない一線が、昔よりグッと手前に引かれているようです。
鈴木 僕が今のテレビ業界を舞台にした小説を書くうえで、ドキュメンタリーを選んだ理由は、この分野がテレビの中では一番自由だからなんです。「リアルだから」という言いぶんで、バラエティでは取り上げられないような人も取り上げることができる。ドキュメンタリーが唯一、この業界で自由なふりをしているというか、動きやすいんじゃないかなって思います。
一穂 自由な「ふり」というのがポイントですよね。こちらの思い描いた台本通りに相手を動かしてしまったらドキュメンタリーではなくなるけれども、ある程度こちらからプランを出して、相手に乗ってもらわなければいけない部分もある。そこの矛盾が、ドキュメンタリーの面白さを生むのかもしれません。
鈴木 うん。そう思いますね。
一穂 私は今回の小説で、ドキュメンタリーも含む報道という分野を扱いました。「マスゴミ」という言葉が象徴的ですが、テレビの負の側面がクローズアップされる際、必ず矢面に立たされるジャンルだと思うんですね。例えば誰かがツイッターに衝撃的な動画をアップしたら、テレビの報道関係のスタッフが「ニュースで使わせてください」とリプを送ったりする。それに対して「自分たちで撮ったものを使えよ」とか「使用料払えよ」みたいなリプが付く、という寒々しい状況をたくさん見てきました。これが今の人たちのテレビというものに対する感覚なのか、と考えざるを得ないところがあったんです。
鈴木 一穂さんの小説だと、第二話(「〈夏〉泥舟のモラトリアム」)でそのテーマが取り上げられていましたよね。そこで、テレビ業界を「泥舟」と表現されていたのが素晴らしかった。泥舟だと全く気付いていない人、泥舟だなんてことは絶対に認めないという人、分かっていて泥舟に乗り続けている人。泥舟という言葉を真ん中に置くことで、ここにいる人たちの立場が鮮明になる気がします。

「視聴率一〇〇%」って何人を想定してるんですか?
鈴木 『僕の種がない』を書き始めたのは、二〇一六年の一二月二七日でした。その前日に、初回から作家で入っていた「スマスマ」(フジテレビ系バラエティ番組『SMAP×SMAP』)が最終回を迎えたんです。国民的バラエティ番組が二〇年の歴史に幕を下ろしたその時に、自分の中でテレビというものに対して一個の「。」を付けることになった。段落を替えてまたテレビでも新しいチャレンジは始めているんですが、それと同時に自分としては、小説という別ジャンルでも表現できることはないかと探っていったんです。
一穂 一つの区切りになったんですね。
鈴木 「スマスマ」が終わったことは、テレビの歴史にとっても大きな区切りになったんじゃないでしょうか。SMAP自体が解散となり、前の事務所を出た三人のメンバーが何をやったかというと、ネットで番組を始めましたよね。それがネットでテレビを作る、観る、ということに世間が注目する大きなきっかけとなっていった。
一穂 三人の「新しい地図」というユニット名は、本当にその通りだったんだなとじわじわ思います。
鈴木 だから、僕がすごく興味があるのは、一穂さんは今回テレビを舞台にした小説を書かれたわけじゃないですか。それはどうしてだったんだろうな、と。
一穂 テレビがオールドメディアになりつつあるからこそ逆に、という感覚ですね。ネットの広告費がテレビの広告費を抜いたのは二〇一九年でしたが、業界が大きな変化に見舞われているからこそ、そこで生きる人たちの葛藤も大きいだろうなと思ったんです。
鈴木 おっしゃる通りで、メディアの王者の座が入れ替わる瞬間って、何十年に一回しか見られないですよね。今、テレビ界を観察するのってめちゃめちゃ面白い。
一穂 なおかつ、キー局と違ってもともとお金がない、大阪の泥臭いローカル局が舞台であれば、これまで描かれてきたテレビ業界にまつわる作品とはちょっと違ったものになるかなとも思いました。
鈴木 ネットに抜かれるまでテレビってマスメディアの王者だったし、キラキラしていたわけじゃないですか。だから、テレビ業界をキラキラしたテレビドラマの舞台にするのはいいんですけど、小説だと難しいなぁと思っていたんですね。もちろん小説でもテレビ業界を舞台にした名作はありますけど、かつてのテレビのキラキラした感じは、小説という表現手段とはどうも似合わない気がしていた。でも、右肩下がりになってきた今なら、マッチしそう。これからテレビを舞台にした小説を書く人が増えるんじゃないかなって、一穂さんの小説を読んで思いましたね。
一穂 これは是非お伺いしたかったんですが、最近は視聴率の他に、TVerでの番組再生回数であったりYouTubeの再生回数も加味して、番組の価値を評価するような流れが業界に出てきているのかなと思うんです。そんな中で、視聴率というものを鈴木さんはどのように捉えてらっしゃいますか?
鈴木 TVerでどれぐらい再生されたとか、いわゆる視聴率とは別の数値が今日では評価対象になっていることは事実です。でも、なんだかんだ言って視聴率なんですよ、テレビ局って。それじゃあダメなんじゃないの、変えなきゃならないんじゃないの、という指摘をかれこれ二〇年以上無視し続けているのがこの業界である、とも言える。だって昔はよく「視聴率一%は視聴者数一〇〇万人」と言われていましたけど、そんなわけないじゃないですか。一〇代の子達はテレビなんか見てないですよ、スマホを見ているんですから。トークイベントで昔、広告代理店の人に「視聴率一〇〇%って、一億三〇〇〇万人中、何人を想定してるんですか?」って聞いたら、すっごいイヤな質問だったみたいで答えてくれなかったんですけど(笑)。
一穂 製造業に原価を聞くような質問だと思います(笑)。
鈴木 テレビって結局のところ視聴率で動いていくものなのに、その数字自体がものすごくあやふやなんです。ちゃんと答えを出すのが怖い、知りたくないって感覚もあるのかもしれない。だから、テレビがどのくらい見られているのかという本格的な調査を、本気ではやらない。知らずにいれば、架空の数字を思い描いていつまでも王者の気持ちでいられるんですから。でもね、そうやって誤魔化し誤魔化しでやっていくのはもう、さすがに限界が来ていると思うんです。
この業界は泥舟だと危機感を抱くからこそ
一穂 鈴木さんはテレビがチャンピオンだった時代のおしまいの方、バブル期の華やかだった頃をご存知だと思うんですけれども、そこからみるみる勢いが下がっていく中で、今もテレビの最前線でお仕事をされている。例えば、社会現象になったドラマ『M―愛すべき人がいて』の脚本を手がけてらっしゃったりするじゃないですか。「あの時代が忘れられない……」みたいな遠い目をした業界の方もたくさんいらっしゃるのに、鈴木さんは現実を見据えながら、時代の変化に敏感に反応しながら、ここまで精力的にもの作りを続けていられるのは何故なんでしょうか。
鈴木 それはありがたいことに、ネットの仕事を早くから始める人が周りにたくさんいて、刺激をもらえたからですね。あとは三〇歳の時、舞台にチャレンジしたことも大きかったんです。その前にドラマをやったらぜんぜん歯が立たなかったことがきっかけだったんですけれども、舞台という超アナログなことをやり始めたことによって、いろんなことに気付けたんですよね。例えば、舞台は視聴率みたいなあやふやな数字ではなく、目の前にお客さんの数が見えるメディアです。お金を払ってまで観たいものと、テレビで観たいものって違うんだなと痛烈に感じましたし、その後もいろんな表現ジャンルへの挑戦を通じて、テレビというものを冷静な目で見ることができたんじゃないかなと思います。やっぱり僕はテレビが好きだからこそ、テレビで面白いものを作りたいし、みんなにも作り続けてほしいと思っている。極端な話、面白いものを作れないんだったらテレビなんてなくなったほうがいい。
一穂 私もなんだかんだでテレビが好きなんです。テレビが一番の娯楽だった世代なので、決まった曜日の決まった時間にテレビの前に座って番組が始まるのをワクワクと待っていた気持ちは、自分にとって今でも大事な感情です。好きだし、すごく力のあるメディアだなと思っているからこそ、現状に対して少しもどかしい気持ちがあるのかもしれません。
鈴木 今もテレビの力はすごいですよ。例えばいまだにM–1で優勝したら、芸人の人生がガラッと変わるじゃないですか。報道番組で「この人が失踪しました」と顔写真を映せば、全国からものすごい数の情報が来るんですよ。それはSNSの比ではないんですよね。だから、力の使い方の問題なのかもしれないですね。
一穂 スマホが一台あれば誰もが手軽に配信をできる中で、テレビの人たちが「テレビだからできることって何なんだろう?」とより深く考えていってほしいなって、勝手な思いを抱いてしまいます。
鈴木 だから、一穂さんが小説の中でテレビ界を「泥舟」と表現してくださったことは、テレビに関わる人間としてはすごくありがたかったんですよ。テレビ界の人間は、みんな一穂さんの本を読んでほしい。この業界は泥舟だと本気で危機感を抱いている人間の方が、絶対にいい番組が作れますから。
(構成:吉田大助 初出:小説幻冬2022年2月号)
砂嵐に星屑の記事をもっと読む
砂嵐に星屑
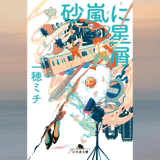
舞台はテレビ局。旬を過ぎたうえに社内不倫の“前科"で腫れ物扱いの四十代独身女性アナウンサー(「資料室の幽霊」)、娘とは冷戦状態、同期の早期退職に悩む五十代の報道デスク(「泥舟のモラトリアム」)、好きになった人がゲイで望みゼロなのに同居している二十代タイムキーパー(「嵐のランデブー」)、向上心ゼロ、非正規の現状にぬるく絶望している三十代AD(「眠れぬ夜のあなた」)……。それぞれの世代に、それぞれの悩みや壁がある。
つらかったら頑張らなくてもいい。でも、つらくったって頑張ってみてもいい。続いていく人生は、自分のものなのだから。世代も性別もバラバラな4人を驚愕の解像度で描く、連作短編集。
- バックナンバー
-
- 一穂ミチを大解剖。直木賞作家の素顔に迫る...
- 新・直木賞作家、一穂ミチを大解剖。一問一...
- 祝・直木賞!一穂ミチインタビュー「寂しい...
- 『砂嵐に星屑』台湾版序文を特別公開!
- 一穂ミチ中毒、続出!書店員さんから絶賛の...
- 一穂ミチ中毒、続出!書店員さんから絶賛の...
- 一穂ミチ中毒、続出!書店員さんから絶賛の...
- 一穂ミチ中毒、続出!書店員さんから絶賛の...
- サイン入りプルーフが当たる!ハッシュタグ...
- 一穂ミチ中毒、続出!書店員さんから絶賛の...
- 関西限定版も!特製POP大公開
- 宇垣美里特別コラム「たくさんの星屑たちが...
- 一穂ミチ中毒、続出!書店員さんから絶賛の...
- 一穂ミチ×鈴木おさむ対談「やっぱりテレビ...
















