
山のさまざまな危険に警鐘を鳴らす『山はおそろしい 必ず生きて帰る! 事故から学ぶ山岳遭難』(羽根田 治著、幻冬舎新書)が発売2週間で重版となり好調だ。
6月某日、渋谷・大盛堂書店にて、本書刊行を記念して羽根田 治氏と、羽根田氏のファンを公言する映画史・時代劇研究家の春日太一氏によるトークイベントが開催された。
大盛り上がりとなった対談をご紹介する全3回の2回目。ノンフィクションの名手どうし、タイトルのウラ話や表現の工夫に話は及んだ。
* * *

著者と編集者のタイトル攻防戦
羽根田 今回のタイトル『山はおそろしい』は企画のスタート時から編集さんの頭の中にあったようです。ただ、自分としては、それはちょっと、うーん、っていう感じで。
春日 そうですよね。山に対してネガティブなイメージを持たれること自体は、羽根田さんの本意ではないでしょうから。
羽根田 「じゃあタイトルは最後に決めましょう」という感じで。で、最後になって、「やっぱりこれがいい」と主張してくるわけですけれど、「うーん、それはちょっと」と言いました。
「山はおそろしい」とつけると、読者は「だったら山には行かないほうがいいね」という思考回路になってしまうと思うので、それは避けたかった。取材させていただいた方が納得するかなという心配もありました。
でもサブタイトルを付けるという妥協案をいただいて、取材させていただいた方にも了解を得られたので、最終的にこのタイトルに決まりました。
春日 本当に、僕ら書き手側にとって、タイトルっていつも悩むところですよね。また編集者さんの言い分も分かるというか、確かにそうすると目を引くし売れる可能性は高いしっていうのがあって。
僕も『なぜ時代劇は滅びるのか』(新潮新書)というタイトルの本を出したときは、相当葛藤があったんですよ。
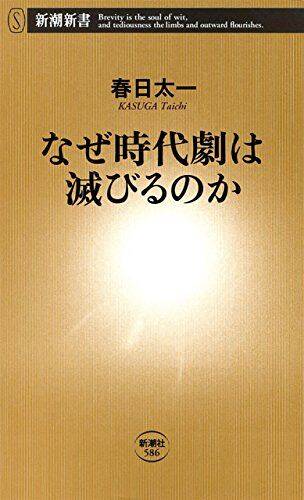

最初に編集者が出してきたのは、さらに極端なタイトルでした。僕は『時代劇は死なず!』(集英社新書、のち河出文庫)という本でデビューしたのですが、それにひっかけて『時代劇は死んだ』というタイトル案だった。
「でも、そう言い切ってしまうと、今も現場で闘っている人たちに申し訳ない」と思ったんです。
それで今度は『なぜ時代劇は滅びたのか』になったのですが、「滅び”た”」だとやっぱり「終わった」という感じになりますからね。
「”まだ終わっていない”というニュアンスで、現在進行形的にしたい」ということで「滅び”る”」というのを提案したんです。「このままだと滅びますよ」みたいなニュアンスにした、一つの助動詞の差で、受け止められ方は違いますから。
羽根田 その違い、大きいですね。
春日 そこは戦いました。向こうの言い分も分かるんだけど、それに乗っかっちゃうと、たとえこの本が売れたとしても、苦いものが残ると思ったわけです。
だから『山はおそろしい』というタイトルには、羽根田さんの中で葛藤があったのかなと思ったのですが、やはりそうだったんですね。
羽根田 それはもう最後までそうでしたね。
事実はそのまま書けば、ドラマチックなものになる
春日 そのぶん、本の帯のところでエクスキューズというか、「ちょっとした知識で生還率が大幅に上がる!」と、これを入れたことによって「ポジティブな本ですよ」という雰囲気が出ていますよね。
羽根田 はい。事例を検証するだけじゃなくて、じゃあどうすればよかったのか、どうするべきだったのかということまで書いていたから、帯にこの一文が入れられたと思うので、それはよかったなと思います。
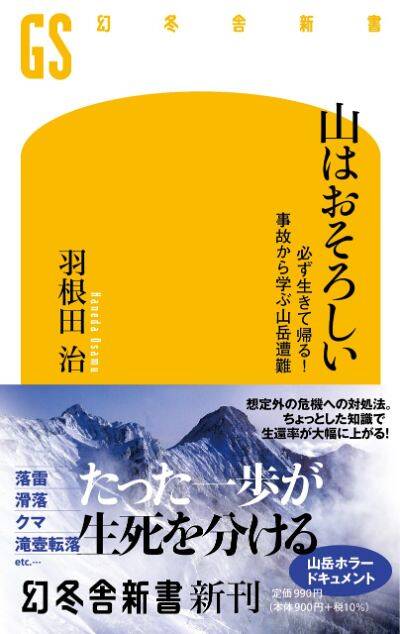
春日 そこは羽根田さんのずっと変わらないスタンスですよね。ただ単にその事例を面白がるということはまったくなくて、それを何らかの教訓に結びつけています。
それから、羽根田さんの本の魅力というと、偉人や有名な登山家ではなく、一般の方を事例にしていることです。我々だっていつ同じ目に遭うか分からない、自分ならこんな目に遭ったらどうなるんだろうっていう、等身大の視線で読むことができます。そうした共感性があるからこそ怖いのだと思うのですが、そのあたりの怖さについてはどう考えていらっしゃいますか。
羽根田 明日はわが身だと思ってはいます。偉そうに取材させてもらって書いていますけれど、「これ、下手したら自分がいつそうなってもおかしくないな」っていうのは毎回思っています。
ヘタレだから、山に行ってちょっとなにかあれば「あ、ヤバい、降りて酒飲もう」って、すぐ降りてきちゃいますし(笑)。
前に山と溪谷社さんから出していただいた『トムラウシ山遭難はなぜ起きたのか』という本に、書店員の方がPOPで「ホラー並みの怖さ」と書いてくださっていて、ああ、そういう読み方もされているんだなと、そのとき初めて自分の本に対して「ホラー」という言葉を聞いたんです。
それに次いで今回の本の帯が2回目ですね。

春日 僕が最初に読んだ羽根田さんの本はその『トムラウシ山遭難はなぜ起きたのか』でした。本当に怖い、しかもそれは、こけおどし的な怖さではなくて、人間の心理面の怖さです。
極限状態になったとき、人間の心理ってこうなるのかと。あるいは極限状態に自分をあえて追いやってしまうような油断であったり、傲慢(ごうまん)さであったり、そういったものを含めての怖さですよね。
最終的に、『山はおそろしい』の章タイトルにあるように、人間の怖さ、そこに行き着く気はしています。
羽根田 そうですね。昔、こうした本を書き始めたときに、山の世界の大先輩から「山岳遭難の検証にドラマはいらない」と批判されたことがあります。
自分はドラマを書いているつもりはないんだけれど、今、春日さんが言ったように、遭難した人がそのときどう感じたか、それでどうしたかというのはすごく大事なことだと思うので、その点は自分の取材、文章には欠かせないということは、そのときから思っていましたね。
春日 充実した取材ができると、その成果をちゃんと書けばドラマチックなものになるんですよね。そうした文章のデコレーションのなさも羽根田文学の大きな魅力です。
人間が危ない瞬間に発する「あっ」の重さ
春日 今回読んでいて、生々しいというか、ああそうだなと納得した点が、人間が滑落する瞬間や危ない瞬間には、一言「あっ」と発する。この「あっ」が重かったです。
羽根田 取材の際、そういう一番核になりそうな場面については、そのときどう思ったか、何を言ったかと、聞き方を変えて何度も質問するんですけれど、返ってくる言葉は「あっ」しかなかったりするんですよね。
春日 本当に一瞬なんでしょうね。あっ、やってしまったっていう感じ。その人の生の感覚がバッと伝わってくる。
前に何かに載っていたホラー体験談で、その人には忘れられない「あっ」があると。
子どもの頃に学校だったかマンションだったかの屋上で、柵の外側にぶら下がって友達が懸垂をやっていて、それで手がすべってしまう。その瞬間にその子が「あっ」って言ったらしいんですね。そして、そのまま落ちていって亡くなったという。「それ以降、彼の”あっ”っていう言葉が耳から離れない」という体験談が載っていたんですよ。

それがすごく記憶に残っていて。普通に生きてきた日常が、一瞬にして崩壊してしまう。その境界を「あっ」というたったひとことが分けているんだなっていうのが、今回の本にもすごく表れていると感じました。
たとえば落雷が直撃した人の事例のところに「越中は『あっ』と思ったという」と書いてあります。
ライターはこういうときにデコレーションした表現を入れたくなるんですよ。
そこをシンプルに書いてあることで、逆に、突然雷に打たれて気を失うという一瞬の衝撃が、これによって伝わってきます。
羽根田 自分はそぎ落として、簡潔にパッパッパッと書くのが、どんどん好きになってきたような気がしますね。
春日 そのソリッドさは、同じ書き手として僕が一番憧れるところです。
(構成:幻冬舎plus編集部)
* * *
ちょっとした知識で生還率が大幅に上がる!『山はおそろしい 必ず生きて帰る! 事故から学ぶ山岳遭難』好評発売中
山はおそろしい

2022年5月25日発売の『山はおそろしい 必ず生きて帰る! 事故から学ぶ山岳遭難』(羽根田 治・著)の最新情報をお知らせします。















