
「量子もつれの実験でベルの不等式の破れを立証し、量子情報科学を切り開いた」という業績で、2022年のノーベル物理学賞は、アラン・アスペさん、ジョン・クラウザーさん、アントン・ツァイリンガーさんの3氏が受賞しました。「量子もつれ」とは、量子に見られる古典物理学では解明できなかった現象で、一瞬で空間を超えて情報が伝わるテレポーテーションのような不可解な振る舞いとも考えられてきました。『量子で読み解く生命・宇宙・時間』から一部を抜粋して紹介し、「量子もつれ」について解説します。

離れているのにもつれている?
量子論の非常識さを強調する際によく言及されるのが、「量子もつれ」と呼ばれる現象である。相互作用していた2つの量子論的システムを遠く引き離したとき、それぞれのシステムで観測される量の相関が、古典的なシステムで見られる相関と異なるという性質である。
解釈によっては、まるでSFに登場するテレパシーか何かのように、遠く離れたシステムが空間を超えて連絡を取り合っているようにも見える。こんな連絡手段が現実にあるのなら、確かに、量子論は常識外れの奇妙な理論である。
空間を一瞬で飛び越える遠隔作用の存在は、場の理論の考え方と両立できない。場の理論は、空間の各地点に物理現象の担い手となる場が実在することを前提とし、さらに、ある地点に生じた出来事の影響が直接作用するのは、隣接する場に限られるとされる。
これが、「局所実在論」と呼ばれる考え方である。この考えに従うならば、遠方に影響が及ぶには、途中の経路にある場を順次伝わっていかなければならない。かけ離れたところに一瞬のうちに作用が到達することは、あり得ないのである。
近代物理学の中には、遠隔作用を認める理論もあった。17世紀に提出されたニュートンの重力理論は、ある地点に置かれた質量が、一瞬のうちに遠く離れた別の質量に力を及ぼすという形式になっていた。この理論に対しては、発表された直後から、遠隔作用をオカルト的な怪しげなものと感じた多くの科学者が批判を浴びせたが、誰も代わりとなる理論を作れなかった。
ようやく20世紀初頭になって、アインシュタインが一般相対論を構築し、ニュートンの重力理論が、遠隔作用のない場の理論の近似であることを示したのである。
一般相対論によると、重力作用を伝える場は、時間と空間が一体化した時空そのものである。ある地点にエネルギーが存在すると、その周囲で時空がゆがみ重力を生み出す。エネルギーが移動した場合は、その結果として生じるゆがみの変化が、隣接する地点に順番に伝わっていく。ただし、その伝播速度はきわめて大きく、一瞬で空間を飛び越えたと感じられるのである。
場の理論をベースとして作られた場の量子論も、遠隔作用を容認しない。それでは、まるで遠隔作用の現れであるかのような量子もつれは、場の量子論と矛盾する鬼っ子なのだろうか?
量子もつれについては、まだ完全に解明されておらず、学界でも意見が分かれている段階なので、クリアカットな説明はできない。特に、「ベルの限界が突破された」ケースに関しては、推論に基づくかなり込み入った解説になる。

アインシュタインによる否定
量子もつれとは、もともとは、量子論が不完全であることを示すために、アインシュタイン= ポドルスキー= ローゼンの連名論文「物理的実在についての量子力学の記述は完全だと考えられるか?」(1935)で論じられた現象であり、3人の頭文字を取ってEPR相関と呼ばれる。
アインシュタインは、ボーアとの論争において、「相互作用をしていた2つのシステムの一方を観測することで、他方の状態を調べる」という思考実験を繰り返し提案した。これは、注目する対象に直接的な観測操作を加えないことで、「観測に伴う擾乱」を避けるための手法である。EPR論文で扱われたのは、そうした思考実験の一種であり、簡単に反論できない精緻な議論を展開している。
アインシュタインらは、相互作用によって特定の量子状態になった2つの粒子が、まるで遠隔作用で互いに連絡を取り合っているかのように振る舞うことを示した。その上で、遠隔作用が存在するはずがないので、量子論の記述が不完全である証拠だと主張したのである。
これに対して、ボーアは、直ちにEPRと同じタイトルの論文を執筆して反論を試みた。もっとも、ボーアの論文は何を言いたいのかさっぱりわからない支離滅裂な内容で、後にデヴィッド・ボームやジョン・スチュアート・ベルによって手厳しく批判された。
また、パウリやハイゼンベルクは、遠隔作用に関するEPRの主張は、量子論に対する批判と言うよりも量子論の特性を指摘したものと解釈し、敢えて反論しなかった。
EPRの議論は、粒子の位置と運動量の関係に注目したもので、2つに分かれた粒子のうち、一方の粒子の位置を測定すると他方の粒子の位置が、運動量を測定すると運動量が確定するという関係が論じられた。量子もつれがある場合、このように、もともと相互作用していた2つのシステムを引き離したとき、一方の状態を測定すると他方の状態が直ちにわかるという関係が成り立つ。
特に重要なのは、最初の測定を行う際に、位置か運動量かというように、測定対象を自由に選べる点である。遠く離れた粒子に対してどんな測定をするかによって、直接測定を行っていない粒子の状態記述が左右されるのだから、量子論には遠隔作用が存在すると言いたくなるのもわかる。
もっとも、EPR論文に記された実験は、実際に遂行するのが難しく、おまけに、その実験で何が明らかにされたのか、見通しがきわめて悪い。
そこで後続研究者がEPRの議論を一般的な形式に書き直し、どのようなタイプの実験を行えば良いかを論じた。こうした研究で明らかになったのは、単一の実験では量子もつれを調べるのに不充分であり、何度も繰り返し実験を行って統計的データを集めなければならないということである。
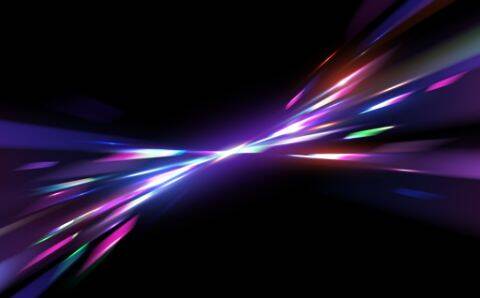
量子もつれを検証するための新たな実験
新たに提案されたEPR相関の実験として最もわかりやすいのが、光子の偏光状態を測定する実験で、ボームが詳しく論じた。偏光とは、電磁場の振動が特定方向に偏っている状態であり、特に、電場が1つの定まった方向にしか振動しない状態は、直線偏光と呼ばれる。
EPR論文のように粒子の位置を問題とすると、どうしても、「その位置に粒子が存在する」とイメージしてしまう。実際に論じられるのは、「何度も実験を行って繰り返し位置を測定したときの統計的なデータ」なのであって、「そこに粒子がある」という命題とは物理的な意味がかなり異なる。
この点、光子の偏光状態を測定対象にすれば、位置のように「粒子がどこかに存在する」といった既存のイメージにとらわれにくく、見通しが良くなる。2つの光子が異なる方向に偏光している場合、それぞれの偏光状態についての量子論的な記述は、数式の上で、位置と運動量の関係と同じ形になる。したがって、位置と運動量の代わりに偏光状態を取り上げても、EPRの議論が正当かどうかを検証することができる。
量子で読み解く 生命・宇宙・時間

2022年1月26日刊行の『量子で読み解く 生命・宇宙・時間』の最新情報をお知らせいたします。

















