
2022年に創業25周年を迎えた、楽天。四半世紀前、たった6人で始まったベンチャーは、今や日本を代表する企業にまで成長しました。そんな楽天と、グループを率いる三木谷浩史氏の25年間に迫った、同氏監修の最新刊『突き抜けろ』は、発売直後にブックファースト新宿店のビジネス部門で1位を獲得するなど、話題となっています。今回は第1章「聖域を作るな」から、一部をご紹介します。
* * *
僕は日本を元気にしたい
「在職中にハーバードに留学され、帰国後はM&A担当という出世コースだったのに、どうして興銀を辞められたんですか」
1996年、日本興業銀行(現みずほ銀行)を辞めて独立した三木谷の姿は、東京・広尾の小さなオフィスの一室にあった。そこを訪ねてきた一人の大学院生は尋ねた。
「理由は簡単だ。僕は日本を元気にしたいからだ」
三木谷は当然のことのように、そう返した。
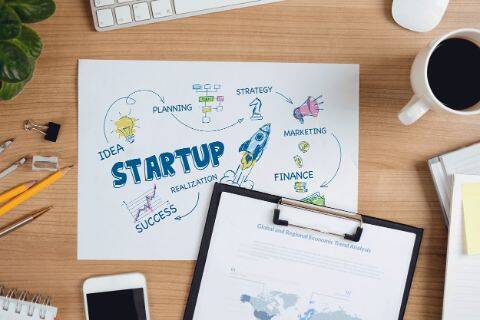
楽天は、1997年2月に三木谷とその大学院生、社員番号2番の本城慎之介によって設立された株式会社エム・ディー・エムが前身となっている。同年5月、インターネット・ショッピングモール「楽天市場」がスタートする。
97年といえば、インターネットのスピードは14.4Kbps。今や1ギガなので当時は今の約10万分の1のネットワークスピードの世界だった。
このとき、社員は三木谷を入れて6人。その中の一人が、社員番号4番、現楽天グループ常務執行役員CWO(チーフ・ウェルビーイング・オフィサー)の小林正忠である。創業期から、社内では「せいちゅう」と呼ばれている。
小林が三木谷と出会うことになったきっかけは、大学の一つ下の後輩であった本城が「面白い人がいる」と声をかけてくれたことによる。
その本城はもともと興銀入社を目指して就職活動をしていた。ある日、OB訪問で出会った先輩から「辞めた人間の話も聞いたほうがいい」と勧められ、退職したばかりの三木谷に会った。このときの三木谷の言葉が、本城の人生を大きく変えることになる。
「日本には、企業が約400万社ある。そのうち、大企業はどのくらいだと思う?」
三木谷はおもむろに本城に問いかけた。
「3割くらい、でしょうか」
本城は咄嗟に答えた。
「いや、数だけでいったら1割にも満たない。9割以上が中小零細企業だ。しかも、そのうちの7割が赤字経営なんだ」
「そうなんですか」
本城は眼鏡の奥で目を見開いた。
「この国を下支えしているのは、決して報われているとはいえない中小零細企業や個人事業主の人なんだよ。興銀にいたんじゃ、そんな人たちを見ないで国を動かしているような錯覚に陥る」
「……」
三木谷は熱っぽく語り続けた。
「銀行や商社といった大企業が日本を変え、社会を作っていく時代はもう終わったよ。これからは個人や中小企業が、既成事実を積み重ねて新しい社会を作り、日本を変えていくんだ。それが日本を元気にするんだ」
本城はこのときの場面が今でも脳裏に鮮明に焼き付いている。
だからこそ、何かを成し遂げたい
ハーバード大学に留学した三木谷は、アメリカのスーパーエリートたちが大きな組織などには関心を示さないことを知った。自分の独自性を活かして価値を生み出していく起業家こそが、アメリカでは尊敬されていたのだ。

帰国後、バブル崩壊で活気を失った日本で気づいたのは、これからの日本経済を支えるのは、起業家だという確信だった。三木谷は興銀で、ソフトバンクの孫正義はじめ、さまざまな起業家を支援する仕事に従事することになる。
しかし、そこにやってきたのが、故郷の兵庫県を襲った阪神・淡路大震災だった。叔父と叔母の突然の死にも直面する。三木谷は、父・良一からこんな声をかけられる。
「普段忘れとるだけなんや。こういうときに思い知らされる。人生なんてあっという間や。せやから懸命に生きる。やれるときに全力でやらんとな」
三木谷は、自ら起業することを決意した。
「人生は一度きりしかない。だからこそ、何かを成し遂げたい」
当時30歳。まずは、クリムゾングループという名の会社を立ち上げ、興銀時代の顧客を相手にコンサルティングを引き受けながら、起業の準備をしていた。そこにやってきたのが、本城だった。
そして本城の紹介で三木谷に出会うことになった小林は当時、勤めていた大手印刷会社を退職、自分の会社を作るための準備期間として、後に一緒に楽天に加わる杉原章郎とともに同級生が立ち上げた会社に転がり込んでいた。

















