
「100分de名著」(NHK Eテレ)で取り上げる作品を九年にわたり選び続けてきたプロデューサー、秋満吉彦さんが最も戦慄を覚えたのは、現代社会のありようを言い当てる「名著の予知能力」でした。秋満さんによる新書『名著の予知能力』から番組の制作舞台裏をお届けします。

通説を揺るがし、常識的な読みを解体するミッチェル「風と共に去りぬ」(2019年1月放送)
「風と共に去りぬ」の講師を担当してくれた鴻巣友季子さんとの出会いは、「翻訳対談」というタイトルで行われた、翻訳家の古屋美登里さんとのトークショーの会場だった。メモによれば2017年9月11日とあるから、もう五年以上も前のことだ。
それまで研究者や作家を講師として招いたことはあるのだが、専門の翻訳家を呼んだことはついぞなかった。ただ翻訳文学好きだった私は、原文と取っ組み合い、その一つひとつの言葉の深い意味を探りながら格闘し続けている翻訳家の人たちがどのように名著を読み解くかには、かねて大きな関心を寄せていた。
鴻巣さんの翻訳は、ノーベル文学賞のJ.M.クッツェーの諸著作や、古典では、エドガー・アラン・ポーの作品などで親しんでいたので、どのような語りをされる人なのかという興味でトークショーに参加した。
期待にたがわず、ビビッドな語り口で魅了された。確か、その感想をSNSでつぶやいたのをきっかけに、鴻巣さんとのやりとりが始まったと記憶する。
ぶしつけながら、鴻巣さんに講師としてポーの作品か「風と共に去りぬ」を解説いただけたらとのメッセージをお送りしたところ、興味をもっていただき、お会いすることになったのだった。
鴻巣さんが「風と共に去りぬ」を新訳したことを知ったのは、恥ずかしながらその段階から一年ほど前のことで、「風と共に去りぬ」の回の番組制作を担当してくれたディレクターが、今後取り組んでみたい作品のアイデアリストに挙げてくれたことがきっかけ。「へえ、新訳が出てたのか。しかも鴻巣さんが」と少し驚いた。どちらかというと純文学寄りの翻訳が中心の人だと思っていたからだ。
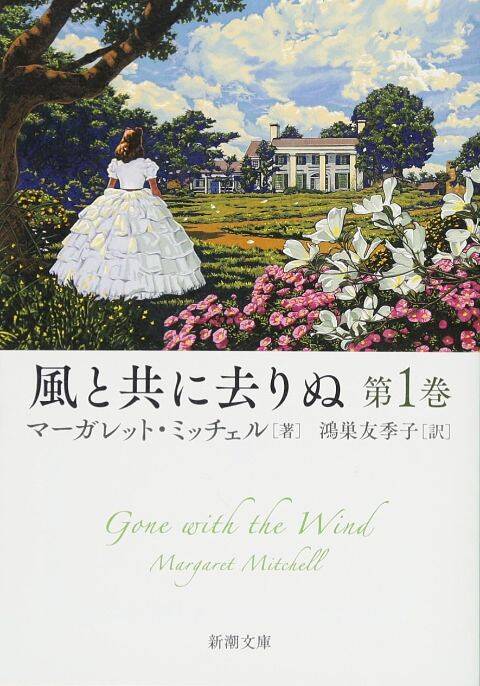
ところが一読して、なぜ鴻巣さんが新訳にチャレンジされたか深く納得。これまでにない瑞々しい文体。リズミカルでぐいぐい読み進めていける心地よさ。
え? 「風と共に去りぬ」ってこんなに面白かったの?……という新鮮な体験だった。ヴィヴィアン・リー主演の映画があまりにも有名なのでストーリーをご存じの方も多いかもしれないが、簡単に振り返っておこう。
舞台は南北戦争前後のアメリカ南部。大農園主の長女スカーレット・オハラは、愛するアシュリの婚約を知り告白するも彼の心を覆すことはできない。当てつけに彼の婚約者メラニーの兄チャールズの求婚を受け入れる。ところが南北戦争の勃発で、スカーレットたちの運命は大きく翻弄されていく。

チャールズの病死、アトランタへの移住、そして彼女のその後の生涯を左右するレット・バトラーとの再会。更に、北軍の勝利は、スカーレットの家族と故郷タラをこれ以上なく荒廃させ、どん底の中で彼女は起死回生を誓う。その後、生きぬくために金の亡者と化すスカーレット。数奇な運命の中、彼女はバトラーとの再会を繰り返し、二人はついに結婚する。しかし、その結婚は更なる悲劇へと二人を追い込むのだった。
あらすじだけを追ってみると、要は、スカーレット・オハラの一大ラブロマンスだ。しかも鴻巣さん新訳の圧倒的なリーダビリティによって、更にエンターテインメント感が倍増して誰に教えられずとも楽しく読めるようになったこの本を、今更番組で解説する必要はあるのだろうか。実は、鴻巣さんと打ち合わせの約束はしたものの、番組で解説する論点が果たして見つかるのか……という一抹の不安は抱き続けていた。
その不安は、鴻巣さんにお会いして吹き飛んだ。NHKの食堂でお茶を飲みながらの打ち合わせだったのだが、途中カップをもつ手が止まってしまった。
「映画では全然目立たなかったメラニーがカギなんですよね、この小説って」
「自由間接話法を使った高度な文体戦略がこの小説の面白さを支えているんですよ」
「この小説って実は後ろのほうから書かれていて、そのことがわかると意外なことがわかるんです」
次々と読み解きのアイデアが鴻巣さんの口から飛び出してくる。私はその間、ずっと心の中で「おもろい」という言葉を繰り返しつぶやいていた。
「第二芸術論」で知られるフランス文学者の桑原武夫は、とんでもない研究者に出会ったときに「おもろい」という言葉を発したという。「頭がいい」でも「できる」でもなく「おもろい」。これが桑原の最上級の褒め言葉だった。哲学者・鷲田清一さんが何かの著書で紹介していたエピソードだ。
「頭がいい」や「できる」は既存のものさしで測られた評価でしかないが、「おもろい」というのは、これまでの通説やそれが依よって立つ基盤そのものを揺るがし、場合によっては解体してしまうような兆候を感じ取ったときに発せられる言葉だという。
鴻巣さんとの対話は、まさにこの「おもろい」を連発してしまうような体験で、「風と共に去りぬ」を取り巻く通説ががらがらと音を立てて崩れさっていく、快感に満ちた時間だった。
トランプ政権までつながる南北戦争以降の暗部
聞き終わった瞬間に、「これは確実におもろくなるな」と確信をもった。その面白さは、番組をご覧になった方々はすでにおわかりだろうが、そのうちの代表的な論点をご紹介しよう。
鴻巣さんによれば、南北戦争後の「再建時代」を描いたパートは、一種のディストピア小説として読むことができるという。南北戦争で北軍が勝利し、奴隷解放や平等社会の実現などという形で、理念上はユートピアが到来した。ところが、ユートピアには必ず暗部がある……というのが鴻巣さんの見立てだ。ユートピアはディストピアと表裏一体で、行き過ぎた理想の追求によってどこかに必ず歪みが起きて、抑圧されるものが必ず出てくるというのである。
南北戦争の新たな体制の中で、スカーレットは、過酷な追徴課税措置によって、故郷であるタラの土地や家屋敷から家や土地を奪い去られそうになる。「いまやゲームのルールが丸ごと変わってしまい、まじめに働いても正当な見返りは得られない時代」だと描写されるほどだ。
新しい支配層の都合でルールがころころ変わり、不正選挙が行われ、内部で汚職が横行。戦争に負けた側がさらされる不当逮捕、リンチ、略式裁判……その一方で、誓約書にサインをして体制に忠誠を誓えば優遇されこの世の春を謳歌できる。スカーレットは、まさにこの矛盾の間で引き裂かれた存在だったのだ。
こうして見ると、アメリカの北部と南部との間に大きな分断が生まれたのがこの時代だったという事実も浮かび上がる。今まであまり描かれることのなかった南北戦争以降の「再建時代」の暗部が「風と共に去りぬ」には克明に描かれているのだ。
更にいうと、トランプ政権時代に奇しくも炙り出された、アメリカの白人貧困層の闇の部分や、根深い同国民同士の分断が、この時代に淵源をもつのではないかとも思えてくる。
そして、このことは決して他人事ではないと思う。極端な排外主義の横行、それを煽り立てることで求心力を高めようとする政治手法、勝ち組たちがマイノリティの意見を数の論理で封殺する風潮、異なる政治スタンスの人と対話するのではなく排撃して貶めることで盛り上がるSNS……そんな状況がここ何年も世を席捲している。
論壇では「分断」という言葉がキーワードのように語られ続けている。同じ国にいながらにして人々が深く分断されている……あるいは、隣り合った国同士でも恐るべき溝が両者を分断し始めた。こうした状況は、「風と共に去りぬ」で描かれたディストピアと酷似しているのではないかと思われてならなかった。
通説でいえば、「一大ラブロマンス」「歴史大河ロマン」といったエンターテインメント小説と見られがちな「風と共に去りぬ」が、「ディストピア小説」という「新たな角度」を鴻巣さんに与えてもらうことで、これまで唱えられてきた通説の数々ががらがらと崩れ落ち、「風と共に去りぬ」がもつジャーナリスティックな魅力が見事に浮かび上がってきた。名著を「常識的読み」の枠組みから解放する……これもまた一つの「名著の蘇生」といえるのではないかと、深く実感する体験だった。
最後にもう一つ、付け加えておきたい。鴻巣さんの語りの魅力、そして文章の魅力を物語るキーワードは「全身」だと思う。その解説には、「頭」だけでなく、「全身」からあふれ出すエネルギーが感じられる。その秘密とは何か?
鴻巣さんはご自身のことを「全身翻訳家」と呼んでいるが、全身で作品に没入し、最深部まで潜ってその細部を味わい尽くし、再び水面に浮上してきて、私たちが表面的にしか読めていなかった、作品の深部にある「宝物」を届けてくれる……私は、そんなイメージで鴻巣さんのお仕事を眺めている。だからこそ、常識を揺さぶるような「新たな角度」を提示できるのだ。「風と共に去りぬ」の解説には、そんな「宝物」がたくさんちりばめられていた。
私自身も、番組企画に取り組む際には、「全身プロデューサー」でありたい……いつも、そう願っている。
名著の予知能力

NHK Eテレ「100分de名著」プロデューサーによるまったく新しい名著の出会い方















