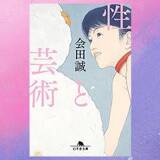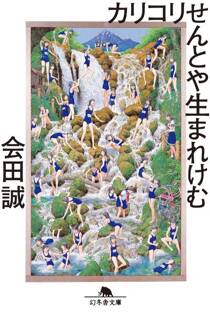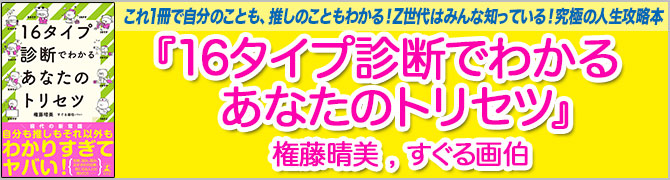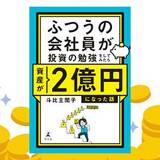
日本を代表する現代美術家・会田誠による「犬」は、2012年森美術館展覧会での撤去抗議をはじめ、数々の批判に晒されてきた。裸の少女の“残虐”ともいえる絵をなぜ描いたのか――? その理由を作者自らが解説した『性と芸術』が文庫になりました。文庫版書き下ろし「僕の母親(と少し父親」」に加え、大野左紀子さん、二村ヒトシさんの解説を収録。単行本からさらに充実した内容です。「はじめに」に続く箇所を抜粋してお届けします。
1980年代後半の美術の状況と私
新潟市出身の私は東京で一浪して、1985年に東京藝術大学(以下藝大)の油画科(一般的には油絵科のこと)に入学した。以下の記述はその時代のことであり、現在の美大や美術界の状況とは様々な面で異なることをあらかじめ断っておく。
藝大の油画科に入学するためには、いわゆる「デッサン力」というものを身につける訓練を美術予備校で施される。そして晴れて入学すると、1、2年生は与えられた課題をこなす期間となる。詳しくは後述するが、私の時代はそのほとんどが「ヌード」であった。
ただし描く対象はヌードモデルであるが、それを光と影を正確に写す、19世紀以前の西洋写実画の技法で描けば褒められる──というものでもなかった。その段階は予備校でクリアしてなさい、大学に入ったら次の段階に行く──という暗黙の了解が、教員と学生の間にあった。次の段階──すなわち19世紀以降のモダン絵画の見方・考え方を取り入れた描法が、大学ではそれとなく推奨されていた。描いている時に手取り足取りの指導があるわけではないが、完成した作品を一堂に並べてなされる「講評会」において、教授たちの口から出る言葉で、それとなく学生たちに伝わるのだ。
簡単に言えば「抽象画の方に行け」ということだった。
もう少し詳しく言えば「具象画から順次、抽象画の要素を取り込んでいきなさい。その先に自分の中で必然性が生じたならば、完全な抽象画になっても構わない」ということだった。そこには例えば、樹木を描いているうちに次第に幾何学的な画面構成に移行していった、モンドリアンの長く忍耐強い画業などが理想形として設定されていただろう。それは課題を与えられる学部1、2年の期間を過ぎ、ほぼ完全に放任され自由制作となる学部3、4年の期間に、暗に求められる油画科の順調な優等生的成長だった。
なぜそのような指導になるかと言えば、それが20世紀の世界的な美術の潮流だからである。それが主流にして正調なのだ。藝大の油画科とは、そういうものと常にシンクロすることを旨としていて、そこに誇りを賭けているセクションだった。そこで尊ばれている概念は「世界」であり「普遍」であり「進歩」だった。つまり逆に蔑まれている概念は「日本」であり「特殊」であり「保守」だったわけだ。
私も一応その基本的な考え方には同意していた。曰く、歴史は常にフレッシュに刷新されていくべきだ。曰く、もはや国際性を抜きに生きていける時代ではない。──今でも基本的にはそう思っている。
しかしそのような教授陣の指導も、当時の私のように糞生意気な学生には、時代遅れに感じられた。抽象画が象徴する教授たちが抱いている「進歩」のイメージが、10年から60年くらい遅れているように思えた。そう思う学生は、私の見たところ5人に1人くらいはいた。
彼らは学部1、2年の間に出されるヌードの課題はおざなりに付き合った/あるいはボイコットした。私は前者だったので、留年から退学という流れにはならなかったが。そして彼らは生意気な言葉を頭の中に詰め込み、あるいはそれを口に出した。私も時々口に出したが、話せる友人は極端に少なかった。
そして彼らのうちの幾割かは、有言実行ということで、課題とは別に、真に自分が作りたいものを作った。自ら求めれば、学内で展示する機会を作れなくはなかった。その一つは、毎年秋にある藝大の学園祭──通称「藝祭」での展示。もう一つは、学食のある「学生会館」に併設された展示室を予約して、グループ展を開くことだった。私は両方の展示に積極的な学生だった。
繰り返すが、これは私が入学した1985年から数年間の話だ。日本における現代美術のほぼ唯一の専門誌「美術手帖」では、インスタレーションやパフォーマンスやビデオアートといった、現在では美術界に定着して普通になった手法が、海外の最新動向として毎月のように紹介されていた。もちろん意識の高い美大生はその写真と記事を目を皿のようにして見、読んだ──英語のアート・マガジンが読めない限り、情報源はそれくらいしかなかったのだ。
1984年にはヨーゼフ・ボイスが西武美術館で日本初個展をするために来日し、藝大でも講演会を行った。そして1986年に彼の病死の報が伝わり、日本の狭い美術界でも数年間は追悼ムードが続いた。ボイスや彼が主導したドイツの芸術祭「ドクメンタ」が指し示すアートの新しい地平は、藝大油画科の「具象画から順次抽象画の方へ行きなさい」などといった指導を、さらにヒドく時代遅れなものに感じさせた。
今の美大生は想像しにくいかもしれないが、当時は世界的に「絵画の冬の時代」だった。世界的に「絵画の復権」が謳われ出したのは、私の感覚では90年代後半からゼロ年代にかけてだった。それは同時に、ヴェネチア・ビエンナーレやドクメンタといった国際的芸術祭と、ニューヨークのギャラリーを中心としたアートマーケットの、今に至る露骨な乖離/棲み分けの始まりだったと個人的には感じている。
* * *
続きは、『性と芸術』をご覧ください。