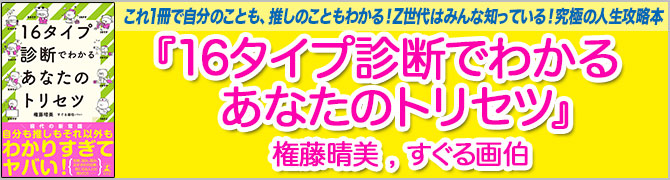「直感ではノー」をフェルミ推定で検証してみる
総論も終わりに近づいてきました。今回は経済について書いてみたい。といってもたいしたことではなくて、まずは家庭菜園の採算とか野菜の値段についてのお話です。
家庭菜園で採算がとれるか? 直感的には絶対にノーだ。きちんと計算するのは面倒だから、ここはフェルミ推定でいってみよう。ノーベル物理学賞を受賞したイタリア人物理学者、エンリコ・フェルミの名に由来する、実際に調べるのが難しい問題を単純な仮定と論理的な推論から概算する方法である。シカゴにピアノの調律師が何人いるかとか、日本にマンホールがいくつあるかとかいう例題がよく知られている。どちらも、まったくどうでもいい問題なのだが、考えてみると面白い。
野菜を作るのに必要なのは、堆肥(たいひ)、肥料、野菜の種あるいは苗、である。仲野家菜園の作付け面積はざっと30坪で、そのうち畝(うね)になるのはおよそ4分の3くらいだから約75平米になる。堆肥とか畝とか、連載で詳しく説明した用語が出てきてなんだか嬉しい。基本的には春蒔きと秋蒔きの年に2回なので、有効面積は延べで75平米の2倍、すなわち150平米になる。
まずは土に必要なお金。使っているバーク堆肥はホームセンターで買ってくるもので20リットルが450円くらい。これを1平米あたり10リットルなので、年間約3万5000円になる。有機肥料は、平米あたり300グラムを撒いているので、年間にして45キログラム。追肥(「おいごえ」または「ついひ」と読んで、生育途中に施す肥料のこと)も入れて約1万円。pH調整には草木灰を使っていて、これが石灰に比べるとけっこう高くて同じく1万円くらい。かくして畑の環境整備におよそ5万5000円といったところ。初めてまともに計算したけど、堆肥がいちばん高いんや。
次は種のお代。少量多品種栽培なので、いちばん小さな袋で十分だ。多くは200~400円で、高いものでも1000円もしない。野菜の種類としては40種類くらいを作っているが、品種となると60種類程度である。ざっくりと掛け算して、2万円弱といったところだろう。百均ショップでも種は売られているけれど、何となく信頼性が低そうなので買ったことはない。偏見かしらん。
苗を買うこともあるのだが、種に比べるとうんと高くて、200~500円くらい。種とあんまり違わんやないかと思われるかもしれないが、苗は1本あたりの値段であるのに対して、種は蒔ききれないほど入っている。苗は年間に10本くらいしか買わないのでたかがしれている。種とあわせて2万円ということにしておこう。
これで年間の消耗品代が出そろった。あと、細かい消耗品としては、マルチシートとか、茎を支柱にとめる針金とかもいるけれど、誤差の範囲だ。なので、総額として年間に7万5000円といったところである。
仲野家では1年に野菜をどのぐらい買っている?
私は「計算くん」と呼ばれることがあるくらいこういうざっくりした計算をするのが好きだ。敬愛する知の巨人、出口治明さんは、正しく物事を決めるには「数字、ファクト、ロジック」が重要とよく書いておられる。さすが、生涯でただ1人尊敬する出口さんだけあって、ええこと言わはる。まったくその通りだ。私の場合は、数字的に有意な差がなかったら意味がないという研究の世界で生きてきただけに、数字信奉が人一倍高い。
なにごともイメージでものを言ってはあかんのだ。高等学校で科学について話をさせてもらうことがあるのだが、その時にも必ずこのことを強調する。たとえば、「カラスは白い」はウソだけど「あのカラスはわりと白い」は正しいこともある。かくのごとく、「『わりと』がつけばカラスも白い」というのは、常に肝に銘じておく必要がある。ちょっと多いとか、比較的少ないとかいった漠然とした言い方はよろしくない。きっちりした数字が必要で、できれば相対的ではなくて絶対的な数字がほしい。
そういう考えが身に染み込んでいるので、いろんなことを概算するのが好きなのだ。人間フェルミ推定かもしらん。いや、そんなええもんとちゃうな。ちょっと言い過ぎた。が、ともかくよく推計している。スーパーのレジでは、支払がいくらくらいかをあてるゲームを1人で楽しんでいる。いちいち品物の値段は見ずに買い物かごに放り込んで推計するのだ。ルーチンの買い物なら、ほとんどの場合1割程度の誤差におさめることができる。一度なんぞ、1円の桁まであたって、さすがに驚いた。
こんなこと誰でもできるのではないかという気がするが、妻に言わせると決してそんなことはないという。理由は、自分ができないから。はて、私に才能があるのか、妻が無能、じゃなくて、そういう才能に欠けるのか。どっちなんやろ。
こんな前置きでなにをしようとしているのかというと、1年に野菜をどれくらい買うかを考えてみたいのである。老人2人住まいなので、それほどたくさん買うわけではない。季節にもよるが、1週間あたり500円はくだらないだろう。かといって3000円もいきそうにない。平均したら1000円ちょっとといったところか。52週として6万円くらいかという気がする。
検索してみると、農林水産省が生鮮野菜の消費動向を調べて発表していて、2人以上の世帯におけるⅰ人あたりの年間購入はおよそ2万5000円である。ちなみに重さは58キロらしい。金額はかなりいい線いってるが、重さについてはナカノ的フェルミ推定をかなり上回っておるぞ。2人分だと毎週2キロ、そんなに買ってるとは思えんけどなぁ。摂取量は88キロとされているので、30キロは外食とかコンビニ弁当とかという計算になる。全食事の3分の1にもなるけど、そんなに多いんか。統計って、いろいろ妄想できてけっこうおもろいわ。
老人家庭なので、それほど量は食べないが、野菜は多い目である。なので、年間に6万円というのはかなりいい数字だろう。もちろんこれは家庭菜園を始める前の購入金額である。これもざっくりとだが、野菜のうち4分の3くらいを自家菜園でまかなえていると思う。となると5万円ほどだが、余剰分=近所へのお配り分があるので、それとあわせて6万円分の生産としておこう。そのためにざっと7万5000円ほどかかっているのだから、採算的には赤字ということになる。さらに、他の経費もかかっている。
「採算がとれない」どころじゃなかった!
農機具が1万円くらい。支柱とか防虫ネットとか防寒用ビニールシートとかで1万円くらい。春先に苗を育てるための保温器とかが1万円くらい。買わなくてもよかったカルチベータ君が4万5000円で、計8万円。これは5~10年ほど使えそうなので、1年分にしたら約1万円。それよりもはるかに大きいのは10万円弱も払わねばならん固定資産税だ。
固定資産税は土地の評価額に対してかかるのだが、農地の評価額はえらく安いと聞いたことがある。ひょっとして農地に指定してもらえたらうんと安くなるのかと調べてみたら、我が家は特定市街化区域農地(3大都市圏の特定市の市街化区域農地)にあるので、たとえ農地として使っても宅地並みに評価されるらしい。残念……。税務署的にはそんなところで畑するなっちゅうこっちゃな。
畑をせずに遊休地にしておいても固定資産税は払わないとあかんのだから、経費に入れるのは妥当でないかもしらんが、そこはそれ、人情として繰り入れてみたい。となると、6万円ほどの野菜のためにかかる年間総経費は19万円近くにもなる。非採算どころとちゃうがな。
農地といえば貸し農園がえらく人気だと聞いたことがある。はて、どれくらいかかるのかを検索してみた。大きくふたつ、公営のものと民営のものがある。公営のものは1区画が10~25平米くらいで年間数千円くらいが相場のようだ。仲野家菜園の固定資産税の方がはるかに高いがな。
1区画1世帯と制限がつけられているのは、人気があるからだろう。倉庫があるところとないところがあるのはいいとして、中にはキッパリと「水道なし」と書いてあるところもある。はたして水を運んで行かねばならんのだろうか。謎だ。
それに比較すると民間の農園はかなり高い。10平米ほどで月に数千円から1万円強が相場だから、公営の10倍から20倍もする。これはいくらなんでも暴利がむさぼられているのではないかと思ったが、そうでもない。民間は単なる農地ではなくて、農具はもちろん、季節ごとの種や苗、肥料も提供されている。そのうえ、アドバイザーがおられて指導してもらえるらしい。10平米だと、およそ3メートルで70センチ幅の畝を3本だから、そこそこ、といっても年に1~2万円分くらいだろうけれど、の野菜はできる。
年間に19万円くらいが高いかどうか。元がとれるかどうかとかいうせこい採算ベースではなくて、趣味として菜産(←しゃれです、念のため)をとらえてみたらどうだろう。
10年以上前から義太夫を習っている。古典芸能にしてはお稽古や発表会が破格の安さなので、基本的には固定資産税込み菜産の費用とトントンといったところ。最近、乗馬を習い始めたのだが、これは菜産経費を大きく上回る。こう考えると、趣味としては決して高くない。土との戯れ、育てる感動、収穫と食べる喜び、この3つを勘案すると安くて満足度の高い趣味ではないか。時間もたっぷり使えるし。
売られている野菜は安すぎる
菜園をしてつくづく感じるようになったのは、どう考えても売られている野菜が安すぎるということだ。もちろん家庭菜園と違って大規模におこなわれるし、化学肥料と農薬が使われているからコスト的にはうんと低いだろう。農地だから固定資産税も安い。
しかし、である。基本的な作業は人に頼らざるをえない。米作りはかなり機械化されているが、野菜の収穫はほぼ手作業でしかできない。さらには、流通や販売にコストがかかる。にもかかわらず、旬になれば、立派なキャベツやらダイコンやらが1個100円とかで売られている。さすがにおかしくはないか。
農家さんたちは大変だと思う。いくら手塩にかけても、天候が悪かったら不作になるし、台風や霜でやられてしまうこともある。不作はもちろん困るが、豊作すぎてもあかんという状況もある。価格が下がりすぎて売っても赤字になるからと、野菜が廃棄されるニュースが流れたりする。理屈はわかるが釈然としない。
もうひとつ不思議なのは、売られている野菜の大きさがものすごくそろっていることだ。作り方が下手だからと言われればそれまでだが、家で作っていると、隣接する野菜でさえ同じようには育たない。売られている野菜は魔法としか思えない。
家庭菜園を始めるまでは、野菜が安すぎるなどと考えたことなどなかった。我が家の近所には安売りの八百屋さんがけっこうあるのだが、最近では行くたびに、なんでこんな立派な野菜がこんな値段で売られてるねんと、つい呟いてしまう。もっと野菜は高くてもいいのではないか、いや、高くあるべきではないか。農作業を経験してみたら、誰もが同じような考えを抱くはずだ。
農水省が「農業経営体の経営収支」というのを発表している、令和5年のデータによると、主業経営体における農業粗収益は2184.8万円になっている。けっこうあるやんと思うのは早すぎる。うち農業経営費が1780.6万円もあるので、農業所得は差し引きで404.2万円になる。ちなみに、主業経営体とは「個人経営体のうち、農業所得が主で、自営農業に60日以上従事している65歳未満の者がいる経営体」のことである。
と書いていて、子どものころに聞いた「三ちゃん農業」という言葉を思い出した。死語ですわなと思って広辞苑を引いたら、なんと載っておった。「爺ちゃん・婆ちゃん・母ちゃんに支えられる農業経営。農家の主な働き手である男性が、出かせぎやサラリーマン化で不在になる社会状況の象徴としていう」日本国語大辞典では「昭和三〇年代後半の流行語」という注釈もついている。おそらく父ちゃんⅰ人で農業を営んでいる家庭は少なそうだから、それを勘案したら400万円というのは決して多くないように思うのだがどうだろう。
「徴農制」を提案します
野菜の自給率(重量ベース)は、昭和40年度にはほぼ100%だったのが今は80%にまで低下している。それでも、食糧自給率全体ではカロリーベースで38%、生産額ベースで61%(令和5年度)であることを考えるとけっこう高い。まぁ、そのまま輸入したら鮮度が落ちるから当然か。
野菜の生産量は昭和57年がピークで以降は減少し、「漬物野菜であるだいこん、はくさい、きゅうり、なすが減少の大部分を占めており、その中でも、だいこん、はくさいは重量野菜で収穫作業の労働負担が大きく、農業者の高齢化等とともに生産量が大きく減少しました」と書いてある(農林水産省「知ってる? 日本の食糧事情」HP)。いろいろ勉強になるわぁ、ホンマに。
農家の高齢化は著しく、いまや平均年齢が68歳を越えている。これは食料安全保障上、由々しき問題ではないか。このままいくと、早晩、野菜の供給も不十分になりそうだ。ここは安全保障のことでもあるし、徴兵制ならぬ「徴農制」が必要ではないか。ええ案やと思うけど暴論かしらん、と思ったら、同じようなことを考える人がいて、ウィキペディアに項目がたっておった。
「ニートを徴農制で叩き直す」などという不健全な発想ではなく、農業というのはいかなるものかを知ってもらうためが主目的だ。伊藤忠商事会長の丹羽宇一郎さんは「国立大学の教養課程必修科目とすることで多くの学生に実際に自然の中で農作物を作る喜びを体験させる」ことを主張したことがあるらしい。いやぁ、それでは足らんやろう。
できることなら全員が1年間、じっくりと体験してほしい。農業に対する理解が深まるだけでなく、農業生産もあがる。知的活動の時間もたっぷりとれる。それに、ある程度の割合で農業に従事しようと考える人も出てくるだろう。人生100年時代、1年くらいモラトリアムがあっていい。悪いアイデアじゃないと思うけど、実行されることは未来永劫ないやろな。
勝手なこと書きましたけど、農業について真剣に考えるようになることも知的菜産の一部ですわ。始める前の私がそうだったように、ほとんどの人は単なる消費者として、野菜なんか安いほどええわという考えに染まってるんとちゃいますやろか。それって、絶対にあかんから。
知的菜産の技術の記事をもっと読む
知的菜産の技術
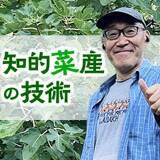
大阪大学医学部を定年退官して隠居の道に入った仲野教授が、毎日、ワクワク興奮しています。秘密は家庭菜園。いったい家庭菜園の何がそんなに? 家庭菜園をやっている人、始めたい人、家庭菜園どうでもいい人、定年後の生き方を考えている人に贈る、おもろくて役に立つエッセイです。