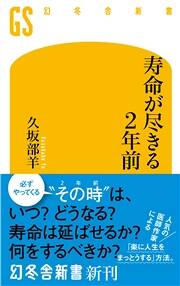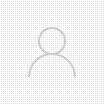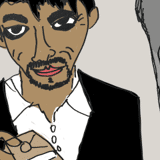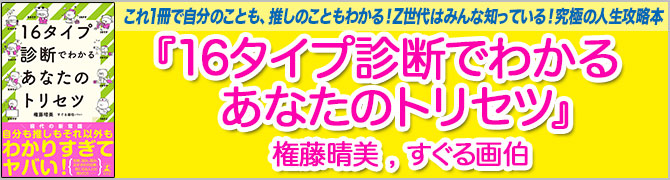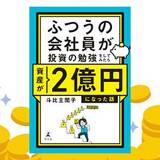
医師であり、ベストセラー作家である久坂部羊さんが『絵馬と脅迫状』を上梓しました。「医」と「病」をめぐる六編の傑作短編小説集。軽快なストーリーのなかから突如として現れる闇、狂気、恐怖、笑い、そして現実とつながるもの――。それぞれの物語がどのように生まれたのか、お話を伺いました。
(構成 河村道子 撮影 鈴木芳香)

――変な医者、病人、研究者らを主人公とする六編は、久坂部さんらしさがそれぞれに滲み出ていますね。
小説を書くとき、いつも「医療小説」という枠のなかで考えていくのですが、新しい技術がどんどん生まれる医療は、進歩した分、必ずその裏に弊害や不条理があるんです。私が目を付けるのはいつもそこ。医療は良い面が強調されやすいけど、そうでない面も必ずある。「そうでない面」をメディアも専門家もなかなか伝えない。でも知っておいてもらった方がいいことってあるんです。この短編集もそうですが、ある意味それは読んだ方が「ちょっと嫌な話だなぁ」と思うものにもなってしまう。でも嫌な小説を書くのが、作家としての私の立ち位置みたいなものですからね(笑)。
――学生時代に自殺した親友と瓜二つの男が新人医師として自分が勤務する病院で働きだし、以後、不可解な事件が頻発する一編「爪の伸びた遺体」もちょっと嫌な話です。自殺した親友である己一が強烈な個性を放っています。
己一には実はモデルがいるんです。高校のとき、それまで本なんて読んだことのなかった私に、「小説家になりたい」と思わせてくれた人物なんですよ。彼とは小学校から高校まで一緒だったんですけど、エキセントリックで早熟で、作中で己一が口にするトルストイ作品に出てくる〝コム・イル・フォ〟(=品のよい、礼節に適った)も、彼がよく言っていた言葉だったんです。〝コム・イル・フォ〟を目指し、トルストイはいつも爪を美しく切り揃えていたというエピソードがあるのですが、その友人との記憶から、いつも爪をきれいにしていた己一、その遺体の爪が伸びていたら――という話を思いついたんです。
世の中の成功者にはサイコパスが多い⁉
――己一にそっくりな新人医師が来てから起こり始める入院患者の不審死。学生時代の己一の行動を思い起こし、〝たぶん、彼はサイコパスだったのだろう〟、そしてこんなことをする人物は、と主人公の疑惑はどんどん膨らんでいきます。
世の中で成功している人のなかにもサイコパスは多いそうです。グレーゾーンだと思える人は外科医にもけっこういますね。「絶対、無理」と言われても「俺ならできる」と手術で患部を取りすぎて患者さんを死なせてしまったり、日常生活が送れないようにしてしまった外科医が昔はよくいたという話もあります。さらに「自分もそうかな?」と思ってしまうこともあるんです。私はそうしたサイコパスの欲求を小説という形で満足させることができる。
――物語では、トリックが仕掛けられていた根底にあるものは凄まじい嫉妬です。
嫉妬という感情って、小説をつくるとき、おもしろいんですよ。どんなに謙虚で鷹揚な人でも、嫉妬心はゼロではないから。嫉妬心の強い人ほど、それを隠したくなる。でも隠そうとすると、そこに無理が生じてくるわけです。嫉妬心なんて、と振る舞おうとするから嘘も出てくる。そこが人間描写のおもしろいところ。むき出しの嫉妬を書くよりそれを隠している方が深みがあったり、本物らしかったりする。そういうのを見つけて書いていくと、人間ってやっぱりおもしろいなと思うんです。
――この一編、最後の一言に背筋が凍りました。
この一作は、サイコパスをひとつのテーマとして置いているんだけど、人のために殺すことができれば、それは良いサイコパスなのでは? と私は思うんですよね。一方で自分が手を下すのが嫌だから、苦しむ人をそのまま放置するのは悪い健常者なのではないかと。善良なサイコパスは殺してあげた方がいいときはスッと殺してあげる。しかも周りを困らせず、上手にね。最後のひと言には善良なサイコパスの優しさが込められていますね。
医者の説明は見せかけ。僧侶や神父と似た面も
――「生検により起こり得るがん転移のリスクについての洞察」という論文を巡って、それにかかわる研究医が描かれる「闇の論文」は、久坂部さんが小説のひとつの核とされている「情報の側面のある小説」が、前面に出てきます。
がん検査は細胞を取り、顕微鏡で見て診断するのですが、取るとき必ず出血するんです。がんの転移は血管の中にがん細胞が紛れ、転移するというパターンがあるなか、生検でも広がるのでは? ということには皆、口を閉ざしているんですよね。でもそういうことを知るのには意味があると思うんです。医者が真面目にそんなことを言ったら世の人は動揺すると思うけど、これは小説なので。ワンクッションあるためマイルドに伝わるのではないかと。
――〝過去に宗教が人々を救ったように、現代は医療が人々を救っている〟と、医療と宗教は似ている、というところにもストーリーは分け入っていきます。
予定調和とそうなってしまった理由を人は欲したがるんですよね。因果関係が分かると落ち着くから。でも時に、医者の説明は見せかけであったり、事実でなかったりすることもある。そういう意味では、お坊さんや神父さんの説明と同じで、信者を納得させはするけれど、正しいかどうかは分からないという可能性があるということを含ませています。
――著書はベストセラー、新聞の人生相談も好評、患者からの信頼も厚い精神科医・深見百合子のもとに、「二度と人前に出られなくしてやる」と差出人不明の脅迫状が届く「悪いのはわたしか」は、最後の最後まで振り回されてしまう一作でした。
私は新聞の人生相談コーナーが好きなんです。「なるほど、こう考えればいいのか」とか、小説の参考になるのもあるからよく読んでいるのですが、なかには「その通りにやったら余計困るじゃないか」という酷い回答もあるんです。それを趣味で切り取っておいてあるんですけど(笑)、とてもいいお答えをされる回答者のなかに、「こんなにすごい人っているんだ!」という経歴の方がいらして。相談を寄せる人たちは皆、困っているし、運も悪かったりするので、こういう恵まれた立場の人が答えていたら反感を買うんじゃないのか、とずっとハラハラしていたんです。この一編はそんな思いが起点となりました。
――誰が脅迫状を彼女に送りつけたのか。作中、姿が見え隠れする死神のような男も気になります。
実はこの一作、『ボディガード』という映画のオマージュでもあるんです。ホイットニー・ヒューストン演じる歌手に脅迫状が来て、ケビン・コスナー演じるボディガードが守る物語なんですけど、死神みたいなファンの男がずっとついてくるんですよ。あれが犯人っぽいという流れで進んでいくんだけど、実は、という。映画を観た方はもちろん真犯人をご存じなので、「あぁ、じゃあ、この人が犯人なんだな」と思いながら読んでくれるかなって。でもね、というところですね(笑)。
――信心がまったくない医学信奉者の内科医が、病院近くの神社で同僚外科医が奉納した「手術が無事に終わりますように」という絵馬を誤って割ってしまい、以降、悲劇が降りかかる「絵馬」では、医学と信仰という相容れぬピースが思わぬ展開を示していきます。
病院のそばにある神社で、自分の担当の患者さんが「治りますように」と書いている絵馬を医者が見たらちょっとムッとくるんじゃないかなと思っていて。神だのみをしているということは医者を信用してないっていうことだから。神だのみなんかするな、俺に任せろという医者もいるんじゃないかと。自信家の医者って結構いるんですよ。名医という幻想に囚われている医者が。そこからストーリーを膨らませていきました。

医者が育ってきている、いい人にならない構造
――絵馬を読んでは嘲笑い、同僚の外科医・長谷部先生の絵馬を見つけてバカにする内科医小栗は嫌な人。でもどこか人間味のある人ですね。
これはね、嫌なやつですよ(笑)。でも医療に熱心なんです。患者さんの病気を治すことに全身全霊かけている。医療の技術は素晴らしい、でも性格が最悪という人をわざと出してるんです。医療面でも優れ、性格もいい医者を多くの人が求めるけど、これはちょっとないものねだりなんですよね。医者って、いい人にならないシステムで育ってきているから。すごく勉強しなきゃいけないし、責任は重いし、失敗は絶対に許されない。大きな病院や公立病院では報酬面であまり優遇されていないし。それで親切で思いやりのある性格になりますか? と。試験のときも同期生を蹴落とすことを考え、そんなところをくぐり抜けてきた人たちが、きめこまやかな配慮や思いやりを期待されてもね。お医者さんは人格者で、全ての人に優しい、医療技術は最先端の知識を漏れなく習得し、とか、そういう情報が世の中に広まってしまうと皆、そういう期待を抱いて病院に行くわけですよね。そうすると、医者は大変なんです。医者は医療技術だけちゃんとしてくれればいい、人格なんて二の次、と思って病院に行けば、「あの先生、話を聞いてくれない」なんて怒ったりしないでしょう(笑)。
――手術の前に絵馬を奉納する長谷部先生は、医療技術と人格、どちらも兼ね備えた先生ですね。
長谷部先生は実際にはいない理想の医師ですね。彼は医療というものは完全ではないということを分かっている。医者って自分の経験に左右されるんです。たとえば難しい手術がうまくいったら、そのとき、着ていたTシャツを次も着るとか、昔、手術室に入るとき、スリッパに履き替えたんですけど、履く前に天気占いみたいに投げる先生もいましたね。この手術うまくいくかどうかって。長谷部先生のように、縁起みたいなものを自分の心の支えにする医師はけっこういると思いますね。
――絵馬も、神様も、縁起もまったく信じず、それを信じる人を嘲り続ける小栗先生の身の上には良くないことが起き、どんどん不思議な方へ連れていかれてしまいます。
書いているうちに自分でも笑ってしまいましたけど、まったく信用してないのに彼はなぜか……(笑)。視野がどんどん狭くなっていくんですよね。自分がしていることの矛盾に気づいてしまう。そこでこの話はいったん終わっていたんですけど、それだけではちょっと私の小説としては寂しい。もうひとひねりと思って、最後、思いっきりブラックにしました。
――五編目の「貢献の病」では、以前はベストセラーを頻発していたけれど、今はどの出版社からも〝オワコン〟と囁かれる小説家が登場してきます。彼もまた強烈な個性の持ち主で、語り手の秘書や編集者を困惑させていますね。
この一編は、『無痛』の続編を書き、編集の方からダメ出しをもらった直後に書いたものなんです。ボツになる小説を書いてしまった自分に対する忸怩たる思い、不甲斐なさみたいなものでいっぱいになっていたとき、ちょうど短編の依頼があり、その不甲斐なさを乗り越えるために書いたものなんです。
――元文部科学省のキャリア官僚でもある六十八歳の今城先生は、「社会貢献」という言葉を錦の御旗のようにかざします。そのワードは日々の暮らしのなかでも常に耳に入ってくるものなのですが……。
私、嫌いなんですよ、「社会貢献」って言葉。それを言い続ける人、「貢献の病」ですよ。そういうのもおちょくって書いているわけです。この不寛容な時代、きれいごとはいくらでも言えるけど、批判されそうな要素があるものに対してはみんな口を噤む。だからいいことばかり言ってしまう。この一編にはそんな世の中に対する強烈な風刺も込めました。
――突如として髪が増え始め、若返った元教員・泉宗一の数奇な体験を描いた「リアル若返りの泉」も風刺の利いた一編ですね。
とにかく今、いつまでも元気で若々しくとか、そういうキャッチフレーズがもてはやされているじゃないですか。老化予防とか元気な老後とか。そういうものに対するアンチテーゼですね。急に若返ったおじいさんが出てきたら、その理由を知りたがって、世間の人は群がるでしょう? バナナを食べるといい、という情報が流れた途端、スーパーからバナナが消えたこともありましたよね。この一編では、そういう世の中の愚かさに、若返りの真相をもって、小説ならではの冷や水を浴びせようと思ったんです(笑)。若返りとか、若さを保つための情報を鵜呑みにして、体を壊した人とか、病気になった人っていっぱいいるんですよ。そういうことの警鐘も込めてね。
――この一冊、とても楽しんで執筆されていらしたのではと読みながら感じていました。短編作ご執筆のおもしろさはどういうところにありますか?
短編は切れ味がいいですよね。アイデアを作るときはすごく苦しかったけど、プロットが見えたらあとは楽しかった。それぞれちょっとだけ警鐘を鳴らしたり、風刺を込めたりというのはあるんですけど、まずは、それ、置いといて、という気持ちが、この一冊に対しては大きいですね。さっと読んで楽しんで、ちょっとハラハラしていただきたいなと。この一冊に限りませんが、私の作品にはそれぞれ自分が一番思いを込めたところがあるんです。読者の方にはそれを汲み取ってほしいんですよね。それを汲み取っていただけたら、この短編集は絶対におもしろい。「読んでよかった!」と必ず言っていただけると思います。
絵馬と脅迫状の記事をもっと読む
絵馬と脅迫状
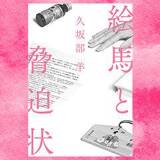
医者、患者、病気、医学部、医学研究、医療。生まれてから死ぬまで、人は病院と医者から離れられない。「医」と「病」をめぐる6篇の傑作短編小説集。
- バックナンバー