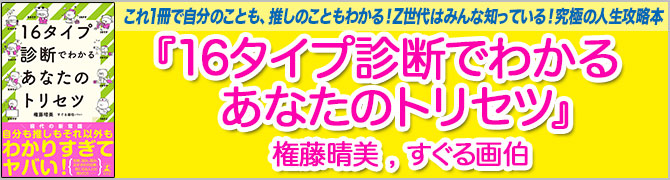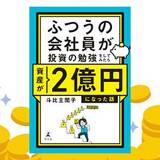
馴染みのスナックに入ると、先客であふれていた。
見慣れない顔ぶればかりだったが、今いる客のほとんどがママの同級生やその家族らしい。結婚や仕事の都合でこの土地を離れてしまった人たちが、久しぶりに集まってくれたのだそう。
「皆様がこれを……」
ママはカウンターに置かれたケーキに目をやる。
今日はママの誕生日なのだ。
実は、僕もそのお祝いを言おうと参じたクチ。
「ああ、おめでとうございます」
まだまだシラフな僕は、まだいくらか遠慮がちな面持ちでママにお祝いの言葉を言い、ついでカウンターの先客に会釈をした。
カウンターには70代の男性が一人と、50代の女性が二人が座っていた。奥の座敷にはその子どもたちであろう人たちが、久しぶりの再会を喜び、仲良さそうに飲んでいる。
沈黙を続けつつも少し酔いが進んだ僕は、話の輪に入ろうと試む気持ちに至り、横に座っていた男性に思い切って声をかけることにした。
「あの、失礼ですがご出身はどちらですか?」
「えっ」という顔をしながらこっちを向く。
「七尾。だけど……分かる?」
「もちろんです。まだ行ってない場所なので、近いうちに行きたいと思っています。でも、震災と大雨のことが落ち着いてからにしようと……」
僕は間髪をいれずに答えると、男性の顔がパッと明るくなった。
「そうなんだよ!親戚が大変だったんだよ!」
男性は、流れるように自身の出自を話し始めた。
集団就職が当たり前だった時代、故郷である石川県の七尾を出て上野駅に降り立ち、そこから川崎市の新丸子の寮に入ったのだそうな。
僕は、最近観た、知り合いが制作に関わったアニメ映画の舞台が石川県だった話をした。松本清張の小説『ゼロの焦点』に出てきた羽咋市の話や、自分が石川県で食べた寿司の話などを繰り出し、果ては新丸子駅前にある大衆食堂の話にまで広げた。
男性は目を丸くして「いったい、なぜそこまでいろいろな土地の事を…?」と言った。
そう。これは、僕なりの処世術なのだ。
誰しも、自分の地元の話を知っている人のことを悪く思うはずがないのである。どんなに関係のない人であろうと、地元の話をすれば一瞬でその人の懐に入ることができる。
それに気づいたのは、20代も半ばを過ぎたころ。
「47都道府県すべてに行っておこう」
そう目標を決めたのは自然の流れだったし、結論から先にいうと、20代が終わるギリギリでそれを達成することができた。47県目は、沖縄県だった。
1. 広島県
ピアノを仕事にするなんて生まれてから考えたこともなかった僕が、ある日、思いついた勢いで当時働いていたリゾートホテルの事務を辞め、今はいつも目の前に鍵盤楽器がある生活をしている。あの時、何かからの啓示を受けたかのごとく、猛烈に「すぐに辞めなきゃ」と思ったのだ。
そういえば、とんねるずの石橋貴明さんも、もともと芸人になる前はホテルマンだったそうな。タモリさんがボウリング場の支配人をやっていた話は有名だし、福山雅治さんは電機メーカーの営業職だったらしい。とかく芸能界において来歴に意外なエピソードが伴う人は少なくない。
歌手の村下孝蔵もその一人だろう。「初恋」や「踊り子」など今でもカラオケで人気のナンバーを生み出した彼もまた、意外な来歴を持っている。歌手になる前は、ピアノの調律師だったのだ。
熊本の生まれだが、父親が事業で失敗し、紆余曲折を経て広島県に居を移すことになる。やがて広島の学校を卒業し、ヤマハの広島店に就職し、ピアノの調律師になったのだそうだ。
僕が村下孝蔵を知ったとき彼はすでに亡くなられて久しかったが、学生の頃から彼の作品を少しずつ聴くようになっており、好んで聞いていた。
僕がホテルを辞めて音楽活動を始めた頃、とある結婚式で演奏する仕事をいただいたことがあった。人には言えぬ、漠然とした未来への不安を抱えていた時期である。結婚式の会場は、遠く離れた地、広島だった。
広島には、かつては軍港であった宇品港という古い港がある。そのすぐ横に宇品島という小島がほぼ隣接していて、島と港とは橋で結ばれている。ほぼ地続きと言ってよい。招待されたホテルは、その宇品島にあったのだ。
場所を聞き、僕は即座に村下孝蔵を思い出した。
胸が高まった。ついにあの歌の場所に行けるんだ、と。
彼もまた、きっとこの港のどこかに座り、海を隔てた遠くの場所に思いを馳せつつあの歌の歌詞を書いたのだろう。
眼の前から消えてしまった誰かのことを思い、見えなくなっていく船の姿を見つめ続けていたのかもしれない。
♪松山行きフェリー / 村下孝蔵
ついにその地を訪れた僕は、仕事を終えるとすぐに宇品港に行き、彼も見たはずの景色を眺め、感慨にふけった。
港に沈む夕陽が とても悲しく見えるのは
すべてを乗せた船が 遠く消えるから

曲のタイトルにもなっている「松山行きフェリー」とは、広島の宇品港と愛媛の松山観光港とを結ぶ客船だが、直行ではない。宇品を出発した後、40分程度でお隣の呉(くれ)港に立ち寄り、そこから松山観光港に向かう。合計すると3時間弱の船旅だ。
僕が、歌詞通りの「宇品港→松山観光港」の路線に乗れたのはつい最近のこと。逆路線である「松山観光港→宇品港」のほうが経験的には先であった。
先日、松山に用事(くしくもこれも結婚式だったのだが)があった際、ギリギリまで予定が組めず松山行きの飛行機を予約しないままでいたところ、その日の便がすべて満席になってしまうという状況に陥ったことがある。
仕方ないので羽田から広島空港へと飛び、バスで呉に行き、呉港から松山行きのフェリーに搭乗して事なきを得た。
なんともコスパの悪い移動方法であるし、急いでいたこともあり旅情を感じるまでもいかなかったが、背に腹は変えられなかった。
松山の用事も終わり、そのまま東京に帰ってもよかったのだが、古くからの友人も多い神戸へと向かうことにし、当然同じフェリーの逆路線に搭乗した。数日前、松山行きの船に乗るためバタバタと通り過ぎただけだった呉の街はまだ詳しく知らない。いい機会だから今度はゆっくり散策しよう、と。
近年、戦時中の生活を描いた「この世界の片隅に」という映画作品で、呉の街は再び脚光を浴びることになった。呉港もまた過去には軍港であった歴史をもつ港であり、その名残を思わせるように、港には大きな戦艦が展示されていてミュージアムとなっている。
呉港から長い歩道橋を渡り切ると、JR呉港にたどり着くことができ、それより先は街が碁盤の目のように区画整理されているのだが、これは1886年に呉に鎮守府が置かれる際に計画されたものらしい。戦争で焼け野原になり復興計画が起こった際も、碁盤の目状の区画整理は以前のまま踏襲したそうな。
駅からすこし歩いたところに中通り商店街という古くからの商店街があるのだが、地元の人からは「れんがどおり」と呼ばれ地域に密着している様子が見て取れる。学校の制服を扱う店を覗くと、呉らしく、水兵さん仕立ての制服を見ることもできる。
さて、この商店街から一歩抜け、本通りとよばれるバス通りを横切ると、年季の入った黄色いひさしが目立つ1軒が見えてくる。
「広島焼き はやと」
関東のお好み焼きとは違い、生地を薄く伸ばしてクレープ状にした上に具材を層状に"重ね焼き"をするのが広島焼き。似て非なるものなのだ。
しかし呉の人たちは、さらなる広島焼きとの違いを明確にしようと、一部の店舗では”呉焼き”と称して区別をしている。
広島風のお好み焼きが正円の形をしているのに対し、呉焼きはそれを折りたたみ、半月型にするというのがアイデンティティだという。
呉市で撮影が行われたドラマ「海猿」の撮影で訪れた役者陣も、好んでこの店に来ていたらしい。店内のポスターにおびただしい数のサインが記されていることで伺い知れる。
たまたま僕が入ったとき自分以外に客はいなかったのだが、自分からの注文を受け黙々と焼いているご主人に「やっぱり肉を入れたほうがいいですかね」と尋ねると「旅行で来られてるなら、そのほうがよろしい。さらにいえば、イカフライも入れたほうがいいだろう」と言った。このイカフライというお菓子は、呉の名物なのだそうだ。
ではその両方を入れてくださいと頼むと「それがええ。それこそ呉焼きじゃけの」とつぶやき、田舎臭く笑った。その後はご主人が、呉焼きに関しての逸話をとうとうと、まるで七味売りの口上のごとく語ってくれたのであった。
なんでも、戦後、この地方に残されていたのは、炎熱をもってしても焼けきらなかった鉄板くらいだったそう。誰かがそれを拾ってきて火にかけ、貴重な粉を水に溶いて薄く焼き、ありあわせの具材を重ねて料理を作ったことが現在のお好み焼きのルーツである、と。
「ここら辺でお好み焼きが有名になったのは、そういうことがあったからじゃけ」
一見怖そうだが人懐こそうなご主人は帰り際に、美味い焼きそば屋を紹介してくれた。残念ながら胃の容量に乏しかった僕には向かうことはできなかったが、また呉を訪れた際は候補に入れたいと思っている。
広島と、呉。
いずれも、戦争の甚大な被害を受けた場所だ。
白黒の映像で見た惨憺たる姿だった街々が、年月を経て、色彩豊かに変わった現在の姿として眼の前に広がっている。
そうだ。そんな白黒だった町に、やがて村下孝蔵という自身の未来を案じた若者がやってきて、広島の海の美しさを歌い、僕がそれを知ることになる。
時代は違えど境遇が似た彼にまた会うために、僕はこれからも広島に行き続けることだろう。
もちろん、脳内であの曲を流しながら。
音楽人の旅メシ日記の記事をもっと読む
音楽人の旅メシ日記

その街では、どんな食事が愛されて、どんな音楽が生まれたのか。
土地の味わいと、そこに息づく全てのものには、どこか似通ったメロディが流れている。
旅と食事を愛するミュージシャン事務員Gが、楽譜をなぞるように紐解きます。
- バックナンバー