
「ミモザもどき」 オキ・シロー
渋谷道玄坂の奥にあるバー・ボロンゴは、開店準備に追われていた。
マスターの大介はカウンターを、見習いバーテンダーの二郎は、フロアのテーブル席を整えている。もう一人の若いバーテンダー敏也は、買物に外へ出ていた。
このボロンゴは、入口のドアを入った右手の、通りに面した部分が大きなガラス窓になっている。その窓から、小さな女の子が中の様子をうかがっているのに、最初に気がついたのはニ郎だった。
「あ、あの子、ミサちゃんじゃあ……」
「ミサちゃん?」
大介は、二郎の声に顔を上げた。
腰板から、やっとオカッパ頭だけを覗かせた女の子が、小さな顔をガラス窓にへばりつかせている。
「ほんとだ、ミサちゃんだ」
大介はなんともいえない不安感を覚えながら、大急ぎでカウンターを飛び出した。
ミサちゃんこと美沙子は、大介の古い友人、山本の一人娘だった。平均よりはかなり小柄らしいが、小学校の二年生のはずだ。
大介が出てくるのがわかったのだろう。ミサちゃんは窓から離れ、大人たちの行きかう夕方の通りに、緊張しきった顔で立っていた。その周囲のどこにも、父親の姿はなかった。
「ミサちゃん、どうしたの」
大介は、精いっぱい穏やかな調子で声をかけながら、彼女に近づいた。
「コンニチハ」
ミサちゃんは固い声でそういうと、口を真一文字に結び、上目使いに大介を見た。赤いジャンパーにジーンズのスカート。肩からは斜めに、赤いビニールのバッグをしっかりとかけている。
「また大きくなったねぇ」
大介は中腰にかがみ、オカッパ頭に手をそっと置いてからきいた。
「パパと一緒?」
大介の大きな手の下で、小さなオカッパ頭が左右に揺れた。
「ここで待ち合わせ?」
ミサちゃんはまた激しく頭を振る。
「じゃ、大介おじちゃんに会いに来てくれたの?」
オカッパ頭は一瞬動きを止め、それからコクリとうなずいた。
「なんだ、そうか、それは嬉しいなあ。寒いから、とにかく中に入ろう」
大介は質問攻めにしたいのをぐっとこらえて、とりあえず心細げな薄い肩を店の中へ促した。
「あ、ミサちゃんいらっしゃい。久しぶりだねぇ」
二郎の声に、ミサちゃんはうつむけていた顔を上げ、ペコリとおじぎをした。
.大介は、ひとまず手近かのテーブルに彼女を落着かせた。
「おなか、すいてない?」
「さっき、ハンバーガー食べたから」
ミサちゃんの声は相変わらず固い。
「じゃ、ミルクでもあっためるから、ちょっとここで待ってて」
大介はそういって立ち上がりながら、さもついでといった感じで、一番気になっていることをきいた。
「ここに来てること、パパ知ってる?」
ミサちゃんはテーブルに目を落としたまま、首を左右に振った。
「よし、じゃ、電話だけしとこうな」
今度はミサちゃんは、首を横にも縦にも振らない。その深くうつむけたままの首が、いかにもか細い。
山本とうまく連絡がとれればいいが……。中途半端な時間であることを気にしながら、大介はカウンターに入った。そして、ミルクを二郎に頼み、自分は電話帳を片手に、受話器を取り上げた。
友人の山本は、大手電機メーカーに勤める技術者だった。二度の離婚経験があり、今は最初の妻との間にできた美沙子と二人で、目黒のマンションに暮らしている。
案の定、山本はつかまらなかった。虎ノ門にある会社は出ており、自宅にはまだ帰り着いていないようだった。自宅の電話は、美沙子が解除したまま出てきてしまったのか、いつもの留守番電話にセットされていなかった。
大介は、山本宅の電話番号をメモして二郎に渡し、十分おきぐらいに電話をかけてくれるように頼んだ。
「パパ、まだ帰ってなかった」
熱いミルクを入れた耐熱カップを持って、大介はテーブルに戻った。
「留守番電話、セットしてこなかった?」
山本が帰宅して解除し、そのまま娘を探しまわっていることも考えられる。しかしミサちゃんは、シテコナカッタ、と抑揚のない声で応え、大介の考えを否定した。
「ミルク、飲めば? まだ熱いかな」
大介のすすめに、ミサちゃんはかすかにうなずき、湯気の立つカップの把っ手を持ち上げた。そして口を尖らせ、真剣な眼差しでフー、フーと息を吹きかけてから、少しずつミルクをすすりはじめた。
こんな風に殻に閉じこもった感じのミサちゃんを見るのは、これが初めてだった。何があったにせよ、こんなところへ来なければならなかった幼い身が、大介にはなんとも哀れに思えた。
最近こそ、たまにしか会わないが、大介にとって彼女ほど、深く関った幼児はいない。山本が最初の妻と別れた時、美沙子はまだ二歳になっていなかった。離婚の原因は、妻に男ができたことだった。山本は激怒し、美沙子を引き取って別れた。女は、もともとあまり子供好きではなかったらしい。意外なほどあっさりと、母親の権利を放棄して家を出て行ったようだ。
その後しばらく、美沙子は仙台の山本の実家に預けられた。その間に山本は、マンションを引っ越し、保育園の手続きをし、保育園の前後の時間の面倒を見てくれる家庭を探して、二人暮らしの準備を進めた。
しかし、その期間が山本の最もやりきれない時期だったらしい。毎夜のようにボロンゴに現れて、時には泥酔し、大介の部屋に泊まっていったことも一度や二度ではなかった。そして三カ月後、とても無理だという周囲の反対の声を押し切って、幼い娘を手元に引き取った。
山本の奮闘がはじまった。大介がよく手を貸したのも、その時からだった。幼児はしょっちゅう風邪をひくし、思いがけない熱を出す。父親もそうそう会社を休んではいられない。そんな時は、いつも大介が駆けつけ、不馴れな手で面倒を見た。
美沙子は愛らしい盛りであり、世話をするのはまったく苦にならなかった。それどころか、毎日でも会いたいくらいで、保育園の運動会も、学芸会のような催しも、何度か大介は見に行った。あの頃ほど、自分が夜の商売だったことを好都合に思えたことはなかった。
山本は、外で酒を飲むひまなどまったくなくなったが、時々、週末にボロンゴだけには娘を連れて顔を出した。幸い人見知りをしないミサちゃんは、みんなから可愛がられ、露骨に不快感を見せるような客はいなかった。ほとんどは途中で眠ってしまい、父親に抱かれて帰るそのあどけない寝顔は、どこか切ないほど可憐だった。
父と幼い娘のそんな生活が、二年半ほど続いた。そして大介は、美沙子のお陰で、子供の愛らしさを初めて知ったのである。
買物に出ていた見習いの敏也が、紙袋をかかえて戻ってきた。
「あれ? ミサちゃん一人?」
「ああ。今夜の口あけのお客さんさ」
大介がそういった時、黙々とミルクを飲み終えたミサちゃんが顔を上げた。
「クチアケって、なあに?」
「一番最初の、って意味だよ。しかし、ミサちゃんの、なあに? って昔の口ぐせ、久しぶりに聞いたなあ」
この時だけ、ミサちゃんはちょっと笑顔を見せた。しかし、あとは何を話しかけても口が重く、胸のつかえを吐き出そうとはしない。二郎と敏也は、二、三分おきに山本の自宅へ電話を入れてくれているようだった。
「おじちゃんに何か話したいことがあるんだろ? どっかよそへ移ろうか」
ずばりとそうきいても、彼女はかたくなに首を横に振るばかりだった。
「よし、じゃあミサちゃんのおなかがすくのを少し待って、何かうまいものでも食べに行こうよ」
途方にくれながらも、大介はなんとか美沙子を元気づけたかった。そして、ふと思いついたことを口に出した。
「そうだ、ミサちゃんの好きなミモザでもつくろうか。それを飲んで:……」
そこまで大介がいった時、美沙子の小さな顔がふいにゆがんだ。と思う間もなく、みるみる目に涙をあふれさせた。そして「あ、ごめん」という大介の言葉をきっかけに、せきを切ったように大粒の涙をこぼし、細い肩を震わせて激しく泣きじゃくりはじめた。
そうか、ミモザか、ミモザが原因なのか……。大介は胸を衝かれた。
「ごめん、ごめんな、おじちゃん変なこといって。だけどミサちゃん、ママに会いたいのか」
「そうじゃないけど……そうじゃないけど……:会いたいわけじゃないんだけど……」
美沙子はしゃくり上げながら、とぎれとぎれにそういった。
ママというのは、山本の二番目の妻、夏江のことである。ミサちゃんに新しい母親ができたのは、彼女が四歳を半ば過ぎた頃だった。結婚に積極的だったのは、若い夏江の方だったらしい。山本は、淋しさからつい関係を持ったようだが、惚れているとはいい難かった。ただ、美沙子が非常になついたことで、再婚を決心したようだ。
その報告がてら、三人で早い時間にこのボロンゴに寄ってくれた時のこと。大介が祝いにシャンパンを抜いた。そして二、三杯飲んだところで、夏江が遠慮がちにいった。
「わたしに一杯、ミモザをつくっていただけます?」
ミモザは、オレンジ・ジュースをシャンパンで割るだけの簡単なカクテルである。正式にはオレンジのシャンパン割り、シャンパン・ア・ロランジュと呼ぶらしい。しかし、その酒の色が、黄白色のミモザの花に似ていることから、いつしかこのミモザの愛称がついたという。かつてはフランスの上流社会の女たちに愛飲されたというカクテルで、味も色も女性好みの華やかな酒である。
その時、大介はミモザを二つ、つくった。一つは夏江用のオレンジのシャンパン割り。もう一つは美沙子のための、オレンジをシャンパンのかわりにソーダで割ったミモザもどき。
「ミサちゃんもママと一緒のミモザだよ。ほら、泡だって同じだろ?」
このミモザもどきが、ミサちゃんは大いに気に入ったらしい。ママと一緒だといわれて、ひどく嬉しそうだった。やはり女手が恋しかったのか、大介も目を見張るほど、彼女は夏江に寄りそっていた。
再婚してからは、年齢の関係もあって、美沙子がボロンゴの営業時間に来ることはなくなった。しかし、山本は大介によほど恩義でも感じているのか、何かの折には自宅へ招待の声をかけてくれる。また、渋谷のデパートに買物に来たからと、三人で、時には、夏江と美沙子の二人で、開店前のボロンゴに顔を見せてくれた。
そういう時には決まって、ミサちゃんはカウンターにちょこんと座り、得意げにいうのだった。
「わたし、ミモザね」
しかし、この結婚生活は昨年、ミサちゃんが一年生の二学期を迎えたところで破綻した。原因は、今度は山本の度重なる浮気だった。どういう愁嘆場があったかは知らないが、大介は何より美沙子のことが気がかりだった。しかし、その後、彼女はいじらしいほど健気にふるまい、決してママという言葉を口にしなくなったという。
そのミサちゃんが今、ママが好きだったミモザという言葉を聞いただけで、泣きじゃくっている。
「どうしたいのか、話してごらん。気持がうんと楽になるよ」
大介は、小さな背中をさすり続けた。
「パパが……パパが……」
ようやくミサちゃんが口を開いた。
「うん、パパが?」
「パパが、結婚するって」
「結婚!?」
また? という言葉を大介はのみこんだ。
「ふーん、それはおじちゃん、知らなかったなあ。で、ミサちゃんはその女の人、嫌いなの?」
「そうじゃないの。嫌いじゃないけど、わたし……、わたし、新しいママ、いらないの、ママはいらないの」
そういって、ミサちゃんはまたどっと涙をあふれさせた。
「わかった、ミサちゃんの気持、よーくわかったから、もう泣かないで大丈夫だよ。おじちゃんがパパにうまく話すから」
不憫さといじらしさで、大介は柄にもなく目頭が熱くなるのを覚えた。
客が二組、たて続けに店に入ってきた。
「顔でも洗わないと、せっかくの美少女が台無しだぞ」
大介はオカッパ頭を立ち上がらせ、奥の調理場へ連れて行った。そして顔を洗わせ、客は二郎と敏也にまかせて、そのまま調理場でミサちゃんの相手をした。
山本が電話でつかまったのは、それから三十分ほどしてからだった。
大介は、外で何か好きなものを食べさせてやってくれと、店から美沙子を二郎に連れ出させた。
「いやあ、すまんすまん」
二十分もしない内に、山本があたふたとボロンゴヘ飛び込んできた。
「まったく、すまんすまんじゃないよ」
珍しく大介はずけずけいいながら、ビールとグラスを手に、フロアの一番奥のテーブルヘ山本を促した。
「いや、帰ったらいないだろ? いつものメモが置いてないんで、おかしいなと思ってるところへ電話をもらったんだよ」
「二郎たちが、たて続けに電話をかけてくれてたんだよ」
大介は二つのグラスにビールを注いだ。
「ほんとに迷惑をかけちゃったな。しかし、まさかここへ来てるとはね」
「家出されたようなもんなんだぜ」
大介は、ちょっと脅しておいてから、詳しくいきさつを説明した。
「そうかあ。いや、参ったね。参った」
山本は深い溜息をつき、しばらく黙りこんでいた。
「結婚の話は本決まりじゃないんだ。ただ、世話をしてくれた人がいて、ミサにも何度か引き合わせたんだけどね」
相手は再婚で、子供はいないという。
「ミサは一度も嫌な顔を見せなかったし、パパがいいんなら結婚してもいいっていうもんだから」
「だから、それは大人たちに気を遣ってるんだよ。いつだったか、大人は子供が思うほど大人じゃないし、子供は大人が思うほど子供じゃないって言葉、あれは本当だなあって、ミサちゃんのこと感心してたじゃないか」
「うん。いや、夏江と離婚した直後に、ミサは俺に黙って、長くしてた髪をばっさり切ってきたんだよ。自分だけでは、まだ上手に髪が結えないからっていうんだ……」
山本は苦そうにビールをすすった。
「里親なんて、つくづく情けないって、あの時、ひどくこたえてさ」
だから、再々婚を考えていたのは、ひたすら美沙子のためを思ってだという。「今でもミサちゃん、夏江さんが恋しいんだよ。ずっと我慢してきてるんだよ」「そうなんだろうな、きっと」
「一度、会わせてやったらどうなんだ。もう夏江さんの気持だってほぐれてるかもしれないし」
「そうだなあ。うーん、ミモザか……」
山本は時々捻り、首をめぐらしながら、何やら考えこんでいた。
ミサちゃんが二郎と一緒に帰ってきた。
「パパ、よくわかってくれたからな」
大介がそういうと、ミサちゃんは腫れぼったい目で父親を見て、ニッと笑った。「さ、迷惑だからすぐ帰るぞ。今度また早い時間にきて、その時は大介おじちゃんにうまいミモザをつくってもらおう」
父親の言葉に、オカッパ頭が大きくうなずいた。そして、ミモザもどきが大好きな、その口あけの小さな客は、弾むような足どりで帰って行った。
カクテル誕生秘話の記事をもっと読む
カクテル誕生秘話
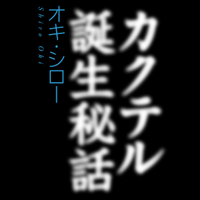
※本連載は旧Webサイト(Webマガジン幻冬舎)からの移行コンテンツです。幻冬舎plusでは2000/11/01から2001/01/15までの掲載となっております。
















