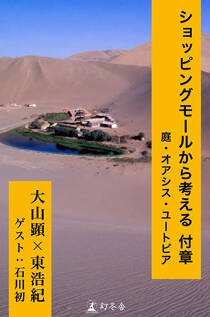戦争する国になってしまった日本――。この危機に、かつてお互い罵り合っていた小林よしのり氏と宮台真司氏、そこに東浩紀氏が加わり、語り怒り合った『戦争する国の道徳』が話題です。暴走する権力を抑制する力を私たちは、いかに持つべきなのでしょうか。
東 今日はテロの話から始まりましたが、最後に変わった補助線を引かせてください。
最近アニメの『宇宙戦艦ヤマト』と『さらば宇宙戦艦ヤマト』を見直す機会がありました。あらためて思ったんですが、最初の『宇宙戦艦ヤマト』はものすごくよくできているんですね。波動砲はあきらかに原爆のメタファーになっているし、ガミラスとイスカンダルが二重星という設定もアメリカの両義性をうまく捉えている。敗戦のトラウマを抱えた日本人が、「戦艦大和」という日本の象徴を使いながら、どうやってそのトラウマを乗り越えるか。サブカルチャーの偉大な達成だったと思います。
それに比べると、『さらば宇宙戦艦ヤマト』はすごくヤバイ映画なんです。敵に必然性がない。オリジナルの『ヤマト』のガミラスは、故郷の惑星が滅びつつあるので地球を侵略するんですね。ちゃんと必然性がある。ところが彗星帝国にはなにもない。とにかくすべてを呑み込んでいくという設定で、超巨大な資本主義のようなものです。地球側も、あまりに向こうが巨大なので、結局は特攻で対抗するほかない。その結果、物語内では愛とか正義とかがやたらと強調されていて、古代進は「(森)雪、これが二人の結婚式だよ」とか言いながら突っ込んでいく。
最後に古代と艦長の沖田十三が会話するんですが、それもまたたいへんな会話なわけです。「僕はいまどうしたらいいんでしょう」「お前にはまだ戦う武器がある」「何があるんですか」「命だよ」と特攻が示唆される。そして最後は「わかるな」「はい」とかになっていく。物語内では沖田十三はすでに死んでるから、じつはこれは古代の妄想にすぎません。主人公が最後、妄想のなかで沖田と会話して「死んで何になる。多くのやつらは言うだろう。だが、そこでも戦うのが男というものだ。わかるな、古代」とかいう声を聞いて特攻に踏み込んでいく。この会話にしても、普通なら、「だが」のあとに「でもそれをやれば未来が築けるんだ」とかいう台詞が来ると思うんです。でもそんなものはない。「わかるな」なんです。理屈じゃないんですね。
じつに薄っぺらい話なんだけど、にもかかわらず、僕は見ながら、こちらのほうが現代のテロを象徴しているように感じて戦慄しました。テロが有効かどうか、彗星帝国が倒せるかどうかはもはや問題ではない。単に「わかるな」ということなんですね。でもそれは現代の世界においてはたいへんなリアリティがある。ISISにしてもボコ・ハラムにしても、突っ込んでいったからといって何が変わるというわけじゃない。チュニジアで観光客を無差別に殺した彼らだって、観光客を殺せばグローバル資本主義の力が衰えると思っていたわけじゃないでしょう。けれども「わかるな」ってことだと思うんです。ものすごく観念的なテロ。現実的な成果もなにも期待してない、このシステムに対して抗わなければ自分の誇りが失われてしまう、ということだけのテロ。サブカルチャー評論の言葉を使えば、いわば「セカイ系」のテロですね。そういうものが現れている現状について、どう考えるか。
宮台 「実存と社会との混同」ないし「あえてする混同」という古くて新しい問題だ。いま風に言えば「セカイと世界との混同」だね。その問題を最初に議論したのがアイザイア・バーリンだった。バーリンと言えば「何々からの自由」という消極的自由と、「何々への自由」という積極的自由を区別したこと、そして積極的自由を否定したことで知られている。
なぜ否定したかがポイント。ギリシャ全盛期はペリクレスの時代つまり紀元前5世紀前半。ストア派の時代はそれから200年経った紀元前3世紀前半。都市国家はすべてマケドニアの弱小都市に落ちぶれ、復興の可能性はなかった。そこでエピクロス派は「精神の平穏」を旗印に「これからはポリテース(市民)ではなくコスモポリテース(世界市民)だ」と賞揚した。
何もかも不可能だと自覚した上、より一層不可能なことを想像する営み。彼はこれが後のナチスにつながるロマン主義の鼻祖と見た。間違ってない。ストア派は確かに不可能な何かに殉じる「美学」だ。だからフーコーも賞揚した。でもバーリンは、こうした「美学的」な営みに、魯迅『阿Q正伝』の精神的勝利法の如き危険が孕まれると危惧したわけだ。
「美的」と「美学的」は違う。「美的」とはいかにも美しいこと。「美学的」とは、見掛けが「美的」でなくても──後ろ指をさされるものでも──いわば抽象的次元でこれが美しいと信じられた状態のこと。そういうものだから、「美学的」振る舞いは「何でもあり」で、いろんなものが入り込む可能性を抑止できない。だからバーリンは危険だと見た。
彼の「積極的自由の否定」をパラフレーズすれは「美学の否定」だ。「美学」は、損得勘定を超えて内から湧く力である「内発性=ヴィルトゥス」の重要なエンジン。だから「美学」の否定は「内発性」の否定に近いという意味で「右翼的なものの否定」だ。「美学」は確かに危険だ。東くんが言ったようにチュニジア無差別テロは損得勘定を超えた「美学」だ。
右翼テロも基本的に「美学」だ。一水会の鈴木邦男元代表も書いていた。右翼とは損得勘定を超えた心意気に感染する構えだ。だから、よど号ハイジャックに感染した三島由紀夫が市ヶ谷駐屯地での自決事件を起こし、それに感染した「東アジア反日武装戦線“狼”」が三菱重工ビル爆破事件を起こし、その事件に感染した野村秋介が経団連襲撃事件を起こしたんだ。
意気に感じること。「美学」に感染すること。これは「感情の劣化」を被った連中の暴発じゃない。まさによしりんが言うとおり。自分のためじゃない。自分はどうなったっていい。貧しき者を救うために黙っていられない。だからやむにやまれずにやる。これが「美的」ならぬ「美学的」な振る舞いだ。よしりんはこれを擁護すると宣言しているわけだ。
これは見方によっては「セカイ系テロ」だろう。確かに見方によっては実存が過剰に持ち込まれている。でも、テロ肯定という言い方を我慢しても、僕は「美学」に殉じて生きたいし、よしりんと同じように東くんも十分に「美学的」人間であるのを僕は知っている。「美学的」な人間は「感情の劣化」を被った輩と違って、浅ましくない。だから好きだ。
意気に感じる。「美学」に感染する。「セカイ系テロ」に突き進む。呼び方に関係なくこれらは危険だ。だからといって僕はこうした営みを否定したくない。「自分はどうなってもいい。理不尽さに黙っていられない。でも叫んでも誰も耳を傾けない」といった構えがリアルになるような理不尽な社会状況を、最小化するほうを選択するべきじゃないのか。
小林 そもそも「対テロ戦争」とか「テロは悪」という言葉が、すでに矛盾だらけなわけですよ。テロの言葉の概念は、もとをただせばロベスピエールがフランス革命のあとにやった恐怖政治から出発している。それは権力を握った側が大衆を抑圧するというかたちで行ったテロなわけで、いまのテロは権力に完全に抑圧されてしまった少数者がやるものだけを想定して言ってるけれども、テロとはそもそも、そういう意味合いのものではない。
あと、日本の保守派は中国が大嫌いだけれど、じゃあ中国がチベットでやってることはどうなのか?
宮台 ウィグルとかね。
小林 ウィグルの人たちは、ようするにテロで中国と戦ってるわけだ。わしはどうしてもウィグル人のテロを支持したくなるわけですよ。チベット僧も、人を傷つけないで自分が焼身自殺するというやり方で、テロリズムをやってるとも考えられる。テロというのは恐怖と宣伝だから、宣伝の効果がつきまとわないといけないわけ。そう考えるとチベット僧だってテロの一形態をやっているわけだ。
それをやってくれないと、中国がどれだけの圧政を敷いてるのかがわしらにはわからない。保守派の言ってることは、だからじつに矛盾しているんだよ。ウィグル人を支持しないのか、チベット人を支持しないのか、ということになってくる。どういう状態ならテロを肯定できるのかということまで考えないと、思考停止のアホでしょう。
わしが『大東亜論』で来島恒喜のテロを描いたのは、テロに効果があったからですよ。確実に効果をもたらして、日本にマイナスにしかならない条約改正をストップさせてしまった。それともう一つは、大隈重信も大した人間なわけですよ。明治維新があった後だけれど、江戸時代の頃の武士の末裔だから、やっぱり器が大きい。
宮台 自分を襲った来島を、立派な青年だと言って許したんだよね。
小林 そう。大隈重信は自分の片足が爆破されてなくなってるのに、そういう若者がこの日本には必要だと言った。それが言える人間がいたわけです。いまの日本は、それと比べると完全に矮小化しているわけですよ。テロをやろうとする側も、テロを受ける側の政治家も矮小化してしまってるから、とにかくもうテロはすべて絶滅だ、政治家もテロが怖いです、という話になってしまってるわけだな。
テロをやるのは相当のリスクがつきまとうから、そう簡単にできない状態になってしまっている。万一わしがテロをやったときに、この日本に何が起こるのか。ものすごくわしの本が売れるかもしれないとか、それによって全部が変わっちゃうかもしれないとか。そういう計算をして、このタイミングでやればわしの考え方に全員が同調する、というところまで持ってこないとやれない。
単にやったって、何を言われるかわかったもんじゃない。自分の才能の限界を感じてやったとか、ガンでもうすぐ死ぬところだったんじゃないかなどと言われかねない。それを避けるためには、タイミングと、それによって何が変わるのかを徹底的に考えるしかない。だからテロは、そんなに安易に起こせないんですよ。実際は明治時代よりテロに対しては厳しくなってる。
宮台 戦前にテロを起こした右翼は、テロがなければ、財閥や君側の奸どもの、やり放題だと思った。そこで、テロを起こせば自分の命が失われる恐怖もあったが、まともな政治をさせようと思った。実際、政治家たちも「無体な政治をやり過ぎればテロに遭う」という恐怖心を持っていた。だからテロには無体な政治を手控えさせる効果が確実にあった。
戦後、日本の右翼はテロをしなくなり、「アメリカのケツを舐める日本政府」のケツを舐める存在にまで貶められた。「アメリカのケツを舐める日本政府」のケツを舐めるマスコミと同じ。結果、政治家どもは、いくら無体な政治をしても、それによって自分が危害を加えられるという恐怖を持たなくなった。いい悪いは別にして、これはすべて事実の問題だ。
小林 テロの恐怖もないし、マスコミもずいぶん甘いから怖くない。個々の政策では「原発推進ノー」のほうが多くなったり、「海外にどこまでも自衛隊は出ていく。それでもいいですか」と世論調査で聞けば、「ノー」が多くなったりする。それなのに、「どこの政党を支持するか」といえば自民党支持となる。そういう時代に、政治家や権力者をどうしたら怖がらせることができるのか、という問題になっている。政権にとっていちばん怖い人間に自分がなれるか、あるいは国民がそれだけの怖さを発揮できるか。それをやらないと権力はやりたい放題だよ。そこの危機感が、新聞にもテレビのジャーナリズムにもない。
東 かつては、言論が最も権力を怖がらせる装置だった。しかしいまは言論がそういう機能を失っている。権力を抑止する力をわたしたちは持てなくなってる。それは日本でも世界でもそうですね。そういうなかで、結局テロしかないんじゃないの、と受け取られかねないところまで来てしまった。
この状況をどうやって立て直すか。これはとても重要な問題で、立て直せなかったときには暴力に頼る人が絶対に出てくる。だってそれしかないのだから。それを避けるためにも、知識人層や責任を持った人たちが、絶望感に囚われるのではなく、権力を抑制する力を発揮していかなければいけないということだと思います。人民が権力に舐められる国が、いい国であるはずがありませんよね。
(第5回は、「水に流してはいけない」です。)