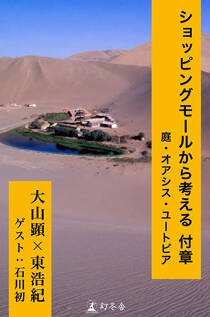長らく、「軽薄な大衆消費の象徴」とされてきた、ショッピングモール。だが、現代の先進国では、都市空間の多くが、ショッピングモールをモデルに設計されています。いまや、「ショッピングモール」を抜きにして、人間の欲望を読み取ることも、社会の見取り図も描くこともできないのです。今回は、『ショッピングモールから考える』から一部抜粋し、東京と地方の関係を考えます。
地方はバックヤード?
大山 「内と外」という観点でさらに考えてみると、いろいろと面白いことが言えそうです。東さんは、東京のバックヤードってどこにあると思われますか?
東 東京を支えている地方すべてがバックヤードかなと。福島第一原発の問題が、まさにその構造を象徴しています。近年よく言われているのは、二一世紀は国家の競争ではなく都市間競争の時代である、ということです。それぞれの国内では地方と都市の生活水準の格差が拡大する一方、世界のグローバルシティ同士では、ほとんど同じ水準で競争になる。これはつまり、グローバルシティがそれぞれの所属する国全体をバックヤードとして使って戦うということを意味している。
こういうことを言うと批判を呼びそうですが、日本全体が東京のバックヤードになって、東京が世界の都市と戦っている。
大山 ぼくは千葉育ちの千葉っ子ですが、千葉はまさにバックヤード扱いされていますよね。房総半島では、コンクリートをつくるときに必要な骨材に使う、良質な石や砂がたくさん産出されます。だから東京でビルを建てるときには、千葉から山の砂がどんどん運ばれていく。東京の建物の多くは房総出身だったりするんです。東京は千葉でできている、と言っても過言ではない。
東 羽田空港の拡張工事が行われていた頃、房総の山道で「羽田行き」と書かれたトラックが列を成していたのを覚えています。それが全部砂を積んでいた。房総の砂を削って、羽田の沖合が埋められていることがひと目でわかり、印象に残っています。
大山 このあたりのビルを崩して千葉に返すと、昔の山並みが再現できますね。——と言っても、これは冗談でもない。東京で古いビルを壊したあとは、産業廃棄物としてどこかに捨てなければならない。で、考えてみると、砂を採ったところが空いているじゃないかと。それでいまは、かつて削った山の跡が、産業廃棄物の処理場になっている。
東 それはすごすぎる。
そうだ、今日はこの問題について考えるために、『メガゾーン23』を紹介しようと思って準備をしてきたんです。これは一九八五年にリリースされたOVAで、同時代の東京を舞台にしています。ご覧になっていただければわかるように、当時の街の風景がかなり忠実に映像化されています。
しかしこの作品が変わっているのは、この東京はじつはすべて、宇宙船のなかに再現された虚構だというところです。というのも、作中の本当の舞台である数百年後の未来世界では、人類はぼろぼろになった地球を脱出して、巨大な都市型の宇宙船のなかで暮らすようになっているんですね。そして、ある宇宙船では、そのなかで暮らす人々のため、歴史的に見て人々が「もっとも幸せに暮らしていた時代」として一九八〇年代の東京が選ばれたという設定になっている。だから住人たちは、自分たちが本当に一九八〇年代の東京にいると思って暮らしている。でも本当は宇宙船のなか。再現されているのは二三区だけなので、『メガゾーン23』。
大山 面白そうですね。
東 これはいまの話と重なるところが多いと思うんです。少し物語を紹介すると、『メガゾーン23』の主人公はあるとき、東京全体が虚構であることを知り、機密保持のために命を狙われることになります。
主人公は女の子三人組と出会って仲良くなり、自主映画の制作を手伝うことになるのだけれど、その過程でフィルムに写ってはいけないものが写り込んでしまい、真実を知っているひとたちに追われるという構図です。その後、主人公は未来のテクノロジーでつくられた、ロボットに変形するバイクを手に入れる。これは明らかに二〇世紀のテクノロジーを超えていて、このあたりから話がおかしくなってくる。だんだん世界の真実が明らかになっていくわけです。
そしてさらに話が展開すると、この架空の東京が入っている宇宙船が、地球から脱出したほかの宇宙船と出会う。しかしうまくコミュニケーションが取れなくて、宇宙船同士で戦争になってしまう。二〇世紀の東京に住んでいると思わされている住人たちは、むろんそのことを知らされないのだけれど、ただ宇宙での現実の戦争を反映して、架空の東京のなかでも事件が起きてくる。具体的には、自衛隊がクーデターを起こして、外国と戦争状態になります。
しかしこの作品、以上のような設定は作中で明らかになるのだけれど、宇宙船の外部がどうなっているかはほとんど描かれないんですね。未来世界の「現実」の描写はほとんどないんです。架空の東京だけがリアルに描かれて、そのくせすべて嘘だと言われている。制作したのは『超時空要塞マクロス』と同じスタッフです。
大山 そうか。この作品では宇宙船の外側はすべてバックヤードで、バックヤードの現実がすべて隠されて東京が存在しているわけですね!
東 まさにそうです。どうしてこういう変な作品が一九八〇年代に現れたのか。クリエイターが現実になにを考えていたのかはよくわからないのだけれど、ぼくはこれは、ある意味で「後ろめたさ」の表現だったのかな、と解釈しています。なんでわれわれはこんなに豊かでハッピーなのか。そういう後ろめたさが一九八〇年代中盤の日本にはあったのではないか。
大山 なるほど。戦争や復興の歴史を十分に知らないまま、いきなり豊かさを謳歌してしまい、どこかにそれを支えるバックヤードがあるはずなのだけれど見えていない。バックヤードは見えないところにつくられるものですからね。その後ろめたい構造に気づいてしまったひとたちが、こうして物語化したのだと。
東 一九八五年前後の東京というのは、とても面白い時代です。高度経済成長を終えてすでにかなり豊かだけれど、プラザ合意の影響もあって、円高不況と叫ばれている時代でもある。直後に不動産価格が急激に上がり始めて、いわゆるバブル経済が始まる。だからこの時点ではめちゃくちゃ金持ちだったり、豊かなグローバルシティだったりするわけではない。全共闘の記憶もまだある。
最近、一九八〇年代の棹忠夫の海外講演の原稿を読みました。面白かったのは、梅棹がそこで、「日本人は世界中からものを買い付けているのに、自分たちはぜんぜん情報を発信しない、だから謎の民族だと思われている」と言っていることです。その頃の日本は、今日の対談の言葉で言えば、国全体がショッピングモールみたいなものになっていて、外から見ても無機質な外観しか伝わらない、ブラックボックスのような場所だったのだと思います。つまり、バックヤードがすべて巧妙に覆い隠され、日本全体が一種のテーマパークになっていた。それを内部から当時の若者世代が表現したのが、『メガゾーン23』というアニメだったのではないか。
「バックヤードからの視線が痛い」
東 しかし、ニコ生のコメントを見ていると、若い世代には「戦後日本で生きていることそのものが後ろめたい」という感覚がうまく伝わらないみたいですね。うーむ……。
大山 「後ろめたさ」の感情を育むのはすごく難しいですよね。ぼくが中学生だったこの当時は、なにかというとアフリカの子どもたちが飢えていると言われていたり、中国残留孤児が連日ニュースで取り上げられたり、それまで見えなかったバックヤードが急に表面化してきた時代で、そういうかたちで「後ろめたさ」を教えられたんだなあ、といま気づかされました。
東 日本の高度経済成長は朝鮮戦争から始まった。そもそもその成り立ちからして危険というか、その後ろめたさの感覚が、一九八〇年代くらいまでは残っていたんじゃないかと思うんです。自分たちは他人を不当に犠牲にして、その上で成功しているという感覚。しかしゼロ年代あたりになると、「おれたちはこんなに虐げられているのに、なぜ後ろめたさなど感じなければならないのだ」という気分が蔓延してくる。
そのどちらが正しいのか、ここで歴史に答えを出そうとは思わないけれど、後ろめたさの感覚によって生み出された作品はたくさんあって、それがわからないとうまく読み解けない。その後ろめたさの感覚と、今日のバックヤードに関する議論は深く関係している。
大山 そういう作品を集めて話してみたいですね。
東 いまニコ生のコメントが教えてくれたところによると、「後ろめたい」というのは、「うしろめ」と「いたし」の合成語だそうです。つまり、「後ろからの視線が痛い」ということだと。
大山 後ろ指を指されている感覚ということですね。
東 「後ろ目」って、まさにバックヤードからの視線ということでしょう。「バックヤードからの視線が痛い」という感覚。
大山 まさに! 今日のテーマに近づいてきましたね。
東 原発事故も同じなんじゃないか。福島というバックヤード。
大山 なるほど。
東 大山さんの先ほどの質問に戻ると、東京のバックヤードは地方であると同時に、過去の歴史でもあるということかなと。日本全体がユートピアのように感じられた時代には、日本人は韓国や中国を一種の「バックヤード」として捉えていたと言える。
大山 しかし日本というショッピングモールの居心地が、だんだん悪くなってきた。
東 そう。そしてバックヤードからの不満がどんどん寄せられるようになってきた。それに対して、なぜそんなことをしなければならないのだと、日本人自体が不満に思うようになっている、というのがいまの状態です。
昔は日本というモールがすごく快適だったので、後ろめたさを感じる余裕があった。けれどいまは快適じゃないので不満だらけになってしまう。『思想地図β』vol・5でユートピアをテーマにしようと思っているのですが、この問題を考えるとどうしても避けて通れないのが、昭和後期、一九八〇年代の日本。この時代の日本はたしかに輝いていた。
たとえば先ほどの講演だと、梅棹忠夫は、そもそも日本はユーラシアの辺境という点で西欧と同じ条件を持っているので、いまのように発展しているのは当然だし、逆に条件の違うほかのアジア諸国には発展は不可能だと断言しているんですね。日本だけがすごいのだと言っている。この自信はすごい。ほかにも、当時坂本龍一は村上龍との対談で、なかば冗談ではあるんだけど、これから一〇年後にはニューヨークのインテリはみんな畳の上に住むだろうとも言っていた。みんな、日本が最高でユートピアだと思っていたわけで、そこから『メガゾーン23』も生まれている。でも、その自信はいったいどこからきていたのか。
あの時代、ぼくはちょうど一〇代でした。たんに豊かというだけではない、閉ざされた変な感覚があった。今日話していてわかったけれど、ぼくのショッピングモールへの関心の原点には、あの時代への疑問があるような気がします。
大山 次回に向けて、テーマが広がってきましたね。一度、一緒にモールに行きましょうか。上海なんてどうでしょう。
東 二泊三日くらいならば気軽に行けますものね。中国の規模は本当にすごくて、ぼくたちが名前も聞いたことがない街でも人口が五〇〇万人を超えている。スケール感が全然違うので、また新たな気づきがありそうです。