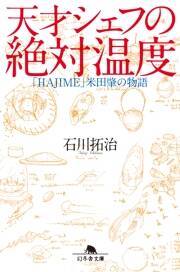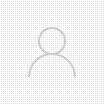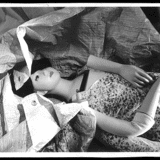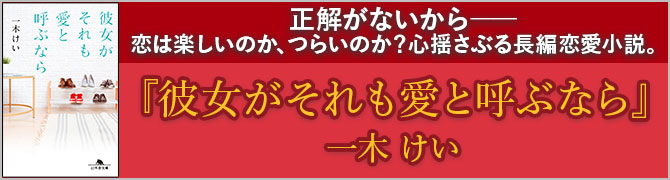開店から1年5ヶ月という史上最速で、ミシュランガイド三ツ星を獲得したシェフがいる。大卒で企業に勤めた後、料理学校に通い、26才で仏料理店の門を叩いた遅まきのスタート。最初は何をやっても失敗ばかりで、シェフに殴られ蹴られる日々だった。しかし……
絶対あきらめない圧倒的な努力と工夫がその後の人生をドラマチックに彩っていく。
フランスに生まれフランスに育ったフランス人シェフでも生涯の憧れである
ミシュラン三ツ星を、なぜこの日本人は手にすることができたのか?
天才シェフ・米田肇の修業時代を描いた『天才シェフの絶対温度 「HAJIME」米田肇
の物語』の試し読みを全4回でお届けします!
* * *
「これで完璧だと思ったら、それはもう完璧ではない。
この世に完璧というものはない。
ただ完璧を追い求める姿勢だけがあるんだよ」
――2006年11月ミシェル・ブラストーヤジャポンの厨房で、ミシェル・ブラスが米田肇にかけた言葉
こうして米田肇は1998年4月、エコール・キュリネール辻フランス料理専門カレッジに入学する。
25歳になっていた。
肇が初めてきちんとしたフランス料理を食べたのは、この学校に入ってしばらく経ってからのことだ。学校では、自分たちが作ったフランス料理を試食する機会が何度もあったが、食べたというよりもあくまで味見だった。「特に美味しいと思った記憶はない」と肇は言う。
学校の料理が不味かったという意味ではないだろう。前にも書いたが、肇の〞美味しい〝のハードルはきわめて高い。現在の彼は毎年、暮れから新年にかけて長期休暇を取る。たいてい一人でフランスに出かけて、気になるレストランを食べ歩くのだが、感想を聞くと生真面目な顔で「美味しいと思った料理はありませんでした」と答える。三つ星クラスのレストランの料理がどれもこれも不味かった、という意味ではないだろう。
彼の使う“美味しい”という言葉の前には、“感動的に”という言葉が隠されている。その料理が人を心から感動させるくらい美味しくなければ、美味しいとは認めないのだ。
授業中の味見ではなく、生まれてはじめて肇が食べたフランス料理は、『ル・ヴァンサンク』というレストランのランチだった。フランス料理を習っている者として、一度くらいはきちんとしたフランス料理を食べなければいけないと考え、学校の同級生を誘って食べに行ったのだ。『ル・ヴァンサンク』は今も大阪にあるフランス料理店で、当時からとても評判の良い店だった。
その日のことを肇がよく憶えているのは、彼がフランス料理が美味しいということを初めて知った日だからだ。特に印象に残ったのは、金目鯛だった。肇が頼んだ皿ではなく、一緒に行った友達のをつつかせてもらっただけなのだが、ほんとうに美味しかった。皮目はぱりっと香ばしいのに、身はしっとりと柔らかい。そのコントラストが見事だった。家庭料理の焼き魚しか食べたことのなかった肇は、そんなふうに焼かれた魚を食べたのは初めてだった。
「フランス料理が美味しいものだとわかってすごく嬉しくなった」と、肇は言う。
逆に言えば、そのときまで、フランス料理が美味しいということを知らなかったということだ。そんなことも知らないまま、せっかく就職した会社を辞めて、フランス料理の世界に飛び込んだのだ。父親が見抜いていたように、肇は夢見るような思いで人生の重大事を決めたのだった。
辻静雄は手塩にかけたこの学校に肇が入学する5年前に、60年の人生を終えてこの世を去っている。二人が出会うことは、ついになかった。
もちろん、仮にそこで会っていたとしても、何が起きたということはないだろう。なんといっても肇は、少しばかり出遅れた料理人志望の若者に過ぎなかった。
ただ、もし、辻静雄がそのときまだこの世にあって、彼が40年近くの歳月をかけて育てたこの学校の廊下でもぶらぶらと歩いているうちに、何気なくそのフランス料理コースの教室を覗き込んだとしたら、と想像を膨らませてしまうのだ。
というには早い。辻は生きていればそのときまだ65歳だ。この好奇心の強い人なら、あるいは肇が他の生徒と違っていることに気づいたかもしれない。肇はいつも教室のいちばん前の席に陣取り、そこにあるものは何から何まで喰い尽くしてやるという顔で授業を受けていた。選んだコースは1年間だった。その1年間でフランス料理のすべてを学び尽くすつもりでいた。
「すごく勉強しました。ほんとに勉強しました」
そう肇は言う。彼がそう言うのだから、ほんとうに冗談じゃないくらい勉強したのだ。その証拠が今も残っている。それは、厚さ15センチほどのファイルだ。そのファイルをめくりながら、最初僕は教科書かあるいは授業のために学校側が作成した資料だと思った。内容はフランス料理の様々なテクニックに関するものなのだが、その説明の文章は活字になっていたし、説明の(たとえばフライパンで魚の切り身をソテーしている)イラストも手書きではなく、簡易なものだがCGで描かれていたからだ。文章とイラストのレイアウトもすっきりしていて読みやすかったし、なによりも、その量があまりにも膨大だったから、考えるまでもなく、これはすべてこういうものを作成する専門のプロの手によって作られたものだと思い込んでいた。
ところが、そうではなかった。
それは、肇がその1年間で学んだことを記したノートだった。正確に言えば、昼間の授業のノートをもとに、肇が自宅に戻ってから整理して、パソコンで仕上げたものだ。母親の和子によれば、彼はその1年間一日も欠かさず夜自宅に戻るとずっと机に向かって作業をしていたという。
「設計をやってたので、こういうのを書くのは得意なんです。仕事の工程表を作るのと一緒です。毎晩1時間から2時間でさっと仕上げてました」
肇はそれをなんでもないことのように言うけれど、ファイルを1枚ずつめくりながら僕は、彼がその1年間でしたことの量に圧倒された。
かつてある場所で、旧日本海軍のパイロットで将校だった人が、太平洋戦争中に作っていたノートを見て慄りつ然ぜんとしたことがある。そのノートは信じられないくらい緻ち密みつで端正な文字の手書きだったのだが、なんといえばいいか、一台のパソコンにおさめられている情報のすべてがそこに書き込まれているという感じだった。
実際にそうなのだろう。その一冊のノートがあれば、一機の飛行機を完全に操縦し、飛行機から投下した爆弾を敵艦に命中させ、あるいは燃料の残量と飛行高度から飛行可能距離を割り出すことができる……というような情報が、ページをめくるごとに次から次へと現れるのだから。ページによっては、書き込まなければいけない数字の量が膨大すぎて、一つの数字が1ミリ四方ほどの大きさになっていた。その将校が優れた才能の持ち主だったことは疑いないが(すべてが手書きなのに、文字の直しは僕の見た限り一文字もなかった)、こんな緻密なノートを人間が作れるというそのことに僕は戦慄した。そして、これは戦時中という非常時だからできたのだと、多少強引に結論づけた。
肇のファイルを見て真っ先に思い出したのは、その海軍将校のノートだった。
緻密さと完成度において、二つはとてもよく似ていた。絶対的な情報量では料理の技術に関するファイルと軍事機密を網羅したノートは比べるべくもなかったけれど、肇なら必要とあらばその軍事機密のノートだって作れるだろうと思った。少なくとも真摯さということにおいて、肇はあの絶望的な戦争を最後まで戦い抜いた海軍将校に負けていなかった。それだけ真剣に学んでいたのだと思う。
(第四章 すべてを自分の仕事と思えるか より)
※第2回は、5月6日(土)の公開予定です。お楽しみに!
この連載は、『天才シェフの絶対温度 「HAJIME」米田肇の物語』の試し読みです。
天才シェフの絶対温度の記事をもっと読む
天才シェフの絶対温度
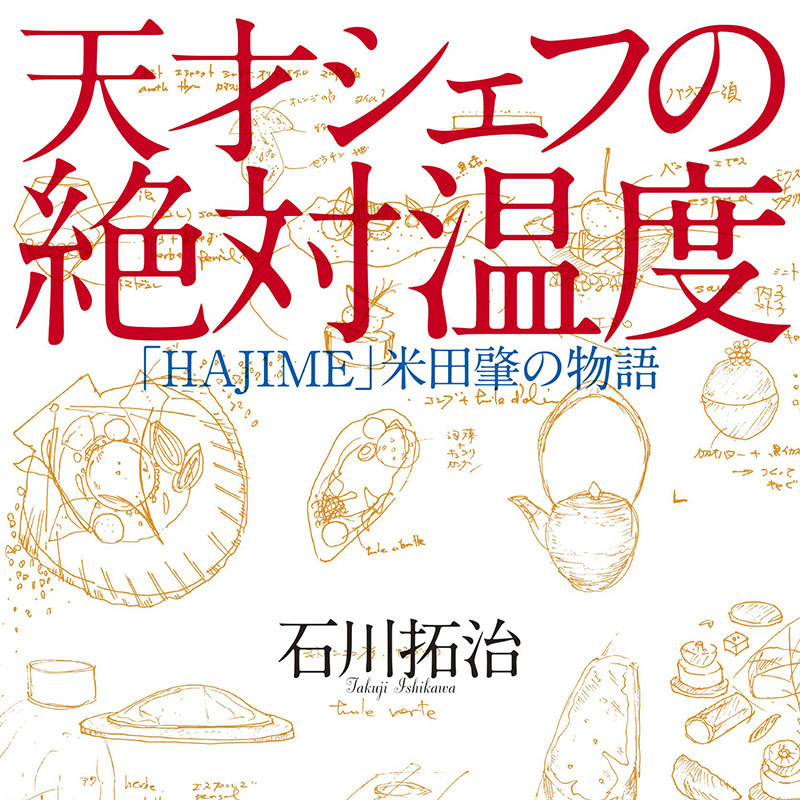
開店から1年5ヶ月の史上最速で、ミシュラン三つ星を獲得!
心揺さぶる世界最高峰の料理に挑み続けるシェフ・米田肇のドキュメント。