

開店から1年5ヶ月という史上最速で、ミシュランガイド三ツ星を獲得したシェフがいる。大卒で企業に勤めた後、料理学校に通い、26才で仏料理店の門を叩いた遅まきのスタート。最初は何をやっても失敗ばかりで、シェフに殴られ蹴られる日々だった。しかし……彼の圧倒的な努力と工夫がその後の人生をドラマチックに彩っていく。
フランスに生まれフランスに育ったフランス人シェフでも生涯の憧れである
ミシュラン三ツ星を、なぜこの日本人は手にすることができたのか?
天才シェフ・米田肇の修業時代を描いた『天才シェフの絶対温度 「HAJIME」米田肇
の物語』の試し読み、いよいよ最終回です。
* * *
勤め始めてすぐにわかったのは、ほとんどのスタッフが短期間で辞めるので、2年以上のキャリアのあるスタッフが厨房には一人もいないということだった。肇が厨房に入って2ヶ月も経たないうちに6人のスタッフのうち3人が相次いで夜逃げ同然に辞めてゆき、3ヶ月後には3人しかスタッフが残っていなかった。肇以外の2人はどちらも19歳の若者だった。
シェフはその3人の見習い同然のスタッフを使って、昼も夜も連日満席になる席数30席のレストランを切り盛りしていた。ただのフランス料理店ではない。飛ぶ鳥を落とす勢いのグランメゾンだ。
ディナーならアミューズからデセールまで、一人の客の皿数は10皿を超える。ランチはその半分としても、毎日450皿の料理を用意するということだ。完璧主義者のシェフはそのすべての皿に渾身の力を注いでいた。人間業ではない。
おそらく彼は1日2~3時間も寝ていなかったはずだ。だから、いつも不機嫌な顔をしていた。表情だけなら何も問題はないのだが、シェフはその不機嫌をそのままスタッフにぶつけた。
愛用の道具は木製の胡椒きだった。本気で殴ったわけではないだろう。本気で殴ったら、死んでもおかしくないくらい大きくて重い胡椒きだ。その胡椒きでよく頭を殴られた。些細なミスや気のゆるみも許されなかった。
トウモロコシの粒まで何粒と数えて、数を書いて、密閉容器に入れて保管しておくようなシェフなのだ。翌日そのトウモロコシが一粒でも足りないだけで大騒ぎになった。「どこかに落とした」と答えれば、その落としたトウモロコシの一粒を朝までかかっても捜し出せと、厨房中を捜させた。
それでも見つからなければ、パイ皿が凶器になった。パイ皿で顔を殴っておいて、皿の端が欠けると、「なんで皿を欠けさせるんだ」といって、今度は頭を殴る。土鍋で頭を殴られて、頭から血を流したら「床を汚すな」とまた殴られる。
肉体的な恐怖を感じた。空手の稽古では一度も感じたことのない恐怖だった。このシェフに比べたら、どんな荒っぽい格闘家だって平和主義者みたいなものだ。無抵抗の人間に対して、そんな攻撃を加える格闘家はいないのだ。
最初のうちは思わず避けたこともある。空手の癖で、本能的に攻撃をかわしてしまうのだ。けれど、そんなことをするとシェフの怒りは倍増して、さらに激しい罵声と攻撃を加えられることになる。
肇が厨房で最初に憶えたのは、襲いかかってくる胡椒きを避けないことだった。
「それでも最初のうちは楽しかったんです。楽しいは言いすぎかな。でも充実感はあった。ようやく子供の頃からの夢だった料理人になって、思い描いていたような一流店に入って修業しているわけです。修業は元々好きだったし、自分は今いちばん有名な店で働いているんだから、厳しいのは当たり前と思ってました。厨房はピカピカでした。ピカピカにするのは私たちですけど。営業が終わった夜中に毎晩掃除をしてました。掃除を終えて部屋に帰るといつも夜中過ぎになる。しかも、掃除が終わった後にシェフがチェックして、指紋一つでもついていたりしたら、『全部やり直せ』って、引き出しから何から全部出して、最初から掃除をやり直ししなきゃいけない。そうなると終わるのは明け方になってしまう。『ああ、また今日も朝になっちゃう』って、泣きそうになりながら掃除をしてました。前の日の帰りがどんなに遅くなっても、翌朝は6時半に起きて出勤しなきゃいけないから、いつも寝不足で、掃除には業務用の強力な洗剤を使うから、手はパンパンに腫れてアカギレだらけだった。痛くて重いものが持てないんです。休日実家に帰って、母親と一緒に買い物に行って、帰りに荷物を持ってあげようとするんだけど、手を握れなくて持てないってことがありました。母親が黙ってボロボロ涙をこぼしながら、私の手をさすってくれました。後から聞いたら父親に『それがあいつの選んだ修業なんだからなんにも言うな』って言われてたんだそうです。あの頃はそんなことはつゆ知らず、すっげえ修業だなあと思って、その厳しさが逆にモチベーションになったくらいです。
ただ問題は、私がまったく仕事ができなかったということです。学校を卒業したときには天狗になってたんです。フランス料理のことなら何でも知っているつもりだった。どこの厨房に入っても、自分は通用すると思っていました。自分は誰よりもフランス料理の勉強をしたという揺るぎない自信がありました。だけどこれは、野球でいうなら要するにルールブックだった」
そういって、肇は目の前に置いた分厚いファイルをポンと叩いた。学校に通っていた1年間、毎晩コンピュータに向かって昼間の授業の内容をまとめた例のファイルだ。
「私は1年かけて、詳しいルールブックを作っただけのことだった。椅子に座ってルールの勉強をしただけなのに、野球をやってるつもりでいたんです。ルールは完璧に暗記してるけど、素振りすらしたことがない野球選手がバッターボックスに立っても、空振りするしかないですよね。それと同じことですよ。なのに、自分はどこでも通用するなんて思ってた。何やってるんだという話ですよね。
野球のルールを憶えることと野球をすることがまったく違うのと同じように、料理の知識を頭に詰め込むのと料理を作るのは別のことなんです。あの最初のレストランの厨房で、そのことを思い知らされました。ものすごい闘志が湧きました。自分ができないのも当たり前だ。いつかできるようになろうと思って毎日を過ごしてました。それまでは何をやるにしても、学校の勉強も、ゴルフも、格闘技も、会社の仕事にしても、普通にやってればなんとかできるようになってた。ところが、これは普通に頑張るくらいのレベルではどうにもならない。命懸けって言葉があるけど、あのシェフの厨房ではそれくらい本気にならなきゃついていけなかった。本気で何かに取り組むというのはどういうことかを、あの厨房で学びました。そして、真剣に仕事に取り組みました。シェフに言われたことは、すべて完全にやり遂げようと自分にできることは何でもやりました。だけど、完璧に空回りだった。1年経っても、何もできるようにならなかった」
(第四章 すべてを自分の仕事と思えるか より)
※この連載は、『天才シェフの絶対温度 「HAJIME」米田肇の物語』の試し読みです。
つづきは、書籍をお手にとってお楽しみください!
天才シェフの絶対温度
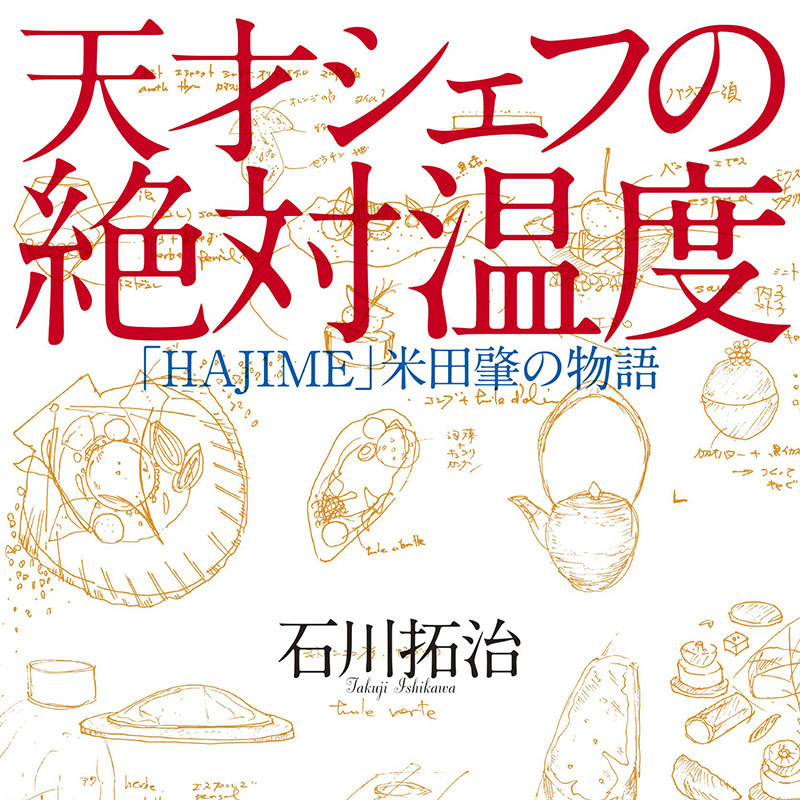
開店から1年5ヶ月の史上最速で、ミシュラン三つ星を獲得!
心揺さぶる世界最高峰の料理に挑み続けるシェフ・米田肇のドキュメント。
















